
先週の土曜日は、専門職大学院の今年度最後の入試でした。
入試管理委員長の僕としては、一つ肩の荷が降りて、ちょっとホッとした感じです。
すぐにまた、来年度の入試広報戦略を組み立てて行かなきゃならないんですけど…。
専門職大学院では、色々な入試を行っています。
社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者入試。
昨年から始めた、一定の基準を満たした社会福祉法人等による指定法人推薦入試。
現職の職場長による推薦入試や、学部新卒者の学内推薦入試。
そして、一番基本になっているのが、一般入試。
この一般入試は、出願書類、小論文、基礎知識、個別面接による審査のほか、グループディスカッションという試験があります。
大学に隣接している清瀬療護園の入所者等、福祉サービス利用者を交えて、受験生がグループで意見交換するものです。
グループの運営進行は、担当した当事者の入試特別委員にゆだねられます。
障害当事者がその場で投げかけた問いかけに応えていくのですから、受験生からすれば準備のしようもなく大変です。
教員は傍らから、ただ黙ってグループの様子を拝見しています。
今回の試験では、精神保健分野の当事者としては、澤田優美子さんにお願いしました。
僕とは、前職の病院で、障害年金の再審査請求を一緒に闘った仲間?です。
世界クラブハウス連盟の委員などの活動を通して、第1回リリー章を受賞し、去年は福祉士W資格にも合格した当事者です。
「何を話したら良いのか…」と、お願いした当初、戸惑っておられましたが、いいグループ運営をしてもらえました。
彼女が受験生に投げかけた質問。
「障害者の存在意義って、なんだと思いますか?」…。
「ただケアやサービスを受ける対象として、障害者である自分を思うと、とても悲しくなります。
自分の存在意義が感じられないと、生きていないみたいで、私は死んでしまいたくなります。
障害者が生きている社会的な存在意義って、皆さんはなんだと思いますか?」
たぶん、そのグループの受験生は、あっけにとられ、さぞかし悩んだと思います。
障害者と言えば、サービスを提供する対象者、利用者としてしか考えたことないでしょうし。
障害者自身の社会的存在意義なんて、考えたことすらないと思います。
専門職大学院では、こういう正解のない議論をよくしますが、僕だって、その場にいたら答えに窮すると思います。
結論を出すことが、入試のグループディスカッションの目的ではないので、答えがなくて良いのですが。
さて、もし、あなたが同じ問いを投げかけられたとしたら、どう答えますか?
…( ̄○ ̄;)?
入試管理委員長の僕としては、一つ肩の荷が降りて、ちょっとホッとした感じです。
すぐにまた、来年度の入試広報戦略を組み立てて行かなきゃならないんですけど…。
専門職大学院では、色々な入試を行っています。
社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者入試。
昨年から始めた、一定の基準を満たした社会福祉法人等による指定法人推薦入試。
現職の職場長による推薦入試や、学部新卒者の学内推薦入試。
そして、一番基本になっているのが、一般入試。
この一般入試は、出願書類、小論文、基礎知識、個別面接による審査のほか、グループディスカッションという試験があります。
大学に隣接している清瀬療護園の入所者等、福祉サービス利用者を交えて、受験生がグループで意見交換するものです。
グループの運営進行は、担当した当事者の入試特別委員にゆだねられます。
障害当事者がその場で投げかけた問いかけに応えていくのですから、受験生からすれば準備のしようもなく大変です。
教員は傍らから、ただ黙ってグループの様子を拝見しています。
今回の試験では、精神保健分野の当事者としては、澤田優美子さんにお願いしました。
僕とは、前職の病院で、障害年金の再審査請求を一緒に闘った仲間?です。
世界クラブハウス連盟の委員などの活動を通して、第1回リリー章を受賞し、去年は福祉士W資格にも合格した当事者です。
「何を話したら良いのか…」と、お願いした当初、戸惑っておられましたが、いいグループ運営をしてもらえました。
彼女が受験生に投げかけた質問。
「障害者の存在意義って、なんだと思いますか?」…。
「ただケアやサービスを受ける対象として、障害者である自分を思うと、とても悲しくなります。
自分の存在意義が感じられないと、生きていないみたいで、私は死んでしまいたくなります。
障害者が生きている社会的な存在意義って、皆さんはなんだと思いますか?」
たぶん、そのグループの受験生は、あっけにとられ、さぞかし悩んだと思います。
障害者と言えば、サービスを提供する対象者、利用者としてしか考えたことないでしょうし。
障害者自身の社会的存在意義なんて、考えたことすらないと思います。
専門職大学院では、こういう正解のない議論をよくしますが、僕だって、その場にいたら答えに窮すると思います。
結論を出すことが、入試のグループディスカッションの目的ではないので、答えがなくて良いのですが。
さて、もし、あなたが同じ問いを投げかけられたとしたら、どう答えますか?
…( ̄○ ̄;)?










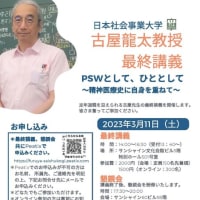
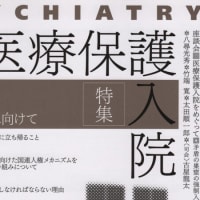
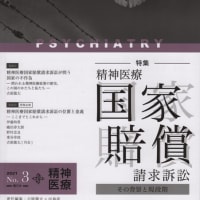




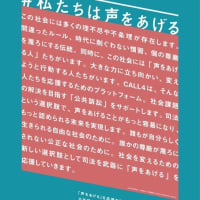
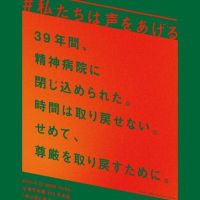
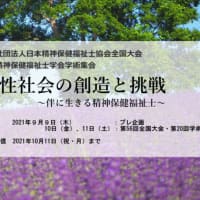
「障害者」としての存在意義の以前にあなたや、わたしの存在意義という個人レベル(ミクロ)の話から障害者と健常者の区分(マクロ)での視点がある。「わたし」の存在意義はあるのかどうか怪しいのですが、ある時はあり、ない時はないような気がします。だけど、あると信じたい、あることに気づきたい。外から意味づけられる「存在意義」や承認欲求よりも、自己実現の主観的な実感が欲しいと思います。「では、承認される必要はいらない?」のかと問われるなら、いいえ、外部からの「存在意義」の保障が全くなくて主観的な実感はもちにくいだろうとと想像します。そんな私がコメントしてみます。
1.「わたしが辛いと思った時に、それまで見えてなかった、もっと辛い状況にある人の存在は、まだ、わたしは恵まれている。まだ、わたしはがんばれるはずと思います。」正直なモノローグであるけれど、鈍感な答えだったかなと思います。
2.「わたしは、ケアには相互性ってあるように思います。頭の固いわたしでも、場を共有すること時間を共有することの意味は少なくともあると思います。それが、悲しませるとしたらわたしは、どうしたらよいのでしょう?」悪い人ではないけれど、押し付けがましいかもしれない答えかな。つい口に出からでてしまいそうになるけれど。もうちょい。共感する人でなくて、共感して欲しい人になってしまっている。
3.「ケアやサービスを受ける対象でしかないと思うことは寂しいですね。自己決定や成長する機会が奪われていると感じているのでしょうか。それともケアやサービスの制度や仕組みを含めた社会的システムによると思いますか?それともケアやサービスに従事する人の資質やかかわり方の課題と感じますか?」
4.「わたしは、これまで障害者と健常者で区別するマクロの議論と個人間のミクロの議論を統合視点をもっていなかったか、パーフェクトな人はいないから、誰もが程度の差のある障害者として考えていましたけれど、それはスティグマについて考えていなかったと思いました。現実には「障害者」として生きるうえでの生きづらさというのは大変なことだと改めて教えられました。これまでどんな生きづらさがあって、それを克服したり、今なお疑問に感じていることを聞かせて貰えませんか?」
5.「一緒に学んだり、楽しめたらいいなと思います。存在意義とか難しいことはわからないけど、生きていく上での困難では、程度の違いはあっても、これだけ自殺の多い国では「健常者」として区分されていても生きづらい世の中なんじゃないかなって思います。」
6.「障がい者って言葉の響きが良くないけど、隠れず出てこれる社会のあり方って必要だと思う。やさしい世の中にしたいというか、これって存在意義かどうかわからないけど、障がい者も暮らしやすい社会ってイイ社会だと思う。それには障がい者でなければわからないことって沢山あると思う。いくら話しても、障がい者にしかわからないんじゃなくて、障がいのない人にもわかって貰えることはあるんじゃないかな。それは、時間のかかることかもしれないけど、お互いのためでもあると思う。」
7.「役割をどう位置づけるかという話しで、外からこうしなさい、あーしなさいとだけ言われるってウザイよね。だけど、何も言ってくれないのもチョッとね、それって自分の甘えなのかもしれないけど、存在意義ってさ、生きてて良かったと思えることなんじゃないの?失敗したとしても、やりたいことがやれること。それが一人じゃできないとしたら、それって協力してくれる人を見つけること、協働する環境づくりだと思う。」
8.「それは間違ってはないけど、プロセスについても考えないといけないよね。なんだか都合の良い話に聞こえる。ほら、障がい者の都合に合わなくなる可能性というか、ケアやサービスを受ける対象」という枠の中で進むとさ、どっか大事なことを見落としている気がするよ。「経験」とか「体験」の機会で障がいのある人が何を求めていてとか、まずは、ケアやサービスを受ける側として社会に対して意見表明をすることの環境が整うことは大事なことだと思う。」
答えになっていないようなコメント書き込み、失礼しました。('o')
結論としては、存在意義という観点などない、と思います。
哲学としては、様々な“ことば”が必要なのかもしれません。
しかし、そこを辿ることに意味はないと思います。
花を見て、美しいと思うことに理屈はないのです。だから、人が生きていることを“なぜ生きるのか”という問いこそねじれた問いだと思います。
だから、対極に“死”について考えてしまうのです。
障害を持った人たちの存在意義を改めて問う必要など、ないのです。それぞれ個人が秘めているものでしょう。
垣内芳子先生が、レクリエーションの定義を「一切の生活上の快」と表現しました。
まさに私たちは、生活上の快を求めていると思います。生活の快は、人によって見つけ方や感じ方が異なります。なぜ心地よさを感じるのかを問うてはいません。
ハンバーガー屋さんの店員がいなければ、ハンバーガーが食べられないのと同様に、支援者がいるのという考えは言い過ぎでしょうか?
人が集まれば、相互作用が生まれることも当然です。
だからこそ、生活の快を求めるべきだと思うのです。
徒然に書き込んでみました。まだまだ未熟と思っています。いろいろと勉強させてください。
気合いのこもった熱いメッセージ、ありがとうございます。
投げかけられた問いに、真剣に向き合ってくれた誠意に感謝致します。
「ケアの相互性」ってことは、やはり考えますよね。
僕も今、病院現場には非常勤でしか行ってませんが、病院で患者さんたちと会うと実感することがあります。
「わぁ~、こんにちは~、お元気ですか~?」
なんて患者さんに声をかけられると、僕はとても幸せを感じます。
ケアする側としてサポートしてるつもりだったけど、彼ら彼女らに僕は四半世紀支えられて仕事していたんだなと実感します。
教員が学生に対して「君たち以上に僕の方が学ばせてもらった」という実感と同じでしょうね。
明確に立場の違いはあり、安直に「当事者の目線で」などと言えないと思いますが、立場の持つ相互性というのはあると思います。
「存在意義ってさ、生きてて良かったと思えることなんじゃないの?」って言葉、僕にはヒットですね。
この世界で、日々色んな体験をし、色んな人と関わり、喜びを実感できることって、とても大事だと思います。
そして、それは多くの場合、人との関わりで得られる喜びだと思います。
限りある生の、一期一会の出会いの中で、語り合い、笑い合い、支え合って、喜びを感じる瞬間、「生きていて良かった」と思えるのでは。
人にはそれぞれ、色んな生活の側面があるし、色んな次元での位置があり、一概に共通の「存在意義」があるはずもないと思います。
でも、一生懸命何かに取り組んでいる時、自分の中で目標や意義を見出してこそ頑張れることは誰でもあるはずです。
それが他者や社会に承認されるような事柄であるかどうかは、別にして。
一生懸命「生きる」「生き続ける」ということを目標に据えている澤田さんにとって、生きる「意義」は身近なテーマなのだと思います。
人はやはり、意味を求めてしまう社会的存在です。
生物としてだけ生きていれば、意味を求めなければ、もっと楽になれるんでしょうけど。
投げかけられた問いに、明確な答えは出ないかも知れないけど、意味を問い続ける意味は常にあると思います。
たくさん記していただいたフーテンさん、本当にありがとう!
今後とも、よろしくお願い致します。
<(_ _)>
龍龍
「存在意義」という言葉を、言葉で意味づけていっても、堂々巡りで意味が無いってことですね?
哲学的に言葉を綴り続けて、自分も他者も答えとしてそれで実感できれば良いけど、そうそうそんな答えには辿り着かないしね?
生きている実感や喜びこそが、とても大事だというのは、その通りと思いますよ。
言葉で語る以前に、自分の体や心が、悦び・快として感じられるものは、一番生きていくのに大切なものと思いますよ。
(違法ドラッグとかの問題は、さておいて…)
うれしい、楽しい、しあわせ、おいしい、気持ちいい、心地よい、満ち足りる、力が湧く…、みんな生きている悦びを感じる時ですよね。
「なぜ心地よさを感じるのかを問うてはいません」っていうのも、わかりますね。
感性の意味を問い始めると、言葉で言葉を説明するメタ言語の迷宮に入ってしまいますからね。
心の宿る体としての身体って、生きてきた過程の意味が一杯詰まっているけど、全部明らかに出来るものでもないしね。
特に、心理職と違ってワーカーは、その人の過去の傷跡より、生きている現在の感覚を大事にしなきゃいけないし。
ワーカー自身も、日々の生活の快を大事にしなきゃね?
ところで、マリリンさんの「生活の快」は、ちゃんと追求できていますか~?(笑)
(^o^)/~~
龍龍