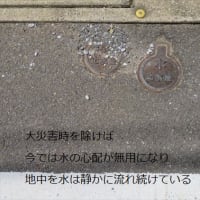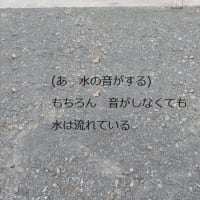作家・作者・作品・語り手・登場人物について ① ―村上春樹から
作家・作者・作品・語り手・登場人物については何度か考えてみた。最近、作家、村上春樹のインタビュー集を読んで、またそのことを再確認してみようと思った。この①の文章では、作者・作品・語り手・登場人物が現れる以前のことに触れている。
この人間社会に個々具体的に生きるわたしたちの姿をひとつの共通性として抽出してみると、誰もが、父親であるとか会社員であるとか時々趣味のクラブに通っているとか、様々なつながりを持ちそれぞれの場での顔を持っている。その様々な顔を持っているひとりの人間を総合性としての人間(個人、個)と捉えるとすれば、以下に平面的な層として図示(註.図1)してみるが、その総合性としての人間は誰でもA、B、C、D・・・などいくつもの位相の異なる世界を日々行き来しながら生きている。付け加えると、現在ではSNSやネットゲームなど仮想空間の位相にも入り込めるようになってきた。
その位相の異なるという意味は、例えば子どもが家を出て学校に行ったら、例え父親が同じ学校で先生をしていても、プライベートな用事でなければ、呼びかけの言葉としては「お父さん」ではなく「先生」と言う言葉を使うはずである。このように、家族という場と学校という小社会とでは世界が違うしその言葉もちがう。つまり、位相が違っている。
テレビが普及し始めた頃の次のような笑い話のようなものに昔、文章で出会ったことがある。テレビの中で一度死んだ者がまた別の日にテレビに出ていてとても驚いたという話である。わたしたちは俳優とはそんなものだと分かっているから、そういうふうに具体的な人間とその人が俳優として演じる世界とを同一化してしまって驚くということはない。時代を遡るとそのような同一化はもっと強くなるような気がする。わたしたちの時代は、現実の人間とその人が俳優として演じる世界を別ものだと分かっているし、そのことは自然なものになっている。
しかし、以下の引用で村上春樹が、作家としての自分と普通の生活者としての自分を割とはっきりと区別していていても、他者と出会ういろんな場面でそのはっきりと分離しがたい二重性に遭遇してふしぎな感情を抱いている。また、わたしたちでも、いわゆる有名人をそのイメージでその人全体やふだんの生活の様子をイメージすることがある。これは、先に挙げたテレビの草創期の笑い話と同質の同一化によるものではないかと思う。そうして、このようなイメージの同一化、すなわちひとりの人間の中のいくつもの位相を同一化しようとしたり一つののっぺりしたものとして捉えようとする意識性は、わが国では負の精神の遺伝子とも言うべきもので、とても根の深い問題だと思われる。
現在でも残っているその意識性は、個人と社会や国家という次元や位相の異なる世界をやすやすと同一化してしまう傾向として残存している。個人にとって社会や国家は、完全に無縁とは言えない。しかし、わたしたちは家族や会社などの小社会に生きていて具体的に「責任」を追わざるを得ない場面がしばしばあり得るが、社会や国家という抽象的な世界に対しては、― そこを根城とする官僚や政治家たちは別にして ― そういう「責任」を持ちようがない。個人の身近な生活世界(小社会)と抽象的な社会や国家という世界は、世界の仕組みが違うのである。これは例えば、近所付き合いや町内会の場で政治的な問題をまじめに語るようなもので、誰にとってもそれが場違いであるということはわかると思われる。
このような負の精神の遺伝子とも言うべきもの、たぶん西欧のようにあらゆるものを位相の異なるものとして区別しそのように対応することなく、ひとつののっぺらぼうのように捉える意識性は、わが国でアジア的な古代国家が成立した時期よりもさらに遙か昔からのもののように感じられる。逆に言えば、国家以前の太古の、上と下との階層差があんまりなかった強固な集落の構造から来ているような気がする。この上に国家が乗っかっていってもその意識性が応用されたのではなかろうか。現在表面化してきている排外的なネトウヨ現象は、この根深い負の精神の遺伝子とも言うべきものから来ているはずである。おそらく彼らの内面は、連続的でなく断続的かもしれないが生活とイデオロギーが転倒した病的な内面になっているはずである。
村上春樹のインタビュー集から、このことに関連することを引用してみる。
1.普通の人間としての村上春樹 (図1の「家族の中の人(生活者)」)
村上 でもいったん机を離れると、僕はすごく普通な人間です。自分で言うのもなんだけど、ごく普通の考え方をして、ごく普通に生活して。だからたとえば道を歩いていてたまに、あ、村上さんですねって声をかけられて、いつも読んでますとか言われると、今でもとても不思議な気がします。もう三十年作家をやっているけど、「なんでまたこの僕に?」という気がしますね。というのは、道を歩いているときは、僕は本当に普通の人だから。たぶん机の前に座っているときは普通じゃないところがいくらか出てくると思うんだけど、そうじゃないときはどこにでもいる当たり前の人ですよね。だから、握手して下さいとか言われると、なんで握手するんだろうって真剣に不思議に思います。サインなんかしても、なんかまるで「こども銀行」のお札を刷っているみたいで。
日本にいれば僕はほとんど人前に出ません。テレビに出たりラジオに出たりしないし、講演もしないし、サイン会もしない。というのは、もちろん苦手だからだし、それにそんなことしてもしょうがないと思うからです。書いたものは多くの人に読んでほしいと、ものすごくそれは強く思うんだけど、それ以外のことっていうのは関係ないんですよね、本当に。
(『村上春樹インタビュー集1997-2011』P532-P534)
2.作家としての村上春樹
―読者を驚かすことは、あなたの作品の強みのひとつだと考えますか。
村上 僕自身、驚かされるのが好きですね。小説を書いているとき、次に何が起きるのか僕にはわかりません。先に何が起きるか、角を曲がってみるまではわからない。そういうのは、とてもわくわくします。僕は毎朝小説を書いています。次はどうなるのかと期待しながら、わくわくして、スリルを感じています。自分でも驚かされるのは楽しいですし、もし僕が驚かされるなら、きっと読者も驚かされるでしょう。僕は何も考え出したりはしないで、ただ何かが起きるのを待っているだけなのです。僕は作家になれてとても幸せです。だって小説を書いていると、日々驚きの連続であるわけですから。
(『同上』P551)
この人間社会の中で様々なつながりを持ちながら具体的に生きているひとりひとりの人間を、抽出してみると「総合性としての人間」という人の総体像が得られる。「総合性としての人間」としてひとりの人間をまるごと捉えるとしても、日々の生活ではわたしたちは家族を中心の場とする生活を重力の中心に引き寄せられるようにして生きている。(施設で生きる子どもにとっては疑似家族と見なし、ひとり住まいの場合には単独家族と見なすことにする。)そうして、その家族を具体的な場として生きる人の有り様が、ひとりの人間の生存の自然基底となっている。この生存の自然基底は無視し得ないある強度を持っていて、人はこれを離れてイメージやイデオロギーなどの世界のみを生きるということはできない。それがもし可能とすれば、現実の具体的な生活は抜け殻のようになりイメージやイデオロギーのみが生き生きした現実味を持つという転倒した内面世界、すなわち精神の病を生きている場合だけである。
したがって、誰もがいくつもの顔を持っているわけだが、普通の生活者の顔をして歩いている時の村上春樹が作家としての村上春樹として呼びかけられて当惑したりふしぎな気持ちになるのはわかるような気がする。これに関連して思い出すのが、何の作品でもいいけど、例えばアニメの作品「君の名は。」で主人公が過ごした駅や図書館などの土地を訪れることをファンの間では「聖地巡礼」といって流行っているらしい。また以前には、韓国のドラマの「ロケ地巡り・聖地巡礼」というのもあった。別にそんな風な楽しみ方を否定する気はないが、わたしや上記のような村上春樹の感覚からすれば、こうしたことは作品にとってはほとんど意味はないということになるだろう。このような「聖地巡礼」もイメージの同一化の意識から来ているように思う。
ところで、わたしたちが家族などの身近な生活世界を中心に生きるという生存の自然基底からすれば、社会や政治の問題はどうでもいい問題としてある。ただ、社会や政治の有り様がわたしたちの生活世界に利をもたらすことは少なくより多く規制したり干渉したり不利益をもたらしたりする歴史の中に依然としてわたしたちはいる。つまり、行政や政治が生活者の利益のためにのみあるという本来的な意味を生きるなら、わたしたちはさらにのんびりと「鼓腹撃壌」(こふくげきじょう)を生きることができるはずである。
わが国で現在でもしばしば否定的に取り上げられる「政治的無関心」という問題についてひと言。まず、わたしは半ば以上はそのことに肯定的である。国家以前の遙か太古の、上と下があんまり格差がなく割と平等な集落社会では、上の方というか担当が、宗教的な行事や経済的な分配などの行政的なものも割とうまくやっていて、別にそれらのことに文句を言う必要もない。自分が当番になればやればよいだけで、普通はあんまり関心を持たない。このような強固な集落性の時代(段階)が長くあったのではないかという気がする。このような意識性は、現在では町内会もいろんな問題を抱えているのかもしれないが、町内会の構造に保存されているように感じる。国家がこのような小さな集落の意識構造に乗っかって社会規模が大きくなり高度化してからも、そういう集落の強固な意識性からうまく接続したり展開することなく、現在まで来ているのではないかという気がする。明治近代以降、欧米からの大きな波をかぶってきた現在では、欧米からの模倣の滲透とは言え、個や社会や国家に対して割と分離した意識を持つ欧米の視線の影響を受けて、そこからの内省が社会レベルで働くようになってきている。要は一方からの啓蒙ではなく、それらの二つの視線がどう交差したらいいかという問題があるように思われる。
作家・作者・作品・語り手・登場人物については何度か考えてみた。最近、作家、村上春樹のインタビュー集を読んで、またそのことを再確認してみようと思った。この①の文章では、作者・作品・語り手・登場人物が現れる以前のことに触れている。
この人間社会に個々具体的に生きるわたしたちの姿をひとつの共通性として抽出してみると、誰もが、父親であるとか会社員であるとか時々趣味のクラブに通っているとか、様々なつながりを持ちそれぞれの場での顔を持っている。その様々な顔を持っているひとりの人間を総合性としての人間(個人、個)と捉えるとすれば、以下に平面的な層として図示(註.図1)してみるが、その総合性としての人間は誰でもA、B、C、D・・・などいくつもの位相の異なる世界を日々行き来しながら生きている。付け加えると、現在ではSNSやネットゲームなど仮想空間の位相にも入り込めるようになってきた。
その位相の異なるという意味は、例えば子どもが家を出て学校に行ったら、例え父親が同じ学校で先生をしていても、プライベートな用事でなければ、呼びかけの言葉としては「お父さん」ではなく「先生」と言う言葉を使うはずである。このように、家族という場と学校という小社会とでは世界が違うしその言葉もちがう。つまり、位相が違っている。
テレビが普及し始めた頃の次のような笑い話のようなものに昔、文章で出会ったことがある。テレビの中で一度死んだ者がまた別の日にテレビに出ていてとても驚いたという話である。わたしたちは俳優とはそんなものだと分かっているから、そういうふうに具体的な人間とその人が俳優として演じる世界とを同一化してしまって驚くということはない。時代を遡るとそのような同一化はもっと強くなるような気がする。わたしたちの時代は、現実の人間とその人が俳優として演じる世界を別ものだと分かっているし、そのことは自然なものになっている。
しかし、以下の引用で村上春樹が、作家としての自分と普通の生活者としての自分を割とはっきりと区別していていても、他者と出会ういろんな場面でそのはっきりと分離しがたい二重性に遭遇してふしぎな感情を抱いている。また、わたしたちでも、いわゆる有名人をそのイメージでその人全体やふだんの生活の様子をイメージすることがある。これは、先に挙げたテレビの草創期の笑い話と同質の同一化によるものではないかと思う。そうして、このようなイメージの同一化、すなわちひとりの人間の中のいくつもの位相を同一化しようとしたり一つののっぺりしたものとして捉えようとする意識性は、わが国では負の精神の遺伝子とも言うべきもので、とても根の深い問題だと思われる。
現在でも残っているその意識性は、個人と社会や国家という次元や位相の異なる世界をやすやすと同一化してしまう傾向として残存している。個人にとって社会や国家は、完全に無縁とは言えない。しかし、わたしたちは家族や会社などの小社会に生きていて具体的に「責任」を追わざるを得ない場面がしばしばあり得るが、社会や国家という抽象的な世界に対しては、― そこを根城とする官僚や政治家たちは別にして ― そういう「責任」を持ちようがない。個人の身近な生活世界(小社会)と抽象的な社会や国家という世界は、世界の仕組みが違うのである。これは例えば、近所付き合いや町内会の場で政治的な問題をまじめに語るようなもので、誰にとってもそれが場違いであるということはわかると思われる。
このような負の精神の遺伝子とも言うべきもの、たぶん西欧のようにあらゆるものを位相の異なるものとして区別しそのように対応することなく、ひとつののっぺらぼうのように捉える意識性は、わが国でアジア的な古代国家が成立した時期よりもさらに遙か昔からのもののように感じられる。逆に言えば、国家以前の太古の、上と下との階層差があんまりなかった強固な集落の構造から来ているような気がする。この上に国家が乗っかっていってもその意識性が応用されたのではなかろうか。現在表面化してきている排外的なネトウヨ現象は、この根深い負の精神の遺伝子とも言うべきものから来ているはずである。おそらく彼らの内面は、連続的でなく断続的かもしれないが生活とイデオロギーが転倒した病的な内面になっているはずである。
村上春樹のインタビュー集から、このことに関連することを引用してみる。
1.普通の人間としての村上春樹 (図1の「家族の中の人(生活者)」)
村上 でもいったん机を離れると、僕はすごく普通な人間です。自分で言うのもなんだけど、ごく普通の考え方をして、ごく普通に生活して。だからたとえば道を歩いていてたまに、あ、村上さんですねって声をかけられて、いつも読んでますとか言われると、今でもとても不思議な気がします。もう三十年作家をやっているけど、「なんでまたこの僕に?」という気がしますね。というのは、道を歩いているときは、僕は本当に普通の人だから。たぶん机の前に座っているときは普通じゃないところがいくらか出てくると思うんだけど、そうじゃないときはどこにでもいる当たり前の人ですよね。だから、握手して下さいとか言われると、なんで握手するんだろうって真剣に不思議に思います。サインなんかしても、なんかまるで「こども銀行」のお札を刷っているみたいで。
日本にいれば僕はほとんど人前に出ません。テレビに出たりラジオに出たりしないし、講演もしないし、サイン会もしない。というのは、もちろん苦手だからだし、それにそんなことしてもしょうがないと思うからです。書いたものは多くの人に読んでほしいと、ものすごくそれは強く思うんだけど、それ以外のことっていうのは関係ないんですよね、本当に。
(『村上春樹インタビュー集1997-2011』P532-P534)
2.作家としての村上春樹
―読者を驚かすことは、あなたの作品の強みのひとつだと考えますか。
村上 僕自身、驚かされるのが好きですね。小説を書いているとき、次に何が起きるのか僕にはわかりません。先に何が起きるか、角を曲がってみるまではわからない。そういうのは、とてもわくわくします。僕は毎朝小説を書いています。次はどうなるのかと期待しながら、わくわくして、スリルを感じています。自分でも驚かされるのは楽しいですし、もし僕が驚かされるなら、きっと読者も驚かされるでしょう。僕は何も考え出したりはしないで、ただ何かが起きるのを待っているだけなのです。僕は作家になれてとても幸せです。だって小説を書いていると、日々驚きの連続であるわけですから。
(『同上』P551)
この人間社会の中で様々なつながりを持ちながら具体的に生きているひとりひとりの人間を、抽出してみると「総合性としての人間」という人の総体像が得られる。「総合性としての人間」としてひとりの人間をまるごと捉えるとしても、日々の生活ではわたしたちは家族を中心の場とする生活を重力の中心に引き寄せられるようにして生きている。(施設で生きる子どもにとっては疑似家族と見なし、ひとり住まいの場合には単独家族と見なすことにする。)そうして、その家族を具体的な場として生きる人の有り様が、ひとりの人間の生存の自然基底となっている。この生存の自然基底は無視し得ないある強度を持っていて、人はこれを離れてイメージやイデオロギーなどの世界のみを生きるということはできない。それがもし可能とすれば、現実の具体的な生活は抜け殻のようになりイメージやイデオロギーのみが生き生きした現実味を持つという転倒した内面世界、すなわち精神の病を生きている場合だけである。
したがって、誰もがいくつもの顔を持っているわけだが、普通の生活者の顔をして歩いている時の村上春樹が作家としての村上春樹として呼びかけられて当惑したりふしぎな気持ちになるのはわかるような気がする。これに関連して思い出すのが、何の作品でもいいけど、例えばアニメの作品「君の名は。」で主人公が過ごした駅や図書館などの土地を訪れることをファンの間では「聖地巡礼」といって流行っているらしい。また以前には、韓国のドラマの「ロケ地巡り・聖地巡礼」というのもあった。別にそんな風な楽しみ方を否定する気はないが、わたしや上記のような村上春樹の感覚からすれば、こうしたことは作品にとってはほとんど意味はないということになるだろう。このような「聖地巡礼」もイメージの同一化の意識から来ているように思う。
ところで、わたしたちが家族などの身近な生活世界を中心に生きるという生存の自然基底からすれば、社会や政治の問題はどうでもいい問題としてある。ただ、社会や政治の有り様がわたしたちの生活世界に利をもたらすことは少なくより多く規制したり干渉したり不利益をもたらしたりする歴史の中に依然としてわたしたちはいる。つまり、行政や政治が生活者の利益のためにのみあるという本来的な意味を生きるなら、わたしたちはさらにのんびりと「鼓腹撃壌」(こふくげきじょう)を生きることができるはずである。
わが国で現在でもしばしば否定的に取り上げられる「政治的無関心」という問題についてひと言。まず、わたしは半ば以上はそのことに肯定的である。国家以前の遙か太古の、上と下があんまり格差がなく割と平等な集落社会では、上の方というか担当が、宗教的な行事や経済的な分配などの行政的なものも割とうまくやっていて、別にそれらのことに文句を言う必要もない。自分が当番になればやればよいだけで、普通はあんまり関心を持たない。このような強固な集落性の時代(段階)が長くあったのではないかという気がする。このような意識性は、現在では町内会もいろんな問題を抱えているのかもしれないが、町内会の構造に保存されているように感じる。国家がこのような小さな集落の意識構造に乗っかって社会規模が大きくなり高度化してからも、そういう集落の強固な意識性からうまく接続したり展開することなく、現在まで来ているのではないかという気がする。明治近代以降、欧米からの大きな波をかぶってきた現在では、欧米からの模倣の滲透とは言え、個や社会や国家に対して割と分離した意識を持つ欧米の視線の影響を受けて、そこからの内省が社会レベルで働くようになってきている。要は一方からの啓蒙ではなく、それらの二つの視線がどう交差したらいいかという問題があるように思われる。