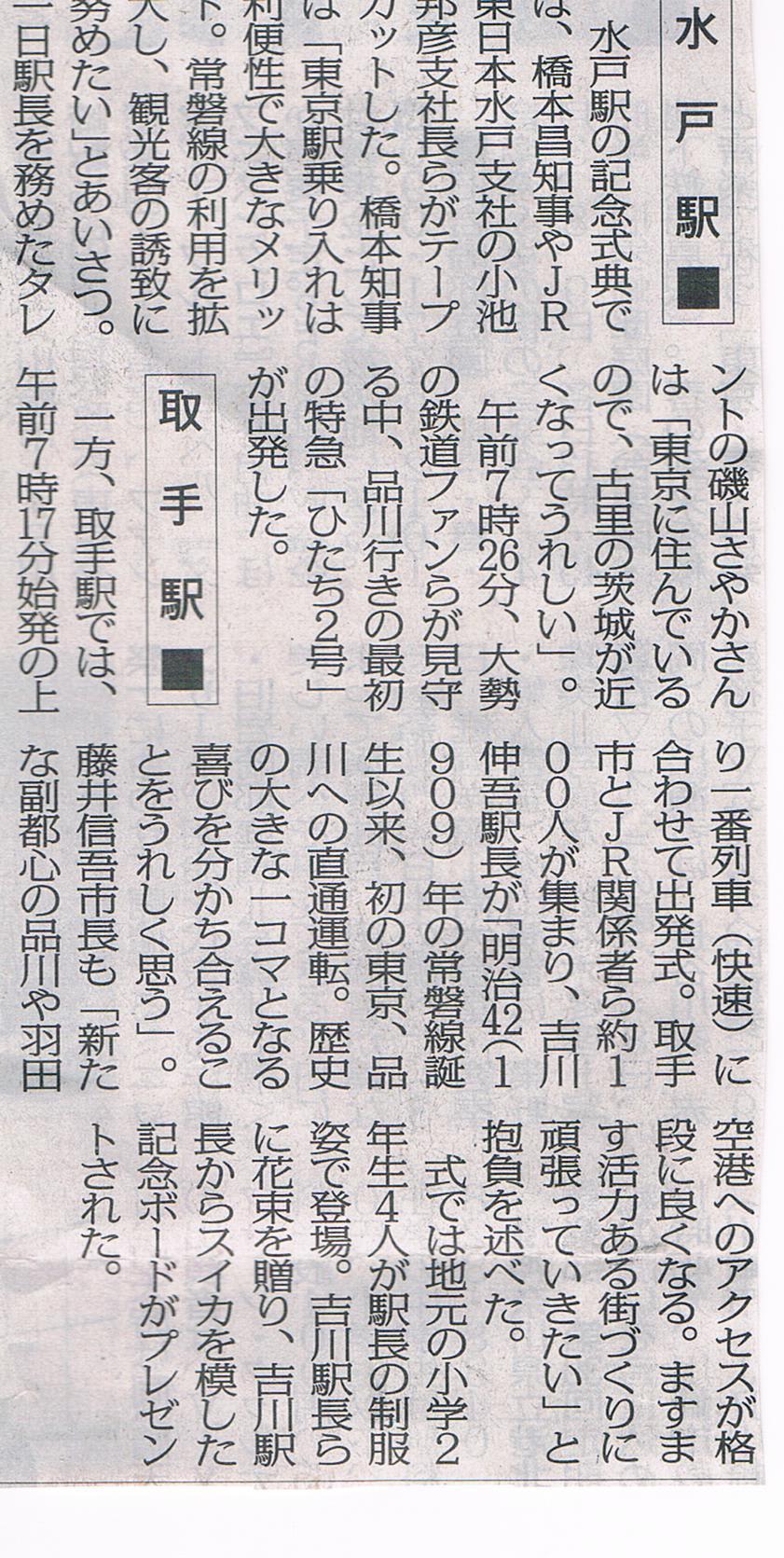金価格下落
2月12日 5140円→3月25日4997円

週報(3/16~3/20)
1120ドル近辺でスタートしたプラチナ相場は、18日に開かれたFOMCを控えて当初は、今後の金融引き締め策(利上げ)に向かう方針の提示があるとの見方や、それを後押しするように米工業関連指数が市場予想を上回った事などからドル高が進行。これを受けてプラチナ価格は軟調に推移し、週央には一時2009年以来の1100ドル割れとなり一時1090ドル近辺まで下落しました。しかし、この水準ではアジア圏を中心に現物需要が強まったほか、19日のFOMC後の声明で景気認識の下方修正から当初の期待ほど利上げを急いでいないとの見方が強まると、週初の水準に急反発。その後も引き続き底堅い現物需要が後押しする展開に1140ドル近辺で越週しました。
1155ドル近辺でスタートした金相場は週央に控えたFOMCでの利上げ期待感から進むドル高を受けて上値の重い展開となりました。直前には一時昨年6月につけた1140ドルの安値に迫る水準まで下落したものの、その後のFOMC後の声明の中で市場が極端に注目していた「Patient(辛抱強く)」との表現が削除されたものの、同時公表の金利見通しやGDP見通しの引き下げにより、過剰に期待感が膨らんでいた利上げへの期待感が縮小すると、対主要通貨に対してドルが急落。金相場にもドル安の動きが波及する形で1170ドル近辺に急騰しました。その後は週末にかけて市場は落ち着きを取り戻していく流れとなるも、これまで軟調を継続していただけに買い戻しの流れや、引き続き安値拾いの買いなどから値を戻す展開は継続し1180ドル近辺で越週しました。
15.5ドル近辺でスタートした先週の銀相場は他貴金属が週央にかけて下落する中で、このレベルは昨年末に底値をとして確認していたレベルであったこともあり実需筋の買い意欲も強く、底堅い展開となりました。その後、FOMC後の声明を受けてドル安が進み、他貴金属が上昇すると銀相場も追随する展開となり16ドル台に急騰。その後は金相場に比較しての値ごろ感も意識され、週末には一段高となり16.75ドル近辺で越週しました。
121.5円近辺でスタートした円相場は16-17日に行われた日銀の金融政策決定会合は特に意識されることなく、市場の注目は18日のFOMCに絞られる展開となりました。発表前までは特に目立った動き無く推移するも、FOMC後の声明から「Patient(辛抱強く)」との表現が削除されたものの、景気認識の引き下げや、利上げ時期に対して慎重な見解が示されると、急速なドル高進行に対する利益確定売りが進むこととなり、円相場は急騰。一時119.50円近辺まで円高が進みました。その後は市場の落ち着きと共に再び121円近辺に戻す展開となるも、週末にギリシャへの金融支援をめぐり追加融資の方針が合意され、同国の資金繰りに対する不安感が減退するとユーロが上昇。ドルが売られる展開に、円相場も追随する形となり120円近辺で越週しました。
2月12日 5140円→3月25日4997円

週報(3/16~3/20)
1120ドル近辺でスタートしたプラチナ相場は、18日に開かれたFOMCを控えて当初は、今後の金融引き締め策(利上げ)に向かう方針の提示があるとの見方や、それを後押しするように米工業関連指数が市場予想を上回った事などからドル高が進行。これを受けてプラチナ価格は軟調に推移し、週央には一時2009年以来の1100ドル割れとなり一時1090ドル近辺まで下落しました。しかし、この水準ではアジア圏を中心に現物需要が強まったほか、19日のFOMC後の声明で景気認識の下方修正から当初の期待ほど利上げを急いでいないとの見方が強まると、週初の水準に急反発。その後も引き続き底堅い現物需要が後押しする展開に1140ドル近辺で越週しました。
1155ドル近辺でスタートした金相場は週央に控えたFOMCでの利上げ期待感から進むドル高を受けて上値の重い展開となりました。直前には一時昨年6月につけた1140ドルの安値に迫る水準まで下落したものの、その後のFOMC後の声明の中で市場が極端に注目していた「Patient(辛抱強く)」との表現が削除されたものの、同時公表の金利見通しやGDP見通しの引き下げにより、過剰に期待感が膨らんでいた利上げへの期待感が縮小すると、対主要通貨に対してドルが急落。金相場にもドル安の動きが波及する形で1170ドル近辺に急騰しました。その後は週末にかけて市場は落ち着きを取り戻していく流れとなるも、これまで軟調を継続していただけに買い戻しの流れや、引き続き安値拾いの買いなどから値を戻す展開は継続し1180ドル近辺で越週しました。
15.5ドル近辺でスタートした先週の銀相場は他貴金属が週央にかけて下落する中で、このレベルは昨年末に底値をとして確認していたレベルであったこともあり実需筋の買い意欲も強く、底堅い展開となりました。その後、FOMC後の声明を受けてドル安が進み、他貴金属が上昇すると銀相場も追随する展開となり16ドル台に急騰。その後は金相場に比較しての値ごろ感も意識され、週末には一段高となり16.75ドル近辺で越週しました。
121.5円近辺でスタートした円相場は16-17日に行われた日銀の金融政策決定会合は特に意識されることなく、市場の注目は18日のFOMCに絞られる展開となりました。発表前までは特に目立った動き無く推移するも、FOMC後の声明から「Patient(辛抱強く)」との表現が削除されたものの、景気認識の引き下げや、利上げ時期に対して慎重な見解が示されると、急速なドル高進行に対する利益確定売りが進むこととなり、円相場は急騰。一時119.50円近辺まで円高が進みました。その後は市場の落ち着きと共に再び121円近辺に戻す展開となるも、週末にギリシャへの金融支援をめぐり追加融資の方針が合意され、同国の資金繰りに対する不安感が減退するとユーロが上昇。ドルが売られる展開に、円相場も追随する形となり120円近辺で越週しました。