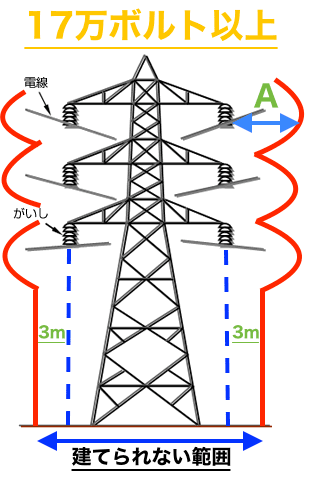このシリーズ、お家を「買う」というところばかり注目してましたので、今回は「借りる」をメインに解説してみます。
お家を借りる、アパートにしろマンションにしろ戸建にしろ、手続きが買う時より楽なのでフットワーク軽めで考えてらっしゃる方などは、賃貸を中心に考える方も多いかと。
メリットデメリットは前回のブログで解説してます。
借りる場合については賃貸借契約書の内容が多くを占めます。」
まず契約内容をみて本物件が契約物件と同じかどうかを確認。
特に設備についてはよく確認しましょう、
大家さんが設置したものは「有り」になってまして、大家さんの修繕義務になるものもありますが、前の入居者の残置物もありますので…
お部屋を見学した際に室内にあった設備が「設備」もしくは「残置物」であるのかを確認しておきましょう。
残置物で多いものは、エアコン、ガスコンロ、照明器具などですね。
残置物は利用してもOKですが、故障は自己責任、また転居する場合は処分しなくてはなりません。
駐輪場、バイク置き場、宅配ボックスなど共用施設の有無も確認しておく必要があります。
また、お金がらみの話ですが…以下の事項はもちろん注意。
- 賃料
- 駐輪場など付属施設の使用料
- 契約期間
- 支払方法
- 支払い先
特に支払方法、期間、支払先は、
「4月末に4月分を振込」
「4月末に五月分の前払いを振込」か
によって扱いが異なります(特に退去の日)
また、締め日、家賃自動引落の利用可否などを確認しましょう。
賃貸借契約書の契約は基本的に賃貸借契約の期間は2年契約で、2年ごとに更新する必要となります。その際に更新料や手数料がかかる場合もあるため、契約時にしっかりと確認しておきましょう。
さらに以下はトラブルになりがちなので注意しましょう。
- 町内会費
- ケーブルテレビ代
- インターネット代
- 使用した分を家賃と一緒に請求される水道代
- 使用した分を家賃と一緒に請求される電気代
家賃(または共益費)に含まれるか、それとも別添で支払うのか、電気代、水道代は毎月か二カ月ごとかについても、地域の実情に合わせてることが多いので注意です。
インターネット、ケーブルテレビは無料!って広告に書いてますが実は共益費にオンされてましたって、話はよく聞きます。内容を確認しましょう。
貸主・管理会社はいざって時にどこに連絡すれば良いか記載しています。
出来れば、契約書記載の連絡先とは別に夜間休日の連絡先も教えてもらいましょう。
以下のようなアクシデントやトラブルなどの際にはどこに連絡をしたら良いのかを確認しておきましょう。
- エアコンが故障したなど、設備トラブルがあった場合
- 上の部屋の入居者が夜中にうるさいので注意してもらいたい場合
- 契約を更新・解約したい場合
借主・同居人
借主、同居人、(借主の)緊急連絡先の名前・年齢・電話番号などが記載されています。
連帯保証人または保証会社
いわゆる保証会社の所在地と電話番号が記載されています。また、保証会社ではなく連帯保証人が記載されるケースもあります。これも地域の実情によりますね。
特約条文
条文における各項目の注意点は以下の通りです。
- 更新:更新料の他に更新事務手数料が別途かかる場合があります。
- 解約について:解約通告期間。一般的には30日前(1ヶ月前)ですが、中には40日前や2ヶ月前通告という物件もあります。
- 違約金:解約時の違約金等があるかなど、違約金の有無や発生する場合の条件などを確認しましょう。
- 禁止事項:ペットの飼育について、楽器の演奏について、石油ストーブの使用などです。違反した場合は退去を求められることもありますので事前にしっかりと確認をしておきましょう。
- 特約:個別の取り決めなどは後になってトラブルにならない様に必ず特約に入れておきましょう。
原状回復について
退去時の原状回復に関する費用(修繕費)の負担について記載してあります。
国土交通省が定めたガイドラインがありますので事前によく読み、原状回復と敷金返還に関する特約が不利な内容になっていないか確認をしておくと良いです。
以上が大まかな留意点となります、
特にトラブルになりそうなのが
設備
賃料以外の支払い
原状回復
が大きなところかと思います。
契約の前に重要事項説明も行われますので、どんな細かい点でも不明な点は担当の宅建士の方にお聞きしましょう。