外房菜園での趣味のさつま芋作りですが、先年に先立たれた妻の姿が思い出されるのが辛くて、此処3年程、さつま芋を植えるのを控えて来ました。
ところが、今春、偶々通り掛った現地の野菜産直店で 「紅はるか」の苗が売り出されているのを見つけ、50本一束を小分けしても結構ですよと言われ、久し振りにさつま芋の苗を15本を植え付けました。
先日、その「紅はるか」を堀上げて東京に持ち帰ったのですが、其の巨大化した姿、尋常の大きさでは無かったので、たかがさつま芋ではありますが、其の姿一部を一寸披露させて頂きます。

―菜園で堀上げた「紅あずま」の株を下げて見せる元気な頃の妻―
その関東ではお馴染みの品種 「紅あずま」に替わって、紛らわしい名称で登場してきたのが、九州沖縄農研さつま芋育種チーム農研作出し、2009年に品種登録された 「紅はるか」であります。
其の品種の背景と開発のねらいは、食用カンショの主力品種 「高系14号」は、早期肥大性で安定した収量性を示すが、サツマイモネコブセンチュウに弱く、栽培条件によっては形状の乱れや丸いもの発生などがみられ、食味は中程度で、特に早掘から標準掘にかけて甘みが強くおいしい品種を望む声が市場や生産者等から寄せられて居たと言い、こうしたことから、「食味が優れ、線虫抵抗性をもち、皮色や形状など、芋の外観が優れた食用品種を育成すること」にあったとあります。
其の特徴は、外観が優れる「九州121号」を母、皮色や食味が優れる「春こがね」を父として交配し、適用選抜した系統であり、蒸しいもの糖度(Brix%)は、「高系14号」より高く、甘みが強くておいしいと言う。
サツマイモネコブセンチュウ抵抗性が強いと言うことは、確かに外皮に傷が無く、見た目の美しい商品価値が上がりそうなさつま芋と言えそうです。
何しろ昨今は、さつま芋と言えども野菜の中では店頭に並んでも、一本売りされる程高級品化されてしまい、其れに貯蔵法も進歩して、年間を通じて市場に出回るようになった事もあり、出来秋の収穫食材として消費者が豊富に購入し、盛んに食する事も、返って少なくなりました。
その結果、大きさや形の不揃い品は流通市場では、商品価値が低くなって卸し値低下に繋がると大方の生産者は、規格品以外は自家消費用に供したりして、残れば廃棄するようになり、今日では、それが多くの一般野菜生産者の実態であり、さつま芋もその類になっているかも知れません。
そのさつま芋といえば、寒い冬の定番のスナックともいえる自家製の焼き芋作りであり、先年に購入した石焼専用鍋で、その高価な市販のさつま芋を、毎年利用しては焼き芋を作って来ました。
それも亡き妻の三周忌も既に過ぎ、想い返される心の痛みもいつしか薄らいで、そのさつま芋の自家供給用にと作る気になった「紅はるか」、其の大部分の余りにも肥大した太り様、とても石焼芋専用鍋には収まらない巨大さであり、一体どこに原因があったのか考えさせられて、芋堀りしながら行きついた結論を敢えて申す事にしたのです。

ー選り分けて小ぶりな芋だけを持ち帰った「紅はるか」ー
先ず言わせてもらいますが、こんな巨大化した「紅はるか」、今や生産者から見れば、全てが廃棄処分対象であり、隣家の方に2ヶずつ、「紅はるか」ですと言って差し上げて見たのですが、特に喜ばれる事も当然ですが、ありませんでした。
しかし、一般に旺盛に育った作物は、其の適時に収穫すれば栄養成分から見ては劣る事は無いのです。一方、今の市場流通の野菜類は、どれもこれも諸般の都合で、規格寸法通りの見た目の良さが最優先されるのであり、其の味の良さ、栄養成分的な評価等、外からは判断できないのを良いことに、ややもすれば、本来の野菜では無いような不味い品物が出回って仕舞う事も起こり得るのです。
其の点では、今般の巨大な「紅はるか」、味の方は食べては確かであり、唯余りにも巨大ゆえ、正月料理の「栗きんとん」作りの素材には、あく取りの厚むきも容易である上に、筋取りのうら漉しも省けそうであり、これならば、きんとん素材の長期冷蔵貯蔵も可能かと目下思案中であります。

―最大品は 全長40cm 重量約3.2kgの巨大紅はるかです!ー
扨て、肝心の 「紅はるか」の巨大化した理由、玉ネギ栽培の後作では、全くの無肥料での植え付けであっても残留肥料分の豊富さが、先ず最大の要因と言えますが、はっきり分かった其の理由は、当菜園の有機栽培土壌に多く棲みつく土壌中の幼昆虫類やミミズにあり、其れ等を盛んに求めて襲い回っている大食漢の 「モグラ」の仕業でありました。
掘って見ると巨大化している芋の周囲には、どの株にも、しっかり「モグラ」の通路が形成されて残って居り、本来なら株元から、何本に分かれて伸長肥大する筈の根茎が、1~2本しか無く、多くても3本と極端に少ないのです。
これでは、根茎に貯蔵される栄養分の分散が、偏って肥大化している仕舞い、吸収できる水分量も制限され、肥大化と共に芋の表面に大きくひび割れが生じて仕舞っています。
其のモグラ、関東地方ではアズマモグラと呼ばれる日本固有種の獣類であり、当外房菜園は、わずか50坪の広さではありますが、其の周り芝生部分と共に点々とモグラ塚を作り、菜園内一面にもしっかり棲みついて、普段は留守の為に、我がもの顔で移動しまくっているのです。

―日本固有種の獣類のあずまモグラーWikipediaより
当初は、其のモグラに業を煮やして退治しようと、色々と策を試みたのですがことごとく無駄に終わり、今では毎々年、其の度に盛り上がったモグラ塚を引きならしては、芝生の芽土替わりに利用する程度にしています。唯、悩みの種は、其の土に含まれて地上に出てくる古い雑草の種であり、毎年発芽して芝生中に生え、それが一面に広がる事であります。

―食料が減る季節に成ると芝面に増えだすモグラ塚-
考えて見れば、こちらが彼らにとっては後からの侵入者であり、大食漢の彼らが生き延びられる程度の食糧が、大きな問題も無く現状で確保されているのであり、絶滅危惧種とも言われ、共存するのが当然の事と思って認容しています。
扨て、こちら側は、モグラの為に太り過ぎで収穫した「紅はるか」、次は石焼芋鍋に収まるように程良く縦割りし、新しい形状の焼き芋作りに挑戦するのも一策になるかも知れません。
![]()



















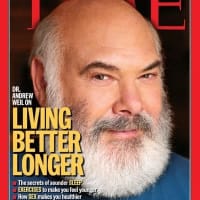


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます