
(BLOGOSより引用。)
マスコミからの情報だけで政治論議をしても床屋政談になってしまうから、この欄では政治の話はしないようにしている。だが、このたびの「集団的自衛権問題」について日本語として語義矛盾があるので、その点だけ表明しておきたい。
報道では歴代内閣は「集団的自衛権は保有しているが行使できない」と表明してきたらしい。歴代内閣はなぜそのように表明してきたのか、その背景が語られないので背景を知りたい。
権利とは必ず行使できるものであって、(有権者が選挙を棄権するように)「行使しない」とは言えても、「行使できない」とは言えない。そもそも「行使できない」ものを権利とは呼ばない。「行使できない」とはまさに「権利がない」というのと同義である。このように、まともな日本語ではない主張を、歴代内閣がせざるを得なかったその理由を知りたい。












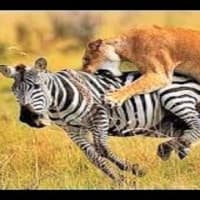






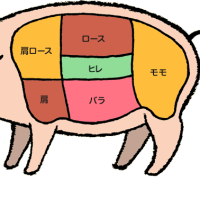
「集団的自衛権は違憲」とする憲法学者のうち、個別的自衛権合憲論者はこういうケースについては合憲であるとしています。
つまり、国連憲章に基づき集団的自衛権を保有するとしても、それは日本国憲法により制約を受けるが、まるっきり行使できないわけではない。ただ、その行使出来ない部分こそ、一般的には集団的自衛権として理解されているものである。そういう事情を「保有しているが行使できない」と表現した、所謂霞ヶ関文学でしょう。
ある権利の行使が、他の権利との競合その他の理由で一定の制約を受けるのは珍しくなく、権利がある事とその権利を行使できない場合がある事は矛盾しません。
「権利」という用語には法律用語としては、必ずしも行使できないこともある、という含意がすでにあるのですね。行使できてこその権利だという日常的な意味に理解してはいけないのですね。専門的なことを教えてくださり、ありがとうございました。