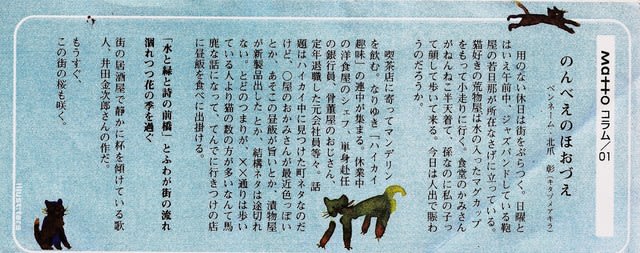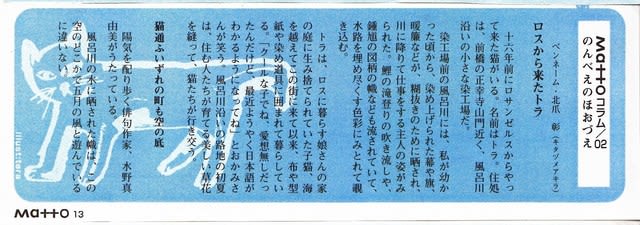これは、1921年(大正10年の)の前橋市街地全図の一部、市街地の中心部です。右上、中川小学校の上のところ、十六本堰で広瀬川が端気川と別れ北東へ向かって行く北側に『字石取河原』と表示されている辺りが今私が暮らしているところなんです。当時は、田畑と荒れ地が広がる田舎だったんです。
この地図は前橋市立図書館の資料室で複写してもらってきたものです。
今朝は寒いです。外は-1℃を下回っています。玄関先の水鉢も凍りついています。寒いのでちぃずを眺めているんです。
 昨日の朝食後のことなんです。電線にとまったスズメが空を見上げて啼いてます。スズメの後ろの東の空はしっかり晴れて冷たい風が吹き抜けていました。
昨日の朝食後のことなんです。電線にとまったスズメが空を見上げて啼いてます。スズメの後ろの東の空はしっかり晴れて冷たい風が吹き抜けていました。
 でも、スズメの目線の先の西から南の空は、暑い雲が北西から南西に向かって流れています。信州の山を越えてきた雪雲の切れ端です。
でも、スズメの目線の先の西から南の空は、暑い雲が北西から南西に向かって流れています。信州の山を越えてきた雪雲の切れ端です。
「白いもんが舞ってるよ!」ってユキ子さんが言うんで外に出てみたんです。寒かったです。
 ほんの少しなのですが白いもんが飛んでいました。セーターの袖に小さな氷の粒みたいのが引っ付きました。雪が飛んできてたんです。
ほんの少しなのですが白いもんが飛んでいました。セーターの袖に小さな氷の粒みたいのが引っ付きました。雪が飛んできてたんです。
 寒いので家に逃げ込んで、昨日夕食つくりながら煮込んでいた牛筋に焼き大根を加えてスジ大根を仕上げることにしました。煮ものをしていると温かいですし、試食するときはもっと温かくなります。
寒いので家に逃げ込んで、昨日夕食つくりながら煮込んでいた牛筋に焼き大根を加えてスジ大根を仕上げることにしました。煮ものをしていると温かいですし、試食するときはもっと温かくなります。
 で、なんで地図を眺めていたのかっていうと、少し昔のことを思い出していたんです。ついでといっちゃなんですけど、面白いことも思い出しました。
で、なんで地図を眺めていたのかっていうと、少し昔のことを思い出していたんです。ついでといっちゃなんですけど、面白いことも思い出しました。
写真は、群馬県庁舎のすぐ南の路地です。私が県庁に入ったころにはこの右側に酒屋がありました。更に昔、私の父が県教委で仕事していたころ、私は小学校低学年でしたけど、この酒屋は『居飲屋』をしてたんです。料理を提供しない立ち飲みの飲み屋です。仕事仲間と話をしながら酒を飲む父の足元で三角のセロハン袋に入った塩豆をかじっていた記憶があります。
 もう一本南の路地には『石川亭』というホルモン焼屋がありました。「おい、早く行って席とっときな!」、先輩の一声で仕事を早めに切り上げて飛んでった店です。今はもうありません。
もう一本南の路地には『石川亭』というホルモン焼屋がありました。「おい、早く行って席とっときな!」、先輩の一声で仕事を早めに切り上げて飛んでった店です。今はもうありません。
今の県庁舎は1999年にできたものです。その県庁舎を造る計画が検討されていたころの、県議会での面白い記憶です。私の好みのすこぶる庶民的だったK議員が委員会だったと思うのですがこんな趣旨の発言をしたんです。
「新庁舎を造るときに、県庁南の『食い詰め横丁』あたりもちゃんと整備した方が良い」という意見を述べたのです。賢い県庁の幹部は「前橋市と協議して検討いたします」とかなんとか答えていたのではないかと思うんですが、こちらは記憶にありません。県庁の南側のあたりがなぜか『食い詰め横丁』って呼ばれていたんです。
地図見ていて、このこと思い出したんです。それで、今日の前橋の路地は、この『食い詰め横丁』の幻想に迫りたいと思います。




前橋の路地 第27回 幻想の『食い詰め横丁』
 現在の県庁の南側一帯は、格子状のちゃんとした街路がめぐり、立派な住宅や小さな事務所が混ざり合っている地区である。住む人のいなくなったところは駐車場となっているところが多い。『食い詰め横丁』呼ばれるようなイメージは全くない。
現在の県庁の南側一帯は、格子状のちゃんとした街路がめぐり、立派な住宅や小さな事務所が混ざり合っている地区である。住む人のいなくなったところは駐車場となっているところが多い。『食い詰め横丁』呼ばれるようなイメージは全くない。
K議員が意見を述べた当時の県議会でも、他の議員から「『食い詰め横丁』などと呼ぶのは住民の皆さんに失礼である!」という批判が出て、「他意はない、申し訳なかった」と、庶民派のK議員は直ぐに謝ったと記憶している。失礼かどうかは別として、確かにこのあたりを多くの人たちが『食い詰め横丁』と呼んでいたのは事実である。
 この辺りが『食い詰め横丁』と呼ばれていたことを知っている人は今でもそれなりにいる。しかし、何故そう呼ばれていたのかを分かっている人は全くといってよいほどいない。私もその一人であった。
この辺りが『食い詰め横丁』と呼ばれていたことを知っている人は今でもそれなりにいる。しかし、何故そう呼ばれていたのかを分かっている人は全くといってよいほどいない。私もその一人であった。
しかし長生きしていると面白いものを見つける。佐藤垢石が1946年(昭和21年)に書いた『烏惠壽毛』という随筆にこの『食い詰め横丁』が登場しているのだ。『烏惠壽毛』は「うえすけ」と読むらしいが、調べているのだけれど未だに意味がよく分からない。
佐藤垢石という人は、1888年(明治21年)に現在の前橋市上新田町で生まれた人である。賢い少年だったらしく、前橋中学に進む。だが、中学でストライキを首謀して中途退学を余儀なくされた。その後、報知新聞(現読売新聞)の記者となり、前橋支局長も務めたが、なぜか途中で新聞記者を辞め、随筆家、釣り雑誌編集者として名を馳せることになる。私が子どもの頃にはNHKラジオの『二十の扉』とか『話の泉』にも出演していた。今風に言えば糸井重里さんみたいなマルチタレントだったのだ。
 これは、明治時代の県庁舎である。垢石が前橋中学に通っていたのは明治30年代後半のことであるからこの写真の県庁舎だったはずだ。
これは、明治時代の県庁舎である。垢石が前橋中学に通っていたのは明治30年代後半のことであるからこの写真の県庁舎だったはずだ。
垢石は、『烏惠壽毛』で、敗戦直後の極貧の生活を、前橋中学の時に見た『食い詰め横丁』の記憶とを比べている。その一部を引用する。
昔、故郷の前橋中学へ通うころ、学校の近くに食詰横町というのがあった。五十戸ばかり、零落の身の僅かに雨露をしのぐに足るだけの、哀れなる長屋である。
住人は、窮してくると、天井から雨戸障子まで焚いてしまう類であったから、一間しかない座敷のなかの、貧しい一家団欒の様(さま)がむきだしだ。そこで、現在の戦災後の壕舎生活と、この食詰横町の生活と、いずれが凌ぎよかろうかと、むかし学生時代に眺めた風景を想い出して比べてみると、地表に住んで直接日光の恵みに浴するとはいえ、横穴の貉(むじな)生活の方が、戸締まりがあって寒風が吹き込んでこないだけ結構であろう。
ところで、われわれ学生は、食詰横町を通るたびに、
おいおいお前、試験のときカンニングはやめよ。
と、連れの学友にからかうのである。
嘘つけ、僕なんぞカンニングはやらないよ。やったのは君だろう。
白々(しらじら)しいや。この間も、僕の見ているところでやってたじゃないか。
あの時、ただの一度さ、はじめのおわりだ。
それならいいが、カンニングが癖になって世の中へ出てからも、カンニングをやるとひどいことになるぞ。
どんなことになる。
この食詰横町に住んでいる人物は、すべてカンニング崩れなんだ。社会生活にカンニングを用いれば、誰でもこの横町へ這い込まにゃならんよ。
こんな冗談を言い合って、笑ったものだ。
さて、私の場合であるが、私は世の中へ出てから、別段カンニングをやった覚えはなし、人の物をちょろまかした記憶もない。
だのに、食い詰めて、せっぱ詰まった。

これは明治41年の前橋市の市街地の地図である。垢石が前橋中学へ通っていたころとあまり変わりないと思う。利根川には利根橋と鉄道橋が架けられている。垢石は上新田からこの橋を渡って中学へ通っていたのだ。利根橋を渡るとすぐに長昌寺、その北が前橋中学校である。東には龍海院、南曲輪町の家並を抜けた北には県庁がある。

 1877年に開設された前橋中学校は、1888年から1933年に天川原町へ移転するまでの間この地にあった。現在の中央総合病院あたりだ。病院の前の通りからは、東に龍海院の本堂の屋根と木立が見える。
1877年に開設された前橋中学校は、1888年から1933年に天川原町へ移転するまでの間この地にあった。現在の中央総合病院あたりだ。病院の前の通りからは、東に龍海院の本堂の屋根と木立が見える。
垢石が見た『食い詰め横丁』は、前橋中学校と県庁の間にあったと思われる。その一帯は、戦後、区画整理が行われ、群馬大橋の架橋に伴って国道17号の新道が拓かれ、大きく変わってしまってっているのだ。

 前橋中央病院と長昌寺の間には、まだ、過日の面影を残している路地がある。しかし、垢石が見たような長屋はない。
前橋中央病院と長昌寺の間には、まだ、過日の面影を残している路地がある。しかし、垢石が見たような長屋はない。
『食い詰め横丁』の幻を見ることはもうできない。あったのかなかったのかも幻想の彼方だ。



前橋の路地 第27回 おしまい
≪注≫ 佐藤垢石についての追記
 垢石という人はこんな顔をしていたらしいのです。声はラジオで聞いていたけれど、顔を見たことはありません。垢石が報知新聞の支局長を辞した後、後任の支局長が支局の金庫を開けて見たらその中は空っぽだったという逸話は聞いたことがあります。みんな酒と女に使い果たして辞めたんだって、本当かな…
垢石という人はこんな顔をしていたらしいのです。声はラジオで聞いていたけれど、顔を見たことはありません。垢石が報知新聞の支局長を辞した後、後任の支局長が支局の金庫を開けて見たらその中は空っぽだったという逸話は聞いたことがあります。みんな酒と女に使い果たして辞めたんだって、本当かな…
 <あんね、おヒゲはさ、この逸話を聞いてからってもの、垢石さんにずっとずっと羨望と憧れを抱き続けてきたらしいんですよ、キキ、さんざん聞かされてたんだから>
<あんね、おヒゲはさ、この逸話を聞いてからってもの、垢石さんにずっとずっと羨望と憧れを抱き続けてきたらしいんですよ、キキ、さんざん聞かされてたんだから>

 利根川岸にある雷電神社を訪ねると、境内に垢石の記念碑が建てられていて、その碑に垢石の顔が刻まれています。
利根川岸にある雷電神社を訪ねると、境内に垢石の記念碑が建てられていて、その碑に垢石の顔が刻まれています。
なお、『烏惠壽毛』を読まれたい方は、青空文庫のコチラで読むことができます。
 一日中風が吹き続けていました。木の枝にとまっているスズメもみんな風上に顔を向けていました。
一日中風が吹き続けていました。木の枝にとまっているスズメもみんな風上に顔を向けていました。

 夕方買い物に出たら、上毛電鉄の線路の向こうの雲の端が光ってました。
夕方買い物に出たら、上毛電鉄の線路の向こうの雲の端が光ってました。

 夕日を浴びた赤城山です。きれいです。ユキ子さんはご用で外食になりました。それで、私一人の夕食になりました。
夕日を浴びた赤城山です。きれいです。ユキ子さんはご用で外食になりました。それで、私一人の夕食になりました。
 これは昼食、ぜいたくなんです。下仁田ネギのカレー汁のつけ麺です。うどんは石田製麺の本うどんです。甘い下仁田ネギはカレーにも良くあいます。
これは昼食、ぜいたくなんです。下仁田ネギのカレー汁のつけ麺です。うどんは石田製麺の本うどんです。甘い下仁田ネギはカレーにも良くあいます。

 コチラは晩酌の肴、下仁田ネギのチーズ焼きと会津見知らずと東毛酪連のエダムチーズのさらだです。下仁田ネギには神津牧場のゴーダチーズを使いました。
コチラは晩酌の肴、下仁田ネギのチーズ焼きと会津見知らずと東毛酪連のエダムチーズのさらだです。下仁田ネギには神津牧場のゴーダチーズを使いました。
下仁田ネギ料理の第4日はこの二品でした。
 直派若柳流の若柳糸駒ことユキ子でございます。
直派若柳流の若柳糸駒ことユキ子でございます。
祖母の初代若柳吉駒、そして伯母の二代目吉駒の下で修業して参りました。
初代吉駒が始めた美登利会は、来春で75回目の節目を迎えます。予定通り、4月8日に開催いたします。
亡くなりました二代目吉駒の遺志と教えをしっかり守って、一生懸命つとめてまいりますので、これからも引き続きよろしくお引き立ていただきますようお願い申し上げます。
今春の第74回美登利会の舞台の様子はコチラでご覧になれますす。
お稽古場は前橋市城東町四丁目です。詳しくはコチラをご覧ください。
 ←クリックしてください。日本ブログ村の関東地域情報に登録してます。応援してください。
←クリックしてください。日本ブログ村の関東地域情報に登録してます。応援してください。
 昨日は冬至、もうちょっとで年が暮れるんですね。身の回りに大きな変化のあった一年でした。静かに暮れてほしいです。
昨日は冬至、もうちょっとで年が暮れるんですね。身の回りに大きな変化のあった一年でした。静かに暮れてほしいです。
 なんてまっとうなこと思いながら、まちで用足しして、昼食は呑竜のヤギカフェ、溶けたチーズが載ってるドライカレーを食べました。サラダに二種の大根、おいしかったです。
なんてまっとうなこと思いながら、まちで用足しして、昼食は呑竜のヤギカフェ、溶けたチーズが載ってるドライカレーを食べました。サラダに二種の大根、おいしかったです。 そうそう、前橋の暮れといえばこの菓子です。本町通りのさくらホテルの向かいにある菓子舗『青柳本店』で年末から初市までの間だけ製造販売している期間限定のおこしなのです。すごく懐かしいし、素朴なおいしさのある菓子なんです。この機を逃さずにお試しください。
そうそう、前橋の暮れといえばこの菓子です。本町通りのさくらホテルの向かいにある菓子舗『青柳本店』で年末から初市までの間だけ製造販売している期間限定のおこしなのです。すごく懐かしいし、素朴なおいしさのある菓子なんです。この機を逃さずにお試しください。 午後、陽が傾くのを待ってまた出かけました。今日の前橋の路地は夕暮れが似合う路地ですから。前橋の路地第28回は『縁切り坂』です。
午後、陽が傾くのを待ってまた出かけました。今日の前橋の路地は夕暮れが似合う路地ですから。前橋の路地第28回は『縁切り坂』です。 本町通りにある東和銀行本店、冬の傾いた日差しを浴びている。昨日は冬至、それに歳末ジャンボ宝くじの販売最終日、日暮れが早い。
本町通りにある東和銀行本店、冬の傾いた日差しを浴びている。昨日は冬至、それに歳末ジャンボ宝くじの販売最終日、日暮れが早い。
 東和銀行の東側に坂道がある。馬場川通りに下る坂道だ。銀行と不動産会社のビルに挟まれた道だから店も何もない。下りきった右側は旧榎町(現在は千代田町5丁目)である。
東和銀行の東側に坂道がある。馬場川通りに下る坂道だ。銀行と不動産会社のビルに挟まれた道だから店も何もない。下りきった右側は旧榎町(現在は千代田町5丁目)である。 坂を下ると馬場川が流れている。昔、この坂道の下に延命地蔵尊というお地蔵さんが祀られていたという。私が子どもの頃には、今はニコニコパーキングという有料駐車場になっている場所にあった政淳寺の境内に移されていた。このお地蔵さんの引っ越しは、地蔵を商店街近くに移せば参詣客が増えて、街中が繁昌するという榎町界隈の商店主たちの思惑からだったという。
坂を下ると馬場川が流れている。昔、この坂道の下に延命地蔵尊というお地蔵さんが祀られていたという。私が子どもの頃には、今はニコニコパーキングという有料駐車場になっている場所にあった政淳寺の境内に移されていた。このお地蔵さんの引っ越しは、地蔵を商店街近くに移せば参詣客が増えて、街中が繁昌するという榎町界隈の商店主たちの思惑からだったという。
 坂の下の右手、旧榎町のところに明聞寺があった。その明聞寺も今は富士見町小暮に移転している。右の写真が富士見町小暮にある現在の明聞寺の本堂である。
坂の下の右手、旧榎町のところに明聞寺があった。その明聞寺も今は富士見町小暮に移転している。右の写真が富士見町小暮にある現在の明聞寺の本堂である。

 坂下の先に続く道は、昔日は料亭や鮨屋、飲食店が並ぶ前橋で屈指の夜のまちの一つであった。私が子どもの頃に見た店は、今は全く姿を消している。
坂下の先に続く道は、昔日は料亭や鮨屋、飲食店が並ぶ前橋で屈指の夜のまちの一つであった。私が子どもの頃に見た店は、今は全く姿を消している。 下仁田ネギを食べ続けていたら、今度は立派な原木椎茸をいただきました。それで、椎茸料理を食べることになりました。
下仁田ネギを食べ続けていたら、今度は立派な原木椎茸をいただきました。それで、椎茸料理を食べることになりました。

 左から椎茸の肉詰めの照り焼き、とうふの椎茸餡かけ、焼椎茸の山かけ、以上三品をいただきました。
左から椎茸の肉詰めの照り焼き、とうふの椎茸餡かけ、焼椎茸の山かけ、以上三品をいただきました。 それから、こんなお酒を旅の土産にいただきました。富山の『三笑楽』の『あまし』です。あましってのは、仕込み水の一部に純米酒を使っている特別な酒です。良い香りです。肴は、岩神町の養田鮮魚店の自家製塩辛、いかの肝を塩漬けして熟成させてある本格的な塩からなんです。酒にぴったしです。
それから、こんなお酒を旅の土産にいただきました。富山の『三笑楽』の『あまし』です。あましってのは、仕込み水の一部に純米酒を使っている特別な酒です。良い香りです。肴は、岩神町の養田鮮魚店の自家製塩辛、いかの肝を塩漬けして熟成させてある本格的な塩からなんです。酒にぴったしです。 直派若柳流の若柳糸駒ことユキ子でございます。
直派若柳流の若柳糸駒ことユキ子でございます。![]() ←クリックしてください。日本ブログ村の関東地域情報に登録してます。応援してください。
←クリックしてください。日本ブログ村の関東地域情報に登録してます。応援してください。