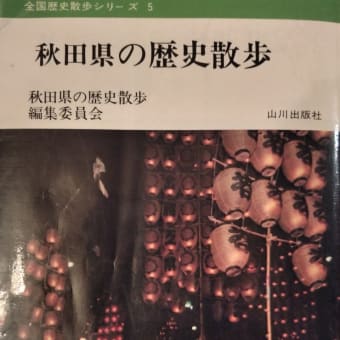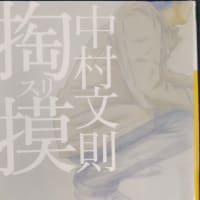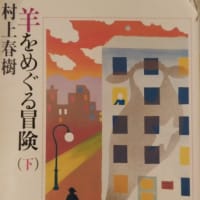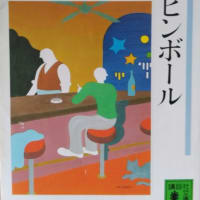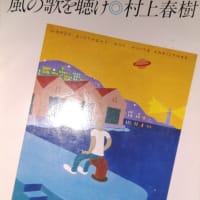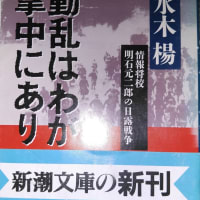ひさびさにブックオフで物色していたら、¥100になっていたので手に取った。
同じ内容なら軽くて小さいほうが良いと思って、文庫化されるものは文庫化を待ち、あわよくば¥100で入手しようという貧乏性なのである。特に急がない場合は大抵このスタンスだ。
先日『羊をめぐる冒険』を読んだので、21世紀版に翻案したものみたいに感じてしまった。物語の構成がなんとなく似ているのである。もちろん主人公の性質も。
ただ興味深いのは、当然のことながら、話に今様の小道具が頻出することだ。スタバとかフェイスブックとか。一方、語り手は空き家のような大きな家で、レコードを聴きながら、インターネットやスタバとは無縁な世界を生きている。
今様なものによって現代風に装いを新たにしているが、扱われる重要なコンテンツは古典的だ。そして、これまでの村上作品を読んだ体験から、私は話に熱中しつつも、幾分かは醒めた目で字面を追っている。
たとえば『1Q84』という小説が、オウム真理教紛いの邪教を扱って大河ドラマ風の伏線を張り巡らしながらも、それは回収もされず、振り返れば、恋愛小説を面白くスリリングにする演出に過ぎなかったと感じたときのように・・・
この小説の謎めいた雰囲気も、食欲をそそらせる香りや色彩の一つに過ぎず、神妙に読んでいたらずっこけてしまうのではと、やや距離を置いている。
それでも興味を引き付けてやまない筆力には感心し通しなのだが。
その筆力について、語り手の言葉を借りて説明するならば以下の一節が相応しいかもしれない。
「考えてみれば、それは他者を前にした自己の定義と通じるところがあるかもしれませんね。自明ではあるが、その自明性を言語化するのはむずかしい。あなたがおっしゃったように、それは『外圧と内圧によって結果的に生じた接面』として捉えるしかないものなのかもしれません」
そう、自己とはそれほど不確定なものなのかもしれないのだ。結果的に生じた接面・・・
外圧と内圧には様々なものがある。不快なもの、中には人を死に至らしめるものも。村上春樹の小説が読まれるのは、その筆力が、適度な外圧として読む者に届き、その接面になんらかの作用を与えるからだろう。
意味ありげなカルトも、物語の材料に過ぎなくて構わないのである。人は自分を知りたくて、小説を手にするのかもしれないのだから。