
『風の歌を聴け』(村上春樹 講談社文庫)
歴史やその他の教養系ばかり読んでいて、読書が進まなくなってきた。加藤周一も『読書術』で書いていたように、新鮮な気持ちで読書を継続するには、一度に複数の本を並行して読めば良い。気分転換になって、飽きがこないし、たぶんジャンルが違えば脳の使われる場所も異なり、一方を休めながら一方を活性化することができる。
というわけで、自室の本棚から選んだのが本書だった。深く考えたわけではないが、選択の条件は、
①純文学的な小説(それをどう定義付けるかは微妙な問題なので、初出の掲載誌で判断)
②軽く読めそうなもの、
③また読みたいと思えるもの。
①と③は大量に蔵書しているが、しかも②を兼ねるものは多くないのだろう。
実際、教養系の新書と交互に読むうち、1日で読了してしまった。
数年前に読んだ気がしていたが、当ブログで確認すると、15年ぶりだった。たぶん3回目である。
久々に読み始めての印象は、『これは純文学なのか?』というクエスチョン、そして『翻訳の文体みたいだな』である。後者は、村上春樹のデビュー時に少なくない評者が言ったことで、私はその予備知識を今回実地に確認した。
翻訳風の文体は、作風をも西欧風にして、結果として、リアリティーを失わせる。作り物感でいっぱいなのだ。
70年の安保改定に向けた闘争を経てきた若者たちの一部は、本書がリアリティーに欠けるのは知った上で、こうした飄々としたタッチの小説を求めていたのかもしれない。地に足のつかない作風ながら、本作は実は時代性を反映している。リスタートするために、或いは冷却するために。
という歴史的前提を踏まえずに読むと、本書はただの軽い文体で描かれた翻訳風のお上品な小説となってしまうだろう。
さて、今回は余計な予備知識のフィルターを通して読んでしまったが、『僕』と『鼠』の役割分担に初めて気づいた。前者は、学生として社会復帰していく者、後者は闘争の後ドロップアウトした者だ。
著者の周囲にもそういった2分類があったであろう。大学は続けながら自営業を始めたという著者は、そのどちらでもない立ち位置にいたのかもしれないが。
となると、この前期三部作の読み方も自ずと変わってくるかもしれない。
歴史やその他の教養系ばかり読んでいて、読書が進まなくなってきた。加藤周一も『読書術』で書いていたように、新鮮な気持ちで読書を継続するには、一度に複数の本を並行して読めば良い。気分転換になって、飽きがこないし、たぶんジャンルが違えば脳の使われる場所も異なり、一方を休めながら一方を活性化することができる。
というわけで、自室の本棚から選んだのが本書だった。深く考えたわけではないが、選択の条件は、
①純文学的な小説(それをどう定義付けるかは微妙な問題なので、初出の掲載誌で判断)
②軽く読めそうなもの、
③また読みたいと思えるもの。
①と③は大量に蔵書しているが、しかも②を兼ねるものは多くないのだろう。
実際、教養系の新書と交互に読むうち、1日で読了してしまった。
数年前に読んだ気がしていたが、当ブログで確認すると、15年ぶりだった。たぶん3回目である。
久々に読み始めての印象は、『これは純文学なのか?』というクエスチョン、そして『翻訳の文体みたいだな』である。後者は、村上春樹のデビュー時に少なくない評者が言ったことで、私はその予備知識を今回実地に確認した。
翻訳風の文体は、作風をも西欧風にして、結果として、リアリティーを失わせる。作り物感でいっぱいなのだ。
70年の安保改定に向けた闘争を経てきた若者たちの一部は、本書がリアリティーに欠けるのは知った上で、こうした飄々としたタッチの小説を求めていたのかもしれない。地に足のつかない作風ながら、本作は実は時代性を反映している。リスタートするために、或いは冷却するために。
という歴史的前提を踏まえずに読むと、本書はただの軽い文体で描かれた翻訳風のお上品な小説となってしまうだろう。
さて、今回は余計な予備知識のフィルターを通して読んでしまったが、『僕』と『鼠』の役割分担に初めて気づいた。前者は、学生として社会復帰していく者、後者は闘争の後ドロップアウトした者だ。
著者の周囲にもそういった2分類があったであろう。大学は続けながら自営業を始めたという著者は、そのどちらでもない立ち位置にいたのかもしれないが。
となると、この前期三部作の読み方も自ずと変わってくるかもしれない。










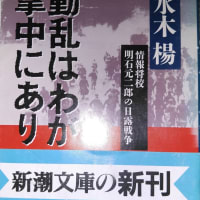





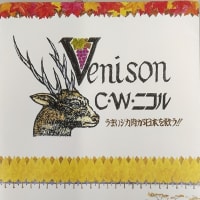

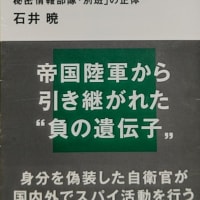

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます