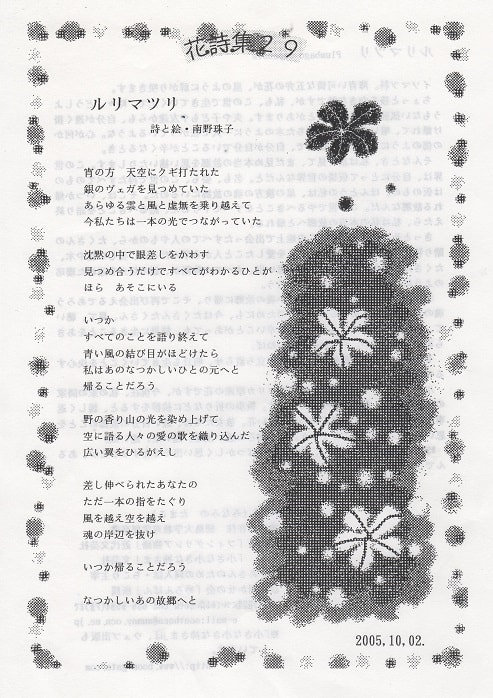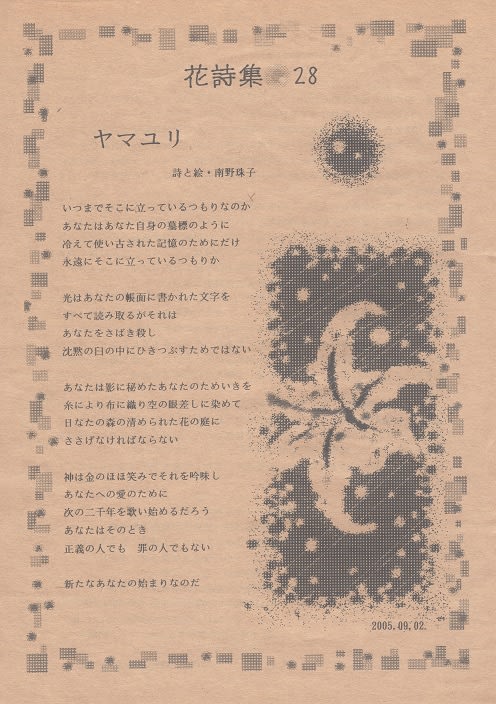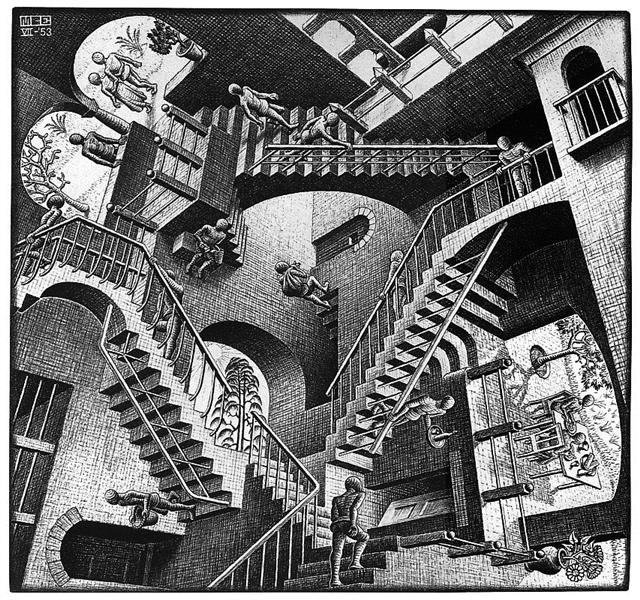ルリマツリ Plumbago capensis
イソマツ科。薄青い可憐な五弁の花が、星のように咲き群がります。
ちょと後ろ向きな詩ですが、私も、この世で生きて行く上で、時々、どうしようもない孤独に縛られることがあります。夫や子供や友だちからも、自分が遠くかけ離れて、暗い夜の底に、朽ちた木のように一人で転がっているような。心が何かの傷のように、ひりひり痛んで、自分が自分でいることがつらくなる時。
そんな時、私は星を見て、まだ見ぬ本当の故郷を思い描いたりしています。この世界は、自分にとって仮構の世界なんだと。名も、姿も、この世で得たすべてのものは仮のもの。ほんとうの私は、星の彼方の魂の故郷にいるのだ。そこは、いつか帰れる故郷なんだ。この世でやるべきことをすべてやり終え、語るべきことを語り終えたら、私は私の本当の故郷へと帰れる。
きっとその時、私は、この地上で出会ったすべての人やものから、たくさんの贈り物をたくされることだろう。人を愛したこと人から学んだこと、美しい花や木、たくさんの豊かな生き物や山河の思い出。全ての物語が、銀の灯火を連ねた瓔珞のように、私の手で燃えているだろう。
私はその贈り物をもって、いつか魂の故郷に帰り、そこで再び出会えるであろう魂の友達に見せてあげるんだ。そのためにも、今はたくさんたくさん、見て、聴いて、学んでおかねばならない。時に辛いことがあっても、簡単に生きることをあきらめてはならない。やらねば。語らねば。
そうやって私は、孤独になえた心を立ち直らせ、明日も生きて行くことを決心するのです。
ルリマツリ(プルンバゴ)は南アフリカ原産の花ですが、今現在、わたしの家の隣家の軒先の鉢で、たくさん咲いています。散歩の折りなどに挨拶をすると、親しく返事を返してくれます。星を思わせる青い花。彼女たちは、遠い自分の故郷のことを、思い出すことがあるんでしょうか。見も知らぬ遠い土地。遠い空。遠い風。
時には、孤独の夜の中で、その香りをなつかしく思い出そうとすることが、あるんでしょうか……
(2005年10月、花詩集29号)