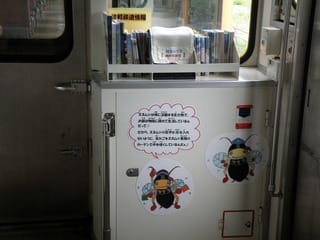老朽化した旧型車の置き換えと冷房化のために東京急行電鉄から7200系電車を
譲り受けたものである。
平成5年に2両編成×5本=10両が入線した。
製造年は昭和42年~43年で製造を担当したメーカーは東急車輛である。
■東急時代の概要
営団日比谷線の直通用に設計され、その規格を満たすために全車電動車方式で
製造された7000系の反省に立ち、東横線以外の高速走行を必要としない路線での
運用を考慮した経済性重視の車両として登場した。
昭和42年~43年、昭和47年にかけて53両が製造された。
メーカーは東急車輛。
構成形式は以下の通り。
デハ7200形(制御電動車。制御装置・空気圧縮機・電源装置付き)、
デハ7300形(中間電動車。制御装置搭載。補助機器は当初搭載せず)、
デハ7400形(中間電動車。制御装置・空気圧縮機・電源装置付き)、
クハ7500形(制御車)
当初は製造順に附番されたが、本形式製造途上の昭和42年12月より運転台や
制御装置などの機器のメーカーの違いを分かりやすくするため、改番を実施した。
これにより、日立製作所製の機器を持つ車両が下2桁0番台、東洋電機製の機器を
持つ車両が下2桁50番台となった。
これも7000系で機器の違いで性能が違ったため、運用を分けていたものの、
車両の番号を分けず現場の混乱を生んだことから取られた措置である。
しかし、本形式では全線で運用可能な車両とすることが前提となったため、
性能が統一されており、この改番はあまり意味を成していない。
車体はオールステンレス製(デハ7200号+クハ7500号のみアルミ合金製)で
正面は三つ折れでさらに中心の貫通扉両脇が「く」の字に折れた「ダイヤモンドカット」と
呼ばれる独自の形態をしている。
塗装はなく、ステンレス無地であったが、昭和63年以降赤帯を正面にのみ巻いた。
行き先表示は当初が正面のみ、後年は側面にも追加されている。
車内はロングシートで側面窓に初めて一段下降窓を採用。
ドアは両開きで片側3箇所である。
冷房は昭和47年に目蒲線・池上線用に投入されたデハ7260+デハ7452+クハ7560の3両が
新造時から、それ以外は昭和50年代後半に改造で装備している。
主制御装置は抵抗制御方式でブレーキは界磁制御器による回生ブレーキ併用
電磁直通ブレーキである。
なお、界磁制御器のスイッチを切ることで回生ブレーキをカットすることも
可能である。
台車は電動車が軸箱支持をペデスタル式としたダイレクトマウント式空気バネ台車、
制御車が防振ゴム支持で軸バネを持たないパイオニア式とした空気バネ台車である。
モーターの駆動方式は中空軸平行カルダン。
制御車の台車は乗り心地が悪かったことから、後年電動車と同じ構造のものに
交換したものがある。
東急では東横線をはじめ大井町線、田園都市線で運用され、その後、池上線、
目蒲線に活躍の場を移し、平成12年8月に事業用のデヤ7290形なったアルミ合金製の
2両と7600系に改造された9両を残して引退した。
■上田電鉄譲渡車の仕様
上田交通時代の平成4年にデハ7200形×5両、クハ7500形×5両の10両を譲り受けた。
新旧の車番変遷は以下の通り。なお、東急時代の改番は省略する。
上田:モハ7251+クハ7551←東急:デハ7257+クハ7551
上田:モハ7252+クハ7552←東急:デハ7252+クハ7557
上田:モハ7253+クハ7553←東急:デハ7253+クハ7553
上田:モハ7254+クハ7554←東急:デハ7254+クハ7511
上田:モハ7255+クハ7555←東急:デハ7258+クハ7558
譲渡にあたっての改造を担当したのは東急長津田車両工場である。
当初の改造内容は帯色の変更(前面のみ赤→正面~側面グリーンの濃淡)、
車番変更、回生ブレーキのカット、側面行き先表示の撤去と正面方向幕の手動化
程度である。
車番を見て分かるとおり、電動車の機器は全て東洋電機製のもので揃えられているが、
クハ7554号車のみ日立製作所の機器となっている。
ただし、制御車なのでマスコンぐらいしか違いが無いので特に問題はない。
平成9年よりワンマン改造を実施し、運賃箱、運賃表、整理券発行機、ドア回路の
変更などが施されている。
平成17年より7253編成に「丸窓電車」モハ5250形を模したラッピングを施し、
「まるまどりーむ」号になった。
当初、同編成1本だけだったが、同年の上田電鉄発足にあわせて7255編成も同様の
ラッピングを施されている。
このラッピングはクリームと紺色のツートンカラーという外見だけでなく、
車内も木目調のカッティングシールを貼り、座席のモケットも東急時代のオレンジと
ブラウンの2色からワインレッド一色になり、丸窓も運転台側に近いドアすぐの
窓で再現された本格的なものである(座席の張り替えは7255編成では未施工)。
また、他の編成でも帯色を紺とクリームの2色に変更したが、7254編成だけ帯を
剥がした無地とされた。
当初は期間限定での実施予定であったが、好評を博したため、そのまま運用された。
平成20年に東急から1000系電車×4本が入線することになり、本形式3本が
置き換えられることになった。
退役したのは7251編成、7252編成、7254編成の3本である。
7251編成は同じ東急7200系を1800系として運用している豊橋鉄道に譲渡され、
同社で部品供給用として保管されていたデハ7255号を整備して組み合わされ、
1810編成モ1860+ク2810として再起した。
7252編成と7254編成のうち、モハ7252号とモハ7254号は東急車輛へ譲渡され、
同社工場の入換牽引車になった。
残ったクハ7552号とクハ7554号は下之郷工場でしばらく保管の後、解体されている。
「まるまどりーむ」号2本は現在も籍を有しているが、予備的な存在となっており、
最近は動く機会が少ない。

○無地になった7254編成。このクハ7554号車は上田電鉄7200系唯一の
日立製マスコン装備車だった。

○車内。ほぼ東急時代のままだが、ワンマン化の際、乗務員室仕切り扉が
大型の引き戸に替えられた。

○運転台。基本的に東急時代と変化は無い。左右にあるレバーはワンマン運転用の
ドアスイッチ。マスコンは東洋電機製。ロゴが見える。

○「まるまどりーむ」号の7553編成。運行当初、ヘッドマークを掲出していたが、
最近は取り付けていない。

○「まるまどりーむ」号車内。
譲り受けたものである。
平成5年に2両編成×5本=10両が入線した。
製造年は昭和42年~43年で製造を担当したメーカーは東急車輛である。
■東急時代の概要
営団日比谷線の直通用に設計され、その規格を満たすために全車電動車方式で
製造された7000系の反省に立ち、東横線以外の高速走行を必要としない路線での
運用を考慮した経済性重視の車両として登場した。
昭和42年~43年、昭和47年にかけて53両が製造された。
メーカーは東急車輛。
構成形式は以下の通り。
デハ7200形(制御電動車。制御装置・空気圧縮機・電源装置付き)、
デハ7300形(中間電動車。制御装置搭載。補助機器は当初搭載せず)、
デハ7400形(中間電動車。制御装置・空気圧縮機・電源装置付き)、
クハ7500形(制御車)
当初は製造順に附番されたが、本形式製造途上の昭和42年12月より運転台や
制御装置などの機器のメーカーの違いを分かりやすくするため、改番を実施した。
これにより、日立製作所製の機器を持つ車両が下2桁0番台、東洋電機製の機器を
持つ車両が下2桁50番台となった。
これも7000系で機器の違いで性能が違ったため、運用を分けていたものの、
車両の番号を分けず現場の混乱を生んだことから取られた措置である。
しかし、本形式では全線で運用可能な車両とすることが前提となったため、
性能が統一されており、この改番はあまり意味を成していない。
車体はオールステンレス製(デハ7200号+クハ7500号のみアルミ合金製)で
正面は三つ折れでさらに中心の貫通扉両脇が「く」の字に折れた「ダイヤモンドカット」と
呼ばれる独自の形態をしている。
塗装はなく、ステンレス無地であったが、昭和63年以降赤帯を正面にのみ巻いた。
行き先表示は当初が正面のみ、後年は側面にも追加されている。
車内はロングシートで側面窓に初めて一段下降窓を採用。
ドアは両開きで片側3箇所である。
冷房は昭和47年に目蒲線・池上線用に投入されたデハ7260+デハ7452+クハ7560の3両が
新造時から、それ以外は昭和50年代後半に改造で装備している。
主制御装置は抵抗制御方式でブレーキは界磁制御器による回生ブレーキ併用
電磁直通ブレーキである。
なお、界磁制御器のスイッチを切ることで回生ブレーキをカットすることも
可能である。
台車は電動車が軸箱支持をペデスタル式としたダイレクトマウント式空気バネ台車、
制御車が防振ゴム支持で軸バネを持たないパイオニア式とした空気バネ台車である。
モーターの駆動方式は中空軸平行カルダン。
制御車の台車は乗り心地が悪かったことから、後年電動車と同じ構造のものに
交換したものがある。
東急では東横線をはじめ大井町線、田園都市線で運用され、その後、池上線、
目蒲線に活躍の場を移し、平成12年8月に事業用のデヤ7290形なったアルミ合金製の
2両と7600系に改造された9両を残して引退した。
■上田電鉄譲渡車の仕様
上田交通時代の平成4年にデハ7200形×5両、クハ7500形×5両の10両を譲り受けた。
新旧の車番変遷は以下の通り。なお、東急時代の改番は省略する。
上田:モハ7251+クハ7551←東急:デハ7257+クハ7551
上田:モハ7252+クハ7552←東急:デハ7252+クハ7557
上田:モハ7253+クハ7553←東急:デハ7253+クハ7553
上田:モハ7254+クハ7554←東急:デハ7254+クハ7511
上田:モハ7255+クハ7555←東急:デハ7258+クハ7558
譲渡にあたっての改造を担当したのは東急長津田車両工場である。
当初の改造内容は帯色の変更(前面のみ赤→正面~側面グリーンの濃淡)、
車番変更、回生ブレーキのカット、側面行き先表示の撤去と正面方向幕の手動化
程度である。
車番を見て分かるとおり、電動車の機器は全て東洋電機製のもので揃えられているが、
クハ7554号車のみ日立製作所の機器となっている。
ただし、制御車なのでマスコンぐらいしか違いが無いので特に問題はない。
平成9年よりワンマン改造を実施し、運賃箱、運賃表、整理券発行機、ドア回路の
変更などが施されている。
平成17年より7253編成に「丸窓電車」モハ5250形を模したラッピングを施し、
「まるまどりーむ」号になった。
当初、同編成1本だけだったが、同年の上田電鉄発足にあわせて7255編成も同様の
ラッピングを施されている。
このラッピングはクリームと紺色のツートンカラーという外見だけでなく、
車内も木目調のカッティングシールを貼り、座席のモケットも東急時代のオレンジと
ブラウンの2色からワインレッド一色になり、丸窓も運転台側に近いドアすぐの
窓で再現された本格的なものである(座席の張り替えは7255編成では未施工)。
また、他の編成でも帯色を紺とクリームの2色に変更したが、7254編成だけ帯を
剥がした無地とされた。
当初は期間限定での実施予定であったが、好評を博したため、そのまま運用された。
平成20年に東急から1000系電車×4本が入線することになり、本形式3本が
置き換えられることになった。
退役したのは7251編成、7252編成、7254編成の3本である。
7251編成は同じ東急7200系を1800系として運用している豊橋鉄道に譲渡され、
同社で部品供給用として保管されていたデハ7255号を整備して組み合わされ、
1810編成モ1860+ク2810として再起した。
7252編成と7254編成のうち、モハ7252号とモハ7254号は東急車輛へ譲渡され、
同社工場の入換牽引車になった。
残ったクハ7552号とクハ7554号は下之郷工場でしばらく保管の後、解体されている。
「まるまどりーむ」号2本は現在も籍を有しているが、予備的な存在となっており、
最近は動く機会が少ない。

○無地になった7254編成。このクハ7554号車は上田電鉄7200系唯一の
日立製マスコン装備車だった。

○車内。ほぼ東急時代のままだが、ワンマン化の際、乗務員室仕切り扉が
大型の引き戸に替えられた。

○運転台。基本的に東急時代と変化は無い。左右にあるレバーはワンマン運転用の
ドアスイッチ。マスコンは東洋電機製。ロゴが見える。

○「まるまどりーむ」号の7553編成。運行当初、ヘッドマークを掲出していたが、
最近は取り付けていない。

○「まるまどりーむ」号車内。