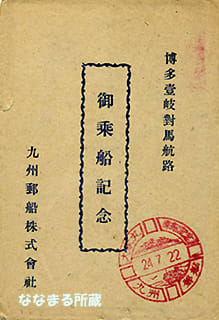日本郵船「兵庫丸」の船影が特定された。明治後期、小笠原航路の主船として活躍した同船には
写真が無かった。「バウスプリットの付いた老朽船」と云うのが島側の記録である。
『小笠原海運社史/別冊』には次のとおり記されている。
1899(M32).05 航路補助金増額され、定期船運航回数大幅に増加、年6回が12回となる。主として
兵庫丸就航。
1910(M43) 定期航路年18航海となる。内6航海は横浜/小笠原間直航。兵庫丸老齢のため売却される。
1912(M45/T01) 8月より芝罘丸が就航。

この画像を見たとき、バウスプリットのある船影から「兵庫丸」ではないかと直感した。日頃よりご教授
賜っているY氏に画像を確認願ったところ、「兵庫丸に相違無かろう」というご回答と共に、その根拠
として『日の丸船隊史話』を挙げておられた。山高五郎著『日の丸船隊史話』には、小菅丸に関し、
次のとおり記載されている。
井上侯御聲がゝりの船
傳ふる處に依れば、此船(小菅丸)は時の工部卿井上馨公が三菱會社の兵庫丸に乗つて
大にお氣に入り、同型の船を長崎工作分局の小菅の船臺で造らせたものであると云ふ。
因に御手本の兵庫丸は後年久しく郵船會社に属し、小笠原嶋通ひをやつて評判がよかつ
た。明治四十三年に至り賣却されて原田商行所属となり、大正二年難破した。
山高五郎著『図説日の丸船隊史話』には「小菅丸」の模型が載っている。確かに二見港で記録された
船影は、同型に見える。その後、別な画像にも巡り会った。


「兵庫丸」は1874(M7)英国Sunderlandで建造の「MIN」の後身で、1411G/T、鉄製汽船。征台の役に際し、
1874.05~1875.03にかけ、政府が香港において購入した外国船13隻の内の一隻である。
1875(M8).09.15政府より13隻の汽船は三菱汽船会社に無償下付された。同社は09.18付で郵便汽船三菱
会社と改名される。
1885(M18)日本郵船会社に継承される。
1894(M27).03月神戸定期船発着一覧には、次のとおり記されている。
凡毎月一回兵庫丸ヲ以テ馬關、長崎、福州、廈門、マニラ等へ往復定航セシム
1910(M43).03.01原田商行に売却される。
1913(T2). 神戸より青島へ向けて航海中、04.26周防灘において濃霧の中「笠間丸」と衝突し、小祝島
付近で沈没。
曾祖父の一人は八丈島出身で、明治三十七八年戦役には父島から出征し、日本海海戦では軍艦「音羽」
に乗り組んでいた。乗艦で父島に凱旋し、二見港に上陸した時の写真が残っている。八丈島から父島への
移住や出征は、「兵庫丸」に乗船したと思われる。その頃は、どの便も八丈島に寄港していた。

同一場所に立ち、「ははじま丸」の出港を眺めてみた。山並みは変わっていない。1970年頃、来航した
自衛隊のLSTは、ここに残っていた戦前の護岸の切れ目の砂浜にビーチングし、重機を揚陸した。
写真が無かった。「バウスプリットの付いた老朽船」と云うのが島側の記録である。
『小笠原海運社史/別冊』には次のとおり記されている。
1899(M32).05 航路補助金増額され、定期船運航回数大幅に増加、年6回が12回となる。主として
兵庫丸就航。
1910(M43) 定期航路年18航海となる。内6航海は横浜/小笠原間直航。兵庫丸老齢のため売却される。
1912(M45/T01) 8月より芝罘丸が就航。

この画像を見たとき、バウスプリットのある船影から「兵庫丸」ではないかと直感した。日頃よりご教授
賜っているY氏に画像を確認願ったところ、「兵庫丸に相違無かろう」というご回答と共に、その根拠
として『日の丸船隊史話』を挙げておられた。山高五郎著『日の丸船隊史話』には、小菅丸に関し、
次のとおり記載されている。
井上侯御聲がゝりの船
傳ふる處に依れば、此船(小菅丸)は時の工部卿井上馨公が三菱會社の兵庫丸に乗つて
大にお氣に入り、同型の船を長崎工作分局の小菅の船臺で造らせたものであると云ふ。
因に御手本の兵庫丸は後年久しく郵船會社に属し、小笠原嶋通ひをやつて評判がよかつ
た。明治四十三年に至り賣却されて原田商行所属となり、大正二年難破した。
山高五郎著『図説日の丸船隊史話』には「小菅丸」の模型が載っている。確かに二見港で記録された
船影は、同型に見える。その後、別な画像にも巡り会った。


「兵庫丸」は1874(M7)英国Sunderlandで建造の「MIN」の後身で、1411G/T、鉄製汽船。征台の役に際し、
1874.05~1875.03にかけ、政府が香港において購入した外国船13隻の内の一隻である。
1875(M8).09.15政府より13隻の汽船は三菱汽船会社に無償下付された。同社は09.18付で郵便汽船三菱
会社と改名される。
1885(M18)日本郵船会社に継承される。
1894(M27).03月神戸定期船発着一覧には、次のとおり記されている。
凡毎月一回兵庫丸ヲ以テ馬關、長崎、福州、廈門、マニラ等へ往復定航セシム
1910(M43).03.01原田商行に売却される。
1913(T2). 神戸より青島へ向けて航海中、04.26周防灘において濃霧の中「笠間丸」と衝突し、小祝島
付近で沈没。
曾祖父の一人は八丈島出身で、明治三十七八年戦役には父島から出征し、日本海海戦では軍艦「音羽」
に乗り組んでいた。乗艦で父島に凱旋し、二見港に上陸した時の写真が残っている。八丈島から父島への
移住や出征は、「兵庫丸」に乗船したと思われる。その頃は、どの便も八丈島に寄港していた。

同一場所に立ち、「ははじま丸」の出港を眺めてみた。山並みは変わっていない。1970年頃、来航した
自衛隊のLSTは、ここに残っていた戦前の護岸の切れ目の砂浜にビーチングし、重機を揚陸した。