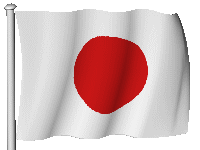解散先送り?延命しか考えていない野田政権
「CafeSta」カフェスタトーク ~水曜担当・三原じゅん子議員~(2012.8.22)
この人権委員会設置法案という売国法は永住外国人参政権付与法案とともに、絶対に成立させてはならない。
公明党や外国人参政権には反対しても「二重国籍を容認する」みんなの党にも解党を願いたいものだ。
産経新聞20120920
政府が19日、「言論統制につながる」との批判が絶えない人権救済機関設置法案(人権救済法案)の閣議決定に踏み切ったのは、衆院解散・総選挙をにらみ、人権団体など民主党の支持基盤にアピールするための「実績作り」が狙いだ。民主党代表選や中国による沖縄県・尖閣諸島での挑発行為のさなかに「どさくさ紛れ」で既成事実を作ったと指摘されても仕方がない。(千葉倫之)
法案の最大の問題点は、救済対象となる人権侵害の定義が「不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為」とあいまいで、拡大解釈の恐れがあることだ。これまで全国の弁護士会が行った人権救済勧告では、学校の生徒指導や国旗・国歌に関する指導、警察官の職務質問が「人権侵害」とされた事例もある。
新設される人権委員会が偏った思想・信条に基づく申し立てに公正な判断を下す保証もない。法案は人種や信条などを理由に「不当な差別的取り扱いを助長・誘発」する目的での文書配布なども禁じているが、これでは北朝鮮による拉致問題への抗議活動も「不当な差別」とされかねない。
ましてや、公正取引委員会などと同じ「三条委員会」として政府からの独立性と強い権限が与えられるため、「人権の擁護に関する施策」を推進する人権委員会が人権侵害の片棒を担ぐ可能性もゼロではない。
「人権委を一度設置すれば、将来、法改正することもできる。『小さく産んで大きく育てる』のが推進派の狙いだ。人権侵害の定義もあいまいで、権力による言論弾圧につながる」
人権救済機関設置問題に詳しい日本大学の百地章教授(憲法学)はこう述べ、閣議決定を強く批判した。
国会閉会中を狙った唐突な閣議決定も、与野党に波紋を広げた。
自民党総裁選候補者は19日、「言論の自由の弾圧につながる」(安倍晋三元首相)、「なぜこのタイミングなのか」(林芳正政調会長代理)などと一斉に批判を始めた。民主党からも「慎重派の松原仁国家公安委員長が外遊中の閣議決定は理解に苦しむ」(長尾敬衆院議員)との反発の声が上がったが、野田佳彦首相の周辺は「慎重な閣僚がいないから閣議決定してもいいではないか」と話した。
法案には選挙で影響力を持つ人権団体のほか、公明党も法整備に前向きだ。「解散風」が強まる中、今秋の臨時国会で成立する可能性は否定できない。
産経新聞20120920 主張 人権救済法案 強引な閣議決定おかしい
野田佳彦政権は、新たな人権侵害や言論統制を招きかねないとの批判が出ていた人権侵害救済機関「人権委員会」を法務省外局として設置する法案を閣議決定した。
今回の閣議決定は不可解な部分が少なくない。藤村修官房長官は「政府として人権擁護の問題に積極的に取り組む姿勢を示す必要がある。次期国会提出を前提に、法案内容を確認する閣議決定だ」と強調した。
だが、国会提出時には再度、閣議決定を経る必要がある。人権救済法成立に前のめりな党内グループに過度に配慮しただけではないのか。同法案に慎重な松原仁国家公安委員長の外遊中を狙った節もあり、疑念がつきまとう。
人権委員会は政府から独立した「三条委員会」で、公正取引委員会と同様の強大な権限を持つ。調査の結果、人権侵害と認められると告発や調停、仲裁などの措置が取られる。
最大の問題は、人権侵害の定義が相変わらず曖昧なことだ。「特定の者」の「人権」を「侵害する行為」で憲法違反や違法行為を対象とするというが、これでは何も定義していないに等しい。恣意(しい)的な解釈を許し、言論統制や萎縮、密告による新たな人権侵害を招きかねない。
こうした法案への疑念や危惧、抵抗感は国民は無論、与党や閣内にも根強い。にもかかわらず、いま行われている民主党代表選、自民党総裁選で、この問題が問われていないのは重大な欠落だ。
閣議決定に対し、自民党の林芳正政調会長代理は「なぜ、この時期なのか」と政府の意図に疑問を投げた。安倍晋三元首相も法案に対し「大切な言論の自由の弾圧につながる」と指摘した。石破茂前政調会長は以前、法案に反対としながらも、救済組織の必要性は認めていた。
政府・与党は先の通常国会終盤にも法案提出に意欲を示したが、批判を受けて見送ったばかりだ。国論が二分している法案を閣議決定して既成事実化するやり方は、到底適切な手続きといえない。
自民党内にも人権法案に前向きな意見もあるが、言論統制とは無縁の自由な社会を維持するために果たしてこの種の法案が必要なのか。民主、自民両党首選の立候補者は少なくともこの問題への立場を鮮明にし、国民的な議論を積み重ねてもらいたい。
総力をあげて領土と国民を守らねばならない。
なぜ、このようなときに「人権委員会設置法案」の閣議決定などできるのだろう。
やるべきことをやらず、やってはならないことを積極的にする。
日本を破壊する左翼政権はもううんざりである。
産経新聞20120919 主張
中国の漁船約千隻が尖閣諸島に向かって出港した。10隻を超す中国の漁業監視船と海洋監視船も接続水域に入っており、合流する可能性が強い。千隻もの漁船が殺到すれば前例のない事態だ。野田佳彦政権は総力を挙げて尖閣防備の態勢を固め、あらゆる事態に備えなければならない。
尖閣諸島などを警備する第11管区海上保安本部(沖縄)には、千トン以上の巡視船が7隻しかない。しかも、5千トン以上の大型巡視船は大都市周辺に配備されているだけだ。他の保安本部から11管に巡視船を応援に回すなどして、万全の防備体制を敷くべきだ。
海保だけで対応できない場合、自衛隊の出動が必要になる。野田首相は7月の衆院本会議で、日本の領土・領海での外国の不法行為には「必要に応じて自衛隊を用いることも含め、政府全体で毅然(きぜん)と対応する」と述べている。
まず考えるべきは、自衛隊法82条に基づく海上警備行動である。海上での人命・財産保護や治安維持のために防衛相が命じるもので、平成11年3月の能登半島沖不審船事件や16年11月の中国原子力潜水艦による領海侵犯事件などに対し、計3度発令されている。
より緊急事態を想定した治安出動(同78、81条)や防衛出動(同76条)はまだ発令されたことはないが、検討内容に含めておかねばならない。そのためには、尖閣の事態に対処する関係閣僚会議に森本敏防衛相が出席して意見を述べる必要がある。関係8省庁の協議にも防衛省が入っていないが、これもおかしい。
海保と自衛隊の連携による堅い守りが、中国との一触即発の危機を回避する抑止力になる。
来日したパネッタ米国防長官は玄葉光一郎外相との会談後の記者会見で、尖閣諸島が日米安保条約第5条の適用範囲との認識を示した。尖閣周辺での日米合同演習も有効な尖閣防護策である。
昭和53年4月には、武装した100隻超の中国漁船群が尖閣沖に現れ、領海侵犯を繰り返した。
海保の巡視船の増強と海上保安官の増員に加え、削減し続けてきた防衛予算の拡充が急務である。農林水産省の岩本司副大臣は違法操業などを取り締まる水産庁の漁業取締船を39隻から41隻に増やす方針を示した。
オールジャパンで領土と海洋権益を守るべきときだ。
大阪市長は???である。何処か信用ならぬ。
20120913産経新聞
消費税増税法は成立した。では、民主党政権の次の政策課題は何なのか-。野田佳彦首相からの発信はないままだ。
民主党は、政権交代を訴え、国民の期待とともに先の衆院選に大勝した。しかし、マニフェスト(政権公約)は早々に破綻し、離党者が相次ぎ四苦八苦している。しかしながら、ただ漫然と政権を維持していることが許されるはずはない。
外交では、今まさに主権護持と領土堅持、つまり独立国家としての政府の毅然(きぜん)たる存在を示すときなのに、曖昧模糊(もこ)となっている。韓国大統領の竹島上陸や天皇陛下をめぐる発言への野田政権の対応はもっと厳然とやるべきであり、尖閣諸島の購入も、世論や石原慎太郎東京都知事の発言に触発されて決めた印象を受けざるを得ない。事が起こってから必死に対応しようとする受け身の姿勢ばかりが目立つ。
内政でも、場当たり的な問題処理に追われるばかりで、積極的な改革論が影を潜めている。中長期の観点からの確信に満ちた国策や政策を打ち出せていない。自民党的政治の延長でしかない感をぬぐえない。
しかし、一方で自民党は、いまだにいささか与党ぼけしている。失策続きの民主党政権を倒す野党精神が見えてこない。
消費税増税法に協力したことは明日の日本を考えれば当を得たことだろう。民主党と組むのか大阪維新の会と組むのか、国民は見ているが、党の主体性が明瞭でない。
野党であるならば、今こそ民主党政権の政策の欠点を徹底的に洗い出し、次期衆院選の公約策定につなげるべきだ。その上で、野田政権を衆院解散へ追い込み、衆院選では「単独過半数」を目標議席に掲げ、自民党単独政権を目指すのが常道ではないか。今から連立政権を想定して発言するのは本末転倒である。
衆院の任期が1年を切った。民主党も自民党も、そろそろ「夏休みぼけ」を払拭し、党の柱となる政策を提示するときだ。国民からみると、今の両党は違いの分からない「同類項」的様相であり、国民の不信を一層助長させかねない。
政策課題は憲法、教育、そして国と地方のあり方を含めた統治機構、外交と山積している。いずれも国家戦略に絡む。一方、原発再稼働の問題はエネルギー問題の将来として考えるべきだろう。「原発廃止」の声は代替エネルギーや料金値上げ、環境という問題に直面するとどうなるか。
大阪維新の会も、「維新八策」で憲法や教育、統治機構を示した。ただ、維新八策には迫力が感じられない。大阪の視点で考えたからであり、中央にどっしり腰を据えて、八方にらみで出てきた重い「国のかたち」、すなわち国家戦略が見えてこないのだ。憲法・外交が欠けるとこのようになる。
大阪で燃え上がった改革の炎を国に広げようとしても、橋下徹代表が大阪市長にとどまる限り、炎は大阪で止まる。しかも、市長を務めながら国政も担おうとは、政治のいろはを知らない。
国を動かしたいのならば、中央に来て雄たけびを上げることだ。全国に檄(げき)を飛ばして国政は始まる。
民主党だけではない。すべての政治家、官僚、そして国民一人一人が日本の主権を守ろうとする強い気持ちを持たねばならないでしょう。
産経新聞20120913
外務省、日本国領有の痕跡を消し去るべきという考えも
尖閣、国防、原発、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)など、日本国にとって喫緊かつ根本的問題のすべてで野田佳彦首相は敗北を重ねつつある。
尖閣諸島を国有化しても、「平穏かつ安定的な維持」のためと称して、島の現状を保ち、日本国領有の実態を強化する船だまりや灯台を整備しないのでは、何のために税で島を買ったのかと問わなければならない。
政府は長年尖閣諸島を賃借して、国民の上陸を禁止し、島々を放置した。言葉だけの実効支配の隙に中国が付け入ったのは当然だ。付け入る中国よりも、あるいは北方領土に付け入るロシアや竹島に付け入る韓国よりも、付け入らせる隙を作った日本が悪い。その愚をいま、政府全体で繰り返そうというのか。
石原慎太郎都知事はもはや国家といえないこの惨状を正すべく立ち上がった。約15億円の寄付は、都知事と国民の心がひとつになったことの証しである。
当初、石原知事の思いに前向きだった首相に、岡田克也副総理および玄葉光一郎外相以下外務省が、船だまりや灯台はもとより、島の国有化さえも中国の怒りを買うとして怖(お)じ気(け)づき、圧力をかけた。
外務省内には中国を恐れるあまり、魚釣島に残されている日本国領有の痕跡を消し去るべきだという信じ難い考えさえあったという。たとえ国土を奪われようとも中国の怒りを買わず摩擦回避を旨とする岡田、玄葉両氏、外務省の説得に屈した野田首相も同罪である。
摩擦回避を試みる日本に対して温家宝首相は10日、「主権と領土問題では、中国政府と人民は絶対に半歩も譲らない」と、人さし指を突き立てて猛反発した。「半歩も譲らない」と、人民解放軍機関紙「解放軍報」も報じ、軍事行動に踏み出す可能性を示唆した。
反発は、想定の範囲内であろうに、藤村修官房長官はうろたえたのか、尖閣諸島の現状に変化はなく以前と同じだと会見で訴えた。以前と同じでは無意味であることが理解できていないのである。
尖閣諸島を中国が奪いに来るとき、唯一、領土を守る手立ては実際に日本人を送り込み、島を活用して領有の実態を作り上げることだ。島の空間を日本人の工夫と力で満たしていくことだ。国際社会は力関係によって形づくられる。加えて領土問題で重要なのは、自国を防衛するという強い国家意思であり、迫力である。
首相も官房長官もいまこの局面が日本国の正念場であると覚悟しなければならないのだ。領土問題は時が過ぎたら収束する問題では決してない。
無為の時を過ごすことで、かえって危機は深まり、火の粉は消すに消せなくなる。
民主党政権のわずか3年の歴史の中で、どれほど国益が損なわれたか、なぜそうなったかを首相はいまこそ考えよ。親中恐中派の菅直人政権時の尖閣問題の処理、丹羽宇一郎大使の任命、目的を履き違えたかのような外務省主導の対中外交はいずれも憲法前文および9条に拘束される戦後体制そのものが、現実の国際政治に対応できず、日本が自壊した事例である。
中国は尖閣をまぎれもない国家主権の問題として真っ正面から挑み続けてきた。民主党は国家観なきゆえに対処できないできた。自国を守る意思と力を欠く国など、まともに相手にされないのである。その意味で日中関係の悪化も、日本の立場が貶(おとし)められてきたことも、まさに日本の戦後体制がもたらした結果なのである。
現在、中国の内情は経済の大失速で背筋が寒くなるほど不安定で厳しい。中国社会に蔓延(まんえん)する心理的不安は常に捌(は)け口を求めており、反日教育の結果、日本への故なき怒りは容易に爆発し得る。内政問題の解決策が見えないとき、一党独裁の中国共産党が突如、国民の怒りが自らに向けられるのを回避するために対日強硬手段に出ることもあり得る。日本は国家としての緊張感を保ち、ありとあらゆる場合に備えて、最速で万全の対策を整えなければならない。
尖閣諸島周辺の海底資源は有望で、貴重な日本の宝だ。島周辺は豊かな漁場でもあり、高さ約360メートルの尖閣一の高い山にレーダーサイトを築き、自衛隊の高性能のレーダーを置けば、排他的経済水域のはるか彼方(かなた)まで、中国船の動きを監視できる。わが国最南端の宮古島のレーダーに魚釣島のレーダーを加えることで、対中監視網をかなりの程度広げられる。この重要な戦略拠点を逆に中国に奪われれば、その場合の損失ははかりしれない。
軍事力の行使を示唆する中国に対して、島々と海の監視体制を整え、制海権と制空権を確立するために何よりもまず、国防予算を増やさなければならないが、野田政権は来年度の防衛予算を逆に削減しつつある。中国の軍事的脅威に備えてアジア・太平洋諸国が尋常ならざる軍拡を進めるのとは対照的に、日本のみ国防予算を削減する愚かな政策をなぜ、継続するのか、厳しく問うものだ。
野田首相以下民主党政権の国家戦略の欠如は国防に限らない。原発、TPPなども同様である。この深い混迷からの立て直しを図るために、いまこそ敗北にまみれたこの戦後体制の元凶である現行憲法を見直すときだ。敢然と憲法改正に取り組み政治生命をかけて闘うことによってのみ、活路が開けることを、首相は認識すべきであろう。