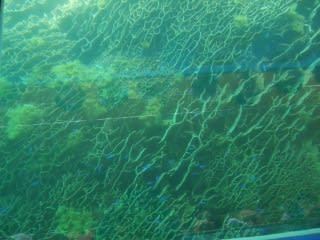2014年11月22日・23日、旅行社のバスツアーに参加
して、紅葉の香嵐渓と伊勢神宮に行ってきました。

往きの途中で寄った中央道の駒ヶ岳SAでは、雪が積もった
木曽駒ヶ岳を見ることができました。

香嵐渓の駐車場へ着きました。桐生からここまで7hかかり
ました。なお香嵐渓は紅葉で有名で、豊田市足助(あすけ)町
にあります。

香嵐渓に向かって歩き始めた処。両側にはいろいろな
お店が並んでいました。

香嵐渓が見えてきました。手前の川は巴川、大勢の人が
渡っている橋は待月橋、山裾に紅葉が見えるのは飯盛山
です。

渡っている待月橋から右側を撮りました。川縁にも人が
たくさん下りていました。

左側の川岸です。

橋を渡り切った所で上を見て撮りました。いろいろな色が
混ざってきれいでした。

川に沿った歩道を右方向に歩いて行きました。

上にも歩道が見えました。ここら辺りもいろいろな色が
混ざっていました。

香嵐渓広場という所まできました。

広場を行った先には、三州足助屋敷という古い民具などが
見られる観光施設がありました。銀杏の黄色がきれいで
したよ。

屋敷の傍から山の中腹にある香積寺へ登る参道です。

参道を横切る歩道も紅葉で覆われていました。

階段を上って香積寺本堂へ出ます。

香積寺をお詣りした後、戻りかける処で撮りました。

香積寺からさらに先を進むと二つ橋が出てきて、その
二本目の橋は香嵐橋という吊り橋でした。

香嵐橋から道を戻り、香嵐渓広場を上から撮りました。
広場の端の舞台では、太鼓の演奏が始まる処でした。

待月橋の袂を通り過ぎた先、すなわち左側の歩道は
もみじのトンネルといって、背の高いもみじに覆われ
ていました。

もみじのトンネルを戻りながら撮りました。

待月橋が見える所まで戻って最後に撮りました。
香嵐渓を終わって、この後、伊勢神宮のある伊勢市に向かい
ました。

二日目は、最初に外宮である豊受大神宮を訪れました。
写真はバスを降りて、表参道の橋を渡る所です。

鳥居が見えてきました。柱に榊が結わえ付けられていました。

表参道を正宮に向けて歩いて行ったのですが、辺り一帯
朝の清々しい雰囲気に包まれていました。

警備の人が道を整理していて、何かと思ったら神主の一団
が歩いてきました。新嘗祭を執り行うためみたいです。

敷地の最奥部の正宮が見えてきました。

正宮では、塀のすぐ後ろの所でお詣りし、さらに中に入る
ことはできませんでした。

神楽殿です。元へ戻る途中で撮りました。

こちらは、せんぐう館といって遷宮にまつわる資料等展示
しているみたいです。中には、入りませんでした。

外宮の後には、本宮の皇大神宮へ向かいました。写真は、
バスを降りて、内宮に架かる宇治橋手前の所を歩いてい
る処です。

宇治橋の上から、五十鈴川を撮りました。紅葉も見えました。

橋の袂の鳥居をくぐって、参道を歩いて行きました。

参道を歩いていると、警備員が道の真ん中を空けていま
した。伊勢神宮の祭主であらせられる池田厚子さんが
通られるとのことでした。天皇陛下のお姉さまにあたる方
ですね。

内宮では、手水舎もあるのですが、水がきれいなので、
五十鈴川で清めることが多いとのこと。そのため、川縁
に皆下りていきました。

これは神楽殿です。屋根が四方向に向かっています。

内宮正宮の社殿が見える場所。正宮社殿は正面から見る
ことができず、ここからだけとのことでした。

正宮で、お祈りで上がれるのはやはり写真の場所までで
した。

戻る途中にあった御稲御倉(みしねのみくら)。

同、外弊殿(げいへいでん)。

こちらは天照大神を祀る別宮の荒祭宮(あらまつりのみや)。

内宮最後に宇治橋を撮りました。

内宮を出た横には、おはらい町がありました。昼食後には
こちらを見学することになっていました。

お昼を摂って、出向いたらおはらい町は人であふれて
いました。

両側には、このような古い建物が並んでいました。皆、
何かのお店でした。

コンビニも、こうした古い建物に入っていました。

屋根に猿の装飾が…、面白いですねー。

こちらは、あの有名な赤福本店。お土産を買う客が列を
作っていました。

赤福の前の横道は、おかげ横丁といった超人気スポットで
した。

こちらも店が立ち並んでいました。

奥へ向かって進むとおかげ座の幟が立っていました。横路
の奥がそのおかげ座みたいで、昔話を上演していました。

横路の入口には、射的場がありました。標的の景品が
いっぱい立ち並んでいました。ただ、弾が当たっても
なかなか落ちません。考えていますねー。

隣にはこんな宝くじ売り場も…

おかげ座の前では、大きな猫が昼寝をしていました!!

おかげ座とは反対側の一画で、若者の長い列が? 何か
と思ったら、コロッケを揚げて売っている店でした。

こちらでは、昔懐かしいアメ細工の店がありました。

最後に昔風の屋敷と土塀を撮って、バスへ戻りました。
その後、8hかけて桐生へ帰ってきました。
香嵐渓と伊勢神宮、時間をかけて行っただけのことはあり
ました。ただ、今度もう一度といっても、時間がかかるの
で、果たして実現できるやら疑問ですね!!
して、紅葉の香嵐渓と伊勢神宮に行ってきました。

往きの途中で寄った中央道の駒ヶ岳SAでは、雪が積もった
木曽駒ヶ岳を見ることができました。

香嵐渓の駐車場へ着きました。桐生からここまで7hかかり
ました。なお香嵐渓は紅葉で有名で、豊田市足助(あすけ)町
にあります。

香嵐渓に向かって歩き始めた処。両側にはいろいろな
お店が並んでいました。

香嵐渓が見えてきました。手前の川は巴川、大勢の人が
渡っている橋は待月橋、山裾に紅葉が見えるのは飯盛山
です。

渡っている待月橋から右側を撮りました。川縁にも人が
たくさん下りていました。

左側の川岸です。

橋を渡り切った所で上を見て撮りました。いろいろな色が
混ざってきれいでした。

川に沿った歩道を右方向に歩いて行きました。

上にも歩道が見えました。ここら辺りもいろいろな色が
混ざっていました。

香嵐渓広場という所まできました。

広場を行った先には、三州足助屋敷という古い民具などが
見られる観光施設がありました。銀杏の黄色がきれいで
したよ。

屋敷の傍から山の中腹にある香積寺へ登る参道です。

参道を横切る歩道も紅葉で覆われていました。

階段を上って香積寺本堂へ出ます。

香積寺をお詣りした後、戻りかける処で撮りました。

香積寺からさらに先を進むと二つ橋が出てきて、その
二本目の橋は香嵐橋という吊り橋でした。

香嵐橋から道を戻り、香嵐渓広場を上から撮りました。
広場の端の舞台では、太鼓の演奏が始まる処でした。

待月橋の袂を通り過ぎた先、すなわち左側の歩道は
もみじのトンネルといって、背の高いもみじに覆われ
ていました。

もみじのトンネルを戻りながら撮りました。

待月橋が見える所まで戻って最後に撮りました。
香嵐渓を終わって、この後、伊勢神宮のある伊勢市に向かい
ました。

二日目は、最初に外宮である豊受大神宮を訪れました。
写真はバスを降りて、表参道の橋を渡る所です。

鳥居が見えてきました。柱に榊が結わえ付けられていました。

表参道を正宮に向けて歩いて行ったのですが、辺り一帯
朝の清々しい雰囲気に包まれていました。

警備の人が道を整理していて、何かと思ったら神主の一団
が歩いてきました。新嘗祭を執り行うためみたいです。

敷地の最奥部の正宮が見えてきました。

正宮では、塀のすぐ後ろの所でお詣りし、さらに中に入る
ことはできませんでした。

神楽殿です。元へ戻る途中で撮りました。

こちらは、せんぐう館といって遷宮にまつわる資料等展示
しているみたいです。中には、入りませんでした。

外宮の後には、本宮の皇大神宮へ向かいました。写真は、
バスを降りて、内宮に架かる宇治橋手前の所を歩いてい
る処です。

宇治橋の上から、五十鈴川を撮りました。紅葉も見えました。

橋の袂の鳥居をくぐって、参道を歩いて行きました。

参道を歩いていると、警備員が道の真ん中を空けていま
した。伊勢神宮の祭主であらせられる池田厚子さんが
通られるとのことでした。天皇陛下のお姉さまにあたる方
ですね。

内宮では、手水舎もあるのですが、水がきれいなので、
五十鈴川で清めることが多いとのこと。そのため、川縁
に皆下りていきました。

これは神楽殿です。屋根が四方向に向かっています。

内宮正宮の社殿が見える場所。正宮社殿は正面から見る
ことができず、ここからだけとのことでした。

正宮で、お祈りで上がれるのはやはり写真の場所までで
した。

戻る途中にあった御稲御倉(みしねのみくら)。

同、外弊殿(げいへいでん)。

こちらは天照大神を祀る別宮の荒祭宮(あらまつりのみや)。

内宮最後に宇治橋を撮りました。

内宮を出た横には、おはらい町がありました。昼食後には
こちらを見学することになっていました。

お昼を摂って、出向いたらおはらい町は人であふれて
いました。

両側には、このような古い建物が並んでいました。皆、
何かのお店でした。

コンビニも、こうした古い建物に入っていました。

屋根に猿の装飾が…、面白いですねー。

こちらは、あの有名な赤福本店。お土産を買う客が列を
作っていました。

赤福の前の横道は、おかげ横丁といった超人気スポットで
した。

こちらも店が立ち並んでいました。

奥へ向かって進むとおかげ座の幟が立っていました。横路
の奥がそのおかげ座みたいで、昔話を上演していました。

横路の入口には、射的場がありました。標的の景品が
いっぱい立ち並んでいました。ただ、弾が当たっても
なかなか落ちません。考えていますねー。

隣にはこんな宝くじ売り場も…

おかげ座の前では、大きな猫が昼寝をしていました!!

おかげ座とは反対側の一画で、若者の長い列が? 何か
と思ったら、コロッケを揚げて売っている店でした。

こちらでは、昔懐かしいアメ細工の店がありました。

最後に昔風の屋敷と土塀を撮って、バスへ戻りました。
その後、8hかけて桐生へ帰ってきました。
香嵐渓と伊勢神宮、時間をかけて行っただけのことはあり
ました。ただ、今度もう一度といっても、時間がかかるの
で、果たして実現できるやら疑問ですね!!