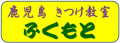見学の方が、来月から講座に参加されます。
2月22日(木)に行なわれた、「日本舞踊着付け、浅草西会館 専門講座」には、第一回目からの参加者でもある二人の芸者さんがお稽古されました。
当日の講座には、関心を持たれたお二人の方も見学にお越しになり、来月から仲間として参加されることになりました。
おひとりは日本舞踊をされていらっしゃる方、もうおひとりは、着付けの先生です。
「つの出し」と、「つの出しの変化」を集中して…
今回の講座の内容は、「つの出し」結び。この帯結びは帯締めを使いません。
全通や六通の帯の歴史を学びながら、全通を使った本来のつの出し、六通の袋帯のつの出し結びの変化などを学びました。
その他にも、舞台裏で衣裳方が結ぶ裏技もご覧頂きました。
来月は、3月29日(木)に開催され、ご見学の方もお越しになる予定です。
●霧島山脈近郊の画像一覧
●霧島火山ライブ情報マップ
●新燃岳の火口ライブ映像へリンク






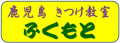





第二回目の「日本舞踊着付け専門講座」が、浅草西会館で行われます。
日時は、2月22日(木)午前10時からと、午後1時からの二講座。
場所は、雷門から徒歩4分の「浅草西会館」。
関心のある方は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 090-4489-9745 いちき まで


自装の第一段階、外出着の着付け
鹿児島の松井さんのお稽古も、7回目。
小紋のきものに、名古屋帯のお太鼓です。
最近はずいぶんと手馴れて着付けが出来るようになりました。
今日は年令にあった衿合わせと、帯の高さを学びながら進めていきました。
お太鼓もきれいに出来て…。
この頃から、実際にご自分できものを着て、外出することも大切かもしれません。
松井さん、思い切ってお出掛けしませんか。
●霧島山脈近郊の画像一覧
●霧島火山ライブ情報マップ
●新燃岳の火口ライブ映像へリンク






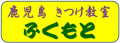





「たかが半巾、されど半巾」
日本舞踊専門講座の着付けは、「はしょり着付け」から一回目が始まります。
日本舞踊は、所作(動き)があるために、一般のきものの着付けとは、ずいぶん違うところが出てきます。
学ぶ帯結びは、「半巾の一文字と片流し」。
張りのある「半巾の帯結び」でないと、舞台に映えません。
「たかが半巾、されど半巾」なのです。
踊りの定番、「つの出し」
カリキュラムの2講座目は、「はしょり着付けにつの出し」。
日本舞踊の定番の形です。
関西巻き、関東巻きを問わず、初々しい町娘にするか、粋な女性にするか、結び手によってずいぶん雰囲気が違ってきます。
踊る演目によって、考えていかなければなりません。
見学者大歓迎です。
講座の見学は自由です。
事前にお問合せくださいませ。
お問合せ先は、090-4489-9745 いちき」 まで。








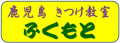





清楚に初々しい着付け目指して
鹿児島の「きつけ塾いちき」の今日のおけいこは、「女性袴の着付け」でした。
お稽古しているのは、着付け師の田原さん。
目指すは、「清楚で初々しい女性の袴すがた」
モデルは、「振袖専科」を学んでいる前村さん。
お互いにモデルをしながら、お勉強されていました。
これから、切磋琢磨しながら一年間、より高い峰に向けて技術を高めていかれることでしょう。
●霧島山脈近郊の画像一覧
●霧島火山ライブ情報マップ
●新燃岳の火口ライブ映像へリンク






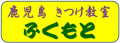





芸妓(京都)と芸者(関東)の着付けをご覧いただきます。
「きつけ塾いちき」の衣裳方は、「熊本県伝統工芸館で、京都と江戸の花街を比較をした着付けショーが出来ないか」との要請があり、お引き受けしました。
開催日は、5月2日(水)/場所は、「熊本県伝統工芸館」です。
京都と江戸では、芸者(芸妓)の着付けも拵えも違います。
その違いを、ご来場頂いた皆さまにご覧いただき、楽しんで頂ければと思います。
同じ会場で、舞妓(京都)と、半玉(江戸)の着付けが出来れば最高なのですが、内容については主催者と検討中です。
着付けの解説は市来康子学院長。着付けは私どもの衣裳方が担当いたします。
細かい内容は、分かり次第、このブログでお知らせ致します。お楽しみに…
6月には、いつもお世話になっている、「はかた伝統工芸館」で、「芸者の着付けショー」を開催する予定です。
テーマは、「京都と博多の芸妓の着付け」。
この催しも、内容が分かりしだいお知らせ致します。
熊本県伝統工芸館 正面
●霧島山脈近郊の画像一覧
●霧島火山ライブ情報マップ
●新燃岳の火口ライブ映像へリンク






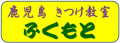





各地の着せ付け講座、楽しく開催
本年も、2月の後半。
「きつけ塾いちき」の着付け教室の受講生の皆さまも、楽しくお勉強をされています。
現在、福岡県では、●福岡市早良区の「ももち文化センター」。 ●北九州市小倉北区の「KMMビル」。
南九州では、●鹿児島市中央区の「きつけ塾いちき 鹿児島」。 ●宮崎市下北方の「きつけ塾いちき 宮崎」。
東京では、●向島の芸者さんたちのお稽古場から始まった、「日本舞踊着付け、浅草西会館講座」などが主なお稽古場です。
それぞれのお教室が、日本舞踊の着付け、和装花嫁着付け、振袖着付け、美容師向けプロコースなどの特徴を持ったものです。
レンタルの担当者の悩みを聞くと…「着崩れない着付けを…」
レンタルの着付け担当者にお話をお聞きすると、「着付けをお願いしても、着崩れのクレームが多くて…」と悩みをお話されます。
成人式の時だけ着付けをされると、手馴れていないために、肝心の腰紐や伊達締めの技術がおろそかになり、ゆるみを生じます。
★私どもでは、一年を通して「振袖の特訓」を開催しています。
「振袖の特訓」は、着付けに関わるスタッフや、「きつけ塾いちき」で学んでいる美容師さんの技術の成果を実践的に磨くためです。
★また、振袖のスタッフには、年間を通して「日本舞踊の舞台裏」で歌舞伎衣裳などの着付けを行なっている「衣裳方」がいることです。
重量が重たく、舞台で踊る舞踊家の着付けに着崩れは許されません。
このスタッフにとって、振袖の衣裳は着せやすいもののひとつです。
鹿児島・宮崎で「振袖特訓」/指導は三人のベテランの手で
鹿児島と宮崎では、振袖のプロ着付け師を養成する為に、「振袖特訓受講生」を募集しています。
指導するのは、海外で、十二単の着付けを通して日本文化を紹介する一方で、松竹衣裳の岸田先生に師事し、歌舞伎衣裳や日本舞踊の着付けを学び続けてきた、時代風俗衣裳研究家・学院長の市来康子。
あと二人の指導講師は、市来学院長を支える両輪。
ひとりは、教室長、「着付けの木下和代」。もうひとりは指導課長、「帯結びの小浦澄子」。
ふたりとも、日本舞踊・振袖、花嫁・十二単の着付けを学び続けて38年。創業以来の草分けです。
福岡では、日本舞踊家・美容師・着付け師・着付け教室の先生方が三人の指導の下で、学んでいらっしゃいます。
宮崎や鹿児島の皆さまが、着付け経験者、未経験者を問わず、一年を通して「特訓講座」に参加され、技術のスキルを上げていただきたいものです。
お問合せは、090-4489-9745 では、市来康子が直接ご相談に応じます。
このほかに、0120-298-144、0985-29-8144、099-206-7337 でもお受けいたします。

●霧島山脈近郊の画像一覧
●霧島火山ライブ情報マップ
●新燃岳の火口ライブ映像へリンク






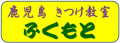





やる気十分…受講生は、ピンチ大好き女子
宮崎の「きつけ塾いちき」では、舞踊の着付け講座がありました。
今日の着付けの課題は、「京都の舞妓」。
肩上げ・袖上げの裾引きの衣裳を着せて、6m以上のダラリの帯を結んでいきます。
今日参加したのは、宮崎市内の H さん。
衣裳方の初級・中級の資格も取って、今は復習をしながら腕を磨いていらっしゃいます。
あとは日本舞踊の会の舞台裏で、実践をしながら経験を積み重ねていくだけです。
「きつけ塾いちき」は、1980年に創立された教室です。
「きつけ塾いちき」は、昭和55年(1980年)に創立されました。今年で、38才を迎えました。
私どもの教室は、「自装の教室」と「他装の教室」のふたつです。
現在は、福岡・東京・宮崎・鹿児島・小倉などにお稽古場があって、多くの方がお勉強されています。
「他装の教室」について…
今回は、私たちの「他装」、つまり「人に着せ付ける」部門を見てみます。
着せ付けの種類は、●十二単の着付け ●和装花嫁着付け ●歌舞伎衣裳をはじめとする日本舞踊の着付け ●振袖の着付け ●美容師のためのプロ着付けなどです。
十二単の需要は少ないのですが、ほかの部門には多くの方が学んでいらっしゃいます。
着付け大好き女子。美容師の仲間。日本舞踊の方。ブライダルや貸衣装の着付け師。芝居の舞台裏の衣裳の着付け師。花街の芸者衆。などがお越しになっています。
教室は「平屋建て」…いきなり「振袖の着付け」を学べます。
一般の教室の場合、着付けの未経験者は、まず「ご自分の着付け(自装)」から学び、それぞれの資格を取って、階段を上がるように上級の着付けを学んでいく「ピラミッド形式」です。
ですから、振袖や、花嫁を学ぶには、相当の時間と経費を要します。
しかし私どもの教室は「平屋建て」…一階建てに、多くの入口のある、全国でも例をみない「平屋の教室」です。
真剣にお勉強をされたい方は、未経験者でも今日から「振袖の着付け」を学べるわけです。受講資格は不要です。
もちろん「日本舞踊の着付け」や「花嫁着付け」も同じです。
生徒さんのなかには、花嫁着付け、舞踊着付けなどを併行しお稽古されている方もいらっしゃいます。
つまり、「きつけ塾いちき」はどこからでも入れる「平屋建て」なのです。
浅草西会館で、舞踊着付け専門の講座
昨年から始まった、「関東芸者…出の衣裳の着付け講座」は、昨年末で終了。
その講座内容と会場を衣替えし、「浅草西会館/日本舞踊着付け講座」として1月からスタートいたしました。
日本舞踊の着付けと、一般のきもの着付けとは、基本的に異なる部分も数多くございます。
また、舞踊の各流派によって、帯結びや着付けが違いますし、歌舞伎衣裳の着付けまで学ぶと、奥行きも巾もかなり広いものになります。
あわてずに、楽しく基本から学んでいくことで、プロの技術を数多く学べます。
時代考証も学びながら、楽しい講座にすることで、皆さまのお役にたちたいと考えていますので、興味のある方は遠慮なくお問合せくださいませ。
この一ヶ月で、日本舞踊の方や、着付け関係の方、着付け教室の先生、一般の舞踊着付けに興味のある女性など、お問合せ頂いています。
まだお問合せをされていない方は、、気軽に下記までご連絡下さいませ。
お問合せ先 090-4489-9745 いちき まで
●霧島山脈近郊の画像一覧
●霧島火山ライブ情報マップ
●新燃岳の火口ライブ映像へリンク