三味線・語り・人形あやつりも代々の家が…台本も江戸時代そのままに
宮崎県都城市山之口町麓の「文弥節人形浄瑠璃」。
江戸時代、京・大阪で流行っていた「岡本文弥」の人形浄瑠璃を習い覚えた、島津藩の参勤交代の郷士たちが持ち帰って演じたのが最初といわれます。
1826年(文政9年)の書き写しの台本が残っています。
以来300年。当時の芸態をそのまま伝承しているところが高く評価され、1995年(平成7年)には、国の重要無形民俗文化財に指定。
貴重な文化遺産として高く評価されています。
全国で、文弥節の人形浄瑠璃が現存しているのは、石川県尾口村、新潟県佐渡、鹿児島県東郷町、山之口町の四ヶ所のみ。
三味線と語りと人形あやつりが、江戸時代の台本そのままに伝えられ、演じられてきています。
驚いたことに、三味線や語り、人形あやつりは、先祖代々その家の者が継いできているのも驚きです。
最後に、地域の方言に演じられる、間狂言(あいきょうげん)はおもしろく、まことに愉快な番外演目です。
三味線を担当している野添さんは、「きつけ塾いちき」(宮崎きもの学院)の着付け講師で、久しぶりの出会いでした。。
ご家族で参加された生徒さんもいらして、楽しい観劇の時間を過ごすことが出来ました。
山之口麓文弥節(やまのくちふもとぶんやぶし )人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり )資料館の内容は、下記のふたつのバナーをクリックしてご覧下さい。
![]()
上のバナーをクリックしてみて下さい。
#日本舞踊着付け #舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け




















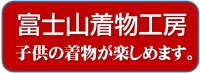




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます