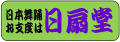「船弁慶」の拵えの最中に…
6月14日、「きつけ塾いちき」の歌舞伎好き14名が博多座に集まり、「六月博多座大歌舞伎」の夜の部の観劇にまいりました。
菊池寛作の、「恩讐の彼方へ」(梅玉丈、翫雀丈の感動の舞台でした。)の幕が下りた幕間に、着到板のある楽屋口から、「片岡愛之助丈(松嶋屋)」の楽屋見舞いに伺いました。
愛之助さんは、次の「船弁慶」の直前に会う事が出来ました。
楽屋では、愛之助丈が、船弁慶の羽二重(カツラや被り物を付ける前の状態)をして、股引を付けていらっしゃる最中でした。
歌舞伎役者であるとともに、上方舞い四流派のひとつ「楳茂都(ウメモト)流」四世家元でもある愛之助さんに、舞踊の事もお聞きしました。
「船弁慶」の舞台が押し迫ったなかで、拵えの迷惑にならないように楽屋を後にしました。

芝居も舞いも堪能した「船弁慶」



「船弁慶」は、片岡愛之助(松嶋屋)の力強い武蔵坊弁慶、市川染五郎(高麗屋)のたおやかな静御前、坂田藤十郎(人間国宝)(山城屋)の気品のある源義経という豪華な舞台。
落ち延びていく義経に乞われて、別れの舞いを静御前が舞います。
松本流家元でもある染五郎丈の壺折姿の舞いは、足元はすべるように、扇子は自然に流れるように…優雅に…充分堪能致しました。
二人を引き離さねばならない弁慶の断固としたな力強さと、受け入れる静御前の凛とした佇まい、静と別れ、高貴なゆえに追われる義経。…いい役者の心地よい芝居でした。
 ●
● ●
●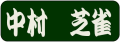 ●
●
 ●
●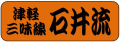 ●
● ●
●
 ●
● ●
● ●
●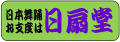
6月14日、「きつけ塾いちき」の歌舞伎好き14名が博多座に集まり、「六月博多座大歌舞伎」の夜の部の観劇にまいりました。
菊池寛作の、「恩讐の彼方へ」(梅玉丈、翫雀丈の感動の舞台でした。)の幕が下りた幕間に、着到板のある楽屋口から、「片岡愛之助丈(松嶋屋)」の楽屋見舞いに伺いました。
愛之助さんは、次の「船弁慶」の直前に会う事が出来ました。
楽屋では、愛之助丈が、船弁慶の羽二重(カツラや被り物を付ける前の状態)をして、股引を付けていらっしゃる最中でした。
歌舞伎役者であるとともに、上方舞い四流派のひとつ「楳茂都(ウメモト)流」四世家元でもある愛之助さんに、舞踊の事もお聞きしました。
「船弁慶」の舞台が押し迫ったなかで、拵えの迷惑にならないように楽屋を後にしました。

芝居も舞いも堪能した「船弁慶」



「船弁慶」は、片岡愛之助(松嶋屋)の力強い武蔵坊弁慶、市川染五郎(高麗屋)のたおやかな静御前、坂田藤十郎(人間国宝)(山城屋)の気品のある源義経という豪華な舞台。
落ち延びていく義経に乞われて、別れの舞いを静御前が舞います。
松本流家元でもある染五郎丈の壺折姿の舞いは、足元はすべるように、扇子は自然に流れるように…優雅に…充分堪能致しました。
二人を引き離さねばならない弁慶の断固としたな力強さと、受け入れる静御前の凛とした佇まい、静と別れ、高貴なゆえに追われる義経。…いい役者の心地よい芝居でした。
 ●
● ●
●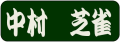 ●
●
 ●
●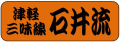 ●
● ●
●
 ●
● ●
● ●
●