
丸山敏雄先生の家紋は亀甲に三階松でした。
丸山 敏雄先生(1892年5月5日 ~1951年12月14日)は、日本の教育者、社会教育家、書家。
戦後の日本において、倫理運動と呼ばれる生活改善運動を創始した。一般社団法人倫理研究所、秋津書道院、しきなみ短歌会の創立者である。
松紋の由来
松は華やかな感じはないが、毅然とした大樹の姿には威厳がある。古くから祖霊の宿る木として、門松などに用いられてきた。松の字を分解すると「十八の公」となる。これは十八年待って、公=大臣になった人の話が中国にある。松は時を待って隠忍し、チャンスがくれば目的を達する訓えにもなった。松が家紋に採用されたのも、このようなめでたい木だからだろう。(丸に一つ松)
主な使用家
「見聞緒家紋」には、出雲の松田氏、讃岐の寒川、福家、飯田、羽床、新居氏などが見える。江戸時代の大名では、永井氏、西尾氏が用いている。松平氏が松を用いず蔦をもちいているのは面白い。
北野天満宮の神紋が「松」、「梅ではないの?」との疑問が生じるところだ。ここは菅公の霊が大宰府から帰る前に一夜にして千本の松が生えたという有名な地で、それに因んで「松」を神紋にしたという。
丸山 敏雄先生(1892年5月5日 ~1951年12月14日)は、日本の教育者、社会教育家、書家。
戦後の日本において、倫理運動と呼ばれる生活改善運動を創始した。一般社団法人倫理研究所、秋津書道院、しきなみ短歌会の創立者である。
松紋の由来
松は華やかな感じはないが、毅然とした大樹の姿には威厳がある。古くから祖霊の宿る木として、門松などに用いられてきた。松の字を分解すると「十八の公」となる。これは十八年待って、公=大臣になった人の話が中国にある。松は時を待って隠忍し、チャンスがくれば目的を達する訓えにもなった。松が家紋に採用されたのも、このようなめでたい木だからだろう。(丸に一つ松)
主な使用家
「見聞緒家紋」には、出雲の松田氏、讃岐の寒川、福家、飯田、羽床、新居氏などが見える。江戸時代の大名では、永井氏、西尾氏が用いている。松平氏が松を用いず蔦をもちいているのは面白い。
北野天満宮の神紋が「松」、「梅ではないの?」との疑問が生じるところだ。ここは菅公の霊が大宰府から帰る前に一夜にして千本の松が生えたという有名な地で、それに因んで「松」を神紋にしたという。




















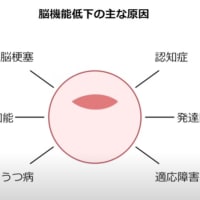







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます