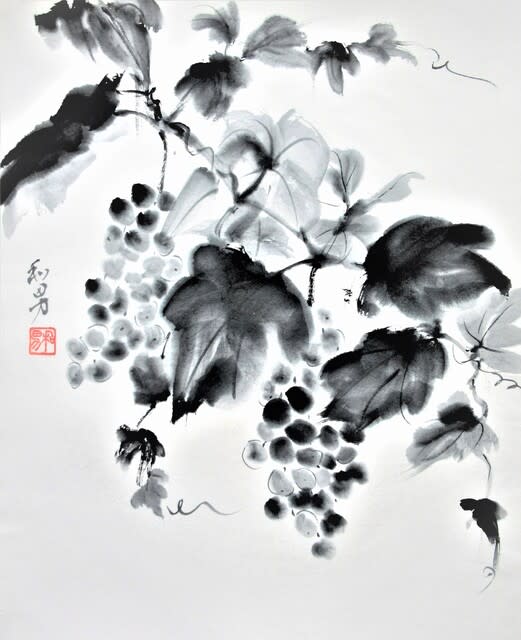トマト連続摘芯栽培は順調に収穫を続けています。現在、第4基本枝を収穫中。

今赤くなっているのが主に第10花房で間もなく収穫が終わるところ。

第1花房、第1基本枝(第2、第3花房)、第2基本枝(第4、5、第6花房)は完全に収穫終了。
第3基本枝も第7、第8、第9花房と終了。
第8、第9花房の着果はやや不安定ながら、まずまずと言える出来でした。
第3基本枝はここで予定の花房は終りですが、おまけの+α花房をつけた株があります。
2本枝が垂れている一番下の花房がそれです。
第3基本枝も第7、第8、第9花房と終了。
第8、第9花房の着果はやや不安定ながら、まずまずと言える出来でした。
第3基本枝はここで予定の花房は終りですが、おまけの+α花房をつけた株があります。
2本枝が垂れている一番下の花房がそれです。


この株は第10花房が赤くなって残っています。その下に着果はイマイチながら第11、第12花房、そして おまけの+α花房を着けています。

反対側はこんな風になっています。穫り終わった第3基本枝。

本来なら第三基本枝までの枯れ葉を整理するところですが、今年はあまり手を掛けていません。
ネットで囲っているため摘葉は省略。ただ、それがむしろ樹勢の維持にプラスになっている可能性があります。
この株は最もステージが進んでいる株。

赤くなっているのは第4基本枝第11花房で、その下に第12花房と+α花房。そして上に変則な第5基本枝2花房を作りました。よく留まっています。
この株はトータル15花房と言うことになります。
下の左の株も上から第5基本枝を試みましたが実が留まりませんでした。右の株の垂れているのは第4基本枝。

昨年は第4基本枝に入り急失速しましたが、今年は概ね順調。
基本枝の花房数を増やしてもあまり競合を起こさず、まずまずの着果が保たれています。
果実も悪くありません。Mサイズ中心ですが、安定して穫れています。
基本枝の花房数を増やしてもあまり競合を起こさず、まずまずの着果が保たれています。
果実も悪くありません。Mサイズ中心ですが、安定して穫れています。

9月中旬の気温が高かったため収穫も進み、残りは大方2、3花房。
害獣の来襲を受け囲っているため、作業をするのも写真を撮るのも少々苦労です。

ここまで早い段階で1株は小生がつまずいて折損、もう1株は株自体が奇形で処分。2株を無駄にしました。
それを考慮すると、2018年以来の出来となるかもしれません。
それを考慮すると、2018年以来の出来となるかもしれません。