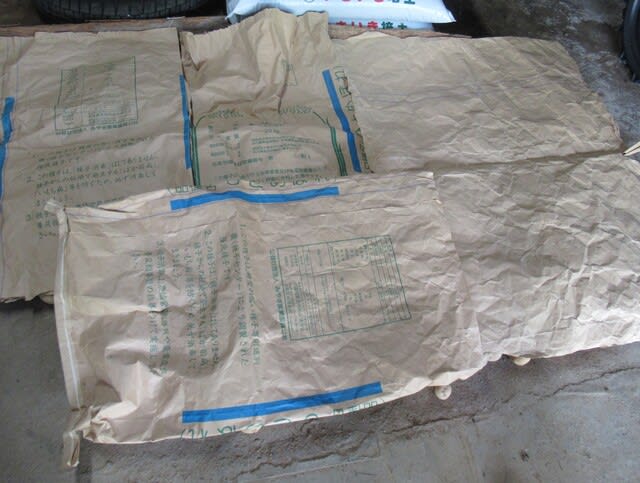ラッキョウの種を植付けました。予定より遅くなりました。
前年は変則で半分を三年子の花ラッキョウとして栽培しました。
当初の予定ではなくアクシデントがあったがためですが、良い経験でした。
今年は例年どおりの普通の栽培です。但し、畝数を3畝に減らしました。
10日前までに苦土石灰を全面、緩効性肥料を帯状施肥し、ロータリー耕耘して準備は出来ています。
前年は変則で半分を三年子の花ラッキョウとして栽培しました。
当初の予定ではなくアクシデントがあったがためですが、良い経験でした。
今年は例年どおりの普通の栽培です。但し、畝数を3畝に減らしました。
10日前までに苦土石灰を全面、緩効性肥料を帯状施肥し、ロータリー耕耘して準備は出来ています。
帯状全層施肥した中心に目印線を付けます。

畝立てには管理機を使用。

畝間は80㎝と広々。
逆転ロータで左回りに往復し畝を立てます。
逆転ロータで左回りに往復し畝を立てます。

鍬で手直しし、かまぼこ型の畝に仕上げます。

2条植も可能な広さかもしれませんが、1条で楽にしっかりと作ることにしました。
種は、収穫した後、竿に吊して乾燥しておいたもの。
余り充実した種とは言えません。
種は、収穫した後、竿に吊して乾燥しておいたもの。
余り充実した種とは言えません。

まず棒で植え穴を開けました。

株間は30㎝。

指で種を土に押し込みます。

深さは覆土後に数㎝になる程度。

覆土しました。

全部で70数球ほどの植え付けとなりました。
覆土して均すと植付け前と見分けがつかないかもしれません。
覆土して均すと植付け前と見分けがつかないかもしれません。

土が固まるのを抑えるため切りわらを掛け終了です。

ラッキョウは収穫した後に漬物にする必要があります。
その役割は助っ人が担ってきました。
今年は小さい花ラッキョウだったので下ごしらえも大変だったと思います。
そろそろラッキョウも終りにしてもいいのではと言う話しが出ました。
少々泣きが入ったと言えるかもしれません。
このラッキョウの種は亡き母が遺したもの。ラクダ種と思われます。
いったん止めてしまうと種が途絶えてしまうので、作り続けてきました。
その母も来年は23回忌。
何はともあれ、まずはしっかり作る必要があります。
その役割は助っ人が担ってきました。
今年は小さい花ラッキョウだったので下ごしらえも大変だったと思います。
そろそろラッキョウも終りにしてもいいのではと言う話しが出ました。
少々泣きが入ったと言えるかもしれません。
このラッキョウの種は亡き母が遺したもの。ラクダ種と思われます。
いったん止めてしまうと種が途絶えてしまうので、作り続けてきました。
その母も来年は23回忌。
何はともあれ、まずはしっかり作る必要があります。