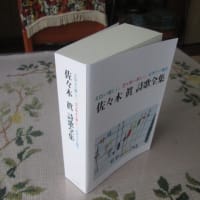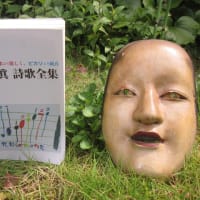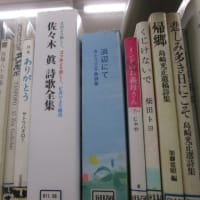倉本一宏訳・藤原道長「御堂関白記 上」を読んで
照る日曇る日 第2124回
脚本家による大河ドラマの道長の描き方を史実と比較するために手に取ってみました。
あのドラマに現代人が恣意的切り貼りした漫画的な奇想や空想はあるが、平安時代の時代の藤原氏の宮廷生活や天皇・貴族の日常生活、そして本当の紫式部や「源氏物語」はまったく描かれていないことがよく分かる日記です。
この上巻では長徳元年995年から寛弘5年1008年までのエピソードがある時は簡単に、またある時は異様なくらい事細かに綴られているのですが、時として日照りが続き、そんな時には安倍晴明などの陰陽師や僧侶を総動員して祈祷し、かなり頻繁に宮中で「作文」しています。
作文とは漢詩を作ることで、例えば寛弘4年3月20日には大雨が降ったので、「林火は落ちて船に漑ぐ」の題で左衛門督、源中納言と、翌21日、22日、23日にも「作文」しています。またかなり頻繁に内裏で犬の屍体が発見され、そのたびに触穢だあ、物忌だあと大騒ぎしています。
道長は最高権力を有する左大臣だったので、年中行事の除目で宮廷人を昇進させたり、争論や喧嘩を成敗することも多かったようですが、寛弘3年5月9日には藤原広業が定佐を闇討ちして定佐の反撃で疵を負った事件を、なぜか悪い方の広業ではなく被害者の定佐を一方的に弾劾したのは、道長の誤審というより、きっと背後に裏事情があったに違いありません。
いま並行して読んでいる荷風やゲルツエンの日記と比べると三者三様で随分生活している空間や時間は違いますが、それぞれにその人の本質が露呈されている。
日記を読むとは、しばしその人と一緒に異なる時空で生きること。げに日記とは面白いものであります。
大リーグ日本リーグに総選挙大統領選挙と出し物続く 蝶人