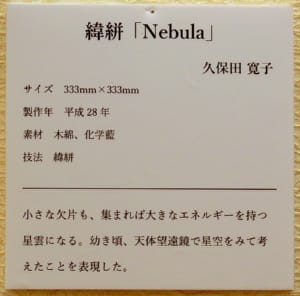朝廷に抗い続ける蝦夷(えみし)の長 阿弖流為(アテルイ)は 悪か、それとも民を護る正義か
古き時代。北の民 蝦夷は国家統一を目論む大和朝廷に攻め込まれていた。そこに、かつて一族の神に背き追放された阿弖流為が、
運命の再会を果たした恋人 立烏帽子(たてえぼし)と共に戻り、蝦夷を率いて立ち上がる。
一方、朝廷は征夷大将軍に、若くとも人望の厚い坂上田村麻呂を据え、戦火は更に激化していく。
戦いの中で、民を想うお互いの義を認め合いながらも、ついに2人が決着をつける時が迫り来ようとしていた。

阿弖流為:市川 染五郎
坂上田村麻呂:中村 勘九郎
立烏帽子/鈴鹿:中村 七之助
阿毛斗:坂東 新悟
飛連通:大谷 廣太郎
翔連通:中村 鶴松
佐渡馬黒縄:市村 橘太郎
無碍随鏡:澤村 宗之助
蛮甲:片岡 亀蔵
御霊御前:市村 萬次郎
藤原稀継:坂東 彌十郎


くまこ 蛮甲 藤原稀繼・坂上田村麻呂・御霊御前(田村麻呂の姉)


佐渡馬黒縄 ・ 坂上田村麻呂 阿弖流為


立烏帽子 鈴鹿

阿弖流為(アテルイ)
京都「清水寺」には
『アテルイ モレ』の碑があるそうだ

東北平定政策反対に反旗を翻しましたが、住民の安泰の為に敵将の軍門に投降し斬首された
蝦夷の勇将アテルイとモレの勇気と賞賛を後世に残す為に碑が建てられたのです。
清水寺の境内にありながら、目立たないこの碑は人間の尊厳を表しているのではないでしょうか。
平安時代、岩手県奥州市地域には蝦夷と呼ばれる種族が住んでいました。
平安朝廷の東北平定政策に対して、首長である阿弖流為(アテルイ)と母禮(モレ)は勇敢に戦いますが
当時の征夷大将軍・坂上田村麻呂の軍門に下り処刑されてしまいます。
平安建都1200年記念にアテルイ モレの碑が建てられたのです。
将軍は両雄の武勇、器量を惜しみ朝廷に助命嘆願しましたが、許されず処刑されてしまいました.
蝦夷の頭領が「阿弖流為」、副頭領が「母禮」で現在では社会科の教科書にも載せられています。
大和政権下には入らない部族を蝦夷と侮蔑して呼び、何度も侵略しますが
789年の巣伏の戦いでは阿弖流為と母禮に大打撃を与えられます。
その後、軍門に下り公家達の押し切りにより処刑されてしまいます。
両雄の武勇と器量を惜しみ、東北経営を任せる任務へと坂上田村麻呂が政府に助命嘆願したことにおいて石碑となったのです。
動きの速い 間髪いれない
とっても面白く もう一度観たい と思うほどでした。
阿弖流為が読めなかったくらい 何も知らなかったのに 今は詳しくなり・・・・