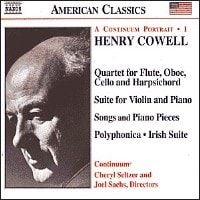「東欧を支配する者はハートランドの死命を制する。ハートランドを支配する者は世界島(ワールド・アイランド)の運命を決する。そして世界島を支配する者はついに全世界に君臨するだろう。*」
(『デモクラシーの理想と現実』)
*Who rules East Europe commands the Heartland :
Who rules the Heartland commands the World-Island :
Who rules the World-Island commands the World.
H. J. マッキンダー(Halford J. Mackinder, 1861 -1947)
英国の地政学者。「現代の地政学の開祖」ともいわれる。
「一八六一年に英国のリンカーンシャーで生まれた。若い頃から周囲の自然が好きで、とくに生物学に深い興味を寄せたが、オックスフォード大学では法律を学んで、弁護士(バリスター)の資格を得ている。しかしながら、その後も彼の英国の自然にたいする関心と情熱はやみがたく、広く国内を旅行して、自然科学と人間社会を結びつける中間的な概念としての "新しい地理学(ニュ―・ジオグラフィー)" を提唱し、学会の注目をひいた。とりわけその『英国と英国の海』(Britain and the British Sea, 1902) は、彼の自信にみちた作品で、英国の地理学をはじめて学問の体系として浮上させた名著として知られている。
(中略)
さらに彼は一九〇四年に、その頃ロンドン大学に新設された政治経済学院(the London School of Economics and Political Science) の院長に就任し、その後約二〇年にわたって同学院の経営に専念するかたわら、経済地理の講義をつづけた。この学校の卒業生や留学生のあいだからは、やがて英本国ばかりでなく、英連邦諸国の政治家や外交官が輩出しているので、その令名は世界的に名高い。」(曽村保信『地政学入門』)
地政学というと、どうしてもカール・ハウスホーファーのような誇大妄想的な学問を連想してしまう。しかも、ナチス・ドイツの東欧侵略の片棒をかついだというイメージが強いので、より一層怪しげな/トンデモな学説と思ってしまう。
けれども、マッキンダーを開祖とする英国系の地政学を見てみると、ごく常識的なことがらを地理学や政治学の用語で語っているに過ぎないことがわかる。
特に、
このような見方で、日本の歴史を考察するとどうなるか。
曽村の前掲書には、小生の興味関心のある「開国」前後から明治維新にかけての記述はないが、日露戦争については、次のように述べてある。
19世紀のロシア帝国(すなわち、マッキンダーの言う「東欧を支配する者」)は、政治的支配力を失いつつあったオスマン帝国のヨーロッパ領をめぐって、バルカン半島への進出を狙っていた(これを「ロシアの不凍港獲得のための南下政策」と見るのは当らない。ランド・パワーであるロシアの、ユーラシア大陸の心臓部(ハートランド)の支配権を獲得しようという動きなのではないか)。
そして、ロシアと同一方向への進出線を持っていたのが、ドイツ帝国。
また、ロシアとドイツとの関係はといえば、
そこで、シー・パワーである大英帝国と同盟を結んでいた日本が、ロシアとの戦争を起こさざるをえなかったというわけである(つまり、イギリス対ドイツの「代理戦争」を、日本対ロシアという形で行なったのが「日露戦争」だ、という考え方もできる)。
ことほどさように、地政学によって、物の見方が、また違ってくることは確かなことであるようだ。
参考資料 曽村保信『地政学入門―外交戦略の政治学』(中央公論社)
(『デモクラシーの理想と現実』)
*Who rules East Europe commands the Heartland :
Who rules the Heartland commands the World-Island :
Who rules the World-Island commands the World.
H. J. マッキンダー(Halford J. Mackinder, 1861 -1947)
英国の地政学者。「現代の地政学の開祖」ともいわれる。
「一八六一年に英国のリンカーンシャーで生まれた。若い頃から周囲の自然が好きで、とくに生物学に深い興味を寄せたが、オックスフォード大学では法律を学んで、弁護士(バリスター)の資格を得ている。しかしながら、その後も彼の英国の自然にたいする関心と情熱はやみがたく、広く国内を旅行して、自然科学と人間社会を結びつける中間的な概念としての "新しい地理学(ニュ―・ジオグラフィー)" を提唱し、学会の注目をひいた。とりわけその『英国と英国の海』(Britain and the British Sea, 1902) は、彼の自信にみちた作品で、英国の地理学をはじめて学問の体系として浮上させた名著として知られている。
(中略)
さらに彼は一九〇四年に、その頃ロンドン大学に新設された政治経済学院(the London School of Economics and Political Science) の院長に就任し、その後約二〇年にわたって同学院の経営に専念するかたわら、経済地理の講義をつづけた。この学校の卒業生や留学生のあいだからは、やがて英本国ばかりでなく、英連邦諸国の政治家や外交官が輩出しているので、その令名は世界的に名高い。」(曽村保信『地政学入門』)
地政学というと、どうしてもカール・ハウスホーファーのような誇大妄想的な学問を連想してしまう。しかも、ナチス・ドイツの東欧侵略の片棒をかついだというイメージが強いので、より一層怪しげな/トンデモな学説と思ってしまう。
けれども、マッキンダーを開祖とする英国系の地政学を見てみると、ごく常識的なことがらを地理学や政治学の用語で語っているに過ぎないことがわかる。
特に、
「彼の地政学を一貫しているのは、主として交通の手段を意味するコミュニケーションの発達が、いかに歴史を変えてきたか」(曽村、前掲書)という問題意識から生まれてきたことを知れば、一層のことであろう。
このような見方で、日本の歴史を考察するとどうなるか。
曽村の前掲書には、小生の興味関心のある「開国」前後から明治維新にかけての記述はないが、日露戦争については、次のように述べてある。
19世紀のロシア帝国(すなわち、マッキンダーの言う「東欧を支配する者」)は、政治的支配力を失いつつあったオスマン帝国のヨーロッパ領をめぐって、バルカン半島への進出を狙っていた(これを「ロシアの不凍港獲得のための南下政策」と見るのは当らない。ランド・パワーであるロシアの、ユーラシア大陸の心臓部(ハートランド)の支配権を獲得しようという動きなのではないか)。
そして、ロシアと同一方向への進出線を持っていたのが、ドイツ帝国。
また、ロシアとドイツとの関係はといえば、
「当時のロシアはドイツからの借金で首がまわらず、また国内の産業もドイツの資本に押さえつけられていて、そのままでゆけば、いずれヨーロッパは、完全にドイツの勢力範囲のなかに吸収されてしまう心配があった。それでロシアは、一八九四年にフランスと秘密同盟を結んで、バランスの回復をはかろうとした。が、一方でドイツの皇帝(カイゼル)ヴィルヘルム二世はその圧力をかわすために、ロシアの宮廷内部の親独的勢力を通じて、しきりに露帝(ツアーリ)ニコライ二世の関心を極東に振り向けようとした。」(曽村、前掲書)との状況であった。
そこで、シー・パワーである大英帝国と同盟を結んでいた日本が、ロシアとの戦争を起こさざるをえなかったというわけである(つまり、イギリス対ドイツの「代理戦争」を、日本対ロシアという形で行なったのが「日露戦争」だ、という考え方もできる)。
ことほどさように、地政学によって、物の見方が、また違ってくることは確かなことであるようだ。
参考資料 曽村保信『地政学入門―外交戦略の政治学』(中央公論社)