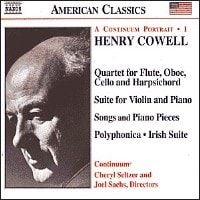(1867: 慶応3年 - 1916: 大正5年)
露伴・荷風を扱ったとなると、やはり、露伴と同年生まれの漱石も俎上に載せざるを得ないでしょう。
と言っても、漱石先生、胃潰瘍で食い意地がはっていた割には、自分で調理をやるといったタイプではなかった。せいぜい、学生時代の自炊程度なのですね。もっとも、これが当時としては一般的なのかもしれませんが。
まずは、成立学舎という私塾に通っていた当時のこと。
1883(明治16)~84(明治17)年頃、漱石(当時はもちろんまだ、その名は名乗っていない)は、実家を出て小石川にある寺の二階に下宿していました。
「其時は間代を払って、隔日に牛肉を食つて、一等米を焚いて、夫で月々二円で済んだ。尤も牛肉は大きな鍋へ汁を一杯拵へて、其中に浮かして食つた。拾銭の牛を七人で食ふのだから、斯うしなければ食ひ様がなかつたのである。飯は釜から杓って食つた。」(『満韓ところどころ』)というのですから、いかにも明治時代の貧乏な書生さんらしい生活。おそらく漱石も当番に当たったときは、汁や飯を拵えたことでしょう。
同様の書生生活は、第一高等中学校予科時代(明治19年頃)も行われました。ただし、今度はアルバイトで私塾の教師をしていたので、多少生活は向上して、外食も併用しています。
(同級生の中村是公と生活費を共同出資して)「あまる金を懐に入れて、蕎麦や汁粉や寿司を食ひ廻つて歩いた。共同財産が尽きると二人とも全く(外へ)出なくなつた。」(『永日小品』)「食ひ廻つ」た、という割には、蕎麦や汁粉、寿司(当時は高級品ではなく、ファースト・フードの屋台店)というのが、かわいらしいではありませんか。
この辺は、『当世書生気質』に描かれている、牛鍋屋で鍋を囲んで酒盛りをする不良書生とはいささかわけが違う(『書生気質』は明治18~19年の発表だから、ほぼ時期が重なる)。
「私は乱暴書生ではない。極く気の小さい大人しいものである。」(『模倣と独立』)と、漱石自身が語ることばに嘘や誇張はありますまい。
さて、成人してからの生活では、松山やロンドン時代、下宿といっても賄い付きですから、調理する必要はまったくなく、ぽーんとお話は、漱石山房へ飛びます。
鏡子夫人が朝寝坊で、いくら弟子たちから「悪妻」視されようと、小女を雇っている以上、明治時代の一家の主人は、炊事・洗濯・掃除などの家事に手をつけることはない。それでも、病気や来客の時以外は、漱石は手のかからない方だったでしょう(ただし、「神経衰弱」がひどくなると、その迷惑は子どもたちにまで及んだという)。
朝食は耳を落とした食パンを、火鉢の網に乗せて自分で焼き、バターをつけて食べていましたし(逍遥の朝食も自分で焼いたトーストで、こちらは神田精養軒のパンに小岩井農場のバターを塗ってから、狐色の焦げ目がつくまで網に載せるというもの)、昼食でもビスケットを好んで摂っていました。
こと漱石の食事に関しては、夕食以外は面倒がほとんどない。それに、転居などの人手が要る時には、弟子たちが集まってくれる。
というのが漱石の生活の基本線でありましたが、この時代の男性にしては、手間が掛からない方ではなかったでしょうか。