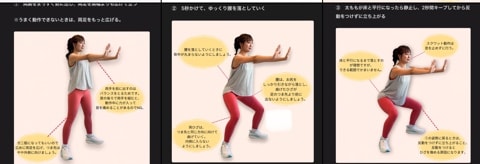【脳の老化を防ぐ食事】認知症を遠ざけ、脳の健康を守る神食品とは
ヨガジャーナルオンライン編集部 より 241210
できるだけ体にいいものを食べたほうがいいとわかっていても、「今日は何を食べよう?」というシンプルな問いが、重荷になることはよくあります。でも、できることなら、手間をかけずに健康的な食事をしたいですよね。
大人気YouTubeチャンネル「本要約チャンネル」が、世界最新の知見と2000冊の書籍から導き出された本当に健康にいい「食べ物、食べ方」を一冊にまとめました。
著書『結局、何を食べればいいのか? 』(アスコム)より、一部内容を抜粋してご紹介します。
⚫︎認知症を遠ざけ、脳の健康を守る神食品
アミロイドβが蓄積しないように、ポリフェノールや質のよい脂質を(主に青魚の生食で)とり、糖質のとりすぎを避ける。これらのポイントを押さえつつ、その他の脳によい影響を与える食品をとり、悪影響のある食品を避けることが、脳の健康を守る鍵となります。
私たちの脳は、精密機械のようなものです。適切な燃料と定期的なメンテナンスがあれば、美しいクラシックカーも長年にわたって性能を発揮し、現役で走り続けることができます。脳においては、その燃料とメンテナンスが日々の食事です。運動や睡眠も大切ですが、食事という燃料がなければ何も始まりません。
想像してみてください。毎日の食事を少し変えるだけで、5年後、10年後のあなたの脳が、より健康で、活発になっている姿を。そして、当たり前の話ですが、私たちの脳は、あれあれ症候群になっても、認知症になっても、車のように乗り換えることはできません。
元気に、幸せな老後を過ごすために、日々の食事を改善していきましょう。また、先述したように、脳によい食事をとり、質のよい睡眠がとれるようになると、驚くほど脳のコンディションが上がります。
ですから、将来の認知症のリスクを避けるだけでなく、今現在の仕事や勉強のパフォーマンスも大きく変えることができるのです。本項では、これまでに紹介した内容のまとめも含めて、具体的に脳にいい食品を網羅的に紹介します。ぜひ食生活の参考にしてください。
⚫︎アミロイドβ の蓄積を予防する食品
アミロイドβの蓄積は、アルツハイマー型認知症の主要な特徴の一つです。これらの食品は、その蓄積を予防または軽減する可能性があります。
▶︎ブルーベリー🫐
ブルーベリーは脳の健康に効果的な果物です。豊富なポリフェノールがアミロイドβの凝集を抑制すると考えられています。フラボノイドやアントシアニンといったポリフェノールには強力な抗酸化作用があり、脳細胞を酸化ストレスから守ります。ベリー類のポリフェノールをしっかりととるには皮ごと食べるのが大切で、ブルーベリーは元々まるごと食べるのが一般的。その点でも優れた食品です。実が小さいので、ぶどうなどに比べて糖質のとりすぎを避けやすい点も最高です。
研究によると、ブルーベリーの摂取は認知機能の改善と関連しており、特に記憶力や処理速度の向上が見られます。2019年に発表されたカナダ農業食品省の論文によれば、毎日3分の1カップのブルーベリーを食べることで、重要な病気や症状のリスクを軽減できるとされています。ヨーグルトに加えて食べると、腸への効果も大いに期待できます。
▶︎🍵緑茶
強力な抗酸化作用があるポリフェノール「カテキン」が豊富な上に、日々の習慣として取り入れやすい飲料です。特に、甘い飲料を好んで飲んでいる方は、ぜひその代わりに緑茶を日常的に飲んでほしいところです。緑茶の主成分・カテキンの一種「エピガロカテキンガレート(EGCG)」に、アミロイドβの凝集の抑制効果があると考えられています。
▶︎🍇ぶどう(特に赤ぶどう)
先述したポリフェノール「レスベラトロール」を豊富に含むぶどう。レスベラトロールには神経を保護する作用があり、アミロイドβの産生を抑制する効果も期待されています。この健康効果を得るためには、皮ごと食べるようにしてください。
▶︎🍫ダークチョコレート
チョコレートやココアの原料・カカオ豆に含まれるポリフェノール「カカオポリフェノール(フラバノール)」は、認知機能の改善に効果的です。また、アミロイドβの凝集を抑制する可能性もあると考えられています。しつこくなりますが、どれだけカカオ含有量が高いものでも、砂糖入りのチョコレートは避けてください。
⚫︎脳に良質な脂質を提供する食品
その多くが脂質でできている脳の健康にとって、適切な種類かつ、良質な脂質をとることは極めて重要です。
▶︎🐟小さめの青魚
まずおすすめしたいのは、イワシやサンマ、サバなどの小さめの青魚です。DHAやEPAだけで言えばマグロも豊富に含んでいます。ただ、大きな魚は生物濃縮によって水銀の含有量が多い問題があります。できれば養殖より天然、加熱調理より生食をしていただきたいところですが、食べないことに比べればサバの水煮缶でも問題ありません。また、刺身が苦手な方は加熱もやむなしですが、揚げるのは可能な限り避けてください。
▶︎🐠サケ
白身魚のサケもオメガ3脂肪酸が豊富です。DHAやEPAを効率よくとるにはサーモントラウトが特におすすめです。こちらも可能であれば生で食べたいところです。また、アルツハイマー型認知症と関連性があると考えられるビタミンDも豊富に含んでいます。さらに赤い身の理由である天然色素の「アスタキサンチン」は、強い抗酸化作用を持っているので、炎症を防ぎ、血管を守る効果もあります。
▶︎亜麻仁油
植物性オメガ3脂肪酸の宝庫で、抗炎症作用もあります。亜麻仁油に含まれる「α −リノレン酸(ALA)」は、体内でDHAやEPAに変換され、脳の健康に役立ちます。サラダドレッシングや冷製料理に使うことで、手軽に良質な油を摂取できます。先ほども書きましたが、熱に非常に弱いので、冷暗所で保管し、加熱調理には絶対に使わないように気をつけてください。
▶︎くるみ
見た目も脳に似ているくるみは、植物性のオメガ3脂肪酸・ALAが豊富です。くるみの定期的な摂取が、認知機能の改善に効果的とする研究があります。おやつや料理の付け合わせとして、毎日少しずつ摂取するのがおすすめです。
▶︎オリーブオイル
オリーブオイルの主成分はオメガ9脂肪酸の「オレイン酸」ですが、ポリフェノールなどの抗酸化物質も豊富に含んでいます。これらの成分によって、脳の炎症を抑え、酸化ストレスから脳を守る健康効果が期待されています。たとえば、オリーブオイルの摂取量が多い人ほど、認知機能低下のリスクが低いことを示す大規模な疫学研究があります。また、オリーブオイルに含まれる「オレオカンタール」という成分が、アルツハイマー型認知症の研究で注目されるたんぱく質「タウ」の蓄積を減少させる可能性も報告されています。
オメガ9脂肪酸が豊富で、ビタミンもバランスよく摂取できるアボカド。脳の血流を改善する効果があり、アボカドの摂取が認知機能向上と関連していることを示唆する研究もあります。これらの食品から良質な油を摂取することで、脳の正常な構造を維持し、機能を向上させることが期待できます。ただし、油は高カロリーなので、適量を守ることが大切です。
⚫︎脳の炎症を抑える食品
慢性的な脳の炎症は、認知機能の低下や神経変性疾患のリスク増加を招きます。その悪影響を避けるには、抗炎症作用を持つ食品をとることが大切です。
▶︎ショウガ(生姜)
古くから薬用植物として親しまれているショウガ。「ジンゲロール」や「ショウガオール」といったポリフェノールが豊富で、近年は脳への好影響が注目されています。これらの成分が脳の炎症を緩和する可能性を示唆する研究や、ショウガの摂取が認知機能の改善につながるとする研究もあります。すりおろして料理に入れたり、生姜茶を飲むことで簡単に摂取できるのもよい点です。
▶︎ブロッコリー🥦
ブロッコリーは栄養価が高く、特にその抗炎症作用が注目されています。豊富に含まれるポリフェノール「スルフォラファン」が、脳の炎症を抑制する鍵となっています。ある研究では、スルフォラファンが脳の炎症を軽減し、酸化ストレスから脳を保護する可能性が示されています。また、ブロッコリーに豊富に含まれる抗酸化物質や葉酸も、脳の健康維持に重要な役割を果たします。加熱調理をするなら、栄養素を損なわないように食感を残す程度が理想です。
▶︎にんにく🧄
肝臓にもよい「アリシン」が豊富で、抗炎症作用と抗酸化作用があります。脳の炎症を抑制し、認知機能を維持する効果が期待されています。
▶︎トマト🍅
さまざまながんの予防効果などでも有名な「リコピン」が豊富なトマト。リコピンには神経保護作用があり、脳の炎症を抑制し、酸化ストレスから脳を守る効果も期待されています。生で調理しても栄養価が高く、毎日の食事に取り入れやすい食材です。加工品ですが、トマトジュースも非常におすすめです。
▶︎パイナップル🍍
「ブロメライン」という酵素が豊富で、強力な抗炎症作用があります。ある研究では、ブロメラインが脳の炎症を軽減し、認知機能を改善する可能性が示唆されています。これらの食品を、日々のバランスのよい食事に取り入れれば、脳の炎症を抑制し、認知機能の維持・向上に役立つことが期待できます。
⚫︎体内から毒をデトックスし脳を守る
ここからは、この章でまだ触れていない理屈を簡単に説明しながら、その他の脳によい食事を紹介していきます。
▶︎解毒作用のあるパクチー、キャベツ、ルッコラ
生活習慣病は、突き詰めると慢性炎症から始まります。体内で自覚症状のない炎症が続くと、血管にダメージが蓄積される。結果、高血圧や動脈硬化につながります。それだけでも命に関わる問題ですが、認知症のリスクも上がってしまいます。炎症を避け、血管を守る。これが、脳に限らず食事術の基本となります。
その上で、もう一つのポイントになるのが「毒になる物質の排出」です。身の回りには、見えないホコリやカビ、排気ガスなどが舞っています。どれだけ気を遣っても、これらの体内への侵入機会はゼロにできません。これは食事にも言えることで、小さなイワシやサンマ、サバにも水銀は含まれています。ただ、マグロほどの量ではないので、基本的には人間の持つデトックス機能で排出できるわけです。裏を返せば、体に悪い物質を排出できないと、健康にも悪いということ。
そこでおすすめなのが、香草のパクチー(コリアンダー)です。好き嫌いの分かれる食材ですが、ビタミンやミネラルが豊富で、水銀や鉛などの重金属を排出する作用もあります。水銀の多い大きな魚を食べるなら、せめてパクチーも一緒に食べましょう。
肝臓の解毒機能を高める「イソチオシアネート」を含むキャベツも、デトックスに役立つ野菜です。抗酸化作用のあるビタミンCも豊富で、全身に効く素晴らしい食材です。春に出回る芽キャベツは、普通のキャベツより栄養価が高く、食物繊維も多いので特におすすめです。
また、イソチオシアネートに加えて、肝臓をサポートする「グルコシノレート」もとれるルッコラもおすすめの野菜です。
▶︎ホモシステインを減らすブロッコリー
認知症対策で意識したいのが「ホモシステイン」というアミノ酸の一種です。ホモシステインは、必須アミノ酸「メチオニン」をつくる際にできる中間代謝物です。メチオニンの代謝にはビタミンB群が必要で、ビタミンB6、B12、葉酸などのビタミンBが不足すると、ホモシステインが体内に溜まります。この「ホモシステインはあるが、メチオニンはつくれない」状態が続くと、ホモシステインが血液中に移っていきます。そうして血中濃度が15μmol/ℓを超えると「高ホモシステイン血症」となり、動脈硬化を引き起こし、認知症リスクも高くなってしまうのです。
つまり、認知症対策にはビタミンB群も大切なのです。そこでおすすめの野菜が、先ほども登場した、葉酸やビタミンB1を豊富に含むブロッコリーです。ビタミンB1も、不足して「ビタミンB1欠乏症」になると、記憶障害や認知機能の低下につながるので、脳を守る上で重要な野菜です。また、先ほど紹介したパクチー、キャベツ、ルッコラもビタミンB群を豊富に含んでいます。
📗『結局、何を食べればいいのか? 』(アスコム)
この本の著者/本要約チャンネル
「真に役立つ知識を、誰にでも分かりやすく伝える」 を信念に、YouTubeチャンネル「本要約チャンネル」を運営。医学部在学中に起業し、チャンネル登録者数167万人、再生回数4億7千万回以上(2024年7月末時点)と、大きな支持を集めている。
1万冊以上の書籍を読み、一日五冊もの読書を続ける生粋の本好きでもある。数々の健康書や難解な医学論文を分かりやすく解説した動画は、若者から高齢者まで幅広い世代から支持を集めている。ファスティングを取り入れた1日1食生活を実践するなど、健康的なライフスタイルを長年実践している。著書に『「読む」だけで終わりにしない読書術 1万冊を読んでわかった本当に人生を変える方法』(アスコム)がある。
▶︎ヨガジャーナルオンライン編集部
ストレスフルな現代人に「ヨガ的な解決」を提案するライフスタイル&ニュースメディア。"心地よい"自己や他者、社会とつながることをヨガの本質と捉え、自分らしさを見つけるための心身メンテナンスなどウェルビーイングを実現するための情報を発信