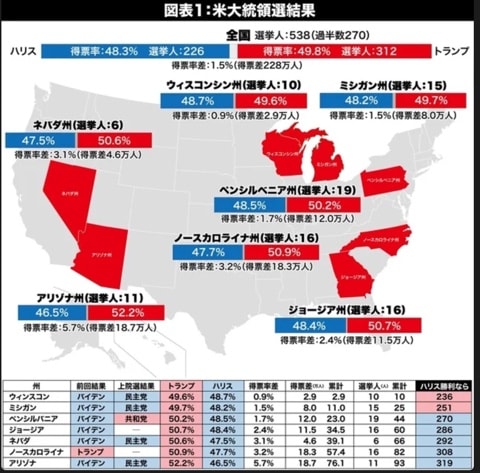島津製作所「ノーベル賞級」新型時計は何がすごい
東洋経済Online より 石川 陽一:東洋経済 記者
発売した光格子時計「イーサクロック」の見本と、その開発メンバーたち(記者撮影)
研究者にとって最大級の名誉とされる、ノーベル賞の受賞者を輩出した日本企業はわずかに数社のみ。
そのうちの1社である島津製作所(2002年に田中耕一氏が化学賞を受賞)が3月5日、100億年たっても1秒程度の誤差しか生じない「光格子時計」を世界で初めて発売した。
【】漆黒の箱に包まれたイーサクロック。複雑な内部も報道陣に初公開された
島津製作所の広報担当者は「ノーベル賞級の製品だ」と胸を張る。
【】漆黒の箱に包まれたイーサクロック。複雑な内部も報道陣に初公開された
島津製作所の広報担当者は「ノーベル賞級の製品だ」と胸を張る。
とは言っても、同社の社員が候補になるというわけではないそう。
実用化を果たしたことで、発明した東京大学・香取秀俊教授の受賞を引き寄せる可能性があるという。
価格は1台5億円、納期は約1年。国内外で3年計10台の受注を目指す。
価格は1台5億円、納期は約1年。国内外で3年計10台の受注を目指す。
光格子時計は「秒」の定義を変え、将来の社会基盤になり得るというが、一体どのようなものなのか。
⌛️2030年に「秒」の再定義を予定
光格子時計は、特殊なレーザーを用いて生成される格子状の空間に、1万個以上のストロンチウム原子を一つずつ格納し、その原子の振動数を計測することで時間を測定する。
⌛️2030年に「秒」の再定義を予定
光格子時計は、特殊なレーザーを用いて生成される格子状の空間に、1万個以上のストロンチウム原子を一つずつ格納し、その原子の振動数を計測することで時間を測定する。
この方式により、現在の「秒」を定義するセシウム原子時計と比較し、100倍以上の精度を誇る。
国際度量衡委員会は2030年に「秒」の再定義を予定しており、ストロンチウム光格子時計は有力候補となっている。
国際度量衡委員会は2030年に「秒」の再定義を予定しており、ストロンチウム光格子時計は有力候補となっている。
つまり、イーサクロックが世界の標準時刻を定める日が来るかもしれない。
イーサクロックは、アインシュタインが唱えた「一般相対性理論」を活用できる。
イーサクロックは、アインシュタインが唱えた「一般相対性理論」を活用できる。
地球の中心から離れるほど重力の影響が弱まり、時間の進みが早くなる、という理論だ。
香取教授らのグループは2018年、東京スカイツリーの展望台(高さ約450メートル)と地上に光格子時計をそれぞれ設置し、時間のゆがみを調べた。すると展望台と地上で、時間の進みに差があることが実際に観測された。
これを地殻の測量に応用すれば、地中奥深くのプレートが動いた際、1センチ単位で観測できるようになるという。地震や火山活動の予知に繋がると期待される。
さらに、光格子時計は通信の高速・大容量化やGPSの高精度化など、多岐にわたる分野への応用が期待されている。
香取教授らのグループは2018年、東京スカイツリーの展望台(高さ約450メートル)と地上に光格子時計をそれぞれ設置し、時間のゆがみを調べた。すると展望台と地上で、時間の進みに差があることが実際に観測された。
これを地殻の測量に応用すれば、地中奥深くのプレートが動いた際、1センチ単位で観測できるようになるという。地震や火山活動の予知に繋がると期待される。
さらに、光格子時計は通信の高速・大容量化やGPSの高精度化など、多岐にわたる分野への応用が期待されている。
国内外の研究機関からの関心も高く、島津製作所は「将来の社会基盤となる」と、その可能性に自信を見せる。
報道陣に公開したイーサクロックの実験風景(記者撮影)
⌛️創業150年目の新事業
光格子時計は構造が複雑で、装置が巨大になることが課題だったが、島津製作所はレーザーや制御システムの効率化を追求し、装置の小型化に成功した。
また、堅牢性の向上や周波数の自動調整機能なども実現し、メンテナンスの手間を大幅に削減した。
ノーベル賞の選考では、研究成果の社会実装も重要な要素となる。今年で創業150年を迎える島津製作所。メモリアルイヤーに手がけた新事業は、偉業達成を手助けするだろうか。
本記事はダイジェスト版です。詳報記事(有料会員限定)は「東洋経済オンライン」のサイトでご覧いただけます。「イーサクロック」の仕組みや、開発までの道のりなども取り上げています。
ノーベル賞の選考では、研究成果の社会実装も重要な要素となる。今年で創業150年を迎える島津製作所。メモリアルイヤーに手がけた新事業は、偉業達成を手助けするだろうか。
本記事はダイジェスト版です。詳報記事(有料会員限定)は「東洋経済オンライン」のサイトでご覧いただけます。「イーサクロック」の仕組みや、開発までの道のりなども取り上げています。