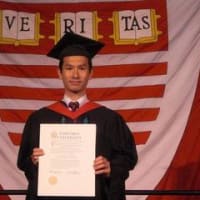「Safe Medicine(安全な医薬品)」というテーマの下、2週間にわたって続いてきたケネディスクールの「春の集中特訓道場」Spring Exerciseもようやく今日で終止符を打ちました。
この2週間、600ページにわたるリーディングや様々なウェブサイト等を使ったサーベイ、David Kessler元FDA長官を含むゲストスピーカーやMPP(Master in Public Policy)プログラムのコアコースを担当する教授陣からの講義、そして5人1組となって取り組むグループワークを通じて、薬事行政のあり方とFDA(Food and Drug Administration:連邦食品医薬品局)の改革案について、今年9月に予定されているPDUFA(Prescription Drug User Fee Act:処方箋薬ユーザー手数料法)の改正の動きとも関連付けながら、頭を悩ませてきました。
既に紹介したとおり、Spring Exerciseを通じて求められるアウトプットは三つ。一つは個人作業として上院議員への政策提言メモの作成(750字)、二つ目はグループワークの成果物としてFDA長官への改革案のプレゼンテーション(30分)、そして三つ目が報告書(25ページ)の作成です。
そして、この二週間の息をもつかせぬディマンディングなスケジュールがこちら。特にプレゼン準備と報告書作成に向けたグループワークが本格化した今週は相当タフでした。
ちなみにチームメンバーは、カナダで財務大臣の政策担当秘書だったカリム、ニューヨーク大で国際関係を学んだ後ダイレクトにケネディスクールに進学したナタリエ、教育関係のNGO出身のジェフ、フロリダ大で経済を学びケネディスクールに進学したブリアン、そして僕の5人。
皆気さくで優秀なヤツらですが、先週木曜日に配布されたメンバーリストを見た瞬間、
「イカン、僕以外全員ネイティブだ・・・」
「英語での作業に大分慣れてきたとは言え、やはり日本語と比べれば読み書きのスピードは相当落ちる。それに彼らが彼らのペースで言いたいことを不規則かつ好き放題しゃべるであろうグループワークで果たして主体的に議論に貢献できるだろうか・・・」
こんな不安がよぎりました。
「どうしたら主体的にグループワークに貢献できるだろう・・・」と考えた結果、「取りあえず先手を打つことが必要」との結論に。
具体的には、グループワークを始めるに当たり、主な論点や全体の作業工程についてまとめた紙を自分で作成、またプレゼン資料についても、僕が全体の叩き台をまず最初に作って示し、それをもとに皆で議論してもらうという作戦です。
もちろん、前日の夜から明け方にかけて翌日のグループワークの論点ペーパーをまとめたり、プレゼン資料の案を一人で作って皆に示すのには相当な労力がかかります。おかげで日曜日から木曜日までは、ほとんど睡眠時間がありませんでしたが、残念ながらこうでもしないと、ネイティブ同士の議論に主体的に参加したり、ましてそれをリードすることなど、とてもできません。
結局、苦労した甲斐あって作戦は成功。皆からは
「ワォ!これからゼロから始めなきゃならないと思ったら、もう出来てるじゃないか!」
と好評。その後も論点メモや叩き台に沿って議論が進んだため、僕にとっても非常に貢献しやすい土壌・雰囲気を作ることができました。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
そしてようやくたどり着いた最終日の今日。担当教授二人とFDA高官を前に、「Reform Strategy for Safety, Accessibility and Trust」と題した僕らの努力の結晶をナタリエが見事なプレゼンで締めくくります。
先週の記事で詳しく紹介したような困難な問題を抱えるFDA改革のキー・ポイントとして僕らが強調したのが以下のスライド。
天秤の上に乗っているFDAの究極の目標「医薬品の安全性・効果(Safety/Efficacy)」と「入手可能性(Accessibility)」がバランスを保ちつつ達成されるために、「独立した持続可能なリソース」「情報の共有」、「医薬品のレビュープロセス」による支えが必要であることを示しています。
この3要素を実現するために必要な具体的な改革案をその優先順位とともに示したところ、やはり議論の焦点になったのが、FDAに対する製薬業界の影響力を如何に最小化できるかという点。
FDA高官からは、
「FDAが“独立した持続可能なリソース”を確保するために、PDUFAから、『FDAは製薬業界から集めた手数料の使い道を決める際、製薬会社と相談しなければならない』という条項を無くすべきだ、という提案は、これまで我々も相当考え議論をしてきた。しかし製薬業界が不利になるような法律改正の実現は中々難しい。何しろ連中はアメリカの主要産業。政治的な影響力はモノ凄いからな。」
「この案を実現するためには、FDAは国内のいずれかのグループとタッグを組んで、製薬業界と対峙していかなければならない。もし思いつくパートナーがいたら是非示してもらいたい。」
との“生々しい”示唆が。
チームメートからは、消費者団体とのつながりの強い有力な議員とのパイプを強化する案や、次善の策として「影響力を排除できないまでも、FDAと製薬会社の交渉の内容を公開することで、彼らが商業上の理由でFDAにプレッシャーをかけることを難しくできるのではないか」との案が示されます。
僕からは、
「FDAがタッグを組めるパートナーは米国内だけでなく、海外、つまり外国政府のカウンターパートにも求めることができると考える。医薬品の安全性審査プロセスについては、他の政策領域と同じ様に、経済のグローバル化を反映して、各国政府間で内容のコンバージェンス(収斂)が進んでいる。FDAはEUや日本の厚生労働省等と連合を組み、彼らを外圧として利用することで、他の先進国では例のない“お伺い条項”の廃止を米国内で主張していけるのではないか。」
と提案。はたして「外圧を利用して国内の改革を進める」という考え方が、「我こそは世界の中心」が国是?のアメリカで通用するかと思いましたが、FDAの高官は大きく頷きながら、
「医薬品審査プロセスの“Harmonization”(調和)については、近年正に外国政府カウンタパートとの議論を本格化しているところであり、その際の論点を議会に提示することは適切で、また法律改正の一つのきっかけになることはあり得る。」
とコメント。ここで僕らのプレゼン時間は終わりました。最後にFDAの高官を囲んでの記念写真。2週間のロードがようやく終わった解放感からか、皆いい笑顔です。
最初はグループワークにしっかり貢献できるか甚だ不安でしたが、皆で一致団結してそれなりのプレゼンと報告書が仕上がったのではないかと思えます。また、Spring Exerciseが始まる前は顔を見ると挨拶をする程度だったチームのメンバーとも、本当に長い間ケネディスクールのミーティング・スペースで議論をともにし、必死になって一緒にキーボードを叩き、家に戻ってからも深夜に電話で話をしながら作業を進めたりしたこともあって、最後は相当意気投合することができました。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
プレゼンが終わった後、昼の1時半からはSpring Exerciseの打ち上げが待っていました。開放感に満ちたMPP1年生の面々だけでなく、学生たちとともに二週間走ってきた教授陣もJFK Street沿いの“Red Line”に集結し、真昼間からビールの飲み放題!また、打ち上げでは、上院議員への政策提言メモで最優等だった5名が教授から表彰されました。
僕の提言メモも、表彰こそ逃したものの、それに準ずる高い評価をもらうことができ、グループワークと併せてこの二週間、妥協せず走り抜けた後の最高のビールを仲間と堪能することができました。
気が付くとボストンは春真っ盛り。「ようやく終わった~!」という開放感に浸るにふさわしい青空です。
でも実は、、、
これから期末試験やレポート等の課題が普通にあるんですよね・・・・