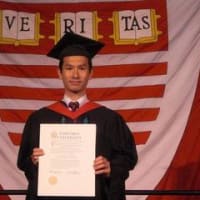言葉では言い尽くせない興奮と感動と、そして疲労・・・がいっぱいだった2度目のKorea-Japan Tripから早1月半。ケネディスクールの授業も終わり、キャンパスからも次第に学生たちの姿が減っていく中で、トリップに参加した一学生からのエッセイが届きました。
日本・韓国を独自の視点で、そして母国インドへの思いを馳せながら綴ってくれたのは、一度このブログでも紹介したMPP(Master in Public Policy)プログラムのデヴプリア君(1月27日付“或るインド人学生の日本・韓国への想い”)。
金銭的な事情でトリップへの参加がどうしても叶わない主として発展途上国出身の学生を両国へ案内すべく今年度初めて立ち上げたKorea-Japan Friendship Fundの受賞者です。今日の記事では、トリップを創り上げた日本人・韓国人の幹事、そしてこのトリップを支えてくれた両国の大勢の人々に向けた彼からのメッセージをお届けしようと思います。
* * *
日本について
建築を学んだ私にとって、日本の地に降り立つことができたのは、東洋の建築物を目の当たりにできる素晴らしい贈り物に他ならなかった。私をかつて鼓舞した偉大な建築家の一人フランク・ロイド・ライトの建築物、伝統的な広島、宮島の建築様式、東京の近代的な建物、あるいは関西空港を支える技術・・・これらを体験する機会に私は恵まれたのだ。
関西空港を支える驚嘆すべき技術水準については、1.7キロにも及ぶ人口の“浮島”に一日10万人もの乗客を扱うことのできる容量を6千人のマンパワーでわずか3年で作り上げたという驚異が、日本人の仲間たちの間であまり知られていなかったこともまた驚きであった。
宮島では日本でもっとも賞賛されている風景美、美しく彩られた大きな鳥居が波間にたたずむ有名な厳島神社と出会うことができた。こうした風景に魅了されただけでなく、美しい鹿たちが参道を行きかう姿もまた印象的であった。宮島に滞在中に泊まった伝統的な旅館の温泉は非常に興味深い経験であった。太平洋を跨ぐ長旅から私の心に活力を与えてくれた温泉はまた、トリップに参加した仲間との友情を深めてくれる場所でもあった。
息を呑むようなスピードで走る新幹線で移動する間、私はこの国は第二次世界大戦後、向かう方向を変えたのだということに改めて思いを致した。広島はまさに平和と力(Power)の象徴のような場所であった。日本人は戦後、力(Power)の追求を捨てたといわれるが、私はむしろ、日本人は追及すべきパワーを再定義し、時間に対する厳しさや素晴らしい品質や技術によって支えられる力強い経済を目指してきたのだと気付いた。
私はまた、インドが日本に匹敵するインフラを提供できないか夢見ている。無論この夢は現実とは程遠い。しかし、私はいつの日か達成できると信じている。日本の成功を見ているとインドの夢の達成に希望が沸いてくるようだ。しかしそのためには、インド人は日本人一人一人が持っている労働倫理、アートのような完璧さを目指して職務に当たる職業人としての姿勢を育てていくことがまず必要だと思っている。
このトリップは日本の様々な省庁出身の日本人幹事と交流できた素晴らしい機会でもあった。なぜなら、彼らは日本がなぜ自国を変革することができたのか、あるいは日本のさまざまな政策やコンセンサスを重視する意思決定が日本の成長にどのような役割を果たしてきたかについて、自分なりの見解を語ってくれたからだ。私はこのトリップの間、ずっと興味深々で多くの質問を投げかけ続けたが、彼らからの答えを聞くことで、私の国、インドが将来どのように前進することができるか、自分の中で頭の体操をすることができたのだ。
しかし、このトリップの中で私の注意を最も引いたのは日本、あるいは東アジア地域における超大国としてのアメリカの影響力の強さである。やや言いすぎと感じられる方もいらっしゃるかもしれないが、アメリカにいても気付かない程強いメッセージを受け取ったのだ。インドではアメリカの影響は比較的最近のもので、また限定的でもある。しかし、アメリカの駐日大使、あるいは日本の外務大臣との対話の中で、私はアメリカという存在が日本の政府高官のマインドのかなりの部分を占めていて、日本や東アジア地域の政策の方向に大きな影響力を及ぼしているのではないかと感じたのである。
一方、日本は私にとって平和と調和の象徴のような国である。技術分野では最高峰の品質を保ちつつ、その豊かな伝統的な文化を誇りを持って保持しているさまざまな顔を持つ国である (つづく)。
* * *