| 城名 | 伊勢上野城 |
| 住所 | 津市河芸町上野曲輪 |
| 築城年 | 天文17年(1548)の記録に分部氏から三間氏にこの城が預けられたと記されているのでそれ以前に原型は築城されている。 |
| 築城者 | 織田信包-分部光嘉(織田信包の指示で分部氏が築城した) |
| 形式 | 平山城 |
| 遺構 | 郭、土塁、井戸、堀切 |
| 規模 | 東西230m×南北120m(本丸 80m×80m) |
| 城主 | 小田信包-分部光嘉-光信 |
| 標高 | 38m |
| 比高 | 35m |
| 歴史 | 永禄11年(1568)信長の伊勢侵攻のとき、弟信包がこの一帯を抑え、分部氏は信包に仕えた。翌永禄12年(1569)津城の仮城として分部信光に築城(修築)させた。 |
| この頃、お市と娘三姉妹がこの城にいたと言われている。お江は0才から7歳までこの城にいた。 | |
| 天正8年(1580)信包が津城に移ったので出城として再び分部(光嘉)氏が上野城を守った。 | |
| 文禄3年(1594年)に信包が近江へ改易になると、光嘉は豊臣家家臣として城主に任ぜられて独立した城となった。 | |
| 分部氏はその後秀吉、家康に仕え加増を重ね大名まで出世した。 | |
| 慶長6年(1601)11月、安濃津城の戦いで脇腹に負った傷が元で分部光嘉が死去すると養子光信が継ぐ。 | |
| しかし元和5年(1619)分部氏は紀州藩の成立によって近江へ転封となり伊勢上野城は廃城となった。 | |
| 環境 | 東に伊勢湾を一望する比高35mの丘陵端にある。 |
| 一族 | 長野工藤氏、兄;細野藤敦(安濃城主) |
| 分部氏、三間氏は長野家与力 | |
| 現地 | 旧伊勢街道を眼下に見ることができ海と街道を監視できる。 |
| 考察 | 大河ドラマで一時有名になりそうな気配があったが思ったほど賑わうことは無かったようである。少し見応えに欠ける遺跡の状況であることが原因かもしれない。 |
| 感想 | 東南側にある土塁は当時を忍ばせる落差のあるいい形が残る。 |
| 地図 | https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ja&authuser=0&mid=1sE7i85-3qeA10HRT1ZDejbj3Ddw&ll=34.791885918418885%2C136.5424767067284&z=18 |
| その他 |
| 城名 | 川北城 |
| 住所 | 三重県津市大里川北町 |
| 築城年 | 一期;文永11年(1274) 二期;文明2年(1470)~永徳3年(1491) |
| 築城者 | 川北氏(注1) |
| 形式 | 山城+居館 |
| 遺構 | 無し |
| 規模 | 城郭;南北150m×東西120m 居住区;南北80m×東西120m |
| 城主 | 川北式部少輔 |
| 標高 | 23m |
| 比高 | 16m |
| 歴史 | 一期(盛期) 鎌倉時代、文永11年(1274) |
| 暦応2年(1339)~貞治5年(1365)北畠VS高師秋の戦いに長野氏も参加していた。 | |
| 康安元年(1360)川北城VS高師秋+土岐頼義の戦いで落城した。 | |
| 1414年、仁木氏(足利幕府方)と長野氏が阿坂城(北畠氏)を攻める | |
| 1428年、北畠氏と長野氏が岩田川で幕府軍と合戦 | |
| 二期(再建) 文明2年(1470)~延徳3年(1491)の頃に川北城は再建された。(落城後110年後) | |
| 応仁の乱(1467~1477)東軍に属した長野氏らと共に失地回復。 | |
| 明応9年(1500)川北内匠亮が川北道場(後の久善寺)を開く。 | |
| 経緯 | S53年に発掘調査。 |
| 堀と土塁で区切られた郭を多数配し、その中に建物を建てた計画性の明らかな城である。 | |
| 構成は溝と土塁と建物から成る。 | |
| 溝は1.5m~2m巾、深さ1m位でV字形断面をし、大きく区画をする。 | |
| 更に溝に直交する土塁を築き区切る。 | |
| 土塁は広いもので基底5mある。 | |
| 建物は44棟あり、小型のものと大型のものに分けられる。 | |
| 遺物としては山茶碗、山皿、天目茶碗、磁器類、中国製青磁・白磁があった。 | |
| 結果;13世紀後半に築城され最盛期は13世紀末から14世紀中頃であると判明した。 | |
| 勢陽五鈴遺響 | 川北砦址;「安濃郡長野工藤分家川北式部少輔居セリ及後裔今ニ居ス」とある。 |
| 現地 | 伊勢別街道と市登茂川に面する台地上の斜面に土塁、空堀、郭を築き背後の丘陵に居館を配して全体では約7,500坪の面積に及ぶ。現地公園に碑、説明版がある。 |
| 考察 | 城郭と居住区が分割された明確な例。 |
| 伊勢別街道との距離は有視界距離である。 | |
| 感想 | 今となっては団地の造成の中に埋もれてしまっているが見晴らしは当時を忍ばせる。発掘報告書だけが頼りである。 |
| 注1 | 川北氏とは=長野氏の六代目式部大輔経藤の子内匠頭藤照が分家して名乗った。 |
| 地図 | https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ja&authuser=0&mid=1sE7i85-3qeA10HRT1ZDejbj3Ddw&ll=34.77092666738542%2C136.50315552257007&z=18 |
|
|
| 城名 | 安濃城 |
| 読み | あのうじょう |
| 住所 | 津市安濃町安濃細野 |
| 築城年 | 弘治年間(1555~1558) |
| 築城者 | 細野藤光 |
| 形式 | 城郭の中に館を設けた珍しい形態。規模も大きい。 |
| 遺構 | 郭、土塁、堀、櫓台、井戸 |
| 規模 | 東西450m×南北350m |
| 城主 | 細野藤敦 |
| 標高 | 30m~59m |
| 比高 | 40m |
| 経緯 | 細野藤光は細野城を築いていたが安濃城を築いて移った。 |
| その子藤敦の時に拡張している。 | |
| 歴史 | 永禄11年(1568)織田軍は安濃津城をほとんど無抵抗で手中に入れた後安濃城に攻め囲んだ。 |
| 細野九郎藤敦 VS 滝川一益 =安濃城の戦い | |
| 安濃城を守っていたのは工藤一族の分家、勇将細野藤敦であった。 | |
| 背後の丘に旗指物を並び立て、夜はかがり火で偽兵を使い、自ら野駆けを繰り返し逃げると見せかけては大手に敵をさそいこみ、たちまち弓矢を浴びせ、敵方の後ろに回って攻め立てるなど、散々に織田方を打ち悩ました。 | |
| 滝川一益も攻め立てたが城はびくともしない。日を改めて攻撃に出るが落とせない。織田方は焦る一方であった。 | |
| 弟、分部光嘉の策により織田信包が細野氏の本家長野氏の養子となったが、安濃城主細野藤敦はこれに従わず、天正8年(1580)についに長野信包によって攻められ自ら城に火を放って落城した。 | |
| これにより信包が長野氏の当主となり長野一族は織田信長の配下となった。細野藤敦はその後蒲生氏郷、豊臣秀吉に仕え西軍に属し領地を失い京都にて64才で没した。 | |
| 書籍 | 伊勢国盗り物語 |
| 環境 | 安濃の丘陵部を北西から南東に下る長さ450m、巾150m~100m程の尾根を階段状に整備した巨大な連郭群である。 |
| 一族 | 長野氏 |
| 現地 | 阿由多神社が主郭に祀られている。 |
| 地図 | https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ja&authuser=0&mid=1sE7i85-3qeA10HRT1ZDejbj3Ddw&ll=34.77650289423616%2C136.45584403775638&z=17 |










 安濃3城 スライドへ
安濃3城 スライドへ
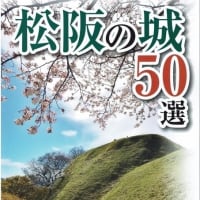

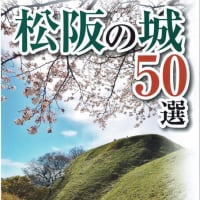
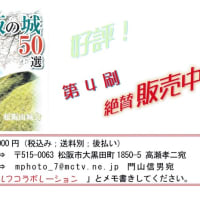




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます