今週は、この2冊。
■ブエノスアイレスに消えた/グスタボ・マラホビッチ 2015.12.19
『ブエノスアイレスに消えた』は、上下2段組でp591もある大部のミステリーです。
そして、話の先がなかなか見通せない、一体ぼくはどこに導かれているのか、皆目見当がつかなかった。
それでも、このミステリーが手放せなかったのは、物語にただよう漠然とした不安に心がつかまれ、この"先"はどうなるのか、いかなる展開と結末が待ちかまえているのだろうか、と気になって、次々とページを繰ったのでした。
宮崎真紀さんの秀逸な訳文もこれを助けました。
主人公のファビアンを助ける強盗課刑事シルバや女性刑事ブランコ、私立探偵ドベルティが、魅力的に描かれています。
ドベルティの奥さんは、彼のことを次のように述懐します。
「あの人は本物のマジシャンだった。私たちが知りあったときも、警察官時代の危険な任務についてあれこれ話し、私の関心を引いた。本当の話もあったのかもしれないし、なかったのかもしれない。でも……それがなに?あの人と暮らせて、ほかのだれよりも幸せだった」
味わい深い、気の利いた言葉です。
女房からも気をつけろといつも言われるよ
奥さんは正しい
女房って人種はいつだって正しいんだ、友よ
女心ほどたくさんの隠し扉がある金庫はないんだぞ
「いや、プロのポーカープレイヤーさ。対戦相手の表情を読んで勝利を収めていたらしい。相手の意図を事前予測したんだ。彼がその技を極められなかったのは残念だけどね。ラスヴェガスのとあるカジノを出たところで殺されちまったから」
「そこでは相手の意図が読めなかったんだな」
「あたりが暗かったんだろう」
作品のなかでは、つぎつぎと人が死んでいく。
人生は、「出会っては別れ」、の連続だった。
必死に"謎"を追い求め、危機に遭遇し、それでも、主人公は生き残った。
ひとり残された彼に、生きるにあたいすることが残されていたのだろうか、ぼくは考えこんでしまった。
神は彼に、忘れるという恩恵さえ与えてくれなかった
日本経済新聞...........ブックレビュー
『 ブエノスアイレスに消えた/グスタボ・マラホビッチ/宮崎真紀訳/ハヤカワ・ミステリ 』
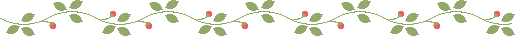
■首切りの歴史/フランシス・ラーソン 2015.12.19
「訳者あとがき」からの引用です。
イギリスの人類学者フランシス・ラーソンの『首切りの歴史』です。
オックスフォード大学内にあるピット・リヴァーズ博物館に研究員として勤務した経験が、本書執筆のきっかけと独自の世界観を与えたのは間違いない。
ピット・リヴァーズ博物館はときに、干し首博物館とも呼ばれている。
干し首はわずか数点しか展示されていない、にもかかわらず、干し首がこの博物館の代名詞になっているのはなぜか。
また、同博物館とその母体であるオックスフォード大学に何千点ものヒトの頭蓋骨が収蔵されているのを知って驚愕する、だれが、なぜ、何のために。
この本では、断頭、斬首、ギロチン、死刑執行人、頭蓋骨の話などふんだんに出てきます。
頭部移植などの考察もされています。
斬首が行われていた時代の刑執行の様子や死刑執行人のこと、ギロチンが使用されるに至った経緯なども詳しく語られています。
フランスの恐怖政治時代に主任執行人を努めたシャルル=アンリ・サンソンにも触れていますが、サンソンについては、当ブログでも『 死刑執行人サンソン/安達正勝/集英社新書 』を紹介しました。
これは切断された頭部についての本である。
断頭は死刑執行人にとって技芸が試される場面で、処刑台を囲む群衆はその芸を瞬時に判定する。
斬首は処刑であると同時にショーなのだ。
イギリスでは、斬首刑は伝統的に富裕層の罪人のために用意されていた措置だった。
オランダでは、戦争ですでに死んだ人にも断頭を施していた。そのほうが名誉ある死に方だと思われていたからだ。
社会学者のハリー・コリンズは、「恐ろしいのは、部外者にとって残酷な行為が内部者にとっては単なる日常であることだ」と書いている。
『 首切りの歴史/フランシス・ラーソン/矢野真千子訳/河出書房新社 』
■ブエノスアイレスに消えた/グスタボ・マラホビッチ 2015.12.19
『ブエノスアイレスに消えた』は、上下2段組でp591もある大部のミステリーです。
そして、話の先がなかなか見通せない、一体ぼくはどこに導かれているのか、皆目見当がつかなかった。
それでも、このミステリーが手放せなかったのは、物語にただよう漠然とした不安に心がつかまれ、この"先"はどうなるのか、いかなる展開と結末が待ちかまえているのだろうか、と気になって、次々とページを繰ったのでした。
宮崎真紀さんの秀逸な訳文もこれを助けました。
主人公のファビアンを助ける強盗課刑事シルバや女性刑事ブランコ、私立探偵ドベルティが、魅力的に描かれています。
ドベルティの奥さんは、彼のことを次のように述懐します。
「あの人は本物のマジシャンだった。私たちが知りあったときも、警察官時代の危険な任務についてあれこれ話し、私の関心を引いた。本当の話もあったのかもしれないし、なかったのかもしれない。でも……それがなに?あの人と暮らせて、ほかのだれよりも幸せだった」
味わい深い、気の利いた言葉です。
女房からも気をつけろといつも言われるよ
奥さんは正しい
女房って人種はいつだって正しいんだ、友よ
女心ほどたくさんの隠し扉がある金庫はないんだぞ
「いや、プロのポーカープレイヤーさ。対戦相手の表情を読んで勝利を収めていたらしい。相手の意図を事前予測したんだ。彼がその技を極められなかったのは残念だけどね。ラスヴェガスのとあるカジノを出たところで殺されちまったから」
「そこでは相手の意図が読めなかったんだな」
「あたりが暗かったんだろう」
作品のなかでは、つぎつぎと人が死んでいく。
人生は、「出会っては別れ」、の連続だった。
必死に"謎"を追い求め、危機に遭遇し、それでも、主人公は生き残った。
ひとり残された彼に、生きるにあたいすることが残されていたのだろうか、ぼくは考えこんでしまった。
神は彼に、忘れるという恩恵さえ与えてくれなかった
日本経済新聞...........ブックレビュー
『 ブエノスアイレスに消えた/グスタボ・マラホビッチ/宮崎真紀訳/ハヤカワ・ミステリ 』
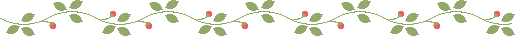
■首切りの歴史/フランシス・ラーソン 2015.12.19
「訳者あとがき」からの引用です。
イギリスの人類学者フランシス・ラーソンの『首切りの歴史』です。
オックスフォード大学内にあるピット・リヴァーズ博物館に研究員として勤務した経験が、本書執筆のきっかけと独自の世界観を与えたのは間違いない。
ピット・リヴァーズ博物館はときに、干し首博物館とも呼ばれている。
干し首はわずか数点しか展示されていない、にもかかわらず、干し首がこの博物館の代名詞になっているのはなぜか。
また、同博物館とその母体であるオックスフォード大学に何千点ものヒトの頭蓋骨が収蔵されているのを知って驚愕する、だれが、なぜ、何のために。
この本では、断頭、斬首、ギロチン、死刑執行人、頭蓋骨の話などふんだんに出てきます。
頭部移植などの考察もされています。
斬首が行われていた時代の刑執行の様子や死刑執行人のこと、ギロチンが使用されるに至った経緯なども詳しく語られています。
フランスの恐怖政治時代に主任執行人を努めたシャルル=アンリ・サンソンにも触れていますが、サンソンについては、当ブログでも『 死刑執行人サンソン/安達正勝/集英社新書 』を紹介しました。
これは切断された頭部についての本である。
断頭は死刑執行人にとって技芸が試される場面で、処刑台を囲む群衆はその芸を瞬時に判定する。
斬首は処刑であると同時にショーなのだ。
イギリスでは、斬首刑は伝統的に富裕層の罪人のために用意されていた措置だった。
オランダでは、戦争ですでに死んだ人にも断頭を施していた。そのほうが名誉ある死に方だと思われていたからだ。
社会学者のハリー・コリンズは、「恐ろしいのは、部外者にとって残酷な行為が内部者にとっては単なる日常であることだ」と書いている。
『 首切りの歴史/フランシス・ラーソン/矢野真千子訳/河出書房新社 』













