A.70年万博と針生一郎
大阪万博開催をめぐって、膨大な予算増額と外国からの出展自体や再検討の動きもあって、ほんとうに開催できるのか、開催したとしても意味がどの程度あるのか、議論が湧いている。そこで成功体験をもって語られる1970年の大阪万博について、それが開かれた時代を振り返るのに、「反博」を主張した美術批評家、針生一郎の『戦後美術盛衰史』東書選書、1979年から、万博にかんする記述を引用してみたい。
著者の針生一郎氏(1925~2010)は、仙台市生まれの美術評論家、文芸評論家。東北大文学部卒、東大大学院で美学を専攻。日大、横浜市大、名大、東大、早大などで講師を務めたのち、多摩美大教授をへて和光大学教授。Wikipediaの記述によれば「大学院在学中、岡本太郎、花田清輝、安部公房らの「夜の会」に参加。1953年、軍国少年だったことへの反省から日本共産党に入党したが、1961年、60年安保闘争時の共産党の指導方針を批判して除名される。反権威的な美術評論・文芸評論で活躍、日本藝術院批判の急先鋒でもあった。1970年の大阪万博に反対。第三世界にも目を向けた活動を行った。新日本文学会の活動にも積極的に参加し、2005年の会の解散時には議長の任にあたっていた。
国際美術展などのプランナーとしても活躍。ヴェネツィア・ビエンナーレ(1968年)、サンパウロ・ビエンナーレ(1977年、1979年)のコミッショナーを務め、2000年には、韓国で開催された光州ビエンナーレの特別展示「芸術と人権」で日本人として初めてキュレーターを務めた。2002年、自由な作品発表・批評の場として来場者による参加型のアートスポット「芸術キャバレー」(主催:JAALA海外交流部)を設立、戦争と芸術のテーマで連続講座を開催するなど積極的な活動を行う。また、ドキュメンタリー映画『日本心中 - 針生一郎・日本を丸ごと抱え込んでしまった男』(大浦信行監督:2005年)へ出演し、話題となった。
2010年5月26日、川崎市で急性心不全により逝去(享年84)
「68年6月、わたしはヴェネツィア・ビエンナーレの日本コミッショナーとして、菅井汲、高松次郎、三木富雄、山口勝弘の四人の出品者とともに現地におもむいた。ところがドゴールに鎮圧された五月革命の余波で、ミラノ・トリエンナーレは学生に占拠され、このビエンナーレも「大国主義と商業主義の祭典」として学生、美術家の攻撃の的となった。それにたいして主催者側は会場の警官隊を常駐させたため、日本、スウェーデン、フランス(コミッショナーのラゴンは、ドゴール政府に抗議して現地にこなかった)の参加者は連名で抗議声明を出した。その後芸術家数人が警官と衝突して逮捕される事件が起こり、スエーデン館は閉館して全員フランス館やイタリア館でも展示室を閉ざし、自作にカヴァーをかけて抗議する作家が続出した。その結果、日本館は「閉鎖すべきだ」「しめないで」という両側の声の焦点となったが、出品者四人の意見が半々にわかれ、しかも日本館は空間を仕切れないので、結局そのまま開会式を迎えたのである。
その年はヴェネツィア開会の一週間後に、カッセルで四年に一度の国際展〈ドクメンタ〉がはじまったので、前者の混乱にくらべて、「国境なき展覧会」をめざして国別コミッショナー制をとらず、国際委員会が全招待作家を選別する、後者の先鋭さは誰の目にも明らかだった。その後、69年のサンパウロ・ビエンナーレでも、軍事政権の介入に反対する学生たちを、軍隊が出動して鎮圧する流血の事態となったため、国際展はいよいよカナエの軽重を問われる。そこで、パリ青年ビエンナーレは73年以後、コミッショナーも賞もやめて「ドクメンタ方式」に変り、ヴェネツィア・ビエンナーレも75年以後、問題の多い賞は廃止し、国別展示に統一テーマを設け、企画展示にも力を注ぐにいたっている。
ところで、68年秋から、わたしは多摩美大教授となったが、学園闘争が全国にひろがるなかで、69年1月、多摩美大でも学生たちが本館をバリケード封鎖した。前学長石田英一郎の死後、学長代行だった福沢一郎は、封鎖直後に辞表を出し、大衆団交などで教授会を代表する「教授会議長」にわたしがえらばれた。2月に封鎖解除となり、大学改革をめぐって団交や討論がつづくうち、4月には同一法人下の多摩芸術学園の学生によって本館が再封鎖され、教授会は残りの教室で自主講座を開始したが、7月には美大生も加わって全学封鎖を迎えた。その間、理事たちは逃亡して、こちらからは連絡も取れない状態におかれたのである。
同年7月、多摩美、多摩芸の学生を中心に、美術、デザインの学生、青年が結成した「美術家共闘会議(美共闘)」は、全共闘運動にはらまれた文化革命の展望の一表現で、その発想の独自さは次の宣言からもうかがわれる。「おそらく、あらゆる個別の場、ジャンルに封じ込められた問いかけが不毛な時代に、僕等は生きているのだろう。類としての変革を指向する所にしか個の解放も、僕等自身の表現さえもあり得ないだろう。…僕等が、美術家に留る必要はないし、僕等はいかなる場に身を置くことも出来るだろう。…が、しかし、僕等は“名前”からのがれる事が出来るだろうか、“美術家”からはのがれ得たとしても、この世のすべての名前からのがれる事が出来ないだろう。この世界に生きている僕等は、与えられた名前を逆手にとってしか、具体的に闘うことはできないだろうと思う。今、美術家と呼ばれているなら、そこが戦場だ」。
ここには、芸術至上主義も街頭闘争的政治主義もこえて、感性と表現の解放のために、美術の支配構造と対決しようとする姿勢がある。彼らが体制の文化に反体制の文化を対置する従来の運動図式を否定し、文化総体に対置されるべきは直接行動のみだと語るとき、わたしは新しい展望を感じたものだ。そういう立場から美共闘は、日宣美展、東京芸大芸術祭、草月フィルム・フェスィヴァル、日展などに直接行動で介入した。だが、それが日宣美のようにやや近代化された組織には、自己解体をうながした半面、日展のような美術権力の中枢では、審査期間から機動隊数十名を常駐させ、初日に金を払って入場した美共闘メンバーが、日展批判のビラをとりだしたとたんに逮捕されたという。五月革命がカリスマ的政治家ドゴールを退陣させて、より近代的な管理者ポンピドーを登場させたように、全共闘の直接行動主義が管理警備体制の一層の強化をもたらした事実も否定できない。
わたしは多摩美大の闘争経過を何度か雑誌に書いたせいか、69年春から70年春にかけて、いくつかの大学で学生によばれてゆくと、大学が講演を許可しない事態に遭遇した。大阪芸大では、地元暴力団から成るという警備員のすきをついて、学生が教室をあけ集会をはじめたが、講演中ハンドマイクをもった警備員がわたしにことわった上で、学生に解散をよびかけた。愛知県立芸大では、60年代美術について講演中、校内放送と学生部長の文書が、学生ではなくわたしに退去を命じ、終わってみると機動隊180名が待機していた。しかも、主催した学生は退学処分となり、傍聴した美術学部長伊藤廉も辞任したので、この処分は愛知県議会でも論議の的となったらしい。名古屋芸大では、学長が私への退去勧告を墨書した紙をもって正門にいたが、学生が押し問答の末座談会形式での許可をとりつけた。それらと対照的なのは京都市立芸大で、三階校舎をバリケード封鎖中の学生によばれてゆくと、車で送迎してくれたのは旧友の木村重信教授だった。ここの教授会は木村を中心に、大学運営を教員、職員、学生の三者代表で協議し、専攻ジャンルの垣根をはずすなど、大胆な大学改革案をまとめて全構成員に賛否を問うたため、やがて封鎖派学生は孤立してバリケードを解き、そのまま中退して国外に出た学生の一人とわたしは数年後、西ドイツの街頭で邂逅した。
69年5月には、毎日現代展コンクール部門の公開審査要求が、岡田隆彦、谷川晃一ら美術家有志からだされ、彼らのよびかけで現代展をめぐる討論会もおこなわれた。その席で、この展覧会の企画、審査に加わってきたわたしは、新聞社主催総合展の変則性を批判するなら、それをこえる展覧会の構想と主体が形成されなければならないと主張した。同年10月、朝日新聞社西部本社主催の〈九州現代美術精鋭展〉では、河北倫明、斎藤義重、浜田知明、わたしが審査員を委嘱されたが、元「九州派」など数人の作家が大きな箱に入った自分自身を出品し、受付を拒否されたため、「材料、形式は自由」の社告に反するとはげしく抗議した。彼らのモチーフも新聞社主催展への批判だから、結局話し合いがつかず、主催者は私服刑事導入を決定したので、斎藤義重とわたしはその時点で審査員をおりた。その直後、多摩美大への機動隊導入を電話で知らされたのも印象的だった。わたしにはこの「九州派」のケースが、管理社会の壁にすぐぶつかる直接行動を、素朴ながら「作品」に内在化させた一例として、いまも忘れられない。
一方、わだしは68年末、「朝日ジャーナル」に万博批判を書き、翌年春、編著『われわれにとって万博とは何か』(田畑書店)をだして以来、万博反対運動の中心のようにみられていた。そのわたしも知らなかったが、69年春、加藤好弘らの「ゼロ次元」、末永蒼生らの『告陰』、小山哲男らの「ビタミンアート」、秋山祐徳太子らの「新宿少年団」など、アングラ芸術集団が連合して「万博破壊共闘会議」を結成し、加藤がユーモラスに書いたつぎのような趣旨から、京大バリケード、福岡、東京、名古屋などで男女全裸の「儀式」をつづけた。博覧会は見るところではなく、九十九%見られるところなんだ。見るところを見られるところにしてしまうことが革命なのよ。巨大なハプニング会場がわれわれを嬉々として待っているのだ。ゲバ棒を持つことが革命であるように、万博会場では白手袋の片手をあげて三十分以上歩こうではないか。片手をあげてカッコいい君を皆がジロジロ見るだろう。そして会場中の人間が君にならって片手をあげたくなるだろう。その時君は本当に観る人と本質的に化するのだ」。だが、69年7月、全裸儀式の写真が二つの週刊誌にのると、すでに新宿西口フォーク広場を弾圧し、六・一五反戦デモに数万人動員したべ平連を手入れした警察は、「万博破壊共闘」派をしらみつぶしに検挙した。しかも取調べでは、わいせつ罪容疑なのにべ平連や新左翼との関連だけが追求され、万博反対論と「国辱的」アングラ芸術を一掃せよ、と自民党筋の圧力があったことも、検事の口から明らかになったという。
同年8月、大阪城公園で開かれた」「反博」=反戦のための万博には、べ平連、全共闘、住民運動、キリスト教団体、日中友好団体、フォーク・ゲリラなどから約二千人あつまり、加藤好弘や金坂健二も参加した。だが呼びかけ人の一人としてのわたしは、反戦、反体制の文化を万博に対置する発想に疑問をいだき、文化総体を支配の手段として告発しながら、集会、デモ、歌、シュプレヒコール、ビラなどを、民衆のメディアとしてとらえ直す場にすることを主張した。事実、反博では予定された展示が公演よりも、会場内で自然発生的におこる大衆討論の方が重要で、中国物産展示、ホットドッグ屋の侵入、高石友也の新宿フォーク広場批判などを契機に、反博もまた権力と資本に浸透された擬似解放区であることが反省され、そこから文化革命の方向が模索されたのである。
反博批判をふまえて、関西の美術家、建築家、キリスト者、中国派、釜ヶ崎労働者などが結成した「安保万博粉砕共闘会議」は、70年3月の万博開会の日、万博中央口駅構内でデモをはじめて68名逮捕され、4月には糸井貫二がお祭り広場を全裸で疾走して逮捕された。そのほかこの年には、愛知県美術館が「NAG」グループのビニール袋入りゴミ作品を一方的に撤去した事件、静岡県展が杉山邦彦の県展死亡届作品を陳列拒否した事件、福岡の森山安英が伝習館高校教師処分反対デモで、むしろ旗に性器を描いて起訴された事件などで芸術裁判が続出し、わたしはその大部分に証人として出廷した。多摩美大でも授業からしめだされた教授会は、半年間学外で自主講座をつづけたのち、70年7月、斎藤義重、杉全直、建畠覚造、土谷武、中原佑介、高松次郎、私など、残った十五人で大学を告訴した。そして、一審勝利は確実でも、控訴されると泥沼化するので、73年3月示談で是認退職し、受け取った未払い金、退職金で渋谷にマンションの一室を買って、「現代文化センター」を開設したのである。
ここで、1970年の万博で主要な役割を演じた、芸術家、デザイナーを列挙しておこう。基幹施設=プロデューサー丹下健三、スタッフ磯崎新、上田篤、大高正人、川崎洋、菊竹清訓ら。テーマ展示=プロデューサー岡本太郎、スタッフ粟津潔、伊藤隆道、伊藤隆康、岡田晋、川添登、黒川紀章、小松左京、千葉和彦、東宮伝、黛敏郎ら。お祭り広場=プロデューサー磯崎新、上田篤、スタッフ秋山邦晴、一柳慧、小松左京、東野芳明、中原佑介、松本俊夫、山口勝弘、吉村益信ら。日本政府館=プロデューサー河野鷹思、スタッフ粟津潔、市川崑、高村英也、田中一光、谷川俊太郎、三林亮太郎ら。
」針生一郎『戦後美術盛衰史』東書選書、東京書籍1979年、pp.183.
以下略したが、三井グループ館、繊維館、鉄鋼館などと続き、そのなかには横尾忠則、前川国男、安倍公房、福田繁雄、柴田南雄、杉浦民平、武満徹、星新一などアーティスト、文化人として当時一流と評される著名人が加わっていたが、女性が一人もいないのは、今から考えると隔世の感がある。

B.24歳の悩み
新聞各紙には昔から人生相談欄があって、人生の知恵者ともみられる著名人が回答者になっている。でも毎日新聞の人生相談欄が高橋源一郎氏の担当であることを、毎日新聞を購読していないぼくは知らなかった。
「未来描けず焦り感じる 人生相談:高橋源一郎
好きな仕事をして週末は友人と遊んで毎日楽しいです。しかし最近婚約したり結婚したりする友人が増えてきました。私自身は恋愛経験も少なく、今後結婚する未来も見えません。ライフステージが変わって、自分だけ置いていかれるような焦りを感じています。恋愛する自信も、この先独りで生きていく覚悟もありません。(24歳・女性)
人生に「正解」はありません。社会や世界が推奨する「生き方」はあるかもしれないけれど。わたしたちが知りたいのは、宇宙に一つしか存在しない「自分」という名の「生き方」。それを見つける旅そのものが「生きる」ということの中身なのかもしれません。
あなたと同じ年の頃、わたしは肉体労働者で、結婚し、子どもを育てていました。学生時代の友人はみんな社会人になり、活躍しているようでした。わたしは、好きな仕事をしているわけでもなく、友人からは遠ざかっていました。妻も子どもも愛していましたが、将来の目標もとりたてて楽しいこともなく、不安を心のうちに隠して、漫然と日を送っていたのです。ほんとうは何をしたいのか、このままでいいと思っているのか、将来どうなるのか。何も考えないようにしていた、というのが事実でした。そして数年たち、自分はなにもない「無に等しい人間」だと認めたとき、はじめてそんなぼくのような人間でも生きていたい、と願ったのでした。
「焦りを感じ」「自身も……覚悟もありません」。いい兆候です。まともなら誰だってそう思いますよ。自分がどんな人間なのか見つめ、確かめ、考え、成長するように全力を尽くす時期が来たのです。そうですね、まずは自分がなにを「好き」なのか考えることから始めましょうか。ゆっくりでいいから。(作家)」毎日新聞2023年11月12日朝刊、19面くらしナビ欄。
高橋源一郎氏が24歳の時どういう状況にあったか、は知る人ぞ知るのだけれど、もちろんまだ作家にはなっていなかったわけで、高橋氏とほぼ同世代で、しかも一時は同じ肩書だったぼくとしては、ま、みんな明日をも知れぬ境遇だったわけですな。若者は優しく励ましてあげないとね。
大阪万博開催をめぐって、膨大な予算増額と外国からの出展自体や再検討の動きもあって、ほんとうに開催できるのか、開催したとしても意味がどの程度あるのか、議論が湧いている。そこで成功体験をもって語られる1970年の大阪万博について、それが開かれた時代を振り返るのに、「反博」を主張した美術批評家、針生一郎の『戦後美術盛衰史』東書選書、1979年から、万博にかんする記述を引用してみたい。
著者の針生一郎氏(1925~2010)は、仙台市生まれの美術評論家、文芸評論家。東北大文学部卒、東大大学院で美学を専攻。日大、横浜市大、名大、東大、早大などで講師を務めたのち、多摩美大教授をへて和光大学教授。Wikipediaの記述によれば「大学院在学中、岡本太郎、花田清輝、安部公房らの「夜の会」に参加。1953年、軍国少年だったことへの反省から日本共産党に入党したが、1961年、60年安保闘争時の共産党の指導方針を批判して除名される。反権威的な美術評論・文芸評論で活躍、日本藝術院批判の急先鋒でもあった。1970年の大阪万博に反対。第三世界にも目を向けた活動を行った。新日本文学会の活動にも積極的に参加し、2005年の会の解散時には議長の任にあたっていた。
国際美術展などのプランナーとしても活躍。ヴェネツィア・ビエンナーレ(1968年)、サンパウロ・ビエンナーレ(1977年、1979年)のコミッショナーを務め、2000年には、韓国で開催された光州ビエンナーレの特別展示「芸術と人権」で日本人として初めてキュレーターを務めた。2002年、自由な作品発表・批評の場として来場者による参加型のアートスポット「芸術キャバレー」(主催:JAALA海外交流部)を設立、戦争と芸術のテーマで連続講座を開催するなど積極的な活動を行う。また、ドキュメンタリー映画『日本心中 - 針生一郎・日本を丸ごと抱え込んでしまった男』(大浦信行監督:2005年)へ出演し、話題となった。
2010年5月26日、川崎市で急性心不全により逝去(享年84)
「68年6月、わたしはヴェネツィア・ビエンナーレの日本コミッショナーとして、菅井汲、高松次郎、三木富雄、山口勝弘の四人の出品者とともに現地におもむいた。ところがドゴールに鎮圧された五月革命の余波で、ミラノ・トリエンナーレは学生に占拠され、このビエンナーレも「大国主義と商業主義の祭典」として学生、美術家の攻撃の的となった。それにたいして主催者側は会場の警官隊を常駐させたため、日本、スウェーデン、フランス(コミッショナーのラゴンは、ドゴール政府に抗議して現地にこなかった)の参加者は連名で抗議声明を出した。その後芸術家数人が警官と衝突して逮捕される事件が起こり、スエーデン館は閉館して全員フランス館やイタリア館でも展示室を閉ざし、自作にカヴァーをかけて抗議する作家が続出した。その結果、日本館は「閉鎖すべきだ」「しめないで」という両側の声の焦点となったが、出品者四人の意見が半々にわかれ、しかも日本館は空間を仕切れないので、結局そのまま開会式を迎えたのである。
その年はヴェネツィア開会の一週間後に、カッセルで四年に一度の国際展〈ドクメンタ〉がはじまったので、前者の混乱にくらべて、「国境なき展覧会」をめざして国別コミッショナー制をとらず、国際委員会が全招待作家を選別する、後者の先鋭さは誰の目にも明らかだった。その後、69年のサンパウロ・ビエンナーレでも、軍事政権の介入に反対する学生たちを、軍隊が出動して鎮圧する流血の事態となったため、国際展はいよいよカナエの軽重を問われる。そこで、パリ青年ビエンナーレは73年以後、コミッショナーも賞もやめて「ドクメンタ方式」に変り、ヴェネツィア・ビエンナーレも75年以後、問題の多い賞は廃止し、国別展示に統一テーマを設け、企画展示にも力を注ぐにいたっている。
ところで、68年秋から、わたしは多摩美大教授となったが、学園闘争が全国にひろがるなかで、69年1月、多摩美大でも学生たちが本館をバリケード封鎖した。前学長石田英一郎の死後、学長代行だった福沢一郎は、封鎖直後に辞表を出し、大衆団交などで教授会を代表する「教授会議長」にわたしがえらばれた。2月に封鎖解除となり、大学改革をめぐって団交や討論がつづくうち、4月には同一法人下の多摩芸術学園の学生によって本館が再封鎖され、教授会は残りの教室で自主講座を開始したが、7月には美大生も加わって全学封鎖を迎えた。その間、理事たちは逃亡して、こちらからは連絡も取れない状態におかれたのである。
同年7月、多摩美、多摩芸の学生を中心に、美術、デザインの学生、青年が結成した「美術家共闘会議(美共闘)」は、全共闘運動にはらまれた文化革命の展望の一表現で、その発想の独自さは次の宣言からもうかがわれる。「おそらく、あらゆる個別の場、ジャンルに封じ込められた問いかけが不毛な時代に、僕等は生きているのだろう。類としての変革を指向する所にしか個の解放も、僕等自身の表現さえもあり得ないだろう。…僕等が、美術家に留る必要はないし、僕等はいかなる場に身を置くことも出来るだろう。…が、しかし、僕等は“名前”からのがれる事が出来るだろうか、“美術家”からはのがれ得たとしても、この世のすべての名前からのがれる事が出来ないだろう。この世界に生きている僕等は、与えられた名前を逆手にとってしか、具体的に闘うことはできないだろうと思う。今、美術家と呼ばれているなら、そこが戦場だ」。
ここには、芸術至上主義も街頭闘争的政治主義もこえて、感性と表現の解放のために、美術の支配構造と対決しようとする姿勢がある。彼らが体制の文化に反体制の文化を対置する従来の運動図式を否定し、文化総体に対置されるべきは直接行動のみだと語るとき、わたしは新しい展望を感じたものだ。そういう立場から美共闘は、日宣美展、東京芸大芸術祭、草月フィルム・フェスィヴァル、日展などに直接行動で介入した。だが、それが日宣美のようにやや近代化された組織には、自己解体をうながした半面、日展のような美術権力の中枢では、審査期間から機動隊数十名を常駐させ、初日に金を払って入場した美共闘メンバーが、日展批判のビラをとりだしたとたんに逮捕されたという。五月革命がカリスマ的政治家ドゴールを退陣させて、より近代的な管理者ポンピドーを登場させたように、全共闘の直接行動主義が管理警備体制の一層の強化をもたらした事実も否定できない。
わたしは多摩美大の闘争経過を何度か雑誌に書いたせいか、69年春から70年春にかけて、いくつかの大学で学生によばれてゆくと、大学が講演を許可しない事態に遭遇した。大阪芸大では、地元暴力団から成るという警備員のすきをついて、学生が教室をあけ集会をはじめたが、講演中ハンドマイクをもった警備員がわたしにことわった上で、学生に解散をよびかけた。愛知県立芸大では、60年代美術について講演中、校内放送と学生部長の文書が、学生ではなくわたしに退去を命じ、終わってみると機動隊180名が待機していた。しかも、主催した学生は退学処分となり、傍聴した美術学部長伊藤廉も辞任したので、この処分は愛知県議会でも論議の的となったらしい。名古屋芸大では、学長が私への退去勧告を墨書した紙をもって正門にいたが、学生が押し問答の末座談会形式での許可をとりつけた。それらと対照的なのは京都市立芸大で、三階校舎をバリケード封鎖中の学生によばれてゆくと、車で送迎してくれたのは旧友の木村重信教授だった。ここの教授会は木村を中心に、大学運営を教員、職員、学生の三者代表で協議し、専攻ジャンルの垣根をはずすなど、大胆な大学改革案をまとめて全構成員に賛否を問うたため、やがて封鎖派学生は孤立してバリケードを解き、そのまま中退して国外に出た学生の一人とわたしは数年後、西ドイツの街頭で邂逅した。
69年5月には、毎日現代展コンクール部門の公開審査要求が、岡田隆彦、谷川晃一ら美術家有志からだされ、彼らのよびかけで現代展をめぐる討論会もおこなわれた。その席で、この展覧会の企画、審査に加わってきたわたしは、新聞社主催総合展の変則性を批判するなら、それをこえる展覧会の構想と主体が形成されなければならないと主張した。同年10月、朝日新聞社西部本社主催の〈九州現代美術精鋭展〉では、河北倫明、斎藤義重、浜田知明、わたしが審査員を委嘱されたが、元「九州派」など数人の作家が大きな箱に入った自分自身を出品し、受付を拒否されたため、「材料、形式は自由」の社告に反するとはげしく抗議した。彼らのモチーフも新聞社主催展への批判だから、結局話し合いがつかず、主催者は私服刑事導入を決定したので、斎藤義重とわたしはその時点で審査員をおりた。その直後、多摩美大への機動隊導入を電話で知らされたのも印象的だった。わたしにはこの「九州派」のケースが、管理社会の壁にすぐぶつかる直接行動を、素朴ながら「作品」に内在化させた一例として、いまも忘れられない。
一方、わだしは68年末、「朝日ジャーナル」に万博批判を書き、翌年春、編著『われわれにとって万博とは何か』(田畑書店)をだして以来、万博反対運動の中心のようにみられていた。そのわたしも知らなかったが、69年春、加藤好弘らの「ゼロ次元」、末永蒼生らの『告陰』、小山哲男らの「ビタミンアート」、秋山祐徳太子らの「新宿少年団」など、アングラ芸術集団が連合して「万博破壊共闘会議」を結成し、加藤がユーモラスに書いたつぎのような趣旨から、京大バリケード、福岡、東京、名古屋などで男女全裸の「儀式」をつづけた。博覧会は見るところではなく、九十九%見られるところなんだ。見るところを見られるところにしてしまうことが革命なのよ。巨大なハプニング会場がわれわれを嬉々として待っているのだ。ゲバ棒を持つことが革命であるように、万博会場では白手袋の片手をあげて三十分以上歩こうではないか。片手をあげてカッコいい君を皆がジロジロ見るだろう。そして会場中の人間が君にならって片手をあげたくなるだろう。その時君は本当に観る人と本質的に化するのだ」。だが、69年7月、全裸儀式の写真が二つの週刊誌にのると、すでに新宿西口フォーク広場を弾圧し、六・一五反戦デモに数万人動員したべ平連を手入れした警察は、「万博破壊共闘」派をしらみつぶしに検挙した。しかも取調べでは、わいせつ罪容疑なのにべ平連や新左翼との関連だけが追求され、万博反対論と「国辱的」アングラ芸術を一掃せよ、と自民党筋の圧力があったことも、検事の口から明らかになったという。
同年8月、大阪城公園で開かれた」「反博」=反戦のための万博には、べ平連、全共闘、住民運動、キリスト教団体、日中友好団体、フォーク・ゲリラなどから約二千人あつまり、加藤好弘や金坂健二も参加した。だが呼びかけ人の一人としてのわたしは、反戦、反体制の文化を万博に対置する発想に疑問をいだき、文化総体を支配の手段として告発しながら、集会、デモ、歌、シュプレヒコール、ビラなどを、民衆のメディアとしてとらえ直す場にすることを主張した。事実、反博では予定された展示が公演よりも、会場内で自然発生的におこる大衆討論の方が重要で、中国物産展示、ホットドッグ屋の侵入、高石友也の新宿フォーク広場批判などを契機に、反博もまた権力と資本に浸透された擬似解放区であることが反省され、そこから文化革命の方向が模索されたのである。
反博批判をふまえて、関西の美術家、建築家、キリスト者、中国派、釜ヶ崎労働者などが結成した「安保万博粉砕共闘会議」は、70年3月の万博開会の日、万博中央口駅構内でデモをはじめて68名逮捕され、4月には糸井貫二がお祭り広場を全裸で疾走して逮捕された。そのほかこの年には、愛知県美術館が「NAG」グループのビニール袋入りゴミ作品を一方的に撤去した事件、静岡県展が杉山邦彦の県展死亡届作品を陳列拒否した事件、福岡の森山安英が伝習館高校教師処分反対デモで、むしろ旗に性器を描いて起訴された事件などで芸術裁判が続出し、わたしはその大部分に証人として出廷した。多摩美大でも授業からしめだされた教授会は、半年間学外で自主講座をつづけたのち、70年7月、斎藤義重、杉全直、建畠覚造、土谷武、中原佑介、高松次郎、私など、残った十五人で大学を告訴した。そして、一審勝利は確実でも、控訴されると泥沼化するので、73年3月示談で是認退職し、受け取った未払い金、退職金で渋谷にマンションの一室を買って、「現代文化センター」を開設したのである。
ここで、1970年の万博で主要な役割を演じた、芸術家、デザイナーを列挙しておこう。基幹施設=プロデューサー丹下健三、スタッフ磯崎新、上田篤、大高正人、川崎洋、菊竹清訓ら。テーマ展示=プロデューサー岡本太郎、スタッフ粟津潔、伊藤隆道、伊藤隆康、岡田晋、川添登、黒川紀章、小松左京、千葉和彦、東宮伝、黛敏郎ら。お祭り広場=プロデューサー磯崎新、上田篤、スタッフ秋山邦晴、一柳慧、小松左京、東野芳明、中原佑介、松本俊夫、山口勝弘、吉村益信ら。日本政府館=プロデューサー河野鷹思、スタッフ粟津潔、市川崑、高村英也、田中一光、谷川俊太郎、三林亮太郎ら。
」針生一郎『戦後美術盛衰史』東書選書、東京書籍1979年、pp.183.
以下略したが、三井グループ館、繊維館、鉄鋼館などと続き、そのなかには横尾忠則、前川国男、安倍公房、福田繁雄、柴田南雄、杉浦民平、武満徹、星新一などアーティスト、文化人として当時一流と評される著名人が加わっていたが、女性が一人もいないのは、今から考えると隔世の感がある。

B.24歳の悩み
新聞各紙には昔から人生相談欄があって、人生の知恵者ともみられる著名人が回答者になっている。でも毎日新聞の人生相談欄が高橋源一郎氏の担当であることを、毎日新聞を購読していないぼくは知らなかった。
「未来描けず焦り感じる 人生相談:高橋源一郎
好きな仕事をして週末は友人と遊んで毎日楽しいです。しかし最近婚約したり結婚したりする友人が増えてきました。私自身は恋愛経験も少なく、今後結婚する未来も見えません。ライフステージが変わって、自分だけ置いていかれるような焦りを感じています。恋愛する自信も、この先独りで生きていく覚悟もありません。(24歳・女性)
人生に「正解」はありません。社会や世界が推奨する「生き方」はあるかもしれないけれど。わたしたちが知りたいのは、宇宙に一つしか存在しない「自分」という名の「生き方」。それを見つける旅そのものが「生きる」ということの中身なのかもしれません。
あなたと同じ年の頃、わたしは肉体労働者で、結婚し、子どもを育てていました。学生時代の友人はみんな社会人になり、活躍しているようでした。わたしは、好きな仕事をしているわけでもなく、友人からは遠ざかっていました。妻も子どもも愛していましたが、将来の目標もとりたてて楽しいこともなく、不安を心のうちに隠して、漫然と日を送っていたのです。ほんとうは何をしたいのか、このままでいいと思っているのか、将来どうなるのか。何も考えないようにしていた、というのが事実でした。そして数年たち、自分はなにもない「無に等しい人間」だと認めたとき、はじめてそんなぼくのような人間でも生きていたい、と願ったのでした。
「焦りを感じ」「自身も……覚悟もありません」。いい兆候です。まともなら誰だってそう思いますよ。自分がどんな人間なのか見つめ、確かめ、考え、成長するように全力を尽くす時期が来たのです。そうですね、まずは自分がなにを「好き」なのか考えることから始めましょうか。ゆっくりでいいから。(作家)」毎日新聞2023年11月12日朝刊、19面くらしナビ欄。
高橋源一郎氏が24歳の時どういう状況にあったか、は知る人ぞ知るのだけれど、もちろんまだ作家にはなっていなかったわけで、高橋氏とほぼ同世代で、しかも一時は同じ肩書だったぼくとしては、ま、みんな明日をも知れぬ境遇だったわけですな。若者は優しく励ましてあげないとね。















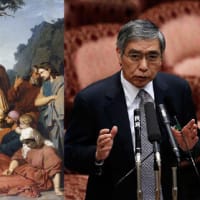










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます