A.女優列伝Ⅸ 浪花千栄子さん1
1990年に出版された「ちくま哲学の森シリーズ」というアンソロジーがあって、哲学というけれども、いわゆる哲学者の難しい論文などではなく、多様な人々が書いたり語ったりした文章を集めてあるものです。その中に、週刊朝日に連載された徳川夢声の対談のある回で、女優浪花千栄子さんが幼児のことを語った部分が収録されていた。当時の浪花さんは50台半ばぐらいだろうか。
「辰野隆先生とは、ある雑誌の座談会で、毎月会うことになっている。その度ごとに先生は、浪花千栄子女史の大阪弁を御推奨になる。私もラジオで数回聞いて感心はしていたが、果たして辰野先生が激賞されるほど、結構な大阪弁であるかどうか、一度はナマで聞いてみたいと思っていた。すると、本誌の企画で、彼女と問答することになった。
その後ある日、私は上野の映画劇場で、人を待ち合わせる間、フラリと映画を見たら、それがアチャコ主演の“お父さんはお人好し”シリーズの一つであって、計らずも彼女の顔を見、彼女の台辞回しを聞くことができた。なるほど巧い台辞である。しかも、なかなかの美人に見えた。
その帰り、私は東京会館の東宝映画関係の受賞祝賀式に出かけた。定刻より一時間も早く行ったので、客は私一人しか来ていなかった。署名簿の第一行に私はサインした。と、その第二行にサインしたのが彼女であった。すなわち、これが初対面だったのである。(夢声前白)」
「浪花 なんと申しましても、無学でございましてね。五つのときに母がなくなりまして、七つから家の役にたちましたんです。家が養鶏場をいたしておりましてね、鳥にごはんをたべさす役から、弟のおもりから……。
夢声 おたくはどこだったんですか。
浪花 南河内の金剛山のふもと、楠公さんの誕生地のとなり村でございます。おとうさんは、そこから乗りもんに乗らずに山を越えて、毎日、大阪へ出ますので、あたし、はようから起きて、ごはんこしらえせんならん。そんなんで、八つになりましても、学校へやってもらえしまへんねん。九つから大阪の道頓堀へ奉公に出まして、とうとう学校へいかずじまいでございます。
夢声 その奉公さきは、道頓堀の……。
浪花 浪花座と中座の中間でございまして、仕出し屋さんでございます。むかしのお芝居は、役者さんの後援会を組見と申しまして、松島屋さんでしたら松見会とか、成駒屋さんでしたら井菱会とか、いろんな会がございましたんです。その会のお弁当をつくっております仕出し屋さんでっさかいに、たいへんおしそがしいおうちでございました。おつかいにいきますと、古雑誌で作った袋に、お菓子やアゲなんかいれてくれはりますわね。あたくし、字が習いとうございまして、その袋をだいじにはがしまして……。
むかしの本は、カナがふってございました。そのカナをたよりに、山いう字はこう書くというふうにおぼえたりしましたんですけども、とってもきびしいうちでございまして、字なんかけいこしてるとこをみられますと、こっぴどうセッカンされますねん。しまいには、それをふところにいれまして、お便所へはいりました。お便所なら、だれも怒りにきやはらしまへん。字ィおぼえたさに、そこでいっしょけんめいやってましたら、あんまりお便所がながいもんですさかい、便所の戸をあけにきやはりまして、コンコンたたかれましてね。(笑)
夢声 学習美談ですな。(笑)その仕出し屋さんには、九つの年からいくつごろまでおられたんですか。
浪花 十七までおりました。十七の年まで、父はあたしの奉公してますところがわからずに、女のひとのうしろばっかり追いかけて歩いてはりましてね。
夢声 ひどいことをしてはりましたな。(笑)
浪花 おとうさんいうのは、ちょっと羽左衛門さんに似てましてね、とっても女のひとにもてまして、あっちからもこっちからも、ひっぱりだこで……。そのために、こどもがえらい苦労しましたんでんねん。あたくしのちいさいときには、ヒシの実をひと月くらいたべつづけたことがございますしね、先生。
夢声 買ったヒシの実ですか。とりにいったんですか。
浪花 池のふちにヒシの実がなりますんです。父が女のひとのあとをおっかけていきますと、ひと月ぐらい帰らはらしまへんさかい、たべるもんがないよになってしまいますんでね。
夢声 そのとき、うちには……。
浪花 あたしと弟とふたりきりです。あたしが八つ、弟が五つでございました。河内のうちにおりましたら、おばあさんやなにかいやはりまっさかい、たべさしてもらえますけど、その時分は、大阪の田辺いうとこへ宿がえ(引越し)してまして……。ゲブツ(米びつ)のなかにヘキリ(仕切り)がでけてましてね、かたっぽにお米が二斗、かたっぽに麦が二斗はいるようになってるんですけども、米が一斗、麦が五升ぐらいのところで、おとうさんが女のあとを追うていかはったんですねん。毎日、ごはん茶わんにいっぱいづつ、おかいさん(かゆ)たいてたべてましたんです。
おかいがないよになっても、まだ帰ってきやはらしまへん。よそのおうちから、三日ほど恵んでいただきましたけど、そうそうご迷惑もかけられません。そのうち、よそのごみ箱のそばへきましたら、なんや黒いのがパーッとのいたら、むしたイモがほって(ほおって)ありますねん。
夢声 ハエがたかってたんですね。
浪花 へえ、おイモの山にハイがたかってるんです。そのイモをひと皮むいて、なかたべました。それが糸をひくようなおイモでございましてね。
夢声 サトイモですな。
浪花 いえ、サツマイモです。
夢声 サツマイモが糸をひくんじゃあ、よほどひどいもんですね。(笑)
浪花 そのイモを全部いただいても、まだ帰ってきいしまへん。そのうちに、池のふちのヒシの実を全部とってたべたんですけど、ほいでも、まだ帰ってきやはらしまへん。池のふちのヒシの実がないよになりまして、池のなかのほうのんをとろうと思いましたら、からだがニュルニュルとドロのなかへはいっていきまんねん。その池の近くに踏切がありまして、踏切り番のおっさんは、ドザエモンが出たりしますと、自分の責任になりまっさかい、あたしたちを追いはらうんです。
踏切り渡らんと、池のほうへいかれまへんさかいに、どないぞしておっさんの目ェむすんで渡ろう思いましてね、電車がくるのん待ってて、踏切り番が電車のくるほうみて旗ふってはるあいだに、すっとぬけていきました。おっさん、なんぼあわてたかて、もう手遅れですねん。(笑)いろいろ考えはりましてね、長いさお竹もってきやはりまして、あたしたちが渡らんさきに、あたしのほうを竹でパッとたたいといて、旗ふっていやはる。(笑)そんなんで、ヒシの実もたべさしてもらえまへんし、こまってしまいましてね。ある日、弟が油であげてひねったお菓子をもってきまして……。
夢声 カリントウみたいなやつ。
浪花 カリントウのおおきいのでございます。弟が「ねえちゃん、これ」ちゅうて、あたしにみせまんねん。
夢声 かっぱらってきたんですか。
浪花 へえ、かっぱらってきたんです。(笑)ヒシをとりにいこうおもても、追いはらわれますし、もうおなかになんにもございませんでしょう。弟もせっぱつまってとったんです。みせたとたんに、とったちゅうことはわかったんですけど、「どないしたんや」いうたら、「もろたんや」ていいまんねん。「もろたて、こんなん、くれはりまっかいな」いいましてね、弟をたたいて、手ェもって、ダーッと走って、駄菓子屋のみえんとこまでいきまして、た菓子をふたつに割ったら、おおきいのとちっさいのとできましてん。
「たべよ」いいましたら、弟が「おっきいほう、ねえちゃんにあげる」いいますねんけども、結局、あたしがちっさいほうをいただきました。たべもって、ワアワア泣きもって……。そんな知らない土地にいることが心ぼそうなって、なんとのう、うまれた南河内へ帰りとうなりましてね、弟に「あすの朝、はよう起きて、電車みちつとうて帰ろ」いうて、おばあさんとこへ帰るいう気もちになりましたら、その晩、うれしいて、おなかのすいたん忘れまして、すぐ寝ました。
暗いうちから起きて、トットッ、トットッ、電車みち歩いてきましたら、しまいに電車みちがないようになって、夜が明けましたんです。二上山がみえたら村ですさかいに、その山ばっかり目当てにして歩きましたら、みえてきました。よろこんで歩いているうちに、また山がないようになってしまう。そのうち、夜になってしまいました。しょがおまへんさかい、小屋をみつけて寝ましたんです。あけがた、なんや、あまいすっぱい、ええにおいいたしまして、それで目ェあきました。
荷馬車に俵がいくつもございまして、それにパンのくずがはいっているんです。ふたりでそれをむしょうにたべまして、おなかいっぱいたべたころに、よそのおっさんがじいとみてはりましてね、「なにしてんねん」「へえ、よばれてまんねん」(笑)そのおっさんと話してみましたら、おとうさんの知りあいで、養豚場やってはるおかたで、ブタにやるパンをはこんできやはったとこでした。それから、おかね十銭づつとお米一升もろて、南河内へ帰ってきましたんです。
夢声 たいへんな苦労をなすったんですねえ。」徳川無声・浪花千栄子「対談」(『ちくま哲学の森シリーズ⑧生きる技術』1990.筑摩書房)pp.34-40.
1965年に浪花さんが出した自伝『水のように』が手に入ったので、上記の少女時代の記述を合わせて読んでみましたが、いくつか細部は違っている箇所がありました。母を失い、愛人を追いかけて子を捨てた理不尽な父によって幼い姉弟が、どういう事態に陥ったかは、現代ではとても想像もつかないお話です。この父親に見捨てられて姉弟が大阪から南河内めざして鉄路を歩いた話についても、養豚場のおっさんに助けられて祖母のいる河内に戻ったんじゃなくて、説得されてやっぱり大阪南田辺に戻るんです。この育児放棄された可哀相な少女の苦労はそこで終らなかったのです。

B.ワシントン体制の破綻まで
日本史に記録される用語に「大正デモクラシー」というのがあって、中国大陸で日本が「事件」とか「事変」とか呼ぶ戦争を始めて、それが最終的に英米との大戦争にいたる時代のまえに、一時軍縮がすすみ国際的に平和な時期、国内でも自由な言論や政党政治が実現した時代があったのだ、と説明される。しかしそれはつかのまで、昭和になると軍人が前面に出てきて、ソ連の共産主義への恐怖と経済不況の不安に対してファシズムへの傾斜が強まる。そこに行くプロセスを、三谷氏の『日本の近代とは何であったか』では、「大正デモクラシー」ではなく「ワシントン体制」という国際政治体制の形成と崩壊という形でみている。
「1921(大正10)年11月から1922年2月にかけて、ワシントンDCで国際会議が開催されました。そこにおいて締結された諸条約や諸決議を枠組みとする国際政治体制のことを、ワシントン体制といいます。これは第一次世界大戦後の米国の政治的影響力の拡大がもたらした結果でもありました。
その特質の第一は、多国間協調を志向する多国間条約のネットワークを基本枠組みとする関係各国(日英米仏)間の四国条約、中国に関して、その領土的行政的保全および門戸開放・機会均等の原則を中国はじめ関係各国が相互に確認した九国(日英米仏伊白葡蘭中)条約、太平洋国家である日米両国を含む主要海軍国五国(日米英仏伊)間の海軍軍縮条約がそれです。
ワシントン体制前の日本の外交の基本路線は日英同盟でした。そして、これを補完していたのが、日露協商・日仏協商(利益範囲と協力関係についての二国間了解)でした。要するに、英国をはじめとするヨーロッパ列強との二国間条約ないし協商によってつくられた国際関係を前提としていました。それを多国間条約を枠組とする国際関係を前提としたものに変えたのが、ワシントン体制だったのです。
米国は伝統的に孤立主義的外交路線をとり、特定国との間で政治的あるいは軍事的コミットメントを伴う二国間条約に対しては消極的でした。そのような立場をとってきた米国がワシントン体制に参入したのも、それが多国間条約を基本枠組とするものだったからです。第一次世界大戦後、国際関係を組織する原則が二国間(bilateral)関係を前提としたものから、政治的軍事的コミットメントのより小さい多国間(multilateral)関係を中心としたものに変わることになったために、米国は国際政治に対して、より積極的になりえたのです。
ワシントン体制の特質の第二は、それが軍縮条約を基本枠組とするものだったことです。大戦以前の国際関係を組織していたのは、日英同盟のような二国間の軍事同盟条約もしくはそれに準ずるもの(日露協商のような軍事同盟の潜在的可能性をもっていたもの)でした。ところがワシントン体制では、国際関係が非軍事化され、軍事同盟ではなく、軍縮条約によって組織されることになったのです。
なお、第一次世界大戦後の国際関係の非軍事化を象徴するものとして、軍縮条約とならんで不戦条約があります。不戦条約もまた軍縮条約とおまじく、多国間条約として各国間に締結されました。いうまでもなく、不戦条約は現行の日本国憲法第九条、特にその第一項「日本国民は……国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という文言の歴史的先例となったものです。現行憲法が公布された1946年11月3日当時の吉田茂首相は、不戦条約が調印された1928年8月当時の田中義一首相兼外相の下での外務次官(当時の外交の実務上の責任者)でした。第九条(第一項のみならず、第二項を含めて)を導入した現行憲法に対して、首相兼外相として憲法正文に副署した当時の吉田には大きな抵抗感はなかったと思われます。
ワシントン体制の特質の第三は、それが当事国間の経済的金融的提携関係によって支えられていたことです。その一般原則を打ち出したのは、ワシントン会議と踵を接して開催されたジェノヴァ会議でした。そこで将来の金本位制を根幹とする国際金融体制の構築が決議されたのです。そのための当事国間の経済的金融的提携関係が東アジアにおいて具体化されたのが、1920年に成立した中国に対する日米英仏四国国際借款団であり、そのイニシアティヴをとったのが米国銀行団(特にそのリーダーであるウォール・ストリート最大の投資銀行モルガン商会)とその背後にあった米国国務省であったことは、すでに第二章で見た通りです。
しかし四国借款団の本来の目的である対中借款供与は、投資対象である中国の政治的経済的不安定、中国自体が中国の財政的自主性を損なうとして国際借款団を敵視したことなどから、遂に一度も行われませんでした。ところが反面で四国借款団を媒介として、四国間(特に日米両国間)の経済的金融的提携関係は強められ、それがワシントン体制を支える基礎となりました。その意味で四国借款団はワシントン体制の経済的金融的部分と見ることができるのです。
1930年の日本の金為替本位制復帰(金解禁)の背景にも、このような密接な日米間の国際金融提携が重要な要因として働いていました。それが、金解禁の必要的前提措置としての金準備のための英米両国金融資本による対日クレジットの設定を実現させたのです。まさに1922年のジェノヴァ会議が打ち出した一般原則が、ワシントン体制の経済的金融的部分を強化する形で、東アジアにおいて具体化されたといえるでしょう。
こうして第一次世界大戦前、英国の海軍力によって維持された極東の平和、日本が日英同盟によってその一翼を担った「パックス・ブリタニカ」は、第一次世界大戦後は英国を含む主要海軍国間の軍縮条約、それと不可分の二つの多国間条約(四国条約及び九国条約)、さらに当事国間の経済的金融的提携関係によって形成されたワシントン体制によって継承・維持されることとなったのです。
ワシントン体制には固有の不安定化要因がありました。それは中国ナショナリズムの進展に対して、関係諸国(九国条約国)間に国際協調が成り立つか否かという問題があったことです。たとえば、日米間、日英間、さらに英米間に中国ナショナリズムへの対応において、国際協調が成り立つか否かの問題が、ワシントン体制それ自体を揺さぶり続けました。
日本は中国ナショナリズムとの協調よりも、中国以外の関係諸国(特に英米)との協調を優先し、それによって中国ナショナリズムの攻勢を凌ごうとしました。ところが中国に権益を持たない米国は、本来的に中国ナショナリズムとの協調を優先し、中国に巨大な権益を持っていた英国は日本との帝国主義的協調を一つの選択肢としながら、結局中国における権益の維持を図る立場から、中国ナショナリズムとの協調を選択しました。
日本は中国において孤立し、満州事変によって隘路の強行突破に走りました。これによって、ワシントン体制の不安定化要因は一挙に破綻要因に転化します。ここに第一次世界大戦の「戦後」は終わり、新しい「戦前」が始まるのです。
冷戦後二〇年を超えた今日においても、安定した国際政治秩序は依然として未完の課題です。その原因は、世界的な傾向としてのナショナリズムを超える理念が不在であること、そして、「国益」に固執する短絡的な「リアリズム」が根強いことでしょう。覇権構造解体後の国際政治の多極化の現実に適合した国際政治秩序の理念が必要とされているのです。それは、かつての覇権構造解体後に成立したワシントン体制の正負両様の歴史的経験に立脚したものでなければなりません。
現在においても、中国をめぐる問題が、世界と日本を揺るがしています。現在の中国は、かつてのワシントン体制下の中国とは比較にならぬ強大国となり、冷戦下の覇権構造が解体した後の国際政治の多極化を推進する最も有力な要因であることはもちろんですが、それ以上にその行動は中国周辺諸国には脅威感を与えるほどに、拡大主義的でさえあります。今日日本において国際環境がどちらかといえば、「安全保障環境」として論じられ、「日米同盟」がともすれば、中国を仮想敵国とする軍事同盟として語られるのも、一因は中国の行動にもあります。
第二章において述べたように、かつて1870年代に沖縄をめぐって、緊張関係にあった日清両国は相互に緊張緩和に努力し、戦争を回避することができました。その際日清両国の間に立って、両国の平和への努力を助けたのは、元米国大統領のユリシーズ・グラントでした。今日の米国が沖縄の周辺をめぐって再び対立する日中両国の間に立って、危機の回避のために貢献することは十分に可能です。おそらく、そのことが日中米三国それぞれの「国益」に資することと信じます。
今日米国やヨーロッパにおいては、短絡的な保護主義の衝動や一国主義に向けての視野の縮小が強まる傾向があります。ワシントン体制はその挫折にいたるさまざまの弱点にもかかわらず、軍縮条約に基づく平和的かつ現実的な多国間秩序のゆえに、無秩序と無理念に流れる今日の世界および日本にとって、歴史の教訓とするに値すると思います。少なくとも、ワシントン体制の重要な遺産を憲法第九条に残している日本は、そのことの意味を考えるべきです。」三谷太一郎『日本の近代とは何であったか —―問題史的考察』岩波新書、2017. pp.260-266.
「近代とは何であったか」What is the Modernity in Japan? ではなく、What was the Modernity in empire Japan? というふうに問うた三谷氏の視点には、この本を読み始めた時点では、明治の日本政府のとった施策を基本的に妥当で賢明なものとし、近代化=西洋化に対して批判的な勢力よりも当時の世界情勢、エゴイスティックな列強の世界分割に対して、冷静な認識と弱小国として出発した日本に可能な有効な対応を考えていたとする肯定的な評価に、ぼくは少々違和感も抱いた。しかし、後半でその帝国主義的な側面が成功の道を歩むことで、日本が貪欲に「国益」追求を軍事に頼っていき、周辺国への侵略的態度を強める側面をみると同時に、それに反する国際協調や国益を超えた世界経済秩序を形成しようとする動きも、日本の指導層の中にあったのだという点を掘り起こしていることに、なるほどと思う点も多かった。
日本近代史、とくに昭和前半の歴史的事実について知るべきこと、考えるべきことは実に多い。それが学校教育でどこまで正確に教えられているのか、ぼくは危惧を感じる。最近の大学生に接していると、日本は優れた国で日本人は頑張ってよい国を作ってきたのに、中国や韓国はそれを否定して過去のあら捜しをするのは不快だ、という漠然とした認識をもっているように感じることがある。そこにはあの大戦争に敗北した歴史について、無知と偏見が浸透しているような印象がぬぐえない。歴史に対する視線が、事実ではなく感情的な自己肯定と国家至上主義があるとしたら、右翼的リヴィジョニストの思想教育運動が、かなりの成果を挙げてしまったことになるのだろうか?
いたずらに「戦前の復活」というのも、これはこれで歴史の正確な理解ともいえないが、トランプといい、われらが安倍晋三といい、幅広い国際協調ではなく「国益」追求・ナショナリズムに思想の基盤を置いていること、しかも克服したはずの人種的民族的偏見を否定しない姿勢は、未来への大きな危険を予感させてしまう。
1990年に出版された「ちくま哲学の森シリーズ」というアンソロジーがあって、哲学というけれども、いわゆる哲学者の難しい論文などではなく、多様な人々が書いたり語ったりした文章を集めてあるものです。その中に、週刊朝日に連載された徳川夢声の対談のある回で、女優浪花千栄子さんが幼児のことを語った部分が収録されていた。当時の浪花さんは50台半ばぐらいだろうか。
「辰野隆先生とは、ある雑誌の座談会で、毎月会うことになっている。その度ごとに先生は、浪花千栄子女史の大阪弁を御推奨になる。私もラジオで数回聞いて感心はしていたが、果たして辰野先生が激賞されるほど、結構な大阪弁であるかどうか、一度はナマで聞いてみたいと思っていた。すると、本誌の企画で、彼女と問答することになった。
その後ある日、私は上野の映画劇場で、人を待ち合わせる間、フラリと映画を見たら、それがアチャコ主演の“お父さんはお人好し”シリーズの一つであって、計らずも彼女の顔を見、彼女の台辞回しを聞くことができた。なるほど巧い台辞である。しかも、なかなかの美人に見えた。
その帰り、私は東京会館の東宝映画関係の受賞祝賀式に出かけた。定刻より一時間も早く行ったので、客は私一人しか来ていなかった。署名簿の第一行に私はサインした。と、その第二行にサインしたのが彼女であった。すなわち、これが初対面だったのである。(夢声前白)」
「浪花 なんと申しましても、無学でございましてね。五つのときに母がなくなりまして、七つから家の役にたちましたんです。家が養鶏場をいたしておりましてね、鳥にごはんをたべさす役から、弟のおもりから……。
夢声 おたくはどこだったんですか。
浪花 南河内の金剛山のふもと、楠公さんの誕生地のとなり村でございます。おとうさんは、そこから乗りもんに乗らずに山を越えて、毎日、大阪へ出ますので、あたし、はようから起きて、ごはんこしらえせんならん。そんなんで、八つになりましても、学校へやってもらえしまへんねん。九つから大阪の道頓堀へ奉公に出まして、とうとう学校へいかずじまいでございます。
夢声 その奉公さきは、道頓堀の……。
浪花 浪花座と中座の中間でございまして、仕出し屋さんでございます。むかしのお芝居は、役者さんの後援会を組見と申しまして、松島屋さんでしたら松見会とか、成駒屋さんでしたら井菱会とか、いろんな会がございましたんです。その会のお弁当をつくっております仕出し屋さんでっさかいに、たいへんおしそがしいおうちでございました。おつかいにいきますと、古雑誌で作った袋に、お菓子やアゲなんかいれてくれはりますわね。あたくし、字が習いとうございまして、その袋をだいじにはがしまして……。
むかしの本は、カナがふってございました。そのカナをたよりに、山いう字はこう書くというふうにおぼえたりしましたんですけども、とってもきびしいうちでございまして、字なんかけいこしてるとこをみられますと、こっぴどうセッカンされますねん。しまいには、それをふところにいれまして、お便所へはいりました。お便所なら、だれも怒りにきやはらしまへん。字ィおぼえたさに、そこでいっしょけんめいやってましたら、あんまりお便所がながいもんですさかい、便所の戸をあけにきやはりまして、コンコンたたかれましてね。(笑)
夢声 学習美談ですな。(笑)その仕出し屋さんには、九つの年からいくつごろまでおられたんですか。
浪花 十七までおりました。十七の年まで、父はあたしの奉公してますところがわからずに、女のひとのうしろばっかり追いかけて歩いてはりましてね。
夢声 ひどいことをしてはりましたな。(笑)
浪花 おとうさんいうのは、ちょっと羽左衛門さんに似てましてね、とっても女のひとにもてまして、あっちからもこっちからも、ひっぱりだこで……。そのために、こどもがえらい苦労しましたんでんねん。あたくしのちいさいときには、ヒシの実をひと月くらいたべつづけたことがございますしね、先生。
夢声 買ったヒシの実ですか。とりにいったんですか。
浪花 池のふちにヒシの実がなりますんです。父が女のひとのあとをおっかけていきますと、ひと月ぐらい帰らはらしまへんさかい、たべるもんがないよになってしまいますんでね。
夢声 そのとき、うちには……。
浪花 あたしと弟とふたりきりです。あたしが八つ、弟が五つでございました。河内のうちにおりましたら、おばあさんやなにかいやはりまっさかい、たべさしてもらえますけど、その時分は、大阪の田辺いうとこへ宿がえ(引越し)してまして……。ゲブツ(米びつ)のなかにヘキリ(仕切り)がでけてましてね、かたっぽにお米が二斗、かたっぽに麦が二斗はいるようになってるんですけども、米が一斗、麦が五升ぐらいのところで、おとうさんが女のあとを追うていかはったんですねん。毎日、ごはん茶わんにいっぱいづつ、おかいさん(かゆ)たいてたべてましたんです。
おかいがないよになっても、まだ帰ってきやはらしまへん。よそのおうちから、三日ほど恵んでいただきましたけど、そうそうご迷惑もかけられません。そのうち、よそのごみ箱のそばへきましたら、なんや黒いのがパーッとのいたら、むしたイモがほって(ほおって)ありますねん。
夢声 ハエがたかってたんですね。
浪花 へえ、おイモの山にハイがたかってるんです。そのイモをひと皮むいて、なかたべました。それが糸をひくようなおイモでございましてね。
夢声 サトイモですな。
浪花 いえ、サツマイモです。
夢声 サツマイモが糸をひくんじゃあ、よほどひどいもんですね。(笑)
浪花 そのイモを全部いただいても、まだ帰ってきいしまへん。そのうちに、池のふちのヒシの実を全部とってたべたんですけど、ほいでも、まだ帰ってきやはらしまへん。池のふちのヒシの実がないよになりまして、池のなかのほうのんをとろうと思いましたら、からだがニュルニュルとドロのなかへはいっていきまんねん。その池の近くに踏切がありまして、踏切り番のおっさんは、ドザエモンが出たりしますと、自分の責任になりまっさかい、あたしたちを追いはらうんです。
踏切り渡らんと、池のほうへいかれまへんさかいに、どないぞしておっさんの目ェむすんで渡ろう思いましてね、電車がくるのん待ってて、踏切り番が電車のくるほうみて旗ふってはるあいだに、すっとぬけていきました。おっさん、なんぼあわてたかて、もう手遅れですねん。(笑)いろいろ考えはりましてね、長いさお竹もってきやはりまして、あたしたちが渡らんさきに、あたしのほうを竹でパッとたたいといて、旗ふっていやはる。(笑)そんなんで、ヒシの実もたべさしてもらえまへんし、こまってしまいましてね。ある日、弟が油であげてひねったお菓子をもってきまして……。
夢声 カリントウみたいなやつ。
浪花 カリントウのおおきいのでございます。弟が「ねえちゃん、これ」ちゅうて、あたしにみせまんねん。
夢声 かっぱらってきたんですか。
浪花 へえ、かっぱらってきたんです。(笑)ヒシをとりにいこうおもても、追いはらわれますし、もうおなかになんにもございませんでしょう。弟もせっぱつまってとったんです。みせたとたんに、とったちゅうことはわかったんですけど、「どないしたんや」いうたら、「もろたんや」ていいまんねん。「もろたて、こんなん、くれはりまっかいな」いいましてね、弟をたたいて、手ェもって、ダーッと走って、駄菓子屋のみえんとこまでいきまして、た菓子をふたつに割ったら、おおきいのとちっさいのとできましてん。
「たべよ」いいましたら、弟が「おっきいほう、ねえちゃんにあげる」いいますねんけども、結局、あたしがちっさいほうをいただきました。たべもって、ワアワア泣きもって……。そんな知らない土地にいることが心ぼそうなって、なんとのう、うまれた南河内へ帰りとうなりましてね、弟に「あすの朝、はよう起きて、電車みちつとうて帰ろ」いうて、おばあさんとこへ帰るいう気もちになりましたら、その晩、うれしいて、おなかのすいたん忘れまして、すぐ寝ました。
暗いうちから起きて、トットッ、トットッ、電車みち歩いてきましたら、しまいに電車みちがないようになって、夜が明けましたんです。二上山がみえたら村ですさかいに、その山ばっかり目当てにして歩きましたら、みえてきました。よろこんで歩いているうちに、また山がないようになってしまう。そのうち、夜になってしまいました。しょがおまへんさかい、小屋をみつけて寝ましたんです。あけがた、なんや、あまいすっぱい、ええにおいいたしまして、それで目ェあきました。
荷馬車に俵がいくつもございまして、それにパンのくずがはいっているんです。ふたりでそれをむしょうにたべまして、おなかいっぱいたべたころに、よそのおっさんがじいとみてはりましてね、「なにしてんねん」「へえ、よばれてまんねん」(笑)そのおっさんと話してみましたら、おとうさんの知りあいで、養豚場やってはるおかたで、ブタにやるパンをはこんできやはったとこでした。それから、おかね十銭づつとお米一升もろて、南河内へ帰ってきましたんです。
夢声 たいへんな苦労をなすったんですねえ。」徳川無声・浪花千栄子「対談」(『ちくま哲学の森シリーズ⑧生きる技術』1990.筑摩書房)pp.34-40.
1965年に浪花さんが出した自伝『水のように』が手に入ったので、上記の少女時代の記述を合わせて読んでみましたが、いくつか細部は違っている箇所がありました。母を失い、愛人を追いかけて子を捨てた理不尽な父によって幼い姉弟が、どういう事態に陥ったかは、現代ではとても想像もつかないお話です。この父親に見捨てられて姉弟が大阪から南河内めざして鉄路を歩いた話についても、養豚場のおっさんに助けられて祖母のいる河内に戻ったんじゃなくて、説得されてやっぱり大阪南田辺に戻るんです。この育児放棄された可哀相な少女の苦労はそこで終らなかったのです。

B.ワシントン体制の破綻まで
日本史に記録される用語に「大正デモクラシー」というのがあって、中国大陸で日本が「事件」とか「事変」とか呼ぶ戦争を始めて、それが最終的に英米との大戦争にいたる時代のまえに、一時軍縮がすすみ国際的に平和な時期、国内でも自由な言論や政党政治が実現した時代があったのだ、と説明される。しかしそれはつかのまで、昭和になると軍人が前面に出てきて、ソ連の共産主義への恐怖と経済不況の不安に対してファシズムへの傾斜が強まる。そこに行くプロセスを、三谷氏の『日本の近代とは何であったか』では、「大正デモクラシー」ではなく「ワシントン体制」という国際政治体制の形成と崩壊という形でみている。
「1921(大正10)年11月から1922年2月にかけて、ワシントンDCで国際会議が開催されました。そこにおいて締結された諸条約や諸決議を枠組みとする国際政治体制のことを、ワシントン体制といいます。これは第一次世界大戦後の米国の政治的影響力の拡大がもたらした結果でもありました。
その特質の第一は、多国間協調を志向する多国間条約のネットワークを基本枠組みとする関係各国(日英米仏)間の四国条約、中国に関して、その領土的行政的保全および門戸開放・機会均等の原則を中国はじめ関係各国が相互に確認した九国(日英米仏伊白葡蘭中)条約、太平洋国家である日米両国を含む主要海軍国五国(日米英仏伊)間の海軍軍縮条約がそれです。
ワシントン体制前の日本の外交の基本路線は日英同盟でした。そして、これを補完していたのが、日露協商・日仏協商(利益範囲と協力関係についての二国間了解)でした。要するに、英国をはじめとするヨーロッパ列強との二国間条約ないし協商によってつくられた国際関係を前提としていました。それを多国間条約を枠組とする国際関係を前提としたものに変えたのが、ワシントン体制だったのです。
米国は伝統的に孤立主義的外交路線をとり、特定国との間で政治的あるいは軍事的コミットメントを伴う二国間条約に対しては消極的でした。そのような立場をとってきた米国がワシントン体制に参入したのも、それが多国間条約を基本枠組とするものだったからです。第一次世界大戦後、国際関係を組織する原則が二国間(bilateral)関係を前提としたものから、政治的軍事的コミットメントのより小さい多国間(multilateral)関係を中心としたものに変わることになったために、米国は国際政治に対して、より積極的になりえたのです。
ワシントン体制の特質の第二は、それが軍縮条約を基本枠組とするものだったことです。大戦以前の国際関係を組織していたのは、日英同盟のような二国間の軍事同盟条約もしくはそれに準ずるもの(日露協商のような軍事同盟の潜在的可能性をもっていたもの)でした。ところがワシントン体制では、国際関係が非軍事化され、軍事同盟ではなく、軍縮条約によって組織されることになったのです。
なお、第一次世界大戦後の国際関係の非軍事化を象徴するものとして、軍縮条約とならんで不戦条約があります。不戦条約もまた軍縮条約とおまじく、多国間条約として各国間に締結されました。いうまでもなく、不戦条約は現行の日本国憲法第九条、特にその第一項「日本国民は……国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という文言の歴史的先例となったものです。現行憲法が公布された1946年11月3日当時の吉田茂首相は、不戦条約が調印された1928年8月当時の田中義一首相兼外相の下での外務次官(当時の外交の実務上の責任者)でした。第九条(第一項のみならず、第二項を含めて)を導入した現行憲法に対して、首相兼外相として憲法正文に副署した当時の吉田には大きな抵抗感はなかったと思われます。
ワシントン体制の特質の第三は、それが当事国間の経済的金融的提携関係によって支えられていたことです。その一般原則を打ち出したのは、ワシントン会議と踵を接して開催されたジェノヴァ会議でした。そこで将来の金本位制を根幹とする国際金融体制の構築が決議されたのです。そのための当事国間の経済的金融的提携関係が東アジアにおいて具体化されたのが、1920年に成立した中国に対する日米英仏四国国際借款団であり、そのイニシアティヴをとったのが米国銀行団(特にそのリーダーであるウォール・ストリート最大の投資銀行モルガン商会)とその背後にあった米国国務省であったことは、すでに第二章で見た通りです。
しかし四国借款団の本来の目的である対中借款供与は、投資対象である中国の政治的経済的不安定、中国自体が中国の財政的自主性を損なうとして国際借款団を敵視したことなどから、遂に一度も行われませんでした。ところが反面で四国借款団を媒介として、四国間(特に日米両国間)の経済的金融的提携関係は強められ、それがワシントン体制を支える基礎となりました。その意味で四国借款団はワシントン体制の経済的金融的部分と見ることができるのです。
1930年の日本の金為替本位制復帰(金解禁)の背景にも、このような密接な日米間の国際金融提携が重要な要因として働いていました。それが、金解禁の必要的前提措置としての金準備のための英米両国金融資本による対日クレジットの設定を実現させたのです。まさに1922年のジェノヴァ会議が打ち出した一般原則が、ワシントン体制の経済的金融的部分を強化する形で、東アジアにおいて具体化されたといえるでしょう。
こうして第一次世界大戦前、英国の海軍力によって維持された極東の平和、日本が日英同盟によってその一翼を担った「パックス・ブリタニカ」は、第一次世界大戦後は英国を含む主要海軍国間の軍縮条約、それと不可分の二つの多国間条約(四国条約及び九国条約)、さらに当事国間の経済的金融的提携関係によって形成されたワシントン体制によって継承・維持されることとなったのです。
ワシントン体制には固有の不安定化要因がありました。それは中国ナショナリズムの進展に対して、関係諸国(九国条約国)間に国際協調が成り立つか否かという問題があったことです。たとえば、日米間、日英間、さらに英米間に中国ナショナリズムへの対応において、国際協調が成り立つか否かの問題が、ワシントン体制それ自体を揺さぶり続けました。
日本は中国ナショナリズムとの協調よりも、中国以外の関係諸国(特に英米)との協調を優先し、それによって中国ナショナリズムの攻勢を凌ごうとしました。ところが中国に権益を持たない米国は、本来的に中国ナショナリズムとの協調を優先し、中国に巨大な権益を持っていた英国は日本との帝国主義的協調を一つの選択肢としながら、結局中国における権益の維持を図る立場から、中国ナショナリズムとの協調を選択しました。
日本は中国において孤立し、満州事変によって隘路の強行突破に走りました。これによって、ワシントン体制の不安定化要因は一挙に破綻要因に転化します。ここに第一次世界大戦の「戦後」は終わり、新しい「戦前」が始まるのです。
冷戦後二〇年を超えた今日においても、安定した国際政治秩序は依然として未完の課題です。その原因は、世界的な傾向としてのナショナリズムを超える理念が不在であること、そして、「国益」に固執する短絡的な「リアリズム」が根強いことでしょう。覇権構造解体後の国際政治の多極化の現実に適合した国際政治秩序の理念が必要とされているのです。それは、かつての覇権構造解体後に成立したワシントン体制の正負両様の歴史的経験に立脚したものでなければなりません。
現在においても、中国をめぐる問題が、世界と日本を揺るがしています。現在の中国は、かつてのワシントン体制下の中国とは比較にならぬ強大国となり、冷戦下の覇権構造が解体した後の国際政治の多極化を推進する最も有力な要因であることはもちろんですが、それ以上にその行動は中国周辺諸国には脅威感を与えるほどに、拡大主義的でさえあります。今日日本において国際環境がどちらかといえば、「安全保障環境」として論じられ、「日米同盟」がともすれば、中国を仮想敵国とする軍事同盟として語られるのも、一因は中国の行動にもあります。
第二章において述べたように、かつて1870年代に沖縄をめぐって、緊張関係にあった日清両国は相互に緊張緩和に努力し、戦争を回避することができました。その際日清両国の間に立って、両国の平和への努力を助けたのは、元米国大統領のユリシーズ・グラントでした。今日の米国が沖縄の周辺をめぐって再び対立する日中両国の間に立って、危機の回避のために貢献することは十分に可能です。おそらく、そのことが日中米三国それぞれの「国益」に資することと信じます。
今日米国やヨーロッパにおいては、短絡的な保護主義の衝動や一国主義に向けての視野の縮小が強まる傾向があります。ワシントン体制はその挫折にいたるさまざまの弱点にもかかわらず、軍縮条約に基づく平和的かつ現実的な多国間秩序のゆえに、無秩序と無理念に流れる今日の世界および日本にとって、歴史の教訓とするに値すると思います。少なくとも、ワシントン体制の重要な遺産を憲法第九条に残している日本は、そのことの意味を考えるべきです。」三谷太一郎『日本の近代とは何であったか —―問題史的考察』岩波新書、2017. pp.260-266.
「近代とは何であったか」What is the Modernity in Japan? ではなく、What was the Modernity in empire Japan? というふうに問うた三谷氏の視点には、この本を読み始めた時点では、明治の日本政府のとった施策を基本的に妥当で賢明なものとし、近代化=西洋化に対して批判的な勢力よりも当時の世界情勢、エゴイスティックな列強の世界分割に対して、冷静な認識と弱小国として出発した日本に可能な有効な対応を考えていたとする肯定的な評価に、ぼくは少々違和感も抱いた。しかし、後半でその帝国主義的な側面が成功の道を歩むことで、日本が貪欲に「国益」追求を軍事に頼っていき、周辺国への侵略的態度を強める側面をみると同時に、それに反する国際協調や国益を超えた世界経済秩序を形成しようとする動きも、日本の指導層の中にあったのだという点を掘り起こしていることに、なるほどと思う点も多かった。
日本近代史、とくに昭和前半の歴史的事実について知るべきこと、考えるべきことは実に多い。それが学校教育でどこまで正確に教えられているのか、ぼくは危惧を感じる。最近の大学生に接していると、日本は優れた国で日本人は頑張ってよい国を作ってきたのに、中国や韓国はそれを否定して過去のあら捜しをするのは不快だ、という漠然とした認識をもっているように感じることがある。そこにはあの大戦争に敗北した歴史について、無知と偏見が浸透しているような印象がぬぐえない。歴史に対する視線が、事実ではなく感情的な自己肯定と国家至上主義があるとしたら、右翼的リヴィジョニストの思想教育運動が、かなりの成果を挙げてしまったことになるのだろうか?
いたずらに「戦前の復活」というのも、これはこれで歴史の正確な理解ともいえないが、トランプといい、われらが安倍晋三といい、幅広い国際協調ではなく「国益」追求・ナショナリズムに思想の基盤を置いていること、しかも克服したはずの人種的民族的偏見を否定しない姿勢は、未来への大きな危険を予感させてしまう。















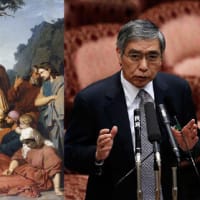










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます