A.原点に還ってみると
1946(昭和21)年11月3日旧明治節にあたる祭日に日本国憲法が公布された。そのとき、日本国民はこの憲法を喜んで歓迎したのが多数派、苦々しい思いでいやいや受け入れたのが少数派だったと推測する。多数派は肉親を失ったあの忌まわしい戦争時代を、もうこりごりだと思っていたから、この憲法が謳う天皇から国民主権への移行、人権尊重と男女の平等、非武装の平和主義などを悪くない理想だと思ったはずだ。確かにそれは、自分たちの中から湧いて出てきたものとはとても思えなかったが、これでこの国が再生するなら子ども達のために頑張ってみようと思ったにちがいない。しかし、戦前の社会でさまざまな利益や特権を享受していた少数派には、占領軍のGHQに強制された理不尽な憲法だとしか思えず、負けたから今は黙っているが、いずれ独立を回復した暁には、ひっくり返してやるのだと臥薪嘗胆の思いであったのだろう。
「あす憲法公布70年 未完の目標に歩み続ける:朝日新聞社説
広島市長だった秋葉忠利さんは、かつて「原爆の日」の平和宣言で憲法の前文をまるごと引用したことがある。
9条ではない。
盛り込んだのは99条である。
「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」
そこに「国民」の文字はない。憲法は、国家権力が勝手な行いをするのを国民が縛り、個人の自由や権利を守るためにあるという近代立憲主義の精神が、条文には込められている。
秋葉さんが生まれたのは1942年11月3日。憲法が公布されるちょうど4年前だ。
中学で憲法を学んだ。留学先の米国では、大統領が就任式で「憲法を維持し、擁護し、防衛する」と誓うと知った。市長3年目に米同時多発テロが起きた。99条の引用はその翌年だ。
世界が憎しみと報復の連鎖に満ちていても、為政者は平和憲法に従う義務がある。この国を戦争ができる国にしてはならない――。安保法制が具体的に動き出そうとしているいま、当時の訴えは一層重く響く。
70年前、天皇に主権があった明治憲法を改正する形式をとって、日本国憲法は生まれた。
憲法を定めた者として、前文でその理念を説くのは「日本国民」である。冒頭で高らかにうたいあげる。「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
だが46年6月に政府が当時の帝国議会に提出した案に、「国民主権」の言葉はなかった。天皇を中心とする国であることは変わらないとの立場から、「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」と、あいまいな表現がとられていた。
そのころ政党や民間がつくった憲法草案の中には、国民主権を明確に打ち出したものもあった。だが政府はその考えをとらず、主権者は誰なのかという議員の追求をけむにまき続けた。
政府の担当大臣はこう答弁している。「点が動いておったか地が動いておったか。議論がいずれにあるにしても。動き方は古より変わってはおりませぬ」
それが今の姿になったのは、連合国軍司令部(GHQ)が国民主権の明記を指示したからだった。「国民主権という言葉をはっきり出さぬと具合悪いのだ」。議事録に残る議員の発言に、本音がかいまみえる。
「日本は立憲主義を語らずに立憲主義を実行した」
昨年亡くなった憲法学者の奥平康弘さんは、こうした経緯を念頭に、憲法の出発点には禍根があると語っていた。
だが同時に「憲法は未完のコンセプトだ」とも訴えていた。その意味するところを、一人ひとりがかみしめたい。
憲法それ自体は一片の文書にすぎない。自由・平等・平和という憲法が掲げる普遍的な理念にむかって、誕生時の重荷を背負い、時に迷い、時に抵抗を受けながらも、一歩ずつ進み続ける。その営みによって、身体全体に血が通い、肉となっていく。
プライヴァシー、報道の自由、一票の価値、働く場での男女平等、知る権利……。社会に定着したこうした考えも、憲法という土台のうえに、70年の年月を超えていきいきと生きていく社会を作るために、憲法は必要なのだ」。奥平さんの言葉だ。
この歩みを否定し時計の針を戻そうというのが、自民党が4年前に発表した改憲草案だ。
冒頭で日本を「天皇を戴く国家」と位置づける。西欧に由来する人権規定は、日本の歴史や伝統を踏まえて見直す必要があるとして制約をかける。家族の互助の大切さを打ちだし、憲法を尊重する義務を負うものとして「国民」を描き加えた。
いずれも、70年前の帝国議会で、敗戦前の日本への思いを断ちがたい議員らが繰り広げた議論と驚くほど重なる。
草案を支える人たちの根底に流れる考えを示す話がある。
案の発表後、自民党議員らの政策集団・創生日本の会合で、元法相が国民主権、基本的人権、平和主義の3原則を挙げ、「これをなくさなければ本当の自主憲法にならない」と発言した。のちに金銭トラブルで離党する若手議員は、3原則が「日本精神を破壊する」とブログに書いた。創生日本の会長は安倍首相その人である。
憲法に指一本触れてはならない、というのではない。だが、長い時間をかけて積み上げた憲法の根本原理を壊そうとする動きに対し、いまを生きる主権者は異を唱え、先人たちの歩みを次代に引き継ぐ務めを負う。
憲法12条には、こうある。
「この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」」朝日新聞2016年11月2日朝刊。
いかにも朝日新聞的、というかお行儀がいい正論だが、ぼくには最後の部分、憲法を根底から否定する思想が、あくまで国民の支持を得られぬ少数派だと考えるのは、ちがうと思う。かつては偏狭で古色蒼然の極右勢力だけの妄想だったのが、いまの日本では必ずしも少数派の意見ともいえなくなっているような気がするからだ。それは日本会議に限らず、この20年ほど憲法をひっくりかえして大日本帝国憲法に戻そうとする勢力が、次世代の教育に潜り込ませようとした国家主義、自衛隊を日陰の存在から国防軍として尊敬されるような心情を育成するミリタリズム、そして中国・韓国・北朝鮮という隣国への憎悪を込めた排外主義の宣伝といった活動が、日本の若い世代にある程度感情的心情的レベルで浸透していることを感じるからだ。そうなってしまったのは、ぼくも関与してきた日本の大学教育が、結局これに十分対抗できなかったということではないか。知の退廃とまでは言いたくないが、「知の大敗」にならぬことを願う。
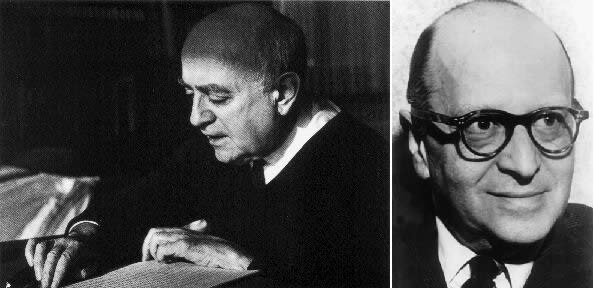
B.アドルノのこと
フランクフルト学派について、大学院の時、ドイツ近代社会思想を専門とされていた先生の授業を毎週受けて、マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノ、エーリッヒ・フロム、ヘルベルト・マルクーゼ、ヴァルター・ベンヤミンなどという名前を知った。その講義は、当時日本語訳が出たマーティン・ジェイのフランクフルト学派研究をなぞっていたように思う。その頃は、フロムやマルクーゼは翻訳があって、ぼくも読んでいたが、ホルクハイマーやアドルノはドイツ語文献ばかりでちょっと手が出なかった。いつか読んでみたいと思ったが、その後もアドルノの英語文献はともかく、ドイツ語の論文は難解でとても歯が立たなかった。
ホルクハイマーとアドルノの共著になる基本文献『啓蒙の弁証法』は、やがて翻訳も出て読めるようになった。芸術と社会と哲学とが混然一体と語られて、魅力的だと思ったがどこまで理解したかは心許なかった。
「オデュッセウスは故郷イタケーへ帰る途中、ある島のわきを通らねばなりません。その島には女神セイレーンたちが住んでいて、通りすがりの船人に甘い歌声で誘いかけます。けれども彼女たちのまわりに堆く積もっているのは、白骨であり干からびた皮です。つまり、彼女たちの歌声に魅せられた者たちは、帰るべき故郷、自分を待ち受けている妻や子どものことも忘れはてて、没落してゆくのです。
このオデュッセウスには、さながら夕暮れの繁華街を通り過ぎて、家路を急ぐサラリーマンの姿が重なりますが、ともあれ、ここでもオデュッセウスは持ち前の策略を弄します(これが女神キルケ―のアドヴァイスによる点も興味深いところですが、著者たちはその点にはふれていません)。彼は、セイレーンの歌がどれほど恐ろしいものか重々言い含めて、仲間の耳には蜜の蠟を詰めて栓をし、自分の体はマストに縛りつけさせます。その島に近づき、セイレーンたちが呼びかけると、オデュッセウスはたちまちその誘惑の虜となって、縄を解くよう仲間たちに懸命に目配せをします。けれども仲間たちは、危険な歌から逃れようと一心に櫂を漕ぎます。むしろオデュッセウスは仲間たちの手によって、さらに何重にもきつく縛りなおされます……。
著者たち(引用者註:『啓蒙の弁証法』の共著者・ホルクハイマー&アドルノ)が注目するのは、セイレーンの歌が過去への自失を誘うものだということです。セイレーンたちは過去の出来事をすべて知っていると歌いかけます。それは、刻苦を経て到達される未來、最終的な帰郷という目的を放棄させるだけでなく、文明の歩みそのものを停止させ、やがては破滅へと引きずりこむ、文明文永に対する文明に対するタナトス(死の欲動)の呼び声そのものなのです。
オデュッセウスは、すなわち西欧文明は、巧妙な策略をつうじてこの危険を乗り切りました。オデュッセウスは歌を聴きつつ生き延びるという新たな経験を積みました。その際、彼の航海の模様は、西欧文明のその後の展開を先取りし、その本質を浮き彫りにしているのです。そこに刻印されているのは、外的な自然の支配と内的な自然の支配、そして人間による人間の社会的支配(身分制と分業)の絡まり合いのうちに自律化を遂げてゆく「芸術」の姿にほかなりません。以下は、『啓蒙の弁証法』のなかでもとくに印象深い一節ですので、長く引用しておきたいと思います。(引用は「啓蒙の概念」の後半からです)。
オデュッセウスは歌声を聴く。だが、彼は力なくマストに縛りつけられたままだ。誘惑が強まれば強まるほど、彼はいっそう固く縛られる。ちょうどのちの市民たちが、彼ら自身の力の増大とともに幸福が身近になればなるほど、それをいっそう頑なに自ら拒んだように。〔……〕自らは歌を聴くことのない仲間たちは、歌の危険を知っているだけで、その美を知らない。オデュッセウスと自分たちを救うために、彼らはオデュッセウスをマストに縛ったままにしておく。彼らは抑圧者の生命を自分たちの生命とひとつのものとして再生産するのである。しかも、抑圧者はもはやその社会的役割から抜け出ることはできない。彼を取り消しようのない形で実践に縛りつけている繩は、同時にセイレーンたちを実践から遠ざけている。つまり、彼女たちの誘惑は中和されて、たんなる瞑想の対象に、芸術になるのだ。縛られている者はいわばコンサート会場にいる。のちの聴衆のように、身じろぎもせず、じっと耳を澄まして。そして、解放をもとめる彼の高ぶった叫びも、拍手喝采の響きと同様に、たちまち虚ろに消え去ってゆく。こうして先史世界との離別に際して、芸術の享受と肉体労働とは別々の道を歩むのである。
著者たちの考えによれば、先史世界において歌声は生活と具体的に結びついていました。祭祀や儀礼のなかで歌はなお呪術的な力を発揮していました。神々の怒りを宥めたり、部族を守護したり、豊穣を祈願したりする「実践」と融合していました。そのとき歌は、聴く者に何らかの形で働きかける力を有していたわけです。セイレーンの歌の危険な魅力は、そういう先史世界における歌の記憶も伝えています。歌の美にふれた者は、もはやその魔圏の外に逃れ出ることはできません。美の魅力に取りつかれた者は、自己保存を不可欠とする社会の発展から取り残され、没落の憂き目に遭うことになります。
ところが、精神労働(オデュッセウス)と肉体労働(船の漕ぎ手たち)への巧妙な分割に依拠して歌を聴きつつ生き延びるオデュッセウスの登場によって、セイレーンたちの支配する世界秩序は崩壊します。オイディプス(エディプス)に謎を解かれることによってスフィンクスが谷に身を投じたように、オデュッセウスの策略によってセイレーンたちは破滅したに違いありません。そのことによって、いまや歌の意味は決定的に反転します。かつて一切を要求した歌声は、もはや現実へのどんな働きかけももちえない、という意味で「絶対的なもの」となります。歌あるいは美は、現実の生活のどんな目的にも仕えないものとして「自律性」を獲得します。
それは、歌が芸術的な美へと純化されるとともに、無力化されてゆくプロセスです。労働に勤しむ者はもはや、耳に栓などしていなくても歌に心を奪われたりはしません。たとえ歌が流されたとしても、それは、耐えがたい労働をすこしでも効率よく進行させるためのBGMに過ぎません。一方、歌を美として享受する者たちは、しょせん歌のもつ美は実生活とは別物だと心得ていて、もはや縛られていなくても持ち場を離れないだけの分別を内面化しています。これらの事態に横たわっているのは、分業の固定化というまぎれもない社会的支配です。」細見和之『フランクフルト学派』中公新書、2014.pp.122-126.
芸術というものが人類史のある段階で、美学的な誘惑への感応として「自律化」する。それは美しさが純化されていくことだが、同時に現実を成り立たせている労働からの乖離であり、分業のなかで芸術家という存在になることで無力化する。そのとき芸術は、歴史を動かす実践の力としてではなく、空虚な瞑想のなかの幻惑のようなものになる。なるほど。このへんは、アドルノ色が強いように思われる。
「テオドーア・W・アドルノ(Theodor W. Adorno)は、1903年、フランクフルトのゆたかなワイン商人の父のもとに生まれました。彼は、フランクフルト社会研究所に集ったメンバーの中では、若手に属していました。父親は形式的にはユダヤ教徒のままでしたが、キリスト教社会に溶け込んだ同化ユダヤ人であり、母親はカトリックでした。その母親、マリアはオペラ歌手、叔母のアガテが本格的なピアニストであったこともあって、アドルノは早くからクラシックの音楽的素養を身につけ、ピアノの演奏にくわえて作曲も非凡な才能を発揮していました。1923年4月、当時19歳だったアドルノ作曲による弦楽四重奏曲がフランクフルトですでに公式に演奏されたという記録がありますから、その早熟の度合いが知られます。そして、アドルノは一〇代の終わりから音楽批評にも手を染め、生涯をつうじて膨大な数の音楽評論を書き継ぐことになります。
アドルノは1922年にフランクフルト大学でホルクハイマーと出会いますが、1924年にフッサール論で博士号を取得したあと、1925年にはアルバン・ベルクのもとで音楽理論と作曲を学ぶためにウィーンに移住したりもします。その当時のアドルノは、哲学を研究しつつも、音楽の理論と実践にどっぷりと浸かっていました。とくに、無調音楽から十二音技法へと突き進んだシェーンベルクの音楽は、アドルノにとって生涯、規範的なものであり続けることになります。
そういうアドルノでしたから、社会研究所のなかでも、当初は、音楽を中心とした文化論がアドルノにあたえられた分野でした。『社会研究誌』にアドルノが発表した原稿を確認しておきましょう。
「音楽の社会的位置について〔Ⅰ〕」(1932年、第一巻一号・二号合併号)
「音楽の社会的位置について〔Ⅱ〕」(1932年、第一巻三号)
「ジャズについて」(1936年、第五巻二号、「ヘクトール・ロットヴァイラー」という偽名による)
「音楽における物神的性格と聴取能力の退化」(1938年、第七巻三号)
「ワーグナーについての断章」(1939年、第八巻一号・二号合併号)
「キルケゴールの愛の教え」(1940年、第九巻一号、英語)
「ポピュラー・ミュージックについて」(1941年、第一〇巻一号、英語)
「こんにちのシュペングラー」(1941年、第一〇巻二号、英語)
「文化に対するウェブレンの攻撃」(1941年、第一〇巻三号、英語)
最初の「音楽の社会的位置について〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕」はいまではアドルノの音楽論の原点に位置づけられている長大な論文です。マルクスの用語を使いながらも、文化といういわゆる上部構造を経済的な生産関係という下部構造に還元する、単純なマルクス主義的文化論にはとうてい収まらない視点で、さまざまな問題が論じられています。それ以降のジャズ論、「音楽の物神的性格」についての論考、さらにはポピュラー・ミュージック論もまた、アドルノのだいじな仕事です。しかし、あくまでアドルノの当初の役割は音楽論である、という印象は否定できません。実際、アドルノが社旗研究所の正式の共同研究員となったのは、1938年にニューヨークに移住してからでした。それまでアドルノは身分的には外部の寄稿者であって、フロムやマルクーゼのほうがホルクハイマーらとずっと親しい関係にありました。
アドルノがフランクフルト大学で哲学の研究者として公的に登場した最初の仕事は、1931年5月にフランクフルト大学の講師就任に際して行なった「哲学のアクチュアリティ」と題された講演でした。さらに翌年、アドルノは「自然史の理念」という講演を行います。いずれも、けっして音楽論には特化しない形で、当時絶大な人気を誇っていたハイデガーの思想を批判しつつ哲学のアクチュアルな課題がどこにあるかを示したものです。
ところで、第1章で紹介したホルクハイマーの社会研究所の所長就任講演は、1931年1月でした。つまり、アドルノとホルクハイマーの講演はほぼ同時期になされたものということになります。にもかかわらず、ふたりの講演から受ける印象はかなり異なったものです。ホルクハイマーが個々の人間を超えた社会のダイナミズムを捉える社会哲学の立場から学際的な探究をもとめていたのに対して、アドルノはそもそも大きな視点で社会を捉えることの不可能性を繰り返し主張しているからです。
大きな哲学におけるあらゆる確実性の崩壊とともに、美学の領域で大胆な試みが開始されるならば、そしてその試みが、美学的エッセイのもつ、限定され、輪郭の際立った、非象徴的な解釈と結びついているならば、対象が適確に選ばれ、その対象が現実のものであるかぎり、弾劾されるべきものとは私には思えません。といいますのも、たしかに精神は現実の総体を生み出したり、現実の総体を把握したりすることはできませんが、微細な姿で侵入し、微細な一点で、現に存在しているものの尺度を破壊することができるからです。(アドルノ『哲学のアクチュアリティ』)
ここには対象の微細な部分に焦点を置いて批評を繰りひろげる、ミクロロギー(微視的探究)という方法が明瞭に告げられています。そして、ここでアドルノが「美学的エッセイ」ということでまずもって念頭においているのは、やはりベンヤミンの仕事、とりわけ『ドイツ哀悼遊戯の根源』です。」細見和之『フランクフルト学派』中公新書、2014.pp.94-98.
大学院で、S先生のフランクフルト学派に関する講義を1年間聴いて、ぼくが理解したように思ったのは、フランクフルト学派のメンバーは哲学、経済学、心理学、社会学、精神分析、人文学、芸術学などの専門領域を自在に超えて、20世紀半ばにさしかかる時点で西洋の知のありようを、3つの伝統のスパークとして捉えていた、だろうということだ。ひとつはカントに象徴されるドイツの批判哲学、つぎにマルクスの唯物論的世界観、そしてもうひとつはフロイトが始めた精神分析の思想的意味である。これらを総合して「批判理論」を彼らの立場として打ち出した。そして、批判理論のエッセンスは、真理というものをこれこそ正しいと打ちだすのではなく、これが真理だと主張する理論をその根底に遡って批判する、ことにしか心理に辿り着く道はない、ということだろう。それは自分自身を批判し否定する精神につながることは当然だ。
1946(昭和21)年11月3日旧明治節にあたる祭日に日本国憲法が公布された。そのとき、日本国民はこの憲法を喜んで歓迎したのが多数派、苦々しい思いでいやいや受け入れたのが少数派だったと推測する。多数派は肉親を失ったあの忌まわしい戦争時代を、もうこりごりだと思っていたから、この憲法が謳う天皇から国民主権への移行、人権尊重と男女の平等、非武装の平和主義などを悪くない理想だと思ったはずだ。確かにそれは、自分たちの中から湧いて出てきたものとはとても思えなかったが、これでこの国が再生するなら子ども達のために頑張ってみようと思ったにちがいない。しかし、戦前の社会でさまざまな利益や特権を享受していた少数派には、占領軍のGHQに強制された理不尽な憲法だとしか思えず、負けたから今は黙っているが、いずれ独立を回復した暁には、ひっくり返してやるのだと臥薪嘗胆の思いであったのだろう。
「あす憲法公布70年 未完の目標に歩み続ける:朝日新聞社説
広島市長だった秋葉忠利さんは、かつて「原爆の日」の平和宣言で憲法の前文をまるごと引用したことがある。
9条ではない。
盛り込んだのは99条である。
「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」
そこに「国民」の文字はない。憲法は、国家権力が勝手な行いをするのを国民が縛り、個人の自由や権利を守るためにあるという近代立憲主義の精神が、条文には込められている。
秋葉さんが生まれたのは1942年11月3日。憲法が公布されるちょうど4年前だ。
中学で憲法を学んだ。留学先の米国では、大統領が就任式で「憲法を維持し、擁護し、防衛する」と誓うと知った。市長3年目に米同時多発テロが起きた。99条の引用はその翌年だ。
世界が憎しみと報復の連鎖に満ちていても、為政者は平和憲法に従う義務がある。この国を戦争ができる国にしてはならない――。安保法制が具体的に動き出そうとしているいま、当時の訴えは一層重く響く。
70年前、天皇に主権があった明治憲法を改正する形式をとって、日本国憲法は生まれた。
憲法を定めた者として、前文でその理念を説くのは「日本国民」である。冒頭で高らかにうたいあげる。「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
だが46年6月に政府が当時の帝国議会に提出した案に、「国民主権」の言葉はなかった。天皇を中心とする国であることは変わらないとの立場から、「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」と、あいまいな表現がとられていた。
そのころ政党や民間がつくった憲法草案の中には、国民主権を明確に打ち出したものもあった。だが政府はその考えをとらず、主権者は誰なのかという議員の追求をけむにまき続けた。
政府の担当大臣はこう答弁している。「点が動いておったか地が動いておったか。議論がいずれにあるにしても。動き方は古より変わってはおりませぬ」
それが今の姿になったのは、連合国軍司令部(GHQ)が国民主権の明記を指示したからだった。「国民主権という言葉をはっきり出さぬと具合悪いのだ」。議事録に残る議員の発言に、本音がかいまみえる。
「日本は立憲主義を語らずに立憲主義を実行した」
昨年亡くなった憲法学者の奥平康弘さんは、こうした経緯を念頭に、憲法の出発点には禍根があると語っていた。
だが同時に「憲法は未完のコンセプトだ」とも訴えていた。その意味するところを、一人ひとりがかみしめたい。
憲法それ自体は一片の文書にすぎない。自由・平等・平和という憲法が掲げる普遍的な理念にむかって、誕生時の重荷を背負い、時に迷い、時に抵抗を受けながらも、一歩ずつ進み続ける。その営みによって、身体全体に血が通い、肉となっていく。
プライヴァシー、報道の自由、一票の価値、働く場での男女平等、知る権利……。社会に定着したこうした考えも、憲法という土台のうえに、70年の年月を超えていきいきと生きていく社会を作るために、憲法は必要なのだ」。奥平さんの言葉だ。
この歩みを否定し時計の針を戻そうというのが、自民党が4年前に発表した改憲草案だ。
冒頭で日本を「天皇を戴く国家」と位置づける。西欧に由来する人権規定は、日本の歴史や伝統を踏まえて見直す必要があるとして制約をかける。家族の互助の大切さを打ちだし、憲法を尊重する義務を負うものとして「国民」を描き加えた。
いずれも、70年前の帝国議会で、敗戦前の日本への思いを断ちがたい議員らが繰り広げた議論と驚くほど重なる。
草案を支える人たちの根底に流れる考えを示す話がある。
案の発表後、自民党議員らの政策集団・創生日本の会合で、元法相が国民主権、基本的人権、平和主義の3原則を挙げ、「これをなくさなければ本当の自主憲法にならない」と発言した。のちに金銭トラブルで離党する若手議員は、3原則が「日本精神を破壊する」とブログに書いた。創生日本の会長は安倍首相その人である。
憲法に指一本触れてはならない、というのではない。だが、長い時間をかけて積み上げた憲法の根本原理を壊そうとする動きに対し、いまを生きる主権者は異を唱え、先人たちの歩みを次代に引き継ぐ務めを負う。
憲法12条には、こうある。
「この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」」朝日新聞2016年11月2日朝刊。
いかにも朝日新聞的、というかお行儀がいい正論だが、ぼくには最後の部分、憲法を根底から否定する思想が、あくまで国民の支持を得られぬ少数派だと考えるのは、ちがうと思う。かつては偏狭で古色蒼然の極右勢力だけの妄想だったのが、いまの日本では必ずしも少数派の意見ともいえなくなっているような気がするからだ。それは日本会議に限らず、この20年ほど憲法をひっくりかえして大日本帝国憲法に戻そうとする勢力が、次世代の教育に潜り込ませようとした国家主義、自衛隊を日陰の存在から国防軍として尊敬されるような心情を育成するミリタリズム、そして中国・韓国・北朝鮮という隣国への憎悪を込めた排外主義の宣伝といった活動が、日本の若い世代にある程度感情的心情的レベルで浸透していることを感じるからだ。そうなってしまったのは、ぼくも関与してきた日本の大学教育が、結局これに十分対抗できなかったということではないか。知の退廃とまでは言いたくないが、「知の大敗」にならぬことを願う。
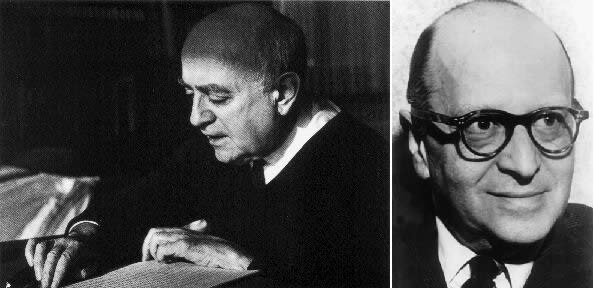
B.アドルノのこと
フランクフルト学派について、大学院の時、ドイツ近代社会思想を専門とされていた先生の授業を毎週受けて、マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノ、エーリッヒ・フロム、ヘルベルト・マルクーゼ、ヴァルター・ベンヤミンなどという名前を知った。その講義は、当時日本語訳が出たマーティン・ジェイのフランクフルト学派研究をなぞっていたように思う。その頃は、フロムやマルクーゼは翻訳があって、ぼくも読んでいたが、ホルクハイマーやアドルノはドイツ語文献ばかりでちょっと手が出なかった。いつか読んでみたいと思ったが、その後もアドルノの英語文献はともかく、ドイツ語の論文は難解でとても歯が立たなかった。
ホルクハイマーとアドルノの共著になる基本文献『啓蒙の弁証法』は、やがて翻訳も出て読めるようになった。芸術と社会と哲学とが混然一体と語られて、魅力的だと思ったがどこまで理解したかは心許なかった。
「オデュッセウスは故郷イタケーへ帰る途中、ある島のわきを通らねばなりません。その島には女神セイレーンたちが住んでいて、通りすがりの船人に甘い歌声で誘いかけます。けれども彼女たちのまわりに堆く積もっているのは、白骨であり干からびた皮です。つまり、彼女たちの歌声に魅せられた者たちは、帰るべき故郷、自分を待ち受けている妻や子どものことも忘れはてて、没落してゆくのです。
このオデュッセウスには、さながら夕暮れの繁華街を通り過ぎて、家路を急ぐサラリーマンの姿が重なりますが、ともあれ、ここでもオデュッセウスは持ち前の策略を弄します(これが女神キルケ―のアドヴァイスによる点も興味深いところですが、著者たちはその点にはふれていません)。彼は、セイレーンの歌がどれほど恐ろしいものか重々言い含めて、仲間の耳には蜜の蠟を詰めて栓をし、自分の体はマストに縛りつけさせます。その島に近づき、セイレーンたちが呼びかけると、オデュッセウスはたちまちその誘惑の虜となって、縄を解くよう仲間たちに懸命に目配せをします。けれども仲間たちは、危険な歌から逃れようと一心に櫂を漕ぎます。むしろオデュッセウスは仲間たちの手によって、さらに何重にもきつく縛りなおされます……。
著者たち(引用者註:『啓蒙の弁証法』の共著者・ホルクハイマー&アドルノ)が注目するのは、セイレーンの歌が過去への自失を誘うものだということです。セイレーンたちは過去の出来事をすべて知っていると歌いかけます。それは、刻苦を経て到達される未來、最終的な帰郷という目的を放棄させるだけでなく、文明の歩みそのものを停止させ、やがては破滅へと引きずりこむ、文明文永に対する文明に対するタナトス(死の欲動)の呼び声そのものなのです。
オデュッセウスは、すなわち西欧文明は、巧妙な策略をつうじてこの危険を乗り切りました。オデュッセウスは歌を聴きつつ生き延びるという新たな経験を積みました。その際、彼の航海の模様は、西欧文明のその後の展開を先取りし、その本質を浮き彫りにしているのです。そこに刻印されているのは、外的な自然の支配と内的な自然の支配、そして人間による人間の社会的支配(身分制と分業)の絡まり合いのうちに自律化を遂げてゆく「芸術」の姿にほかなりません。以下は、『啓蒙の弁証法』のなかでもとくに印象深い一節ですので、長く引用しておきたいと思います。(引用は「啓蒙の概念」の後半からです)。
オデュッセウスは歌声を聴く。だが、彼は力なくマストに縛りつけられたままだ。誘惑が強まれば強まるほど、彼はいっそう固く縛られる。ちょうどのちの市民たちが、彼ら自身の力の増大とともに幸福が身近になればなるほど、それをいっそう頑なに自ら拒んだように。〔……〕自らは歌を聴くことのない仲間たちは、歌の危険を知っているだけで、その美を知らない。オデュッセウスと自分たちを救うために、彼らはオデュッセウスをマストに縛ったままにしておく。彼らは抑圧者の生命を自分たちの生命とひとつのものとして再生産するのである。しかも、抑圧者はもはやその社会的役割から抜け出ることはできない。彼を取り消しようのない形で実践に縛りつけている繩は、同時にセイレーンたちを実践から遠ざけている。つまり、彼女たちの誘惑は中和されて、たんなる瞑想の対象に、芸術になるのだ。縛られている者はいわばコンサート会場にいる。のちの聴衆のように、身じろぎもせず、じっと耳を澄まして。そして、解放をもとめる彼の高ぶった叫びも、拍手喝采の響きと同様に、たちまち虚ろに消え去ってゆく。こうして先史世界との離別に際して、芸術の享受と肉体労働とは別々の道を歩むのである。
著者たちの考えによれば、先史世界において歌声は生活と具体的に結びついていました。祭祀や儀礼のなかで歌はなお呪術的な力を発揮していました。神々の怒りを宥めたり、部族を守護したり、豊穣を祈願したりする「実践」と融合していました。そのとき歌は、聴く者に何らかの形で働きかける力を有していたわけです。セイレーンの歌の危険な魅力は、そういう先史世界における歌の記憶も伝えています。歌の美にふれた者は、もはやその魔圏の外に逃れ出ることはできません。美の魅力に取りつかれた者は、自己保存を不可欠とする社会の発展から取り残され、没落の憂き目に遭うことになります。
ところが、精神労働(オデュッセウス)と肉体労働(船の漕ぎ手たち)への巧妙な分割に依拠して歌を聴きつつ生き延びるオデュッセウスの登場によって、セイレーンたちの支配する世界秩序は崩壊します。オイディプス(エディプス)に謎を解かれることによってスフィンクスが谷に身を投じたように、オデュッセウスの策略によってセイレーンたちは破滅したに違いありません。そのことによって、いまや歌の意味は決定的に反転します。かつて一切を要求した歌声は、もはや現実へのどんな働きかけももちえない、という意味で「絶対的なもの」となります。歌あるいは美は、現実の生活のどんな目的にも仕えないものとして「自律性」を獲得します。
それは、歌が芸術的な美へと純化されるとともに、無力化されてゆくプロセスです。労働に勤しむ者はもはや、耳に栓などしていなくても歌に心を奪われたりはしません。たとえ歌が流されたとしても、それは、耐えがたい労働をすこしでも効率よく進行させるためのBGMに過ぎません。一方、歌を美として享受する者たちは、しょせん歌のもつ美は実生活とは別物だと心得ていて、もはや縛られていなくても持ち場を離れないだけの分別を内面化しています。これらの事態に横たわっているのは、分業の固定化というまぎれもない社会的支配です。」細見和之『フランクフルト学派』中公新書、2014.pp.122-126.
芸術というものが人類史のある段階で、美学的な誘惑への感応として「自律化」する。それは美しさが純化されていくことだが、同時に現実を成り立たせている労働からの乖離であり、分業のなかで芸術家という存在になることで無力化する。そのとき芸術は、歴史を動かす実践の力としてではなく、空虚な瞑想のなかの幻惑のようなものになる。なるほど。このへんは、アドルノ色が強いように思われる。
「テオドーア・W・アドルノ(Theodor W. Adorno)は、1903年、フランクフルトのゆたかなワイン商人の父のもとに生まれました。彼は、フランクフルト社会研究所に集ったメンバーの中では、若手に属していました。父親は形式的にはユダヤ教徒のままでしたが、キリスト教社会に溶け込んだ同化ユダヤ人であり、母親はカトリックでした。その母親、マリアはオペラ歌手、叔母のアガテが本格的なピアニストであったこともあって、アドルノは早くからクラシックの音楽的素養を身につけ、ピアノの演奏にくわえて作曲も非凡な才能を発揮していました。1923年4月、当時19歳だったアドルノ作曲による弦楽四重奏曲がフランクフルトですでに公式に演奏されたという記録がありますから、その早熟の度合いが知られます。そして、アドルノは一〇代の終わりから音楽批評にも手を染め、生涯をつうじて膨大な数の音楽評論を書き継ぐことになります。
アドルノは1922年にフランクフルト大学でホルクハイマーと出会いますが、1924年にフッサール論で博士号を取得したあと、1925年にはアルバン・ベルクのもとで音楽理論と作曲を学ぶためにウィーンに移住したりもします。その当時のアドルノは、哲学を研究しつつも、音楽の理論と実践にどっぷりと浸かっていました。とくに、無調音楽から十二音技法へと突き進んだシェーンベルクの音楽は、アドルノにとって生涯、規範的なものであり続けることになります。
そういうアドルノでしたから、社会研究所のなかでも、当初は、音楽を中心とした文化論がアドルノにあたえられた分野でした。『社会研究誌』にアドルノが発表した原稿を確認しておきましょう。
「音楽の社会的位置について〔Ⅰ〕」(1932年、第一巻一号・二号合併号)
「音楽の社会的位置について〔Ⅱ〕」(1932年、第一巻三号)
「ジャズについて」(1936年、第五巻二号、「ヘクトール・ロットヴァイラー」という偽名による)
「音楽における物神的性格と聴取能力の退化」(1938年、第七巻三号)
「ワーグナーについての断章」(1939年、第八巻一号・二号合併号)
「キルケゴールの愛の教え」(1940年、第九巻一号、英語)
「ポピュラー・ミュージックについて」(1941年、第一〇巻一号、英語)
「こんにちのシュペングラー」(1941年、第一〇巻二号、英語)
「文化に対するウェブレンの攻撃」(1941年、第一〇巻三号、英語)
最初の「音楽の社会的位置について〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕」はいまではアドルノの音楽論の原点に位置づけられている長大な論文です。マルクスの用語を使いながらも、文化といういわゆる上部構造を経済的な生産関係という下部構造に還元する、単純なマルクス主義的文化論にはとうてい収まらない視点で、さまざまな問題が論じられています。それ以降のジャズ論、「音楽の物神的性格」についての論考、さらにはポピュラー・ミュージック論もまた、アドルノのだいじな仕事です。しかし、あくまでアドルノの当初の役割は音楽論である、という印象は否定できません。実際、アドルノが社旗研究所の正式の共同研究員となったのは、1938年にニューヨークに移住してからでした。それまでアドルノは身分的には外部の寄稿者であって、フロムやマルクーゼのほうがホルクハイマーらとずっと親しい関係にありました。
アドルノがフランクフルト大学で哲学の研究者として公的に登場した最初の仕事は、1931年5月にフランクフルト大学の講師就任に際して行なった「哲学のアクチュアリティ」と題された講演でした。さらに翌年、アドルノは「自然史の理念」という講演を行います。いずれも、けっして音楽論には特化しない形で、当時絶大な人気を誇っていたハイデガーの思想を批判しつつ哲学のアクチュアルな課題がどこにあるかを示したものです。
ところで、第1章で紹介したホルクハイマーの社会研究所の所長就任講演は、1931年1月でした。つまり、アドルノとホルクハイマーの講演はほぼ同時期になされたものということになります。にもかかわらず、ふたりの講演から受ける印象はかなり異なったものです。ホルクハイマーが個々の人間を超えた社会のダイナミズムを捉える社会哲学の立場から学際的な探究をもとめていたのに対して、アドルノはそもそも大きな視点で社会を捉えることの不可能性を繰り返し主張しているからです。
大きな哲学におけるあらゆる確実性の崩壊とともに、美学の領域で大胆な試みが開始されるならば、そしてその試みが、美学的エッセイのもつ、限定され、輪郭の際立った、非象徴的な解釈と結びついているならば、対象が適確に選ばれ、その対象が現実のものであるかぎり、弾劾されるべきものとは私には思えません。といいますのも、たしかに精神は現実の総体を生み出したり、現実の総体を把握したりすることはできませんが、微細な姿で侵入し、微細な一点で、現に存在しているものの尺度を破壊することができるからです。(アドルノ『哲学のアクチュアリティ』)
ここには対象の微細な部分に焦点を置いて批評を繰りひろげる、ミクロロギー(微視的探究)という方法が明瞭に告げられています。そして、ここでアドルノが「美学的エッセイ」ということでまずもって念頭においているのは、やはりベンヤミンの仕事、とりわけ『ドイツ哀悼遊戯の根源』です。」細見和之『フランクフルト学派』中公新書、2014.pp.94-98.
大学院で、S先生のフランクフルト学派に関する講義を1年間聴いて、ぼくが理解したように思ったのは、フランクフルト学派のメンバーは哲学、経済学、心理学、社会学、精神分析、人文学、芸術学などの専門領域を自在に超えて、20世紀半ばにさしかかる時点で西洋の知のありようを、3つの伝統のスパークとして捉えていた、だろうということだ。ひとつはカントに象徴されるドイツの批判哲学、つぎにマルクスの唯物論的世界観、そしてもうひとつはフロイトが始めた精神分析の思想的意味である。これらを総合して「批判理論」を彼らの立場として打ち出した。そして、批判理論のエッセンスは、真理というものをこれこそ正しいと打ちだすのではなく、これが真理だと主張する理論をその根底に遡って批判する、ことにしか心理に辿り着く道はない、ということだろう。それは自分自身を批判し否定する精神につながることは当然だ。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます