こんばんは、室長です。
今日は、室長も所属する地元の若手経営者の組織である那須烏山商工会青年部にて、「烏と烏山の関係性について」というテーマで勉強会を実施しました♪

講師に中村彰太郎氏(那須烏山商工会前会長・(株)中村製作所 代表取締役)をお招きして、30分程のダイジェスト版のレクチャーをいただいたのちに、質疑応答しつつ歓談するという、青年部ではなかなか斬新かつ文化的な企画ですw
旧烏山町の時代に青年部が中心となって行なった、地域のCI(コーポレート・アイデンティティ)を見つめる活動に始まり、那珂川フェスティバルイン烏山(平成元年~10年間)の運営、そして日本カラスフォーラムイン烏山(平成3年)の開催のあらましを紹介され、まずはかつての青年部のパワフルさに圧倒されてしまいました。。
地域のアイデンティティを見つめる過程で、烏(カラス)という、一般的には不吉とされる名称を町名に使うようになったいきさつを調べていく中で、烏をとりまく歴史的・文化的な広がり/深みを発見し、調べていくうちにすっかりその虜になってしまったそうです。
その結果、こんなものまで作ってしまったというから驚きというか、感服してしまいます。
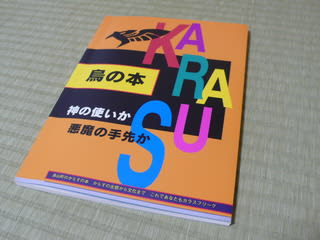
我々が住む「烏山」の地名の発祥には諸説あり、
①民話
②烏主山(カラスが主人の山)
③空州(からす)
④宮原の八幡神社
といった説があるそうです。
これという決定打はないものの、「民話というのは根拠や理由があって作られたもの」という性格が強いため、民話の中で言及される「稲積城から城を移築する際に、烏がくわえた幣束を落とした場所に新たな城(烏山城)を築いた」という一説が示すような由来が多分に有力なのではないか、というのがその場での見解でした。*参考:地名の由来
ちなみに、烏は神の仕えとして崇められており、また陰陽で言えば陽(太陽)を示す存在なのだとか。とりわけ熊野神社との関わりが深いようです。
話は地名の由来にとどまらず、八咫烏(やたがらす)と烏山の関連についても広がっていきます。八咫烏とは、「日本神話において、神武天皇を大和の橿原まで案内したとされており、導きの神として信仰されている」存在で、サッカー日本代表のシンボルマークにもなっています。
八咫烏の烏山との関係性はもとより、国内(熊野三山、出羽三山、厳島神社)や国外(中国、韓国)との関係性にまで及び、なかなか消化しきれず…。神話や神社仏閣の話になると、歴史に関する知識の浅い人間には到底理解が難しいもので。。勉強の必要性を感じた次第です。
なにぶん若輩者なので理解の深浅はさて置くことにしまして、烏山の地名の由来が諸説あり、今でこそ人気のない烏も神聖なものの象徴だったことなどを知り、もう少し若い時分に知っておけば良かったと悔やむメンバーもいたりして、なかなか刺激的な機会だったのではないかと思います♪
「幼少の頃に学習しておけば、故郷への愛着も少し違ったものになったのでは」と惜しむメンバーもいましたが、ひょっとすると、それはこのレクチャーを聞いた我々が次の世代に向けて課せられた仕事なのではないかと責任感を意識した瞬間でもあったと思います。
いずれにせよ、講師の中村氏は、烏の研究をライフワークの一つとして向き合っておられることから分かるように、烏の歴史は非常に奥の深い分野です。微力ながら我々がそのお役に立てる…とは毫も思っていませんが、その広大無辺に広がる世界の入り口にとりあえずは立つことができたというのは、非常に意義深いことなのではないかと思った次第です。
また一つ、青年部に課せられたテーマが増えましたが、じっくりと向き合っていきたいと思います!
今日は、室長も所属する地元の若手経営者の組織である那須烏山商工会青年部にて、「烏と烏山の関係性について」というテーマで勉強会を実施しました♪

講師に中村彰太郎氏(那須烏山商工会前会長・(株)中村製作所 代表取締役)をお招きして、30分程のダイジェスト版のレクチャーをいただいたのちに、質疑応答しつつ歓談するという、青年部ではなかなか斬新かつ文化的な企画ですw
旧烏山町の時代に青年部が中心となって行なった、地域のCI(コーポレート・アイデンティティ)を見つめる活動に始まり、那珂川フェスティバルイン烏山(平成元年~10年間)の運営、そして日本カラスフォーラムイン烏山(平成3年)の開催のあらましを紹介され、まずはかつての青年部のパワフルさに圧倒されてしまいました。。
地域のアイデンティティを見つめる過程で、烏(カラス)という、一般的には不吉とされる名称を町名に使うようになったいきさつを調べていく中で、烏をとりまく歴史的・文化的な広がり/深みを発見し、調べていくうちにすっかりその虜になってしまったそうです。
その結果、こんなものまで作ってしまったというから驚きというか、感服してしまいます。
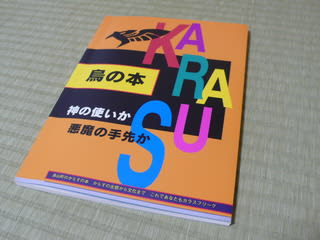
我々が住む「烏山」の地名の発祥には諸説あり、
①民話
②烏主山(カラスが主人の山)
③空州(からす)
④宮原の八幡神社
といった説があるそうです。
これという決定打はないものの、「民話というのは根拠や理由があって作られたもの」という性格が強いため、民話の中で言及される「稲積城から城を移築する際に、烏がくわえた幣束を落とした場所に新たな城(烏山城)を築いた」という一説が示すような由来が多分に有力なのではないか、というのがその場での見解でした。*参考:地名の由来
ちなみに、烏は神の仕えとして崇められており、また陰陽で言えば陽(太陽)を示す存在なのだとか。とりわけ熊野神社との関わりが深いようです。
話は地名の由来にとどまらず、八咫烏(やたがらす)と烏山の関連についても広がっていきます。八咫烏とは、「日本神話において、神武天皇を大和の橿原まで案内したとされており、導きの神として信仰されている」存在で、サッカー日本代表のシンボルマークにもなっています。
八咫烏の烏山との関係性はもとより、国内(熊野三山、出羽三山、厳島神社)や国外(中国、韓国)との関係性にまで及び、なかなか消化しきれず…。神話や神社仏閣の話になると、歴史に関する知識の浅い人間には到底理解が難しいもので。。勉強の必要性を感じた次第です。
なにぶん若輩者なので理解の深浅はさて置くことにしまして、烏山の地名の由来が諸説あり、今でこそ人気のない烏も神聖なものの象徴だったことなどを知り、もう少し若い時分に知っておけば良かったと悔やむメンバーもいたりして、なかなか刺激的な機会だったのではないかと思います♪
「幼少の頃に学習しておけば、故郷への愛着も少し違ったものになったのでは」と惜しむメンバーもいましたが、ひょっとすると、それはこのレクチャーを聞いた我々が次の世代に向けて課せられた仕事なのではないかと責任感を意識した瞬間でもあったと思います。
いずれにせよ、講師の中村氏は、烏の研究をライフワークの一つとして向き合っておられることから分かるように、烏の歴史は非常に奥の深い分野です。微力ながら我々がそのお役に立てる…とは毫も思っていませんが、その広大無辺に広がる世界の入り口にとりあえずは立つことができたというのは、非常に意義深いことなのではないかと思った次第です。
また一つ、青年部に課せられたテーマが増えましたが、じっくりと向き合っていきたいと思います!



















