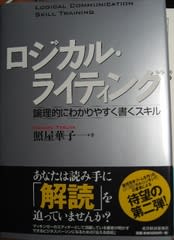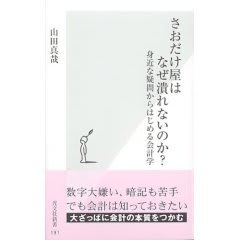ロジカル物の書籍は多いが、今日、照屋華子著「ロジカル・ライティング」を読んだ。
事例を使いながら、分かりやすく書かれているが、一つ、疑問をもった。
体言止めは、主語と述語がないので、使わないようにと言っているが、本質(本当の問題点)を理解していないと思う。
体言止めは、文章の末尾を体言(名詞、代名詞)で終わらせること。(広辞苑より)
この本のP167 改善例2(良い文章として挙げている)より引用
「・商品:品揃えをメーカー任せにしているために、商品のテイストに統一感がない」
この例を、体言止めにした場合:
・商品:品揃えをメーカー任せにしているため、商品のテイストの統一感なし
この体言止めで、悪いところは無い。
この本で、体言止めが良くない例の文章は、改善例1(P166)
・商品:商品テイストの統一感の欠如
しかし、これを文章にしたら、
・商品:商品テイストに統一感が欠けている
となる。
これでは、説明が不十分。文章にすれば良くなる訳ではない。
適切な文章(読んだら何を言いたいのかがわかる文章)にすることが大事で、体言止めは、良くないと考えるのは、筆者の思い込みである。
確かに、体言止めでは、何を言いたいのかがわからない文章が多いとは思いますが、文章でも、何を言いたいのかわからない場合もある。
逆に、体言止めの、直ぐに何を言いたいのかが、早く分かる方が、書き手と読み手の両方にとって、良いことと考えます。
体言止めの文章は、何を言いたいのかがわからないことが多い現象(現状)を言いたかったのではと思います。
読んだら何を言いたいのかがわかる表現になっていない点が、問題点であって、体言止めは現象である。
現象と問題点の区別がついていない。
この本以外で、ロジカル・シンキングを書いている筆者であるが、この点は、ロジカルでない。