GoogleとIBMの量子競争 日本突き放す知のコラボ
本社コメンテーター 村山恵一
2019/11/12 2:00
- 情報元
日本経済新聞 電子版
米航空宇宙局(NASA)、スパコンで有名な米オークリッジ国立研究所、欧州を代表するユーリヒ総合研究機構……。
2014年に研究室ごと引き抜いた米カリフォルニア大学の人材に加え、さまざまな組織の研究者が集まった。グーグル社内に閉じず、広範。量子オールスターズだ。
求心力の源はグーグルの資金力だけではない。個性的な才能を束ねて方向づけるリーダーシップもいる。
量子のような大テーマで、スピード感をもって突破口を開くための研究モデルのひな型を示した――。
西森氏はそうみる。オープンな体制で多様な人材を生かすところがポイントといえる。
グーグルと競う米IBM。ネイチャー論文に異議を唱え、対抗心を隠さないが、自らの研究所に閉じこもっていない点は同じだ。
量子コンピューターは誰がどんな用途で使うのか。
それを理解するのも研究の一部と考え、発展途上の量子コンピューターを公開し、世界で15万人の登録利用者を抱える。
プログラム開発者が交流するソーシャルメディア的なしくみがあり、IBMとともに利用法を探るコミュニティーには80近くの企業や大学が参加する。
社内で秘密裏に研究し、世の中に届けられる段階になってはじめて提供するかつてのIBMの流儀から様変わりだ。
コンピューター科学や物理、数学、化学、ソフト開発、デザインなど多分野の学生をインターンに誘う。
研究者のつながりを外へ外へと伸ばす。
量子コンピューターの実用化には長い時間を要し、暗号破りのリスクも指摘される。
一方で気候変動やエネルギー、ヘルスケアの難問を解く潜在力を秘めている。
限られた場所と人で研究していては大事な芽を見落としかねない。
日本は大丈夫だろうか。
量子コンピューター研究の歩みを振り返れば、目を引く日本発の成果があったが、ひょっとするとチャンスを逃したかもしれない。
東工大の西森氏らが土台となる理論「量子アニーリング」を提唱したのは1998年。
同じころNECは超電導による量子ビットを世界で初めて実現した。先頭を走る専門家同士がそばにいた。
もしもそこに対話が生まれ、知識が交じり合えば、世界をリードできるような研究の進展がみられた可能性があるが、双方が連絡をとり合うことはなかった。
時は流れ、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の案件で両者の連携が決まったのは昨年だ。
NECもIBMに似たコミュニティーづくりをめざすが、具体化はこれから。海外のダイナミックなうねりと差がある。
研究のあり方が刷新を迫られているのは量子の領域に限らない。
人工知能(AI)やアルゴリズムの時代だ。
テクノロジーを創出するにも、暴走を防ぎながら駆使するにも、いろいろな発想やアイデア、価値観の融合が欠かせない。
トランジスタや太陽電池、パソコンの原型の開発など技術史に残る結果を出した米国のベル研究所、ゼロックスのパロアルト研究所は多士済々が活気のもとだった。
さらにいま、組織の壁を越え、大きなスケールで人と人が化学反応を起こす研究環境をコーディネートできるところが優位に立つ。
日本の研究者は67万人と米国や中国の半分以下。研究費も両国の3分の1ほどだ。
問題はそうした資源が無駄なく生かされているかどうか。
論文数や特許出願の推移をたどると、日本の存在感はじわじわ縮んでいる。
よその国以上に知のコラボレーションが必要なはずが、そうはなっていない。
人材の流動性を高め、大学と企業をまたいで研究者が活躍できるようにと国が整えたクロスアポイントメント制度。
だが大学から企業に動いたのは17年度でわずか7人。
聞けば大学と企業の給与体系の違いなどイノベーションとかけ離れた事柄が障害だ。
専門性を携えて研究者が産官学をわたり歩く米国とは景色が異なる。
望みがないわけではない。
AIスタートアップのカラクリ(東京・中央)でデータサイエンティストをつとめる吉田雄紀氏。
機械学習を研究する東京大学の大学院生、内科の医師でもある。
量子コンピューターを使いこなすコンテストで優勝経験があり、能力を縦横に発揮している。
ひとつだけに打ち込めばときに行き詰まるが、「3足のわらじ」なら新たな問題意識が芽生え、知見が高まるという。
柔軟な研究スタイルを欲する若者は日本にも少なくない。うまく環境をつくれば組織間の人の流れも太くできる。
VALUENEX(バリューネックス)という情報解析ベンチャーがある。
大量の特許文書を分析し、企業がもつ研究の強み、弱みを浮き彫りにするサービスを手がける。
大手を中心に日本でも導入する会社が増えている。
自社の研究の実力を知れば、どんな企業と手を組むべきか、スタートアップを買収すべきか見極めやすい。
内向き色が濃い伝統的な研究体制から脱するひとつのきっかけになりうる。
グーグルやIBMの動きを遠巻きに眺めているだけでは、日本の研究力が細るばかりだ。











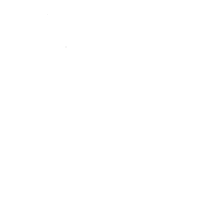

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます