デフレ崖っぷちの韓国、文在寅がハマる「財閥改革」の罠
田中秀臣(上武大学ビジネス情報学部教授)
韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は対外・対内的に厳しい環境の中での船出を強いられている。
対外政策的には、さっそく大統領就任への「祝砲」ともいえる北朝鮮の弾道ミサイルの発射が待っていた。
核開発・弾道ミサイル問題で緊張する北朝鮮情勢をめぐっての、近隣諸国との調整がほぼ待ったなしで待ち構えている。
今回の「新型」弾道ミサイルの発射をめぐっての対応を含めて、内外で文政権の姿勢を問う声は大きくなっていくだろう。
日本とはさっそく安倍晋三首相との電話会談を行い、そこで日本と韓国の慰安婦問題をめぐる認識の違いが早くも明らかになっている。
「慰安婦問題」と書いたが、現状で「問題」化させているのは韓国側であることは言を俟(ま)たない。
経済政策的には、朴槿恵(パク・クネ)前政権が倒れた要因の一つともいえる、若年層を中心にした雇用の悪化をどうするのか、という課題がある。
さらに雇用悪化が長期的に継続したことにより、社会の階層化・分断化が拡大している事実も忘れてはいけない。
韓国の若年失業率(15歳から29歳までの失業率)は11%を超えていて、最近は悪化が続く。
全体の失業率は直近では4・2%であり、韓国の完全失業率が2%台後半と考えられるので、高め推移の状態であることはかわらない。
韓国経済のインフレ目標は消費者物価指数で前年比2%であるが、インフレ率は前年同月比では1・9%(総合)と、目標を若干下回るだけで一見すると良好に思える。
だが、この点がくせ者であることはあとで再び考える。
文政権の経済政策は、基本的に雇用の改善を大きく力点を置くものになっている。
もちろん、政権発足まもないのでその実体は不明だ。
だが、新しい雇用を公共部門で81万人、民間部門では50万人を生み出す、さらに最低賃金も引き上げるという文政権の公約は、主に財政政策拡大と規制緩和を中心にしたものになりそうだ。
公共部門で従事している非正規雇用の人たちを正規雇用に転換していくことで、雇用創出と同時に正規と非正規の経済格差の解消も狙っているという。
これはもちろん賃金など待遇面での政府支出が増加することになるので、文政権の公約では、前年比7%増の政府支出を計画しているという。
韓国経済は完全雇用ではないので、このような財政支出は効果があるだろう。
ただし完全雇用が達成された後で、膨れ上がった政府部門をどのように修正していくかは大きな問題になるだろう。
だが、その心配はまずは現状の雇用悪化への対処がすんでからの話ではある。
増税の選択肢は限られたものになるだろう。
政府の資金調達は国債発行を中心にしたものになる。
政府債務と国内総生産(GDP)比の累増を懸念する声もあるが、完全雇用に到達していない経済の前では、そのような懸念は事態をさらに悪化させるだけでしかない。
不況のときには、財政政策の拡大は必要である。
ただし文政権の財政政策、というよりも経済政策の枠組みには大きな問題がある。
それは簡単にいうと、「韓国版アベノミクス」の不在、要するにリフレ政策の不在だ。
リフレ政策というのは、現在日本が採用しているデフレから脱却して、低インフレ状態を維持することで経済を安定化させる政策の総称である。
第2次安倍政権が発足したときの公約として、2013年春に日本銀行が採用したインフレ目標2%と、それに伴う超金融緩和政策が該当する。
韓国でもインフレ目標が採用されている。
対前年比で消費者物価指数が2%というのが目標値であることは先に述べた。
この目標値は、15年の終わりに、従来の2・5%から3・5%の目標域から引き下げて設定されたもので、現状では18年度末までこのままである。
韓国の金融政策は、政策金利の操作によって行われている。
具体的には、政策金利である7日物レポ金利を過去最低の1・25%に引き下げていて、それを昨年6月から継続している。その意味では金融緩和政策のスタンスが続く。
だが、韓国の経済状況をみると、最近こそ上向きになったという観測はあるものの、依然完全雇用には遠い。
さらに財政政策を支えるために、より緩和基調の金融政策が必要だろう。
だが、その面で文政権関係者の発言を聴くことはない。
どの国でも金融政策と財政政策の協調が必要であろう。
特に韓国のように、最近ではやや持ち直している物価水準でも、実体では高い失業と極めて低い物価水準が同居する「デフレ経済」には、金融政策の大胆な転換が必要条件である。
日本でも長期停滞を、現在の文政権と同様に財政政策を中心にして解消しようという動きが10数年続いた。
だが、その結果は深刻な危機の回避(1997年の金融危機など)には一定の成功をみせたものの、デフレ経済のままであり、むしろ非正規雇用の増加など雇用状況は一貫して停滞した。
雇用の回復の本格化がみられたのは、日本がリフレ政策を採用しだした13年以降から現在までである。
もちろんさらに一段の回復をする余地はあるが、金融政策の大きな転換がなければこのような雇用回復は実現できなかったろう。
文政権の財政政策主導で、なおかつ現状の微温的な金融政策では、本格的な雇用回復とその安定化は難しいだろう。
具体的には、韓国銀行はインフレ目標を3-4%の目標域に引き上げ、同時にマネタリーベース拡大を中心にした超金融緩和政策に転換すべきだろう。
そのとき政府の財政政策の拡大は、より効率的なものになる。
つまり毎年いたずらに政府支出の拡大を目標化することなく、その雇用増加の恩恵をうけることができるはずだ。
リフレ政策のようなインフレによる高圧経済が持続すれば、
非正規雇用の減少が民間部門中心にやがて起こるだろうし、
また現在の安倍政権がそうであるように最低賃金引き上げもスムーズに転換できるだろう。
だが、実際には金融政策の大きな転換の意識は、文政権にはない。
むしろ民間部門を刺激する政策として、財閥改革などの構造改革を主眼に考えているようだ。
だが、この連載でもたびたび指摘しているが、そのような構造改革はデフレ経済の解決には結びつかない。
韓国の歴代政権が、超金融緩和政策に慎重な理由として、ウォン安による海外への資金流出を懸念する声がしばしばきかれる。
しかし超金融緩和政策は、実体経済の改善を目指すものだ。
さらに無制限ではなく、目標値を設定しての緩和である。
日本でもしばしば聞かれる「超金融緩和するとハイパーインフレになる」というトンデモ経済論とあまりかわらない。
私見では、リフレ政策採用による韓国の急激な資金流出の可能性は低いと思うが、もし「保険」をさらに積み重ねたいのならば、日本など外貨資金が潤沢な国々との通貨スワップ協定も重要な選択肢だろう。
ただし、日本とは現状では慰安婦問題によりこの協議は中止している。
通貨スワップ協定は、いわば「事故」が起きたときの保険のようなものなので、事故が起きない限り必要にはならないものだ。
この点の理解があまりないため、「日韓通貨スワップ協定がないと韓国経済が破綻する」という論を主張する人たちがいるが、それは単なる誤解である。
ただし保険はあるにこしたことがない。
特にリフレ政策を新たに採用するときには、市場の不安を軽減させるためには、日韓通貨スワップ協定は相対的に重要性を増すだろう。
その意味では、慰安婦問題を再燃させる政策を文政権がとるのは愚かなだけであろう。もっともこの点は、日本側からすれば相手の出方を待っていればいいだけである。
ただし、そもそも文政権がリフレ政策を採用する可能性はいまのところないに等しい。
その意味では、韓国経済の長期停滞、特に雇用問題が本格的に解消する可能性は低い。











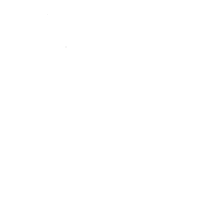

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます