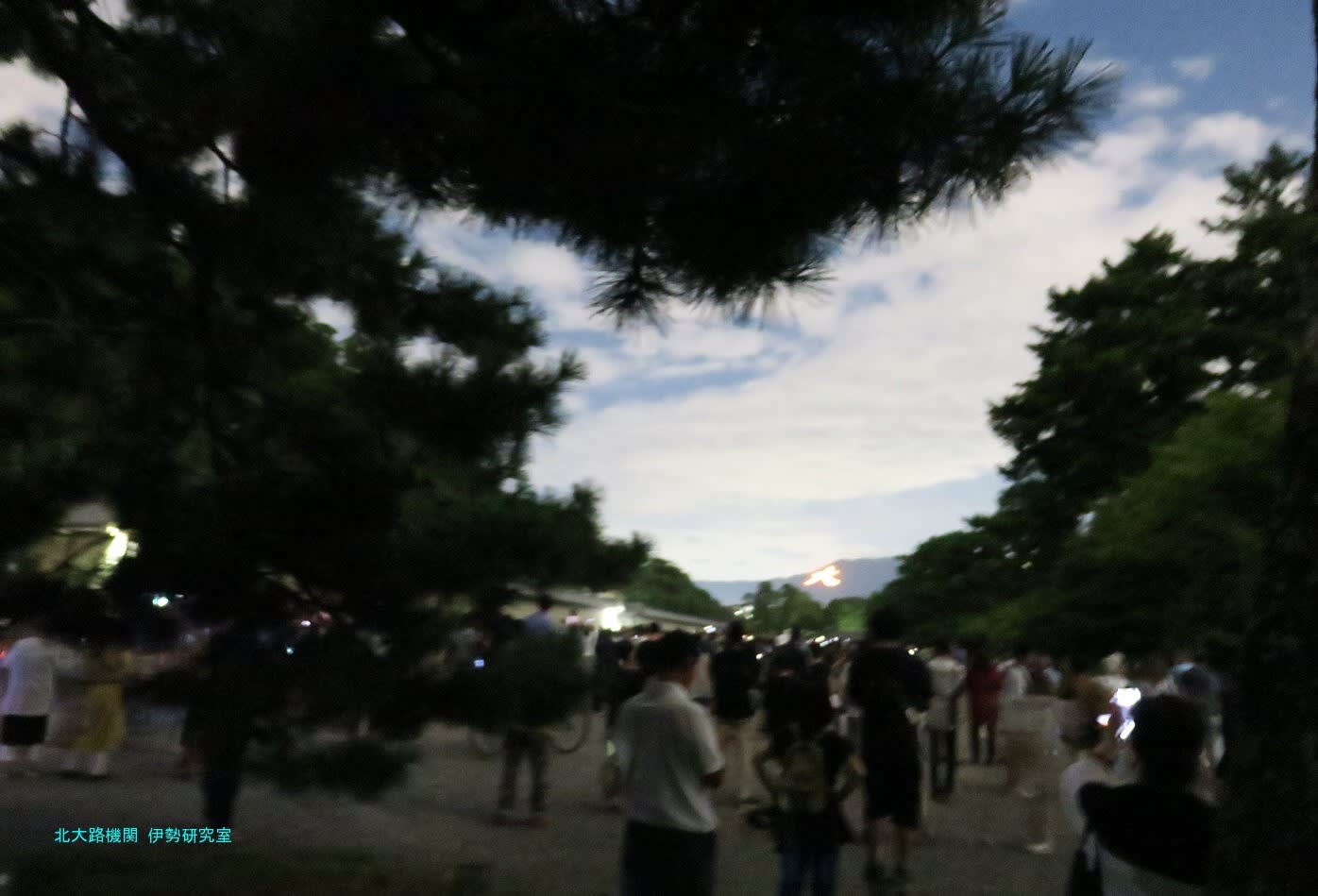■gooブログ時代
葵祭の写真と共に雑談を。

AIが危機をもたらす、スマートフォンが負担を増やす、こう思うのは昨今のAIの描画能力の高まりと、そしてスマートフォンの制裁だけれどもデータ容量の大きな画像データや動画データです。これ、個人がアップロードするデータ量の増え方が急加速している。

OCNブログ時代、北大路機関のデータ容量は30MBまで、と言うと驚かれるでしょうか、おどろかれるでしょうね、30MBなんて要領はいまのRAW画像だと数枚でもう一杯になってしまう、そもそもSDカードでも最近は30MBなんて容量は見ない。

300MBに増えたのは数年後でしたか、それでも結局データ容量を増やすために有料プランに移行したのが、2009年だったように記憶します、あのころはフォトアルバムサービスがあって、行事の写真ファイルをサイドバーに並べていました。

OCNブログの廃止とgooへの移行のさいにフォトアルバムは移行できないというやむを得ない理由で消えてしまいましたが、東北方面隊記念行事が一番上にあったフォトアルバムの北大路機関画面構成、覚えておられるのはかなり古い読者の方でしょう。

TwitterというかXは、いま動画とあと写真を最大4枚までアップロードできますが、iPhoneで撮影した高画質の写真は一枚6MBくらいのものがありますから四枚貼れば24MB、最初のOCNブログの時代ならば、もう大半が四枚で埋まる。

AIの特に生成系AIによる描画、アニメーションキャラクターの描画などは一瞬で、いうほど項目指定は簡単では無いようで慣れるまでは数時間かかるそうですが、慣れてしまうと手書きより遙かに描画が早い、短時間でたくさん作成できるのです、おどろくほどに。

無料でデータをかなりの容量、アップロードすることができまして、TwitterといいますかXについては一定以上経過したデータを自動消去するような機能があるといいますが、YOUTUBE等を含めるとかつてとは考えられないほどのデータが行き交う。

HDの容量、というよりも北大路機関創設当時のPCがHDD容量で20GBしかなく、いまはカメラのSDカードが256GBありまして、1TBがパソコンのほぼ標準的な容量でHD容量という単語さえ死語となりストレージ容量とよばれる時代ですが。

AIについては、基本的に様々な分野を自動化するため、省力化が逆に雇用を奪う、こう危惧されていた一方、それよりもこれまで描画をしなかった方々が大量のイラストなどを投稿する時代となり、これも様々な負荷を与えることとなるのではないかな、と。

リソースは有限ではなく拡張されているというのは、PCのHD容量というかストレージ容量をみていますと納得します、いや、正確にはストレージ容量はHDDからSSDへの転換で速度重視により容量はたしかに一時的に低下はしていますけれども。

写真と云いますか、個人が映像や画像を投稿する手段は増えていますが、増え方がどのくらい急なのか、スマートフォンの普及で誰もが高画質の写真を、生成AIの影響で誰もが秀逸なイラストを大量に投稿できる時代が定着して既に数年を経ているのですが。

既に掲載した写真をどのようにWeb上に残すかがしくはくしている一方、大量の画像データが行き交う時代に、負担というものはどうなるのか、Weblogを19年維持している身の上からしますと19年後の2044年を考えてしまうのですよね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
葵祭の写真と共に雑談を。

AIが危機をもたらす、スマートフォンが負担を増やす、こう思うのは昨今のAIの描画能力の高まりと、そしてスマートフォンの制裁だけれどもデータ容量の大きな画像データや動画データです。これ、個人がアップロードするデータ量の増え方が急加速している。

OCNブログ時代、北大路機関のデータ容量は30MBまで、と言うと驚かれるでしょうか、おどろかれるでしょうね、30MBなんて要領はいまのRAW画像だと数枚でもう一杯になってしまう、そもそもSDカードでも最近は30MBなんて容量は見ない。

300MBに増えたのは数年後でしたか、それでも結局データ容量を増やすために有料プランに移行したのが、2009年だったように記憶します、あのころはフォトアルバムサービスがあって、行事の写真ファイルをサイドバーに並べていました。

OCNブログの廃止とgooへの移行のさいにフォトアルバムは移行できないというやむを得ない理由で消えてしまいましたが、東北方面隊記念行事が一番上にあったフォトアルバムの北大路機関画面構成、覚えておられるのはかなり古い読者の方でしょう。

TwitterというかXは、いま動画とあと写真を最大4枚までアップロードできますが、iPhoneで撮影した高画質の写真は一枚6MBくらいのものがありますから四枚貼れば24MB、最初のOCNブログの時代ならば、もう大半が四枚で埋まる。

AIの特に生成系AIによる描画、アニメーションキャラクターの描画などは一瞬で、いうほど項目指定は簡単では無いようで慣れるまでは数時間かかるそうですが、慣れてしまうと手書きより遙かに描画が早い、短時間でたくさん作成できるのです、おどろくほどに。

無料でデータをかなりの容量、アップロードすることができまして、TwitterといいますかXについては一定以上経過したデータを自動消去するような機能があるといいますが、YOUTUBE等を含めるとかつてとは考えられないほどのデータが行き交う。

HDの容量、というよりも北大路機関創設当時のPCがHDD容量で20GBしかなく、いまはカメラのSDカードが256GBありまして、1TBがパソコンのほぼ標準的な容量でHD容量という単語さえ死語となりストレージ容量とよばれる時代ですが。

AIについては、基本的に様々な分野を自動化するため、省力化が逆に雇用を奪う、こう危惧されていた一方、それよりもこれまで描画をしなかった方々が大量のイラストなどを投稿する時代となり、これも様々な負荷を与えることとなるのではないかな、と。

リソースは有限ではなく拡張されているというのは、PCのHD容量というかストレージ容量をみていますと納得します、いや、正確にはストレージ容量はHDDからSSDへの転換で速度重視により容量はたしかに一時的に低下はしていますけれども。

写真と云いますか、個人が映像や画像を投稿する手段は増えていますが、増え方がどのくらい急なのか、スマートフォンの普及で誰もが高画質の写真を、生成AIの影響で誰もが秀逸なイラストを大量に投稿できる時代が定着して既に数年を経ているのですが。

既に掲載した写真をどのようにWeb上に残すかがしくはくしている一方、大量の画像データが行き交う時代に、負担というものはどうなるのか、Weblogを19年維持している身の上からしますと19年後の2044年を考えてしまうのですよね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)