・久しぶりに高橋さんと2人で岩魚沢の倒木上実生の生存調査。去年までは週2回くらいのペースで来ていたのだが・・・。それにしても、エゾハルゼミであろうか、実ににぎやかである。本日は、既に親子解析をしているトドマツに加えて、既にサンプルを取り、ラベルをつけているエゾマツ実生の生存もあわせて調査する。積雪前の11月に生存を調べていたのだが、積雪-雪解けの期間にどれだけ消失しているかが今回の興味の対象である。

・午前中はすいすいと進み、快調なペース。存外、一冬越えたことで死亡したものが少ないのに驚く。もう少し雪腐れ病で消失するかと思ったのだが、それらしい状態の実生はあまり見当たらない。むしろ、樹皮が滑り落ちることによって、実生が一緒に滑落して消失するのが多い。どちらかというと、冬よりも夏の乾燥が問題になりそうだ、ということで高橋さんとお話する。

・午後からは実生数が少ない倒木の調査にかかる。これが楽かとおもいきや、実は倒木を探すのからして大変。実生が多い倒木は何となく記憶が残っているのだが、実生が1本しか乗っていないような倒木だと、そもそもの印象が薄い。岩魚沢の場合にはササ丈もかなり高い上に大型草本もかなり繁茂している。結局、2本の実生だけはどうしても発見できず・・・。もう一度、倒木IDなどの確認が必要である。4時過ぎまでかかってようやく終了。

・クマイザサの開花が認められる。同所的に紫色と黄色のタイプが混在している。クローンが違うのか!?不思議!と、さらに鳥の巣と卵も発見。写真だけ撮影させてもらって、そっとしておく。

・帰り道に2人でQooを飲む。今日は、いい汗かいた。この一杯はビールよりもうまい!

・午前中はすいすいと進み、快調なペース。存外、一冬越えたことで死亡したものが少ないのに驚く。もう少し雪腐れ病で消失するかと思ったのだが、それらしい状態の実生はあまり見当たらない。むしろ、樹皮が滑り落ちることによって、実生が一緒に滑落して消失するのが多い。どちらかというと、冬よりも夏の乾燥が問題になりそうだ、ということで高橋さんとお話する。

・午後からは実生数が少ない倒木の調査にかかる。これが楽かとおもいきや、実は倒木を探すのからして大変。実生が多い倒木は何となく記憶が残っているのだが、実生が1本しか乗っていないような倒木だと、そもそもの印象が薄い。岩魚沢の場合にはササ丈もかなり高い上に大型草本もかなり繁茂している。結局、2本の実生だけはどうしても発見できず・・・。もう一度、倒木IDなどの確認が必要である。4時過ぎまでかかってようやく終了。

・クマイザサの開花が認められる。同所的に紫色と黄色のタイプが混在している。クローンが違うのか!?不思議!と、さらに鳥の巣と卵も発見。写真だけ撮影させてもらって、そっとしておく。

・帰り道に2人でQooを飲む。今日は、いい汗かいた。この一杯はビールよりもうまい!












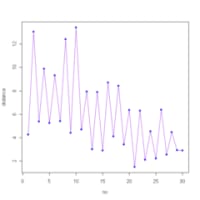







Barkの脱落による死亡、これは結構馬鹿にならないという印象を持っています。Harmon and Franklin (1989) は、「倒木更新した個体は必ずBarkと一緒に落とされるから、倒木は結局更新立地にはならない」とすら言っています。
ただ、個人的な感覚では、日本の方が倒木の分解速度が速いので、Barkを持ったまま倒木がつぶれ、更新がうまくいくのですが、そのうちの何割かが、Bark脱落で死亡する、という感じだと思います。Bark脱落による枯死率なんかもそのうち調査したいですね。