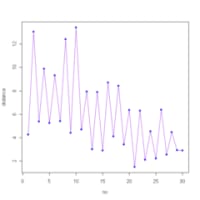・ようやく雪が落ち着いたので,雪かき作業から解放された.旭川空港へ.丘の街美瑛あたりにさしかかると,いい感じで晴れてきた.文句のつけようがない風景である.

・東京にてヤチダモとニレの新プライマーの結果を見る.ヤチダモについては1つのプライマーはまずまずだが,後はイマイチだ.ニレについても1つはOKだが,そもそも青で蛍光した以外のプライマーが増えていない.どうもU19を使うとうまく増えないのだが,どうしてだろうか・・・(RさんがPCRすると増えたりするんだよねえ,これが・・・).それにしても,開発した中で使えるプライマーの確率が低い.やはりプライマー設計に問題がある気がするのだが,それともやはり単に実験の”腕”の問題だろうか・・・.
・昨日の午後10時前に,気合の投稿クリックをした焼松峠論文について,その後すぐに編集部から受け取った旨のメールが届いた.こんな遅くまで仕事をされているとは,まったく,ご苦労さまです.などと思っていたら,本日付けで正式受理の知らせが届いた.このスピードは尋常ではない.それにしても,今回の論文がこうして無事に受理されたのは,編集委員のご尽力によるといっていいだろう.最初の投稿時の1人の審査者からのリジェクト査定にもかかわらず,あれこれと手を尽くしていただくなど,ご配慮いただいたのが,今から思えば非常に効いていると思える.
・それにしても,一つの論文を受理させるのは大変なことだと,改めて勉強になった(お世話になった皆さん,ありがとうございました!).学術的なことはともかく,実用的には,重要な論文になるはずである.ところで,当方にとっては,これで投稿中の論文がなくなってしまった.投稿中のものがあると,審査結果が届くたびにどきどきしながら結果を見るという過程があったり,査読結果に対して闘いを挑んだりするといったことがあるわけだが,そうした可能性がなくなってしまうと,それはそれでさびしいものだ.現在進行形の3つの論文を早いとこ投稿して,”どきどき感”を維持したいところである.
・12月22日に東京で行うゼミのタイトルを考える.今回は倒木上トドマツ実生の親子解析に関する結果を発表しようと思っているわけだが,少し楽しげなタイトルにしたいと思いつつ,今のところ考えたのは,
「倒木上で繰り広げられる散布と定着をめぐる物語
-”逃げる”トドマツ,浮上する新たな仮説-」
といったところだ(当方のセンスのなさが露呈している気もするが・・・).ついでに,提出する仮説の名前も考える.逃避仮説の中でも個体特異的なものについては,「隣の芝生」仮説とでも呼ぶか・・・.質の悪い種子が近くに散布される方は「低質種子近傍散布仮説」とでも呼んでみるか,などと妄想の世界をさまよう.
・こういうセンスって,どうやって磨かれるものなんだろうか.やっぱりドラマの脚本とか無理だろうねえ,当方には.まあ,頼まれることもないわけなんだけど・・・.夕刻,6時過ぎから,富良野と西東京の両K先生と飲みつつ,これらの仮説に関する話を聞いてもらう.「本当にそうかどうかはよく分からないなあ」と言われつつ,それでもいくつか重要な指摘を頂く.「妥当性はともかく,面白いじゃない」,といった評価に気をよくしつつ,やはり他人を納得させるためには,周辺の証拠固めが大事だと感じたりして・・・.
・これはむろん,論文執筆でも同じことが言えるわけだ.そういう意味では,投稿者は,同時に,自分の主張を守る”弁護士”の役もしないといかんわけである.弁護士たるからには,分野横断的な証拠固めが重要となってくるわけで,そこにこそ,自由な発想と思い切ったアイデアを盛り込む必要がある.これが考察をアトラクティブにするコツ,なのかもしれんなあ・・・.

・東京にてヤチダモとニレの新プライマーの結果を見る.ヤチダモについては1つのプライマーはまずまずだが,後はイマイチだ.ニレについても1つはOKだが,そもそも青で蛍光した以外のプライマーが増えていない.どうもU19を使うとうまく増えないのだが,どうしてだろうか・・・(RさんがPCRすると増えたりするんだよねえ,これが・・・).それにしても,開発した中で使えるプライマーの確率が低い.やはりプライマー設計に問題がある気がするのだが,それともやはり単に実験の”腕”の問題だろうか・・・.
・昨日の午後10時前に,気合の投稿クリックをした焼松峠論文について,その後すぐに編集部から受け取った旨のメールが届いた.こんな遅くまで仕事をされているとは,まったく,ご苦労さまです.などと思っていたら,本日付けで正式受理の知らせが届いた.このスピードは尋常ではない.それにしても,今回の論文がこうして無事に受理されたのは,編集委員のご尽力によるといっていいだろう.最初の投稿時の1人の審査者からのリジェクト査定にもかかわらず,あれこれと手を尽くしていただくなど,ご配慮いただいたのが,今から思えば非常に効いていると思える.
・それにしても,一つの論文を受理させるのは大変なことだと,改めて勉強になった(お世話になった皆さん,ありがとうございました!).学術的なことはともかく,実用的には,重要な論文になるはずである.ところで,当方にとっては,これで投稿中の論文がなくなってしまった.投稿中のものがあると,審査結果が届くたびにどきどきしながら結果を見るという過程があったり,査読結果に対して闘いを挑んだりするといったことがあるわけだが,そうした可能性がなくなってしまうと,それはそれでさびしいものだ.現在進行形の3つの論文を早いとこ投稿して,”どきどき感”を維持したいところである.
・12月22日に東京で行うゼミのタイトルを考える.今回は倒木上トドマツ実生の親子解析に関する結果を発表しようと思っているわけだが,少し楽しげなタイトルにしたいと思いつつ,今のところ考えたのは,
「倒木上で繰り広げられる散布と定着をめぐる物語
-”逃げる”トドマツ,浮上する新たな仮説-」
といったところだ(当方のセンスのなさが露呈している気もするが・・・).ついでに,提出する仮説の名前も考える.逃避仮説の中でも個体特異的なものについては,「隣の芝生」仮説とでも呼ぶか・・・.質の悪い種子が近くに散布される方は「低質種子近傍散布仮説」とでも呼んでみるか,などと妄想の世界をさまよう.
・こういうセンスって,どうやって磨かれるものなんだろうか.やっぱりドラマの脚本とか無理だろうねえ,当方には.まあ,頼まれることもないわけなんだけど・・・.夕刻,6時過ぎから,富良野と西東京の両K先生と飲みつつ,これらの仮説に関する話を聞いてもらう.「本当にそうかどうかはよく分からないなあ」と言われつつ,それでもいくつか重要な指摘を頂く.「妥当性はともかく,面白いじゃない」,といった評価に気をよくしつつ,やはり他人を納得させるためには,周辺の証拠固めが大事だと感じたりして・・・.
・これはむろん,論文執筆でも同じことが言えるわけだ.そういう意味では,投稿者は,同時に,自分の主張を守る”弁護士”の役もしないといかんわけである.弁護士たるからには,分野横断的な証拠固めが重要となってくるわけで,そこにこそ,自由な発想と思い切ったアイデアを盛り込む必要がある.これが考察をアトラクティブにするコツ,なのかもしれんなあ・・・.