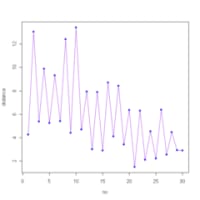・午前中は珍しく予定がなく,のんびりと起きた。朝食後、フライブルグを散策。一人でひたすら路地へ路地へと入り込んでいく。方向音痴のくせに,知らない街を歩くのは大好きだ。相変わらず日本人率はほとんどゼロに近い。それにしても,ドイツ語だと簡単な言葉が分からないので,各種案内が全く意味が取れない。少しは勉強してから来るべきだった。市場付近で迷っていると,不思議なことにHekkiに遭遇。駅の行き先を教えてもらう。

・2時に待ち合わせていた,フライブルグ大学のSpiecker教授の車でパーマネントプロットへ。黒い森の小さな農家にとって,“生きるため”に択伐方式は必要不可欠なシステムだったことを聞かされる。初日と同じ内容であるが,小さな農家にとっての収入源確保という経済的な目的で,このシステムが自然発生的に出来上がっていたことは、改めて当方の中では新鮮であった。

・さすがに3度目になると,森自体を見る目はかなり養われてきたようだ。ここでは樹冠を形成する高さは30m前後と富良野とあまり変わらない。林道密度は50m/haとこれまた同様である。しかし,後継樹のストックは豊富である(というか,今まででも一番多いかも・・・)。森林は見事なぐらい複雑な階層構造をしており,持続性が保証されていることが一目で分かる。この付近ではヨーロッパブナを欠くが,意図的に伐採して,Abiesとトウヒの2種の世界で択伐施業を回している。ブナがあると耐陰性が強いので他を排除してしまうというのがその理由とのこと。

・教授によれば,極相林はむしろ一斉林に近い状態で,下層には後継樹を欠く構造になっており,ブナの比率が増えるという。実はほったらかしにしてしまうと,ブナ林にモミが混じるような林になるのであろう。Spiecker教授の言葉を借りれば,こうした複層林(異齢林)は人の手によって人為的に作られたものであるという言葉が印象に残った。自然保護の人たちは,この森をみて「この森は素晴らしい森だから,手をつけるのはやめるべきだ」というという話を聞いて,さもありなん,という感じである。
・個体の健全性や将来性を考える上で,樹冠長(樹高から枝下までの高さ)が大事な指標であるとされていたのが興味深かった。調査でも実際に測定をしているらしい。アイデアとしては,樹冠長が着葉量に高い相関があり,着葉量が成長と相関するという図式のようだ。着葉量を健全度の指標とする点は富良野と同じだが,定量的か,定性的か,という点が異なる。
・雑談的に、学生への指導についてのお話も伺う。教授の場合,まず50個(!)の研究テーマを用意して,その中から学生に選ばせて研究させるとのこと。こうしないと,学生が自ら考える力が育たないという考えであるが,論文の生産性は決して高くないというのが悩みのようである。大学当局から,最近,急に成果を求められるようになってきているという話を聞く。いずこも事情はよく似ているようである。

・2時に待ち合わせていた,フライブルグ大学のSpiecker教授の車でパーマネントプロットへ。黒い森の小さな農家にとって,“生きるため”に択伐方式は必要不可欠なシステムだったことを聞かされる。初日と同じ内容であるが,小さな農家にとっての収入源確保という経済的な目的で,このシステムが自然発生的に出来上がっていたことは、改めて当方の中では新鮮であった。

・さすがに3度目になると,森自体を見る目はかなり養われてきたようだ。ここでは樹冠を形成する高さは30m前後と富良野とあまり変わらない。林道密度は50m/haとこれまた同様である。しかし,後継樹のストックは豊富である(というか,今まででも一番多いかも・・・)。森林は見事なぐらい複雑な階層構造をしており,持続性が保証されていることが一目で分かる。この付近ではヨーロッパブナを欠くが,意図的に伐採して,Abiesとトウヒの2種の世界で択伐施業を回している。ブナがあると耐陰性が強いので他を排除してしまうというのがその理由とのこと。

・教授によれば,極相林はむしろ一斉林に近い状態で,下層には後継樹を欠く構造になっており,ブナの比率が増えるという。実はほったらかしにしてしまうと,ブナ林にモミが混じるような林になるのであろう。Spiecker教授の言葉を借りれば,こうした複層林(異齢林)は人の手によって人為的に作られたものであるという言葉が印象に残った。自然保護の人たちは,この森をみて「この森は素晴らしい森だから,手をつけるのはやめるべきだ」というという話を聞いて,さもありなん,という感じである。
・個体の健全性や将来性を考える上で,樹冠長(樹高から枝下までの高さ)が大事な指標であるとされていたのが興味深かった。調査でも実際に測定をしているらしい。アイデアとしては,樹冠長が着葉量に高い相関があり,着葉量が成長と相関するという図式のようだ。着葉量を健全度の指標とする点は富良野と同じだが,定量的か,定性的か,という点が異なる。
・雑談的に、学生への指導についてのお話も伺う。教授の場合,まず50個(!)の研究テーマを用意して,その中から学生に選ばせて研究させるとのこと。こうしないと,学生が自ら考える力が育たないという考えであるが,論文の生産性は決して高くないというのが悩みのようである。大学当局から,最近,急に成果を求められるようになってきているという話を聞く。いずこも事情はよく似ているようである。