学術会議会員の任命拒否は、行政手続きの是非を越えて「学問の自由」の解釈論議に発展しているので、学問の自由について勉強した。
学問の自由は憲法23条「学問の自由は、これを保障する」とされる権利で、一般的には
・学問研究の自由(真理探究が目的とされる学問・研究の自由で,、「思想良心の自由」の一部とされるため、内心にとどまる限り絶対的に保障される。)
・研究発表の自由(研究した内容を発表する自由で、「表現の自由」の一部とされ、一定の制限は受け得る。)が、保障レベルは高い。)
・教授の自由(大学における教授の自由で大学の自治も該当する。) とされているらしい。
これは世界で初めて「学問の自由」を憲法に規定したドイツのフランクフルト憲法(1849年)制定時の世相に警鐘を鳴らす概念であるが、世界各国の憲法に継承されて今や世界基準とされているらしい。
しかしながら一方で、憲法の「学問の自由」を広義に捉えて、大学のみならず初等中等教育機関の教育の自由にも拡大すべきとする学説もあるとされている。
さらに今回の論争に対して篠田英朗教授(東京外大総合国際学研究院)が、「憲法で保護されている学問とは、大学でお給料を貰っている人々の特権的地位を保証するものでなく、全ての国民の個人の尊厳を形成する精神活動を指している」と述べておられるよう更に広義に解釈して、憲法が保障する自由は特定の権利を指すものでは無く精神規定とする意見もあるらしい。
学問とは無縁の門外漢には「学問の自由」はさっぱり理解できなかったが、ある思想・主張を継承するために後任者を指名するような日本学術会議会員の選定方法は、異論を封じるもので学術会議自体が学問の自由を侵害する結果に陥っているものに思える。一般概念に従って任命拒否された人物を眺めると、「内心に留まる限り保証される学問研究の自由」の域を超えて、具体的に反基地闘争に参加する以上に主導的な立場に位置し、もはや学問とは言えない活動に注力しており、憲法に基づく保護を求めることには違和感を感じる。
自分が日本学術会議に求めるところは、例えばクローン技術・遺伝子研究の限界、高齢者社会では避けて通れぬ尊厳死是非等についての結論である。キリスト教国では絶対神の教義を忖度しての解決が期待できるが、絶対的な価値観を共有していない日本では、それら諸々を科学的・学術的に考察して答えを導き出さざるを得ないように思う。今回の騒動によって、時代遅れの軍用技術研究拒否という一部の狂信者に率いられた学術会議が若手研究者の研究を闇に葬った多くの例が明るみに出されたが、学術会議は枝葉に血道をあげることなく、日本人の根幹にかかわる命題を科学的・学術的に討議して欲しいと願うところである。



















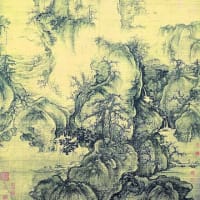
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます