

諸泉俊介講演「「家族」はどこへ向かうのか」~放送大学スペシャル講演
放送大学で内容もよく判らないまま偶然録画していたのだけど、これは凄く面白い一見の価値ある講義でした。偶然に感謝です。
講師は経済学者の諸泉俊介さん。佐賀大学所属、と経歴にあります。初めて知った方ですが、ユーモアがあって判りやすい話し方をされていました。
タイトルは「家族」ですが、内容としては「女性の在り方」としての「家族」というものでした。そして「女性の不満」というものを中心に話が進んでいくのが面白かったです。
それにしても。
私は経済学など全く知らないのでこの講義を聞いて初めて知りぎょっとなってしまったものがありました。
それは
「家族賃金の中の子供の養育費というものが今の賃金から削除されてしまっている」
ということです。
諸泉氏の講義の中では「かつては家族賃金の中で支給されていた養育費が個人賃金になってから宙に浮いてしまっている」という表現でした。
この説明はいきなり最後の重要な部分で本当は講義通りに順を追っていかないと判りにくいものかと思います。このブログで興味を持たれた方はどこかでこの講義を見て欲しいものです。
とりあえず自分なりに説明していきたいと思います。
女性は歴史の中で男性から差別をされる存在でありました。フランスで革命が起こり「自由・平等・博愛」が謳われてもそれは男性に関するものであって女性はその中に含まれてはいなかったのです。男性は家族の代表であり、女性はその庇護下に置かれる存在でしかない、というわけですね。
産業革命が起きてもやはり女性の権利が認められるわけではなかったのです。
ここで登場してくるのがジョン・スチュワート・ミルという哲学者・経済思想家なのですが、彼が提唱したのが「男女同権」だったのですが、その「同権」は男女がそれぞれの役割を持つ、という意味での同権なのですね。
ミルは女性も男性と同じように自由に社会に出て男性と同じように働くべき、というのですが、結婚した後は女性の役割として家庭内での女性の仕事=出産・育児・家事をするべきだと唱えたわけです。家庭内でも男女は同権であり、そのうえで女性は女性の仕事(出産・育児・家事)をすべきである。ここで女性が無理に外で働いても家族としての賃金は変わらないという法則が成り立つので、女性が結婚後外で働くのは無意味というわけです。
ただしその時の女性の家庭内の仕事には賃金は支払われないのですが、ミルはその点には言及せず、その後家庭内に入った女性の不平等不満は高まっていくことになります。
この「男女の役割分担」という考え方は今現在も特に日本では強く作用していて女性を苦しめていると思います。女性の中にもこの考え方を良しとして主張する人が結構いますね。政治家の中にもこの主義の方が散見できます。
この考え方、別に悪くはないんですよ。たぶんこれ有史以来自然と男女の在り方として続いているわけですよね。暗黙の了解的に契約されてきたのです。
それが「お金」というものが存在する社会では報酬としての賃金が支払われない家庭内の女性の地位が低くなってしまうわけですね。つまりこの時に家庭の主婦にも平等に賃金と権利が分け与えられたなら問題はなかったのかもしれません。だけどどういうわけか、人間というのはどうしても金を持ってくる方が偉くてもらう方は卑下される、という形になってしまうのですね。平等に分配する、ということができない動物なんです。
共産主義がどうしても理想論でしかないのも同じ理屈であると思います。
さて女性の立場がどう変わっていくか、続けます。
それが、昨日ちょうどその話を書いたばかりでちょっとした偶然に驚くのですが
結局「戦争が女性に権利を与え、解放していくのでした」ということだったのです。
つまり男性は戦争に行って不在となったがために警官や運転手や工員といった男性の仕事も女性がやらざるを得ません。しかも女性たちはその仕事をこなしていくわけですね。
ゆえに戦後、女性たちが男性の仕事をやれるのは当然になっていくわけです。
時代は変化していきます。
とはいえ女性はまだまだ結婚後は家庭に入るのが普通の社会です。
ところが家庭内の仕事は電化製品の普及や家事の商品化つまり家での洗濯でなくクリーニングに出す、食事はテイクアウトやレストランへ行く、などで家事が軽減され従って暇になった主婦がキッチンドランカーや浮気に走るといった現象が起き問題となる。そこでやはり女性も外での仕事に従事すべきだ、職業を持つというのは自然権だという話し合いが行われたわけです。これが1975年の国際婦人年での会議で言われたのです。
男女同権は進み、雇用機会均等法が制定施行されます。
ところがここに大きな落とし穴があったと諸泉氏は言われるのです。
それが上で書いた「かつて家族賃金として支払われていた子供の養育費が宙に浮いてしまっている」ということです。
「家族賃金」というのはかつて男性が外で働き女性は家庭で家事育児をする、のが当然の中で従って男性の給与には配偶者と子供の養育費も含まれる、という仕組みだったわけですね。
それゆえ、女性はそれがないために男性よりも賃金が低いという考え方があったわけです。どうせ女性は男性と結婚して家庭にはいるのだから男性にその分まで支払うのだから、というわけです。
ところが男女雇用均等法になれば配偶者のことまで心配する必要はなくなります。男女を雇用する会社としてもこの考え方はむしろ歓迎だったというわけです。社員の将来のことまで慮って雇用する義務はない、ただ男女平等に給与すればいいのです。
そこまでは良い、と諸泉氏は言います。
「問題なのはその時に「子供の養育費というものまで給与から外されてしまったことです。そのことは今問題になっている子供の貧困と無関係ではないのです」
愕然としました。
日々、ネットで色んな人の絶望的な愚痴、批判、疑問を読んできました。
以前に比べ、日本はどうしてこうも貧しくなったのか。
私たち(50代)の子供時代はまだ親たちがマイホームを買い、マイカーを買い、子供たちも2・3人いたものです。大学に行く子供たちにまで車を買ってあげたり上京して大学に行く子供には生活費やお小遣いまであげてたようにも記憶します。
それが今の若い世代はマイホームどころか自分の給料では結婚すらできないと嘆く男性が増え、女性たちは男女平等どころか非正規雇用でしか職を得られないという状況が続く。
それが男女平等の給与と見せかけた制度の中でいつの間にか差し引かれた養育費、ということが様々なことに影響していっているのでは、という疑問はどう釈明されるのでしょうか。
特に女性への差別的制度はますます悪化しているように思えます。
母子家庭の貧困は全く改善されないようです。食事も満足にできない子供たちの問題が根本的に解決されているように思えません。
男女平等、の名のもとに社会が悪化していく。これをどうすればいいのか。
諸泉氏はフランスのように「宙に浮いた養育費を女性の給与に入れてもいいのではないでしょうか」と提示されました。
問題は山済みで茫然とするばかりですが、少しずつ改革していくしかないものです。
まずは子供を守ることが一番です。食事と教育は絶対ではないですか。
急いで子供への養育費を考えないと本当に日本の社会は崩壊してしまいます。










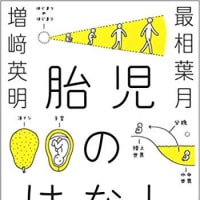



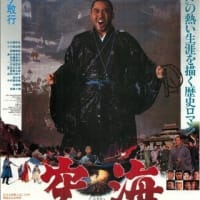

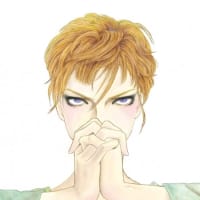

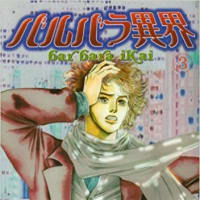
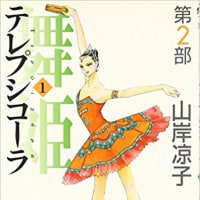
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます