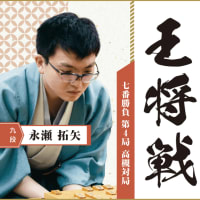1月17日、中国国家統計局は2024年のマクロ経済統計を発表した。それによると、2024年の実質GDP伸び率は5%だったといわれた。おそらく5%前後と発表されるだろうと事前に思っていたが、実際に5%と聞いてやはり驚きを隠せなかった。IMFなどの国際機関と欧米の投資銀行のアナリストたちの事前予測では、いずれも5%未満の成長だった。
同統計局が公表した同年1-9月期の経済成長率は第1四半期5.3%、第2四半期4.7%、第3四半期4.6%と下り坂を辿るものだった。しかし、第4四半期は5.4%に跳ね上がった。確かに、中国政府は暮れに一連の景気刺激策を発表した。12月の経済工作会議では、中立的な経済政策を「積極的な財政政策と適当な金融緩和」へと大きく舵が切られた。しかし、これらの政策パッケージのほとんどはまだ実施されておらず、2025年3月の全人代で予算が承認されてから、ようやく実施に移される。
したがって、どのようにして中国経済は第3四半期の4.6%から第4四半期5.4%に跳ね上がったのだろうか。マジシャンの仕業としか言いようがない。
そもそも経済統計はある一つの指標が突出して伸びることはなく、それ以外の部門の統計がそれをサポートしないといけない。経済統計は一つの連立方程式のようなもので一つの統計が変わると、ほかの統計も変わらないと可笑しいことになる。
中国のマクロ経済統計は1990年代、世界銀行の援助で国連が定めたSNA基準に基づいて作成されている。しかし、それ以降も中国経済統計の信ぴょう性について疑問を呈されている。有名な事例の一つは中国の電力消費量の伸び率と経済成長率と相関性が弱いと指摘されていた。一般的によほど省エネの技術が発明されなければ、電力消費量と経済成長率は同じ動きを示すはずである。
2023年死去した李克強前首相は現役のとき、国家統計局が発表する経済統計を信用せず、「鉄道貨物輸送量、電力消費量と銀行の融資残高」をみて経済の動きを判断していたといわれている。この三つの指標が「李克強指数」と命名されている。しかし、一国の首相が自国の経済統計を信用しないというのはやはり普通のことではない。
統計がどんなにポジティブな表現で経済を描写して順調に成長していないのは事実である。消費者物価指数(CPI)はゼロパーセント前後で推移しており、生産者価格指数(PPI)は依然マイナスで推移している。物価のマイナスの状態が続き、失業率が高止まりしている。この動きは経済学の理論(フィリップス曲線)に合致する。中国経済全般をみると、明らかにすでにデフレ状態になっていると判断される。
一方、トランプ政権2.0が発足された。これから中国に対する制裁が強化されるとみられている。習近平政権はトランプ政権に向き合わないといけないが、対抗するためのカードを持っていない。中国にとってアメリカは最重要な輸出市場であり、得意先である。これまでの対米政策で一番の失敗といえば、売られた喧嘩を間違って買ってしまったことだった。とくに王毅外相が主導して戦狼外交を展開していたのはまずかった。戦狼外交によって対米だけでなく、G7を中心とする先進国のほとんどとの関係を著しく悪化させてしまった。
中国国内にいるエコノミストの高善文氏とスタンフォード大学フェローの許成剛氏のいずれも中国経済の実際の成長率は公式統計の値を3ポイント引いたものであるとの推計を発表している。