5月16日に観察会をしました。
西武立川の駅に集まると小雨が降り始めました。仕方がないので、その中を歩き始めました。この辺りは高さ2 mくらいの柵がはられているので、小平のように身近な感じがありません。松中橋からは南側(右岸)を歩きました。この辺りは大きなコナラやクヌギの木があって、鬱蒼をした感じさえします。小平あたりの太さ30cm程度の林とは違い50-60cmほどもあるので、どっしりした印象がありました。また道路が細いせいか自動車が走らないので、閑静というのがふさわしい雰囲気でした。エゴノキは大体終わり、カマツカが比較的多くありましたが、花は終わっていました。

エゴノキの写真を撮る(小口)
歩いていたらクサイチゴが実っていて食べたらとても甘くておいしかったです。
私がうっかりカメラを忘れてきたので、今日は写真は諦めることにしましたが、記念撮影はした方がいいので、同じ機種(オリンパスのTough)を使っている長峰さんのを貸してもらいました。

そのあとで、長峰さんが以前「私のカメラではうまくピントが合わなくて」と言っていたのを思い出して、ピントを合わせるには、その花の位置に手を持っていってから離すとピントが合うことを伝えました。そして手元にあったカモガヤの花を接写して、モニターで拡大したらみなさん歓声を上げていました。

カモガヤ
牧田さんも同じ機種を使っていて、接写でも「テントウムシ・マーク」を選んだら、被写界深度が深くなることを力説していました。この通りは歩くのにとても気持ちがよく、大きなケヤキがあり、中には直径2 m近いものもありました。
ここは林は立派ですが、花はあまりなかったので、カモガヤを取り上げてイネ科の説明をしました。
「イネ科は区別が難しいので、観察会でもあまり取り上げませんが、これは特徴的なカモガヤです。イネ科は紡錘型の小穂がいろいろな形、大きさで着きますが、カモガヤは全体に丸っこい形になります。牧草なので、ウシが太るように改良されてみずみずしく消化率が良くなっています、さわってみると、滑らかで気持ちいいです」
「あ、ほんとだ」

カモガヤの説明をする(小口)
「カモガヤというのはこの丸っこい穂の形がカモの足みたいだと言うことだと思います。あ、そうだせっかく持ってきたから」
と言ってホワイトボードを取り出してカモの絵を描いて説明しました。

ホワイトボードに描いたカモガヤの説明
目立ったイネ科としてイヌガヤ、イヌムギ、イチゴツナギ、ムギクサなどを説明しました。


カモガヤ ムギクサ
天王橋を渡ってからは北川(左岸)を歩くことにしました。2年前に花マップをしていた頃、ここは私の担当だったのでよく歩きましたが、ここは木がやや少ないために明るくて、ここの柵にはさまざまなつる植物があります。センニンソウ、ヘクソカズラ、アオツヅラフジ、ボタンヅル、ヤブカラシ、オニドコロなどがありました。
「当たり前かもしれませんが、芽生えて上に伸びている時はどちらに葉をつけたかわかりませんが、柵に絡まってからは例外なく外側に葉をつけています。当然光合成に都合がいいように葉の向きを変えるわけです」
さらに進むとツタがありました。それで、またToughを借りて茎から触手のような吸盤を伸ばして柵の鉄棒に密着しているところを撮影してモニターで拡大したら、また歓声が上がりました。

ツタの吸盤
「なんだか動物みたいね」
「ヘクソカズラみたいに茎に巻きつくのをツル、こういうふうにくっつくのをツタと言うみたいです」
その後、スイカズラの蜜を舐めてみました。
「いい匂いだよね」
「鼻って女性の方がいいんじゃない?」
長峰さんがチガヤを見て「子供の頃、チューインガムだといって食べた」と言うので
「え、ほんと?飲み込んだの?」
「うん」
「なんだか、口の中がモサモサしそうだなあ」
などとたあいのない話に花が咲きました。
しばらく歩くと残堀川と玉川上水が交差するところに達しました。橋は3つあって違う名前がついていました。その一つは上宿橋と言いました。川と川がぶつかるわけだから同じ高さなら玉川上水の水は残堀川に流れてしまいます。それで川の下を潜ってサイホンの原理でまた戻すという離れ技をしたということです。そうは言っても、うまくいくかどうかどうして確かめたのでしょう。実験でもしたのかなあと素人話をしました。こういうことを調べている人に話を聞きたいものです。
「ところで、以前この辺りをよく歩いたんだけど、このくらいの季節の時にここにアオダイショウが日向ぼっこをしてたんですよ。そこに幼稚園さんたちが散歩に来たんだけど、最初に見つけた子が<ヘビがいた!>と言い、みんなが<ヘビだ、ヘビだ>と大騒ぎ。子供たちは私の前を通り過ぎて行きましたが、ヘビの話が後ろの子に伝えられて行って、最後の方になったら<ヘビが100匹いたんだって!>」(大笑い)
「話に尾ヒレがつくわけね」
クワの実が熟して、鳥が吐き出している場所がありました。
せっかく持ってきた実体顕微鏡を使っていなかったので、ムラサキツメクサの花を取り出して見てもらい、
「ボールのように丸い花という印象がありますが、一つ一つの花はエンドウと同じようにマメ科らしい花で、この中にエンドウ豆のような鞘と小さなマメが入っています」
という話をしました。

実体顕微鏡で見るためにムラサキツメクサの花をボードに並べる(小口)


ムラサキツメクサ
砂川の新家橋まできたので上水を見ると幅が広く水が滔々とながれ、その流れも早いようでした。自然に17世紀にこの大工事をしたことのすごさに話が行きました。
「さっきの上宿橋の工事もそうだけど、あれを17世紀の半ばにやったんだからすごいよね」
「玉川兄弟はそれで苗字をもらうんだよね」
「身分が上がるためには命をかけるに値することだったわけだ」
「途中でお金が足りなくなったんでしょう」
「でもそれだけ価値があったんだ」
「晩年は不遇だったらしいけど」
「そうなんだ」
「このあとで江戸の人口は百万になるんだけど、それを予測してこの大工事をしたと言うことだよね」
「どこかの政府と違って先を予測して危機管理をちゃんとしたんだ」(笑)

雨は途中で上がり、3キロほどを2時間ほどかけてゆっくり歩きました。
後で長峰さんから写真が送ってきました。
「雨を懸念しましたがたいした降りでもなく欅の大樹にも出会えた半日でした。西武立川から武蔵砂川区間は水の流れも一体となった素晴らしい区間ですね」
「携帯拡大鏡で見ると植物の内面、外面、営みまでオミトオシなんですね」
とありました。












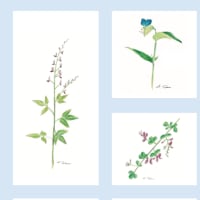
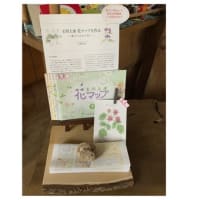






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます