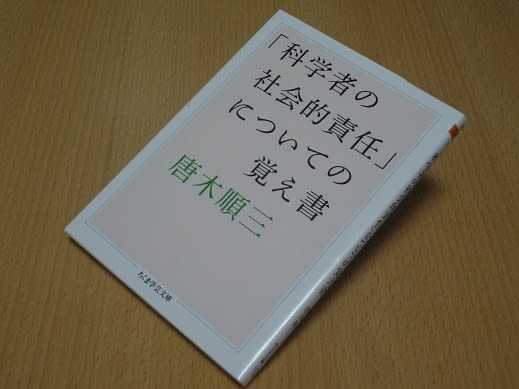
☆『「科学者の社会的責任」についての覚え書』(唐木順三・著、ちくま学芸文庫)☆
アインシュタインは晩年(広島・長崎の惨劇の後)「今度生まれ変わるときは科学者や教師ではなく、行商人かブリキ職人になりたい」と言い、無抵抗主義者のガンジーに傾倒していたという。それはとりもなおさず、ナチスの暴走に先んじるためとはいえ、自らの進言で原爆開発の端緒を開き、人類史上かってない惨劇を引き起こしたことに対する罪の意識によるものだった。原爆が完成し実験に成功したころにはナチスドイツはすでに崩壊し、原爆は無用の長物と化していた。日本の無条件降伏も想定内であった。それにもかかわらず2度にわたって原爆は投下された。アインシュタインは原爆開発の現場にいたわけではなかったが、その悔恨の深さが推察される。先の言葉は、科学の発展に内在する原罪への気づきの発露であった。
1955年アインシュタインは亡くなるわずか数日前に、核兵器廃絶を訴えたいわゆる「ラッセル・アインシュタイン宣言」に署名した。その2年後1957年に、その精神を引き継ぐものとして「パグウォッシュ会議」が開催された(ちなみに昨年2015年11月に長崎で第61回世界大会が開かれた)。しかし、著者の唐木順三はこの「パグウォッシュ会議」の「科学者の社会的責任」の声明に違和感を抱き、自らも「科学者の社会的責任」の考察をはじめた。唐木順三は日本文化史などの著作で知られ、たしか明治大学の教授を長く勤めていた。唐木の文章には受験生時代に問題文として接した記憶があり、名前も覚えていたが、著作を読むのは本書が初めてである。
唐木によれば「パグウォッシュ会議」では核兵器の使用に反対し平和を希求しているが、科学そのものが人類存続の危機を招いているという反省が示されていないという。科学そのものに罪があるわけではなく、科学者もまた研究は自由に行えるのであって、科学の用い方にこそ問題があるという、いまとなっては伝統的な捉え方に唐木は疑義をさしはさんだ。唐木は「知ること」と「用いること」とは分かちがたいものであって、「真・善・美」の「真」を「善・美」と調和させることを主張し、そこに「科学者の社会的責任」の所在を求めた。科学者の、科学に内在する原罪の認識欠如にこそ問題があると言い換えてもよいであろう。
かりに科学には罪がなく、科学を応用した技術には責任が求められるとしても、いまや科学と技術との線引きはますます曖昧になっている。しかしながら、そうであっても、いや、そうであるからこそ、科学や技術の進歩が人類の幸福につながるとする捉え方に無批判的であってはならないだろう。これからはますます科学者に対して、原罪意識の認識の有無が問題視されるようになると思われる。科学者の一人ひとりが、いまいちど自らの研究とこころの内を見つめ直してほしいものである。
唐木は「科学者の社会的責任」について、アインシュタイン、オットー・ハーン、ハイゼンベルク、朝永振一郎に(さらにノーベルにも)高い評価を与えている一方で、湯川秀樹には(思想的転向前の武谷三男にも)厳しい評価を下している。湯川の研究至上主義的な一面を断罪しているようである。朝永の高評価についてはあまり触れられていないのが残念だが、「科学者の社会的責任」の面からの湯川と朝永との対比は興味深い。

アインシュタインは晩年(広島・長崎の惨劇の後)「今度生まれ変わるときは科学者や教師ではなく、行商人かブリキ職人になりたい」と言い、無抵抗主義者のガンジーに傾倒していたという。それはとりもなおさず、ナチスの暴走に先んじるためとはいえ、自らの進言で原爆開発の端緒を開き、人類史上かってない惨劇を引き起こしたことに対する罪の意識によるものだった。原爆が完成し実験に成功したころにはナチスドイツはすでに崩壊し、原爆は無用の長物と化していた。日本の無条件降伏も想定内であった。それにもかかわらず2度にわたって原爆は投下された。アインシュタインは原爆開発の現場にいたわけではなかったが、その悔恨の深さが推察される。先の言葉は、科学の発展に内在する原罪への気づきの発露であった。
1955年アインシュタインは亡くなるわずか数日前に、核兵器廃絶を訴えたいわゆる「ラッセル・アインシュタイン宣言」に署名した。その2年後1957年に、その精神を引き継ぐものとして「パグウォッシュ会議」が開催された(ちなみに昨年2015年11月に長崎で第61回世界大会が開かれた)。しかし、著者の唐木順三はこの「パグウォッシュ会議」の「科学者の社会的責任」の声明に違和感を抱き、自らも「科学者の社会的責任」の考察をはじめた。唐木順三は日本文化史などの著作で知られ、たしか明治大学の教授を長く勤めていた。唐木の文章には受験生時代に問題文として接した記憶があり、名前も覚えていたが、著作を読むのは本書が初めてである。
唐木によれば「パグウォッシュ会議」では核兵器の使用に反対し平和を希求しているが、科学そのものが人類存続の危機を招いているという反省が示されていないという。科学そのものに罪があるわけではなく、科学者もまた研究は自由に行えるのであって、科学の用い方にこそ問題があるという、いまとなっては伝統的な捉え方に唐木は疑義をさしはさんだ。唐木は「知ること」と「用いること」とは分かちがたいものであって、「真・善・美」の「真」を「善・美」と調和させることを主張し、そこに「科学者の社会的責任」の所在を求めた。科学者の、科学に内在する原罪の認識欠如にこそ問題があると言い換えてもよいであろう。
かりに科学には罪がなく、科学を応用した技術には責任が求められるとしても、いまや科学と技術との線引きはますます曖昧になっている。しかしながら、そうであっても、いや、そうであるからこそ、科学や技術の進歩が人類の幸福につながるとする捉え方に無批判的であってはならないだろう。これからはますます科学者に対して、原罪意識の認識の有無が問題視されるようになると思われる。科学者の一人ひとりが、いまいちど自らの研究とこころの内を見つめ直してほしいものである。
唐木は「科学者の社会的責任」について、アインシュタイン、オットー・ハーン、ハイゼンベルク、朝永振一郎に(さらにノーベルにも)高い評価を与えている一方で、湯川秀樹には(思想的転向前の武谷三男にも)厳しい評価を下している。湯川の研究至上主義的な一面を断罪しているようである。朝永の高評価についてはあまり触れられていないのが残念だが、「科学者の社会的責任」の面からの湯川と朝永との対比は興味深い。

























