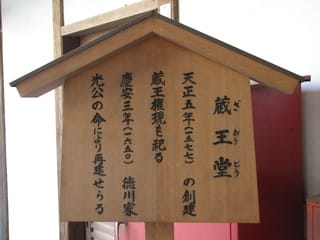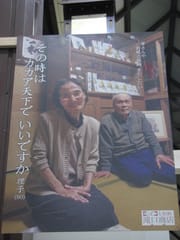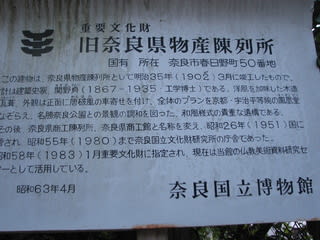浄瑠璃寺から戻って12時。さてどこへ行こう。
初日に行けなかった東大寺か。
バス乗り放題のチケットがあるので、近鉄奈良駅から東大寺南大門までバス。
歩ける距離だと思っていたが、実際に乗ったところ、1キロくらいはあるようだった。
こういう距離が積もり積もると結構コタエるんですよ。バスに乗って良かった。

バスから降りると鹿のニオイがプンと来る。もっとはっきり言うと鹿のフンのニオイが。
南大門の前は激混み。鹿も人もいっぱいいる。


大仏殿を目の前にしながらそれへ行かずに、まずわたしは右へ折れて二月堂・三月堂に向かう。
「お水取り」の儀式を行うのが二月堂。大仏殿からはだいぶ離れている。


ぎりぎりもみじ。

こんな幟がある。この並びだと、鹿せんぺいも当然メニューのうちですよね?
比較的緩やかな階段を登り切ると、左に二月堂、右に三月堂の建物が表れる。


ここの眺望の開け方が好きだな。
二月堂は、日本には珍しいような空間構成である気がしている。手前の空間と高低差の使い方がね。雄大。
ここでお水取りの儀式がある。お水取りの儀式のためにこういう設計になったのかな。
それとも建物を作ってから、その建物の劇的効果を利用して儀式がああいう形に定着したのかな。
後者だと思うんだけどね。
だが高低差に恐れをなして、中には入りませんでした(^_^;)。
三月堂はこじんまりした建物。浄瑠璃寺でも思ったけど、ラインがきれいですよねえ。
三月堂の方には、仏像が多数収蔵されている。入って見ましょう。
だが、入場料を払って仏像の前に立った途端、衝撃の出来事が!
……修学旅行生が入って来たんです(泣)。
さすがにねえ。100人も200人もいそうな学生の襲来には耐えられない。
そもそもその人数、建物内にホントに入るの?という感じの狭さだし。
ほとんど仏像を見ないで、早々に退散しました。
せめてあと5分早めに姿を表してくれたら、時間をずらすとか何とか対応出来たのに……。
あとから思うと、ここの近くの茶屋で茶がゆを食べておけば良かった。
茶がゆもご当地もんだろうと思って、食べたかったのだが。
その後、三月堂への再入場をお願いしてみても良かったかもしれない。ちっ、抜かったぜ。
しかしその時はもうしょうがないので大仏殿に向かいました。

大仏殿を横から。

石畳に散り敷く紅葉。
初日に行けなかった東大寺か。
バス乗り放題のチケットがあるので、近鉄奈良駅から東大寺南大門までバス。
歩ける距離だと思っていたが、実際に乗ったところ、1キロくらいはあるようだった。
こういう距離が積もり積もると結構コタエるんですよ。バスに乗って良かった。

バスから降りると鹿のニオイがプンと来る。もっとはっきり言うと鹿のフンのニオイが。
南大門の前は激混み。鹿も人もいっぱいいる。


大仏殿を目の前にしながらそれへ行かずに、まずわたしは右へ折れて二月堂・三月堂に向かう。
「お水取り」の儀式を行うのが二月堂。大仏殿からはだいぶ離れている。


ぎりぎりもみじ。

こんな幟がある。この並びだと、鹿せんぺいも当然メニューのうちですよね?
比較的緩やかな階段を登り切ると、左に二月堂、右に三月堂の建物が表れる。


ここの眺望の開け方が好きだな。
二月堂は、日本には珍しいような空間構成である気がしている。手前の空間と高低差の使い方がね。雄大。
ここでお水取りの儀式がある。お水取りの儀式のためにこういう設計になったのかな。
それとも建物を作ってから、その建物の劇的効果を利用して儀式がああいう形に定着したのかな。
後者だと思うんだけどね。
だが高低差に恐れをなして、中には入りませんでした(^_^;)。
三月堂はこじんまりした建物。浄瑠璃寺でも思ったけど、ラインがきれいですよねえ。
三月堂の方には、仏像が多数収蔵されている。入って見ましょう。
だが、入場料を払って仏像の前に立った途端、衝撃の出来事が!
……修学旅行生が入って来たんです(泣)。
さすがにねえ。100人も200人もいそうな学生の襲来には耐えられない。
そもそもその人数、建物内にホントに入るの?という感じの狭さだし。
ほとんど仏像を見ないで、早々に退散しました。
せめてあと5分早めに姿を表してくれたら、時間をずらすとか何とか対応出来たのに……。
あとから思うと、ここの近くの茶屋で茶がゆを食べておけば良かった。
茶がゆもご当地もんだろうと思って、食べたかったのだが。
その後、三月堂への再入場をお願いしてみても良かったかもしれない。ちっ、抜かったぜ。
しかしその時はもうしょうがないので大仏殿に向かいました。

大仏殿を横から。

石畳に散り敷く紅葉。