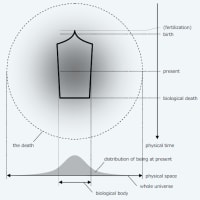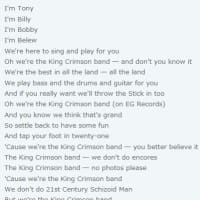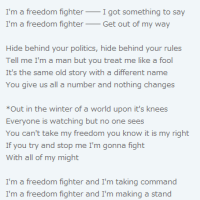付録(承前)
(後半──大槻訳を含む既存の訳註において、「付録」は上までの前半と以下の後半が別々の時期に書かれたものであろう、という但し書きが付されている)
・・・わたしは、これまで、ある希望を抱いていたのである。それは、知性的世界(intellectual world)についての我々の理論にどんな欠陥があるにせよ、それは物質の世界について人間の理性が与えうるすべての説明に伴うと思われるような矛盾と不合理からは免れているであろう、ということである。ところが、人格の同一性について述べた節をもっと厳格に再検討してみたところ、自分が途方もない迷路に入り込んだということに、わたしは気づいたのである。(どんな風に途方もないかといえば)正直、前説を訂正して矛盾のないようにしようにも、いったいどうすればいいのかわからない有様なのである。このことは、仮にそれが懐疑論(を採ること)の一般的でよい理由ではなかったとしても、わたしが自分のすべての判断について弱気で控え目にならざるを得ない、少なくともその十分なひとつの(ほかにもたくさんあるというわけではなかったとしてであるが)理由ではあるのである。(そういうわけで以下、)人格の同一性について、その(肯定的と否定的論証の)両方を提示しよう。まずは自己(self)、すなわち考える存在についての、厳密かつ適正な、同一性と単一性を否定する方へわたしを誘導した方(の論証)から始めるとしよう。
(I) 自己とか本体(substance)について語るときは、これらの語に何か観念を結びつけなければならない。そうでなければ、これらの語はまったく理解できないわけである。すべての観念は先行する印象に由来する。そして素かつ個的な何かとしての自己とか本体という印象は存在しない。ゆえに、この意味での自己とか本体という観念は存在しない。
(II) 何であれ別個なものはすべて区別することができる。そして何であれ区別できるものはすべて「考え」や想像によって分離できる。知覚はすべて別個である。ゆえにそれら(知覚)は区別でき、分離でき、分離して存在すると思うことができ、(実際)分離して存在できる。いかなる矛盾も不合理もなく、である。
(III) たとえばわたしが「このテーブル」と「あの煙突」を見るとき、わたしの心に現れるのは個々の知覚だけである。これらの知覚は、他のあらゆる知覚とおんなじような本性をもつ。これが哲学者の説である。けれどもわたしの心に現れている「このテーブル」と「向こうの煙突」は分離して存在できるし、実際、分離して存在する。これが普通の人の考え方であって、矛盾はない。ゆえに同じ説をすべての知覚に(ついての説となるように)拡張しても矛盾は生じない。
(IV) 一般的に言って、以下の推理は納得できるもののように思われる。すべての観念は先行する印象から採られる。ゆえに、対象の観念も同じところ(先行する印象)に由来する。したがって知覚に関してそうでない(矛盾があり、理解不能である)ようなどんな命題も対象に関して矛盾がない、もしくは理解可能であるということはありえない。ところで、対象が共通の素なる本体、つまり対象に固有な主体をまったく持たないとき、その対象は(我々から)はなれて存在するという命題は矛盾なく理解可能である。ゆえに、この命題は知覚に関してもバカ気たものではありえない。
(V) 考察を自分自身に転じてみると、わたしはひとつまたはそれ以上の知覚なしにはこの自己なるものをまったく知覚できない。また、わたしは知覚より以外の何物もまったく知覚できない。ゆえに、自己を形作るものはこうした知覚の合成である。
(VI) 考える存在は多数の、あるいは少数の知覚を持つものであると思うことができる。いま心が退化してカキ(oyster)にも満たないそれになったとしよう(※なぜカキなのか。カキに怨みでもあるのだろうか?)。つまり飢えとか渇きとかの、たったひとつの知覚しか持たなくなったとしよう(※カキは飢えることはあるだろうが、渇くことはあるのだろうか?)。そういう場合について考えてみる。(その場合)知覚以外の何かを思うということがあるだろうか。自己とか本体とかの概念(notion)を持つということがあるだろうか。もし持たないとすれば、そこに他の知覚を追加してもそれらの概念を与えることは決してできない。
(つづく)
(後半──大槻訳を含む既存の訳註において、「付録」は上までの前半と以下の後半が別々の時期に書かれたものであろう、という但し書きが付されている)
・・・わたしは、これまで、ある希望を抱いていたのである。それは、知性的世界(intellectual world)についての我々の理論にどんな欠陥があるにせよ、それは物質の世界について人間の理性が与えうるすべての説明に伴うと思われるような矛盾と不合理からは免れているであろう、ということである。ところが、人格の同一性について述べた節をもっと厳格に再検討してみたところ、自分が途方もない迷路に入り込んだということに、わたしは気づいたのである。(どんな風に途方もないかといえば)正直、前説を訂正して矛盾のないようにしようにも、いったいどうすればいいのかわからない有様なのである。このことは、仮にそれが懐疑論(を採ること)の一般的でよい理由ではなかったとしても、わたしが自分のすべての判断について弱気で控え目にならざるを得ない、少なくともその十分なひとつの(ほかにもたくさんあるというわけではなかったとしてであるが)理由ではあるのである。(そういうわけで以下、)人格の同一性について、その(肯定的と否定的論証の)両方を提示しよう。まずは自己(self)、すなわち考える存在についての、厳密かつ適正な、同一性と単一性を否定する方へわたしを誘導した方(の論証)から始めるとしよう。
(I) 自己とか本体(substance)について語るときは、これらの語に何か観念を結びつけなければならない。そうでなければ、これらの語はまったく理解できないわけである。すべての観念は先行する印象に由来する。そして素かつ個的な何かとしての自己とか本体という印象は存在しない。ゆえに、この意味での自己とか本体という観念は存在しない。
(II) 何であれ別個なものはすべて区別することができる。そして何であれ区別できるものはすべて「考え」や想像によって分離できる。知覚はすべて別個である。ゆえにそれら(知覚)は区別でき、分離でき、分離して存在すると思うことができ、(実際)分離して存在できる。いかなる矛盾も不合理もなく、である。
(III) たとえばわたしが「このテーブル」と「あの煙突」を見るとき、わたしの心に現れるのは個々の知覚だけである。これらの知覚は、他のあらゆる知覚とおんなじような本性をもつ。これが哲学者の説である。けれどもわたしの心に現れている「このテーブル」と「向こうの煙突」は分離して存在できるし、実際、分離して存在する。これが普通の人の考え方であって、矛盾はない。ゆえに同じ説をすべての知覚に(ついての説となるように)拡張しても矛盾は生じない。
(IV) 一般的に言って、以下の推理は納得できるもののように思われる。すべての観念は先行する印象から採られる。ゆえに、対象の観念も同じところ(先行する印象)に由来する。したがって知覚に関してそうでない(矛盾があり、理解不能である)ようなどんな命題も対象に関して矛盾がない、もしくは理解可能であるということはありえない。ところで、対象が共通の素なる本体、つまり対象に固有な主体をまったく持たないとき、その対象は(我々から)はなれて存在するという命題は矛盾なく理解可能である。ゆえに、この命題は知覚に関してもバカ気たものではありえない。
| ※ | このパラグラフの論証を独立して眺めると論理的におかしなことを言っているとしか思われないが、どうであろうか。 |
(V) 考察を自分自身に転じてみると、わたしはひとつまたはそれ以上の知覚なしにはこの自己なるものをまったく知覚できない。また、わたしは知覚より以外の何物もまったく知覚できない。ゆえに、自己を形作るものはこうした知覚の合成である。
(VI) 考える存在は多数の、あるいは少数の知覚を持つものであると思うことができる。いま心が退化してカキ(oyster)にも満たないそれになったとしよう(※なぜカキなのか。カキに怨みでもあるのだろうか?)。つまり飢えとか渇きとかの、たったひとつの知覚しか持たなくなったとしよう(※カキは飢えることはあるだろうが、渇くことはあるのだろうか?)。そういう場合について考えてみる。(その場合)知覚以外の何かを思うということがあるだろうか。自己とか本体とかの概念(notion)を持つということがあるだろうか。もし持たないとすれば、そこに他の知覚を追加してもそれらの概念を与えることは決してできない。
| ※ | ついカキにこだわってしまったが、ここは現代の我々ならば「細胞」のようなものを想像すべきところかもしれない。18世紀には人間の体が細胞で構成されているという考えは一般的ではなかったかもしれないし、そうではなかったとしても(人体を構成する)細胞が意識も何も持たない、いくつかの刺激に反応はするとしてもただの生化学機械だという考えは一般に認められたものではなかったに違いない。一方で漁夫以外の人の想像力にとってカキは単なる食用海産物以外の何物でもなかったということはありえよう。今日の我々は自分の体が数十兆個の細胞で構成されており、それらが生化学分子の工場だったりヒミツ基地のごときものであったりはしても、それ自体としては機械にすぎないことを知っている。一方ではカキのような貝類が犬や猫にも劣らないほど豊かな生態を持っている(意識は持たないとしても、あらゆる存在の中でみれば意識を持つ人間にきわめて近い方に属する)ことも知っているわけである。 |
(つづく)