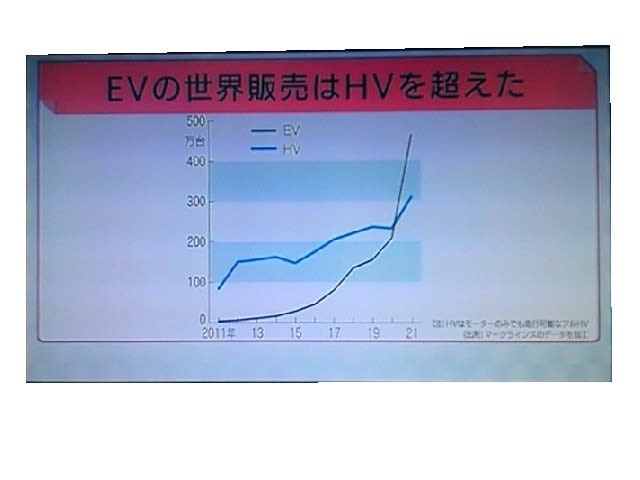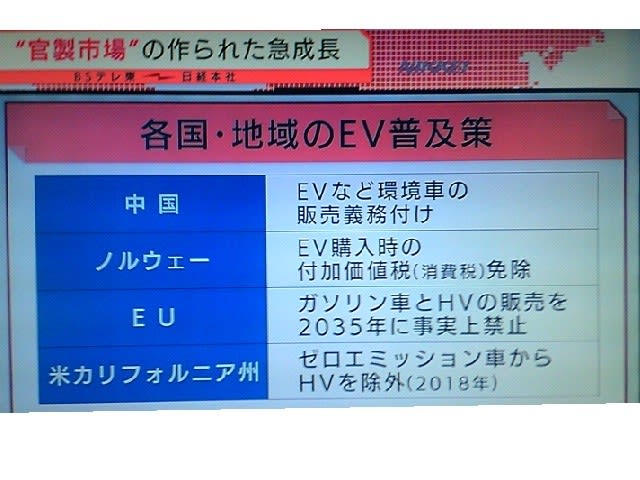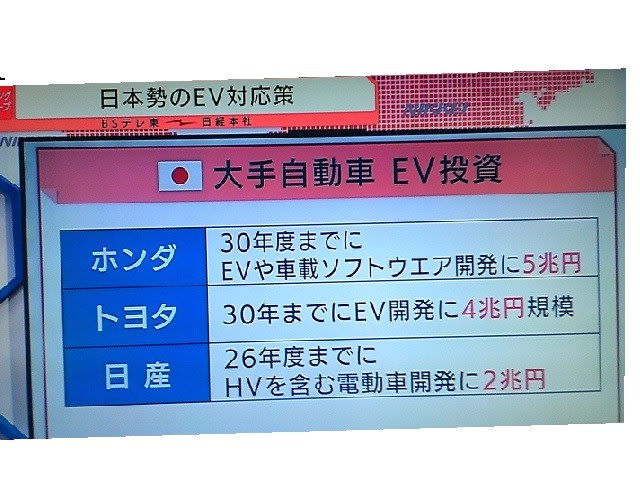迷走を続けたセブン&アイ・ホールディングス(HD)傘下の百貨店、そごう・西武の売却問題に
ようやく片が付いたでつ。
買い手は米投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」。
事業や不動産などのバイアウト投資に強みを持つが、不動産の観点では「そごう・西武は魅力に欠ける」と
いう指摘あるでつ。
むしろ隠れた主役は、フォートレスと組んだ家電量販店大手のヨドバシホールディングス。
旗艦店である西武池袋本店。
建物の規模は大きく立地も申し分ないが、土地の所有は一部に限られるでつ。
セブン&アイ・ホールディングス(HD)は11月11日、百貨店子会社「そごう・西武」の売却先が
米投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」に決まったと発表。
そごう・西武の企業価値を2500億円と算定し、負債額などを調整してフォートレスへの最終的な売却額を
決めるとしているでつ。
フォートレスは同じくSBG傘下の上場REITであるインヴィンシブル投資法人と連携するなど、日本国内では
不動産投資に力を入れているでつ。
そのため、そごう・西武OBなどからは「駅前という好立地の不動産が本当の狙いで、百貨店は切り捨てられるのでは」と
いった警戒の声が聞かれるでつ。
だけど、ある国内の証券アナリストは、「切り出せる資産なんてほとんど残っていない」と指摘。
セブン&アイHDの有価証券報告書によると、そごう・西武が建物と土地の両方で帳簿価格の
記載があったのは、西武池袋本店、そごう千葉店、そごう大宮店。
土地や建物全体を所有しているわけではないでつ。
例えば、西武池袋本店は西武鉄道の池袋駅と一体化しており、底地の多くを現在は資本関係がない西武グループが
所有しているでつ。
そごう千葉店、そごう大宮店は区画整理事業に参画して出店しているため、土地・建物の権利関係は複雑。
そごう横浜店は再開発ビルに入居しているため、土地の所有権はないでつ。
つまり、建て替えなどで資産価値を上げようとしても、複雑な地権者との調整に時間がかかる可能性が高いでつ。
むしろフォートレスと組む家電量販店大手のヨドバシHDが陰の主役と言えるでつ。
そごう・西武の百貨店と連携した新たな店舗の出店をはじめ、より一層、価値ある店づくりに努めていくとの
コメントを発表。
ヨドバシカメラの店舗網とそごう・西武の10の店舗を見比べると、重複の少なさが分かるでつ。
両社の大型店が近接して立地しているのは横浜駅前だけ。
千葉駅前にも両社の店舗があるが、ヨドバシの店舗は規模が小さいでつ。
折しも11月1日にライバルであるビックカメラの大型店舗が開店したこともあり、そごう千葉店に増床移転すれば
対抗策になりうるでつ。
また、ヨドバシはさいたま新都心駅前に大型店を持つが、商業施設が集積する大宮駅前のそごう大宮店のほうが
立地条件はいいでつ。
収益力の低い地方店舗は切り捨てられるという見方もあるが、そうとも言い切れないでつ。
秋田、福井、広島はいずれもヨドバシが進出していない空白域。
有楽町駅前のそごう東京店がビックカメラに変わり、池袋駅前の三越池袋店がヤマダデンキに変わるでつ。
そんな動きが立て続けに起きたのは、今から約20年も前のこと。
ECが拡大するなか、もはや駅前立地の大型店は時代遅れとの見方もあるでつ。
新型コロナウイルス禍で都市型店舗の集客力は落ちており、ビックカメラの場合、足元で業績をけん引しているのは
郊外立地が中心の子会社・コジマ。
しかしヨドバシの出店には、集客とは別の狙いがあるでつ。
ECの強化でつ。
21年12月に日経ビジネスが消費者1万人に行った顧客満足度調査のECサイト部門で、アマゾンや楽天市場を差し置いて
トップに輝いたのはヨドバシ・ドット・コム。
高い評価を支えるのが自社配送のヨドバシエクストリームサービス便。
最短即日で届き、消しゴム1個でも配送料は無料。
そして西武池袋本店はヨドバシ出店の最有力候補。
駅前にはビックカメラ、ヤマダデンキの旗艦店がひしめくでつが、
西武池袋本店は駅直結である分で有利。
西武渋谷店もヨドバシが未出店のエリア。
ヨドバシエクストリームサービス便の対象エリアを見ると、面白いことに気づくでつ。
東京23区全域や横浜市など首都圏を除くと、ヨドバシの大型店舗の周辺に限られているでつ。
例えば「甲府市・甲斐市・中巨摩郡の一部地域」の中心には、甲府駅前の大型店舗があるでつ。
新潟市、仙台市、札幌市、大阪市、京都市、福岡市…
いずれもヨドバシの大型店舗が立地するエリア。
ヨドバシは具体的な配送拠点を公表していないが、店舗あるいは近隣に整備した物流拠点から配送していると
みられるでつ。
つまり新たな地域に大型店舗を出せれば、その分ヨドバシエクストリームサービス便の対象エリアも広がるでつ。
ヨドバシのライバルであるアマゾンは22年、東北・四国・九州などに自社配送拠点を18カ所開設。
地方部でも配送サービスを拡充しているでつ。
ECの戦いは大都市圏から地方へと広がりつつあるでつ。
加えて、家電量販の枠を超えて総合通販サイトとなっているヨドバシ・ドット・コムにとって、そごう・西武が取り扱う食品、
化粧品、アパレルなどの商品ラインアップも魅力的に映るかも…
ヨドバシHDは店頭で買いたいものと、ネットで買いたいものは違うと考え、店舗では扱っていない書籍や日用品・食品へと
取り扱いジャンルを拡大していったでつ。
社内でバイヤーを養成し、自社での仕入れにこだわってきたが、最近は傘下に収めた石井スポーツやアートスポーツの「ストア」も
サイト内に開設。
セブン&アイHDが鳴り物入りで15年にオープンさせたグループ横断の統合型ECサイト「オムニ7」は、23年1月に完全閉鎖。
そごう・西武がヨドバシ・ドット・コムに“出店”する可能性もあるでつ。
懸念材料は、そごう・西武が変化に向けて一歩を踏み出せるかどうか。
セブン&アイHDが売却検討を公に認めたのは4月だったでつが、決定がここまで長引いた背景には、ブランドイメージを
気にする宝飾や化粧品といった取引先との信頼関係や、地方店をたたむ場合のレピュテーションへのマイナス影響を懸念する声を
無視できなかったことがあるでつ。
だけど今や、老舗の日本橋三越本店にすらビックカメラが出店する時代。
セブン&アイ傘下では相乗効果が出せず、22年2月期まで3期連続の赤字に陥っていただけに、
一刻の猶予も許されないでつ。
堤清二さんが流通界に革新を持って作った西武セゾングループの旗艦事業百貨店。
時代の流れとはいえ、継続していくことの難しさ、カリスマ経営者の後というのが
難しいでつ。
ヨドバシはやっぱり出店に際しては、西武・そごうの利用価値は絶大だなぁ~
神戸そごうにヨドバシが来ると家電の競争も激しくなるでつ。
ヨドバシが関西方面に来るのは大歓迎だなぁ~
そういう意味ではこの買収に期待したでつ。
ようやく片が付いたでつ。
買い手は米投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」。
事業や不動産などのバイアウト投資に強みを持つが、不動産の観点では「そごう・西武は魅力に欠ける」と
いう指摘あるでつ。
むしろ隠れた主役は、フォートレスと組んだ家電量販店大手のヨドバシホールディングス。
旗艦店である西武池袋本店。
建物の規模は大きく立地も申し分ないが、土地の所有は一部に限られるでつ。
セブン&アイ・ホールディングス(HD)は11月11日、百貨店子会社「そごう・西武」の売却先が
米投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」に決まったと発表。
そごう・西武の企業価値を2500億円と算定し、負債額などを調整してフォートレスへの最終的な売却額を
決めるとしているでつ。
フォートレスは同じくSBG傘下の上場REITであるインヴィンシブル投資法人と連携するなど、日本国内では
不動産投資に力を入れているでつ。
そのため、そごう・西武OBなどからは「駅前という好立地の不動産が本当の狙いで、百貨店は切り捨てられるのでは」と
いった警戒の声が聞かれるでつ。
だけど、ある国内の証券アナリストは、「切り出せる資産なんてほとんど残っていない」と指摘。
セブン&アイHDの有価証券報告書によると、そごう・西武が建物と土地の両方で帳簿価格の
記載があったのは、西武池袋本店、そごう千葉店、そごう大宮店。
土地や建物全体を所有しているわけではないでつ。
例えば、西武池袋本店は西武鉄道の池袋駅と一体化しており、底地の多くを現在は資本関係がない西武グループが
所有しているでつ。
そごう千葉店、そごう大宮店は区画整理事業に参画して出店しているため、土地・建物の権利関係は複雑。
そごう横浜店は再開発ビルに入居しているため、土地の所有権はないでつ。
つまり、建て替えなどで資産価値を上げようとしても、複雑な地権者との調整に時間がかかる可能性が高いでつ。
むしろフォートレスと組む家電量販店大手のヨドバシHDが陰の主役と言えるでつ。
そごう・西武の百貨店と連携した新たな店舗の出店をはじめ、より一層、価値ある店づくりに努めていくとの
コメントを発表。
ヨドバシカメラの店舗網とそごう・西武の10の店舗を見比べると、重複の少なさが分かるでつ。
両社の大型店が近接して立地しているのは横浜駅前だけ。
千葉駅前にも両社の店舗があるが、ヨドバシの店舗は規模が小さいでつ。
折しも11月1日にライバルであるビックカメラの大型店舗が開店したこともあり、そごう千葉店に増床移転すれば
対抗策になりうるでつ。
また、ヨドバシはさいたま新都心駅前に大型店を持つが、商業施設が集積する大宮駅前のそごう大宮店のほうが
立地条件はいいでつ。
収益力の低い地方店舗は切り捨てられるという見方もあるが、そうとも言い切れないでつ。
秋田、福井、広島はいずれもヨドバシが進出していない空白域。
有楽町駅前のそごう東京店がビックカメラに変わり、池袋駅前の三越池袋店がヤマダデンキに変わるでつ。
そんな動きが立て続けに起きたのは、今から約20年も前のこと。
ECが拡大するなか、もはや駅前立地の大型店は時代遅れとの見方もあるでつ。
新型コロナウイルス禍で都市型店舗の集客力は落ちており、ビックカメラの場合、足元で業績をけん引しているのは
郊外立地が中心の子会社・コジマ。
しかしヨドバシの出店には、集客とは別の狙いがあるでつ。
ECの強化でつ。
21年12月に日経ビジネスが消費者1万人に行った顧客満足度調査のECサイト部門で、アマゾンや楽天市場を差し置いて
トップに輝いたのはヨドバシ・ドット・コム。
高い評価を支えるのが自社配送のヨドバシエクストリームサービス便。
最短即日で届き、消しゴム1個でも配送料は無料。
そして西武池袋本店はヨドバシ出店の最有力候補。
駅前にはビックカメラ、ヤマダデンキの旗艦店がひしめくでつが、
西武池袋本店は駅直結である分で有利。
西武渋谷店もヨドバシが未出店のエリア。
ヨドバシエクストリームサービス便の対象エリアを見ると、面白いことに気づくでつ。
東京23区全域や横浜市など首都圏を除くと、ヨドバシの大型店舗の周辺に限られているでつ。
例えば「甲府市・甲斐市・中巨摩郡の一部地域」の中心には、甲府駅前の大型店舗があるでつ。
新潟市、仙台市、札幌市、大阪市、京都市、福岡市…
いずれもヨドバシの大型店舗が立地するエリア。
ヨドバシは具体的な配送拠点を公表していないが、店舗あるいは近隣に整備した物流拠点から配送していると
みられるでつ。
つまり新たな地域に大型店舗を出せれば、その分ヨドバシエクストリームサービス便の対象エリアも広がるでつ。
ヨドバシのライバルであるアマゾンは22年、東北・四国・九州などに自社配送拠点を18カ所開設。
地方部でも配送サービスを拡充しているでつ。
ECの戦いは大都市圏から地方へと広がりつつあるでつ。
加えて、家電量販の枠を超えて総合通販サイトとなっているヨドバシ・ドット・コムにとって、そごう・西武が取り扱う食品、
化粧品、アパレルなどの商品ラインアップも魅力的に映るかも…
ヨドバシHDは店頭で買いたいものと、ネットで買いたいものは違うと考え、店舗では扱っていない書籍や日用品・食品へと
取り扱いジャンルを拡大していったでつ。
社内でバイヤーを養成し、自社での仕入れにこだわってきたが、最近は傘下に収めた石井スポーツやアートスポーツの「ストア」も
サイト内に開設。
セブン&アイHDが鳴り物入りで15年にオープンさせたグループ横断の統合型ECサイト「オムニ7」は、23年1月に完全閉鎖。
そごう・西武がヨドバシ・ドット・コムに“出店”する可能性もあるでつ。
懸念材料は、そごう・西武が変化に向けて一歩を踏み出せるかどうか。
セブン&アイHDが売却検討を公に認めたのは4月だったでつが、決定がここまで長引いた背景には、ブランドイメージを
気にする宝飾や化粧品といった取引先との信頼関係や、地方店をたたむ場合のレピュテーションへのマイナス影響を懸念する声を
無視できなかったことがあるでつ。
だけど今や、老舗の日本橋三越本店にすらビックカメラが出店する時代。
セブン&アイ傘下では相乗効果が出せず、22年2月期まで3期連続の赤字に陥っていただけに、
一刻の猶予も許されないでつ。
堤清二さんが流通界に革新を持って作った西武セゾングループの旗艦事業百貨店。
時代の流れとはいえ、継続していくことの難しさ、カリスマ経営者の後というのが
難しいでつ。
ヨドバシはやっぱり出店に際しては、西武・そごうの利用価値は絶大だなぁ~
神戸そごうにヨドバシが来ると家電の競争も激しくなるでつ。
ヨドバシが関西方面に来るのは大歓迎だなぁ~
そういう意味ではこの買収に期待したでつ。