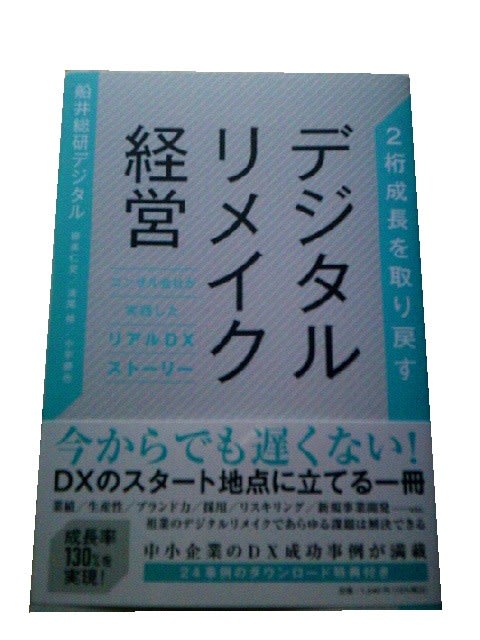テレビの放映権ってのは凄い費用。
それゆえ、テレビ局の言い分が通りやすい。
スポーツではFIFA]の力も強い。
規格のテレビの放映権が強く反映。
バレーボールは、時短のため別物のルールに改正されてるでつ。
パリ五輪の開幕が1カ月後に迫ってきたでつ。
高まる機運の陰で、大会のテレビ視聴者は世界的に減少傾向にあるでつ。
メディア環境の変化やスポーツ中継の有料化が進み、生中継でスポーツを観戦する習慣が希薄になってきたでつ。
主流はSNSなどで効率よくハイライトだけをチェックするタイムパフォーマンス観戦」に移りつつあるでつ。
IOCのOlympic Marketing Fact File 2024によると、2021年の東京大会の中継視聴者はテレビとインターネットを
合わせて全世界で30億5000万人。
16年のリオデジャネイロ大会に比べて5%減、12年のロンドン大会からは15%も減ったでつ。
一方、急増したのがハイライトなどを切り取ったネット動画の再生回数。
ロンドンでは19億回、リオでは116億回、東京では280億回。
とあるアンケートでは、面白いシーンはSNSにまとめられているでつ。
テレビでは見ないと断言。
お手軽なSNSでのタイパ観戦は大会側にとって不穏な兆候。
放映権料はIOCの収入の6割を占める最大の米びつ。
その規模は商業五輪の起点となった1984年ロサンゼルス大会以降、夏季だけでも10倍に拡大。
生中継の視聴者減少はその土台を揺るがしかねないでつ。
嗜好の細分化やメディアの個別化が進む現在、スポーツの視聴者層はコアなファンが中心になりつつあり、
五輪といえども求心力の低下は避けられないでつ。
そこに拍車をかけるのが、放映権料の高騰を受けた相次ぐプロスポーツの中継有料化。
テレビをつければ自然とスポーツが目に入る状況は消えつつあるでつ。
某国営放送は近年、米ゴルフツアー、男子テニスツアーなどのBS中継から撤退。
サッカーワールドカップは五輪同様、某国営放送と民放各社が協力して放送していたでつが、
22年のカタール大会では民放3局が撤退。
地上波での中継試合数が大幅に減少したでつ。
W杯以外でも、サッカー日本代表戦の地上波中継は減っているでつ。
五輪は無料中継を原則。
高額な放映権料に加えて制作費もかさむ中継はテレビ局にとって大きな負担。
日本民間放送連盟によると夏季五輪は直近3大会続けて赤字。
円安に加え、時差で広告収入も期待しにくいパリ大会も見通しは厳しいでつ。
多くの種目が同時並行で行われるでつ。
協力してやっていく意味はあると語ったでつが、テレビ局の使命感頼みでは、無料中継の継続は心もとないでつ。
国民的な祭典でもある五輪のテレビ中継は古くは街頭、その後はお茶の間で老若男女の目を釘付けにし、
一体感の醸成や感動の共有を促してきたでつ。
スマホでのタイパ観戦はこうした体験を損ない、若い世代がスポーツに触れる機会をも減らすでつ。
スポーツライフに関する調査によると、06年にはテレビでスポーツ観戦をする習慣があると答えた人の比率が
20〜70歳代の全年代で9割を超えていたでつが、22年は20代で61%、30代で71%と若年層で大きく低下。
また、23年の中学生の運動部活動への加入率は男子が64.1%、女子が49.8%と15年比でそれぞれ10.3ポイント、8.6ポイント少ないでつ。
少子化も加わり、するスポーツも状況は厳しいでつ。
テレビゲームの延長のようなeスポーツが五輪種目として採用されることが現実味を帯びていることからは大会側の危機感がうかがえるでつ。
スポーツ界で大金が飛び交うほど、その土壌は細ることになりかねないでつ。
それゆえ、テレビ局の言い分が通りやすい。
スポーツではFIFA]の力も強い。
規格のテレビの放映権が強く反映。
バレーボールは、時短のため別物のルールに改正されてるでつ。
パリ五輪の開幕が1カ月後に迫ってきたでつ。
高まる機運の陰で、大会のテレビ視聴者は世界的に減少傾向にあるでつ。
メディア環境の変化やスポーツ中継の有料化が進み、生中継でスポーツを観戦する習慣が希薄になってきたでつ。
主流はSNSなどで効率よくハイライトだけをチェックするタイムパフォーマンス観戦」に移りつつあるでつ。
IOCのOlympic Marketing Fact File 2024によると、2021年の東京大会の中継視聴者はテレビとインターネットを
合わせて全世界で30億5000万人。
16年のリオデジャネイロ大会に比べて5%減、12年のロンドン大会からは15%も減ったでつ。
一方、急増したのがハイライトなどを切り取ったネット動画の再生回数。
ロンドンでは19億回、リオでは116億回、東京では280億回。
とあるアンケートでは、面白いシーンはSNSにまとめられているでつ。
テレビでは見ないと断言。
お手軽なSNSでのタイパ観戦は大会側にとって不穏な兆候。
放映権料はIOCの収入の6割を占める最大の米びつ。
その規模は商業五輪の起点となった1984年ロサンゼルス大会以降、夏季だけでも10倍に拡大。
生中継の視聴者減少はその土台を揺るがしかねないでつ。
嗜好の細分化やメディアの個別化が進む現在、スポーツの視聴者層はコアなファンが中心になりつつあり、
五輪といえども求心力の低下は避けられないでつ。
そこに拍車をかけるのが、放映権料の高騰を受けた相次ぐプロスポーツの中継有料化。
テレビをつければ自然とスポーツが目に入る状況は消えつつあるでつ。
某国営放送は近年、米ゴルフツアー、男子テニスツアーなどのBS中継から撤退。
サッカーワールドカップは五輪同様、某国営放送と民放各社が協力して放送していたでつが、
22年のカタール大会では民放3局が撤退。
地上波での中継試合数が大幅に減少したでつ。
W杯以外でも、サッカー日本代表戦の地上波中継は減っているでつ。
五輪は無料中継を原則。
高額な放映権料に加えて制作費もかさむ中継はテレビ局にとって大きな負担。
日本民間放送連盟によると夏季五輪は直近3大会続けて赤字。
円安に加え、時差で広告収入も期待しにくいパリ大会も見通しは厳しいでつ。
多くの種目が同時並行で行われるでつ。
協力してやっていく意味はあると語ったでつが、テレビ局の使命感頼みでは、無料中継の継続は心もとないでつ。
国民的な祭典でもある五輪のテレビ中継は古くは街頭、その後はお茶の間で老若男女の目を釘付けにし、
一体感の醸成や感動の共有を促してきたでつ。
スマホでのタイパ観戦はこうした体験を損ない、若い世代がスポーツに触れる機会をも減らすでつ。
スポーツライフに関する調査によると、06年にはテレビでスポーツ観戦をする習慣があると答えた人の比率が
20〜70歳代の全年代で9割を超えていたでつが、22年は20代で61%、30代で71%と若年層で大きく低下。
また、23年の中学生の運動部活動への加入率は男子が64.1%、女子が49.8%と15年比でそれぞれ10.3ポイント、8.6ポイント少ないでつ。
少子化も加わり、するスポーツも状況は厳しいでつ。
テレビゲームの延長のようなeスポーツが五輪種目として採用されることが現実味を帯びていることからは大会側の危機感がうかがえるでつ。
スポーツ界で大金が飛び交うほど、その土壌は細ることになりかねないでつ。